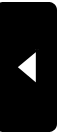「そばの味と学びの味」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年08月05日21:47
昨日、今日と、真夏の猛暑が続いています。
実は、昨日は、2年生の「経営ビジネス系列」を選択している生徒たちが、そばの栽培・加工・販売といった一連の課題研究を行うための最初の実習がありました。
担当の商業科の楯先生からのレポートです。
「夏の日差しが本格化した8月4日、2年生「課題研究」におけるそば実習として、栽培から製造・販売までの一貫した取組を行う学習が、いよいよ始まりました。そばを学習ツールにして、簿記会計・マーケティング・情報処理を「見える化」して学習を結びつけていく活動で、今回が第3期目(3年目)になります。
7月下旬に予定していた事前学習が休校(大雨のため電車運休)により実施できなかったため、実習前には、南木曽町役場の服部様・JA木曽の小原様より講義をしていただきました。
南木曽町農業委員の方3名と地域おこし協力隊の川本様のご指導・ご協力をいただきながら、参加生徒6名が、播種作業を行いました。」
…という魅力的な学習のスタートです。まずは、播種をしてそばの栽培から始めることになりました。
そばが大好きで県内のそば屋をはじから訪問してきた私としては、どのようなそばの学習が展開されるのか、興味津々です。(実は、今晩の我が家の夕食は、冷やしかきあげそばでした。)
生徒たちのそば学習は、そばの味だけではなく、学習からどんな気付きを重ねていくかが勝負になります。「学びの味」です。
まずは、そばが野生の動物たちに食べられることなく、うまく育ちますように!

実は、昨日は、2年生の「経営ビジネス系列」を選択している生徒たちが、そばの栽培・加工・販売といった一連の課題研究を行うための最初の実習がありました。
担当の商業科の楯先生からのレポートです。
「夏の日差しが本格化した8月4日、2年生「課題研究」におけるそば実習として、栽培から製造・販売までの一貫した取組を行う学習が、いよいよ始まりました。そばを学習ツールにして、簿記会計・マーケティング・情報処理を「見える化」して学習を結びつけていく活動で、今回が第3期目(3年目)になります。
7月下旬に予定していた事前学習が休校(大雨のため電車運休)により実施できなかったため、実習前には、南木曽町役場の服部様・JA木曽の小原様より講義をしていただきました。
南木曽町農業委員の方3名と地域おこし協力隊の川本様のご指導・ご協力をいただきながら、参加生徒6名が、播種作業を行いました。」
…という魅力的な学習のスタートです。まずは、播種をしてそばの栽培から始めることになりました。
そばが大好きで県内のそば屋をはじから訪問してきた私としては、どのようなそばの学習が展開されるのか、興味津々です。(実は、今晩の我が家の夕食は、冷やしかきあげそばでした。)
生徒たちのそば学習は、そばの味だけではなく、学習からどんな気付きを重ねていくかが勝負になります。「学びの味」です。
まずは、そばが野生の動物たちに食べられることなく、うまく育ちますように!

「100を0にしないチャレンジは続く」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年08月04日21:53
今日は、3年生12名のためにワンデイ・イングリッシュ・セミナーを開催しました。
3月にカナダ語学研修を予定していた生徒たちは、2年生の後半に20回に及ぶ準備学習を重ねてきたにもかかわらず、コロナのためにカナダに行けなかったのです。
文部科学省は、調査書に「〇〇に行く予定であったがコロナのために中止になった」旨を書いてもよいと全国の教育委員会に通知しました。でも思うのですが、大切なことは「〇〇に参加して◇◇の学びを重ねた」という点です。
ならば「〇〇に行く予定であったがコロナのために中止になり、こんなことでくじけてたまるかと代替の▽▽に参加して◇◇の学びを進めた」という高校時代にしてあげたい。
とはいえ、3年生はもう受験勉強の補習の毎日だったり、就職に向けての準備の真っ最中だったりする。研修旅行担当の今井先生や3年の学年団と相談して何とか「1日」だったら、空けられるかも…となりました。でも企画はどうする? 蘇南高校の先生たちの企画ならば、補習のひとつになってしまう。学校では味わえない、この生徒たちだけのための特別企画にしたい。英語オンリーで1日を過ごすことで外国語を使う喜びを体感し、さらには異文化とふれあい理解し合うことの感動を体験したい。
松本市にある英語スクールで、多くのALTを育成している「A to Z」さんに私たちの思いを相談したのが2カ月前のこと。「A to Z」さんはこの思いの実現に本当に尽力してくださいました。
そして南木曽町が生徒の参加費用の半額を支援してくださいました。
会場は、松本市のネッツトヨタ信州・鎌田店の中にある会議室。企業の研修で使うような素敵な部屋でした。この非日常的な雰囲気もいい。南木曽から松本まで野球部のマイクロバスを借りて2時間半をかけて松本に来たのです。今井先生と竹岡先生の引率です。運転手は野球部顧問の大野田先生。
…で、セミナーがどうだったかと言うと、まあよく生徒が英語をしゃべること! 必死に、そして楽しく、笑顔で、普段ならば考えられないくらいの身体表現とともに、です。それを引き出したのは、「A to Z」の先生方です。生徒12人に3人のALTですから、生徒は待っている時間がない。つねに対話をする当事者でありつづける環境に身をおいています。
今日のテーマを一言で言えば、「広い世界をふれあい、わかりあおうとすることほど楽しいものはない」ということ。「A to Z」の先生方が渾身の力を込めた、そのメッセージは、生徒たちの心にしっかり届いていたと思いました。
帰りのバスのなかで生徒たちは「つかれた~」と笑顔で言っていたとか。
それって、外国旅行からな成田空港の到着ロビーに帰ってきたときに、思わずつぶやく言葉ですよね。
生徒たちは、今回も「100を0にしなかった」のです。

3月にカナダ語学研修を予定していた生徒たちは、2年生の後半に20回に及ぶ準備学習を重ねてきたにもかかわらず、コロナのためにカナダに行けなかったのです。
文部科学省は、調査書に「〇〇に行く予定であったがコロナのために中止になった」旨を書いてもよいと全国の教育委員会に通知しました。でも思うのですが、大切なことは「〇〇に参加して◇◇の学びを重ねた」という点です。
ならば「〇〇に行く予定であったがコロナのために中止になり、こんなことでくじけてたまるかと代替の▽▽に参加して◇◇の学びを進めた」という高校時代にしてあげたい。
とはいえ、3年生はもう受験勉強の補習の毎日だったり、就職に向けての準備の真っ最中だったりする。研修旅行担当の今井先生や3年の学年団と相談して何とか「1日」だったら、空けられるかも…となりました。でも企画はどうする? 蘇南高校の先生たちの企画ならば、補習のひとつになってしまう。学校では味わえない、この生徒たちだけのための特別企画にしたい。英語オンリーで1日を過ごすことで外国語を使う喜びを体感し、さらには異文化とふれあい理解し合うことの感動を体験したい。
松本市にある英語スクールで、多くのALTを育成している「A to Z」さんに私たちの思いを相談したのが2カ月前のこと。「A to Z」さんはこの思いの実現に本当に尽力してくださいました。
そして南木曽町が生徒の参加費用の半額を支援してくださいました。
会場は、松本市のネッツトヨタ信州・鎌田店の中にある会議室。企業の研修で使うような素敵な部屋でした。この非日常的な雰囲気もいい。南木曽から松本まで野球部のマイクロバスを借りて2時間半をかけて松本に来たのです。今井先生と竹岡先生の引率です。運転手は野球部顧問の大野田先生。
…で、セミナーがどうだったかと言うと、まあよく生徒が英語をしゃべること! 必死に、そして楽しく、笑顔で、普段ならば考えられないくらいの身体表現とともに、です。それを引き出したのは、「A to Z」の先生方です。生徒12人に3人のALTですから、生徒は待っている時間がない。つねに対話をする当事者でありつづける環境に身をおいています。
今日のテーマを一言で言えば、「広い世界をふれあい、わかりあおうとすることほど楽しいものはない」ということ。「A to Z」の先生方が渾身の力を込めた、そのメッセージは、生徒たちの心にしっかり届いていたと思いました。
帰りのバスのなかで生徒たちは「つかれた~」と笑顔で言っていたとか。
それって、外国旅行からな成田空港の到着ロビーに帰ってきたときに、思わずつぶやく言葉ですよね。
生徒たちは、今回も「100を0にしなかった」のです。

「誠実に聞けているか、鋭く問えているか」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年08月03日19:31
先週の金曜日、7月31日の午後に、3年生の「総合研究」(総合的な探究の時間)で信濃毎日新聞社の読者センター次長の山嵜さんを講師にお迎えして、特別講座を実施しました。
本校の「総合的な探究の時間」は、金曜日の午後全て(4~6時限)にあてられています。フィールドワークや今回のような特別講座をどんどん行えるようになっているところが、大きな特色なのです。そして班ごとに支援する担当教員がつきますから、この時間帯は学校をあげて取り組んでいます。
以下は3年の「総合研究」のまとめ役である半場先生からの報告です。
「生徒たちは、これまで研究概要を作成し、研究の見通しを立ててきました。今後の活動では独自のデータを収集するために外部への取材を計画している生徒が多くいます。そのような中で、信毎の山嵜読者センター次長さんに、『取材の仕方を学ぼう』というテーマで授業をしていただきました。5W1Hを活用して質問を考えること、取材ノートの作り方、などをとても具体的に丁寧に教えていただきました。さらには講師の山嵜さんを取材対象として実際に質問を考える演習もあり、生徒たちは実践的に学ぶことができました。」
私も後ろから参観したのですが、取材するということがいかに難しいことか、そしてうまく取材できた時の充実感がどれほど大きいものかが、生徒たちは実感としてわかったのだと思います。プロの新聞記者の経験を交えた講義の説得力に勝るものはありません。
すぐれた「探究」のためには、よき「テーマ」をたてること。そして他者の語りをきちんと「聞く」こと。…これが出発点です。
日頃、何気なくみている新聞が、いかに記者さんたちのすぐれた「問う力」と「聞く力」(そして「書く力」)によるものであるかを認識できたことは、生徒にとっては大きな収穫でした。
ちなみに私も今、ある学術出版社の雑誌から書評原稿を依頼されて執筆中です。対象とする書物の書き手の言葉の本質を「聞き取り」、その書物から浮かび上がってくるアクチュアリティを「問う」ことを一生懸命やっています。生徒とやっていることは基本的に同じです。 それだけに、自分が誠実に聞けているか、鋭く問えているかを、今晩も延々と考え抜きたいと思います。

本校の「総合的な探究の時間」は、金曜日の午後全て(4~6時限)にあてられています。フィールドワークや今回のような特別講座をどんどん行えるようになっているところが、大きな特色なのです。そして班ごとに支援する担当教員がつきますから、この時間帯は学校をあげて取り組んでいます。
以下は3年の「総合研究」のまとめ役である半場先生からの報告です。
「生徒たちは、これまで研究概要を作成し、研究の見通しを立ててきました。今後の活動では独自のデータを収集するために外部への取材を計画している生徒が多くいます。そのような中で、信毎の山嵜読者センター次長さんに、『取材の仕方を学ぼう』というテーマで授業をしていただきました。5W1Hを活用して質問を考えること、取材ノートの作り方、などをとても具体的に丁寧に教えていただきました。さらには講師の山嵜さんを取材対象として実際に質問を考える演習もあり、生徒たちは実践的に学ぶことができました。」
私も後ろから参観したのですが、取材するということがいかに難しいことか、そしてうまく取材できた時の充実感がどれほど大きいものかが、生徒たちは実感としてわかったのだと思います。プロの新聞記者の経験を交えた講義の説得力に勝るものはありません。
すぐれた「探究」のためには、よき「テーマ」をたてること。そして他者の語りをきちんと「聞く」こと。…これが出発点です。
日頃、何気なくみている新聞が、いかに記者さんたちのすぐれた「問う力」と「聞く力」(そして「書く力」)によるものであるかを認識できたことは、生徒にとっては大きな収穫でした。
ちなみに私も今、ある学術出版社の雑誌から書評原稿を依頼されて執筆中です。対象とする書物の書き手の言葉の本質を「聞き取り」、その書物から浮かび上がってくるアクチュアリティを「問う」ことを一生懸命やっています。生徒とやっていることは基本的に同じです。 それだけに、自分が誠実に聞けているか、鋭く問えているかを、今晩も延々と考え抜きたいと思います。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長