「漱石の小説をめぐって問いをたてる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月29日19:19
2年の現代文Bの授業(横山先生が担当)で、夏目漱石の『こころ』を読んでいます。この小説を高校生が読むのは、私が高校生の頃と変わらぬ光景です。(ちなみに高校時代の私は、『漱石全集』を買い込んで、『行人』を愛読していました。)
私の頃と授業がまったく違うのは、『こころ』をいくつかの部分にわけて、班ごとに協働的な学びを進めている点です。特に、各班が自分たちの担当部分のなかで、読み進めていく中で鍵になりそうな点を「問い」の形で表現して、その投げかけられた問いをクラスみんなで考える学びをしています。
「なぜ奥さんの調子は、『まるで私の気分に入り込めないような軽いもの』だったのだろうか。」という問いを投げかけた班がありました。いいセンスの問いだなあと思いました。それをクラス全員が一生懸命考えている光景も、とてもよかった。
横山先生のファシリテートのもと、生徒が主体となって考える国語の授業が展開されているのでした。
何年ぶりかで『こころ』を読み返してみると、「私」の「K」に対する一方的な想像(思い込み)が「私」を行動にかりたて、「私」が追いつめられていくという、近代的自我の悲劇が描かれています。シェイクスピアの『マクベス』を連想してしまいます。(たしか高校時代の私もそんなことを考えていました。)
そして改めて「私」の一方的な思い込みの対象のなかに「女性」が不在であるという、このジェンダー感覚は何なのだろうかという、戸惑いを覚えたのでした。
授業の後、校長室で横山先生と『こころ』をめぐって、そんな対話をしました。生徒も問いを作るし、私たちも問いを作る。そんな学校でありたいと思います。

私の頃と授業がまったく違うのは、『こころ』をいくつかの部分にわけて、班ごとに協働的な学びを進めている点です。特に、各班が自分たちの担当部分のなかで、読み進めていく中で鍵になりそうな点を「問い」の形で表現して、その投げかけられた問いをクラスみんなで考える学びをしています。
「なぜ奥さんの調子は、『まるで私の気分に入り込めないような軽いもの』だったのだろうか。」という問いを投げかけた班がありました。いいセンスの問いだなあと思いました。それをクラス全員が一生懸命考えている光景も、とてもよかった。
横山先生のファシリテートのもと、生徒が主体となって考える国語の授業が展開されているのでした。
何年ぶりかで『こころ』を読み返してみると、「私」の「K」に対する一方的な想像(思い込み)が「私」を行動にかりたて、「私」が追いつめられていくという、近代的自我の悲劇が描かれています。シェイクスピアの『マクベス』を連想してしまいます。(たしか高校時代の私もそんなことを考えていました。)
そして改めて「私」の一方的な思い込みの対象のなかに「女性」が不在であるという、このジェンダー感覚は何なのだろうかという、戸惑いを覚えたのでした。
授業の後、校長室で横山先生と『こころ』をめぐって、そんな対話をしました。生徒も問いを作るし、私たちも問いを作る。そんな学校でありたいと思います。
「汗を流して幸せを作り出す」その2
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月28日19:30
火曜日の「ハピネス・チャージ」と題したボランティア活動の続きのレポートです。
新しく発足した生徒会執行部の公約の一つは、ボランティア活動などをつうじてもっと地域の人々とつながる学校にしたいということでした。今回は、日課変更をして1・2年生全員の活動の時間をつくりました。これが放課後や休日の自主参加の活動に展開すればいいと願ってのことです。
南木曽町交通安全協会さんのご協力をいただき、川向・天白・沼田地区のカーブミラーの清掃を生徒たちが行いました。普段、多くの人々が当たり前に利用しているカーブミラーが、実は大人の地道な努力によって維持されているということを知りました。
天白区長さんにご協力をいただき、天白公園一帯の落ち葉拾いとガードレール磨きを行いました。ここに最も人数が必要でした。生徒の通学路でもあり、南木曽町の大切な観光地でもある天白公園が、とても美しい景観になりました。長年の風雨にさらされて黒くなったガードレールが真っ白くなったのです。「日本で最も美しい村連合」の景観を生徒たちが守ることができました。
学校に戻ってきた生徒たちは、「疲れたけど楽しかった」と一様に語っていました。
社会の中で活動したあとの「心地よい疲労」というのは、「大人」の大切な感覚です。

新しく発足した生徒会執行部の公約の一つは、ボランティア活動などをつうじてもっと地域の人々とつながる学校にしたいということでした。今回は、日課変更をして1・2年生全員の活動の時間をつくりました。これが放課後や休日の自主参加の活動に展開すればいいと願ってのことです。
南木曽町交通安全協会さんのご協力をいただき、川向・天白・沼田地区のカーブミラーの清掃を生徒たちが行いました。普段、多くの人々が当たり前に利用しているカーブミラーが、実は大人の地道な努力によって維持されているということを知りました。
天白区長さんにご協力をいただき、天白公園一帯の落ち葉拾いとガードレール磨きを行いました。ここに最も人数が必要でした。生徒の通学路でもあり、南木曽町の大切な観光地でもある天白公園が、とても美しい景観になりました。長年の風雨にさらされて黒くなったガードレールが真っ白くなったのです。「日本で最も美しい村連合」の景観を生徒たちが守ることができました。
学校に戻ってきた生徒たちは、「疲れたけど楽しかった」と一様に語っていました。
社会の中で活動したあとの「心地よい疲労」というのは、「大人」の大切な感覚です。
「学校を映画館にする」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月27日19:52
今日の午後は、体育館で全校映画鑑賞を行いました。
昔は南木曽町にも二軒の映画館があったと言います。映画館の大きなスクリーンで映画を観た経験のある高校生は、年々少なくなっているはず。これは文化の衰退でもあります。
塩尻の東座さんと長野映研さんのご尽力により、体育館が「映画館」のようになりました。
シネマコラムニストの合木梢さんによる映画の紹介から始まります。(これがあるから映画を観る楽しさが倍増する。)そして、片渕須直監督、こうの史代原作「この世界の片隅に」(2016年)を上映しました。
広島と呉を舞台に、太平洋戦争の時代を懸命に生きた人々を描いた秀作です。この世界の「片隅」に生きる小さな人々の「圧倒的ないのちの重み」について考えたひとときになりました。
上映会の後、生徒会長が東座さんと長野映研さんに、これから映画の感想を友人と語り合いたいと御礼の思いを述べました。
コロナの時代だけれども、できることは山ほどあります。町に映画館がなければ、作ればいいのです。映画は、やはり最高です。(中学生の頃は映画評論家になる夢を抱いていた小川の述懐。)

昔は南木曽町にも二軒の映画館があったと言います。映画館の大きなスクリーンで映画を観た経験のある高校生は、年々少なくなっているはず。これは文化の衰退でもあります。
塩尻の東座さんと長野映研さんのご尽力により、体育館が「映画館」のようになりました。
シネマコラムニストの合木梢さんによる映画の紹介から始まります。(これがあるから映画を観る楽しさが倍増する。)そして、片渕須直監督、こうの史代原作「この世界の片隅に」(2016年)を上映しました。
広島と呉を舞台に、太平洋戦争の時代を懸命に生きた人々を描いた秀作です。この世界の「片隅」に生きる小さな人々の「圧倒的ないのちの重み」について考えたひとときになりました。
上映会の後、生徒会長が東座さんと長野映研さんに、これから映画の感想を友人と語り合いたいと御礼の思いを述べました。
コロナの時代だけれども、できることは山ほどあります。町に映画館がなければ、作ればいいのです。映画は、やはり最高です。(中学生の頃は映画評論家になる夢を抱いていた小川の述懐。)
「汗を流して幸せを作り出す」その1
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月26日16:45
今日の午後、秋晴れのなか、「ハピネス・チャージ」と題したボランティア活動を1・2年生全員が行いました。(3年生は受験勉強。)
本校初の試みで、企画したのは生徒会です。
南木曽町の方々から「若者の力を借りたい」という要望をたくさん出していただきました。その要望に対して生徒会執行部が必要な人員を割り当て、作業内容の打ち合わせをしたうえで主体的な活動として取り組みました。
たとえば、田立地区にある木曽あすなろ荘では、外回りの側溝の落ち葉や泥をかきだし、庭を徹底的にきれいにしました。感染状況は落ち着いているとはいえコロナ禍が続いている中で、高齢者施設のために高校生がボランティア活動をできたのは、貴重な経験でした。
妻籠宿では、あちこちの建物の清掃を行いました。外壁や畳などを生徒がきれいにふき取りました。歴史的な建造物の外回りのクモの巣も、細心の注意を払いながら除去しました。日本遺産の保存を支えるボランティアができました。
作業をしている生徒たちに私が「がんばってね」と声をかけると、たいてい「まかしてください」という元気のよい返事がかえってきます。
頼もしい若者たちの姿がそこにはありました。(つづく)

本校初の試みで、企画したのは生徒会です。
南木曽町の方々から「若者の力を借りたい」という要望をたくさん出していただきました。その要望に対して生徒会執行部が必要な人員を割り当て、作業内容の打ち合わせをしたうえで主体的な活動として取り組みました。
たとえば、田立地区にある木曽あすなろ荘では、外回りの側溝の落ち葉や泥をかきだし、庭を徹底的にきれいにしました。感染状況は落ち着いているとはいえコロナ禍が続いている中で、高齢者施設のために高校生がボランティア活動をできたのは、貴重な経験でした。
妻籠宿では、あちこちの建物の清掃を行いました。外壁や畳などを生徒がきれいにふき取りました。歴史的な建造物の外回りのクモの巣も、細心の注意を払いながら除去しました。日本遺産の保存を支えるボランティアができました。
作業をしている生徒たちに私が「がんばってね」と声をかけると、たいてい「まかしてください」という元気のよい返事がかえってきます。
頼もしい若者たちの姿がそこにはありました。(つづく)
「遠い世界と自分の足元」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月25日17:43
この土日は、765ページという圧倒的な分量の杉原薫『世界史のなかの東アジアの奇跡』(名古屋大学出版会、2020年)を読みました。(半分は好奇心、半分は抱えている執筆のため。)
世界史を国別の歴史の集合体(各国史)として見るのではなく、その時代の横断的なつながりの歴史としてとらえる「グローバル・ヒストリー」が、近年、さまざまに試みられています。杉原さんのこの大著は、その一つの金字塔です。
経済発展には、西ヨーロッパで始まった「産業革命経路」と東アジアで発展した「勤勉革命経路」の二つがあり、20世紀の後半から後者の東アジア型発展経路が、世界経済において大きな役割を果たすようになったと、本書は大きな見取り図を描きます。
同時に、東アジア型発展経路が「東アジアの奇跡」を実現したというサクセス・ストーリーだけになっていない点も、本書の魅力です。
たとえば、日本の高度成長期を通じて形成された国際経済のつながりは、日本が中東諸国から原油を輸入し、その日本の貿易赤字を、欧米諸国に工業品を輸出することで解消するものでした。それに対して中東諸国の貿易黒字は、欧米諸国から武器と工業品を輸入することに利用され、ここに日本・欧米諸国・中東諸国が緊密につながる「オイル・トライアングル」が形成されたと杉原さんは分析します。「欧米諸国の対中東諸国への兵器輸出と日本との間には構造的なリンケージが存在した」という分析です。
遠い世界(たとえば中東の出来事)が自分の足元とつながっています。大きな世界のつながりのなかで自分の立っている地点を見つめることの大切さを改めて感じた読書経験でした。
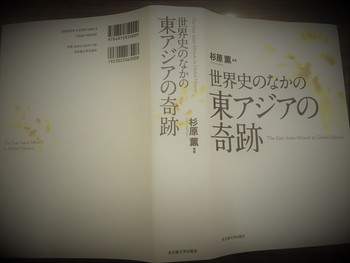
世界史を国別の歴史の集合体(各国史)として見るのではなく、その時代の横断的なつながりの歴史としてとらえる「グローバル・ヒストリー」が、近年、さまざまに試みられています。杉原さんのこの大著は、その一つの金字塔です。
経済発展には、西ヨーロッパで始まった「産業革命経路」と東アジアで発展した「勤勉革命経路」の二つがあり、20世紀の後半から後者の東アジア型発展経路が、世界経済において大きな役割を果たすようになったと、本書は大きな見取り図を描きます。
同時に、東アジア型発展経路が「東アジアの奇跡」を実現したというサクセス・ストーリーだけになっていない点も、本書の魅力です。
たとえば、日本の高度成長期を通じて形成された国際経済のつながりは、日本が中東諸国から原油を輸入し、その日本の貿易赤字を、欧米諸国に工業品を輸出することで解消するものでした。それに対して中東諸国の貿易黒字は、欧米諸国から武器と工業品を輸入することに利用され、ここに日本・欧米諸国・中東諸国が緊密につながる「オイル・トライアングル」が形成されたと杉原さんは分析します。「欧米諸国の対中東諸国への兵器輸出と日本との間には構造的なリンケージが存在した」という分析です。
遠い世界(たとえば中東の出来事)が自分の足元とつながっています。大きな世界のつながりのなかで自分の立っている地点を見つめることの大切さを改めて感じた読書経験でした。
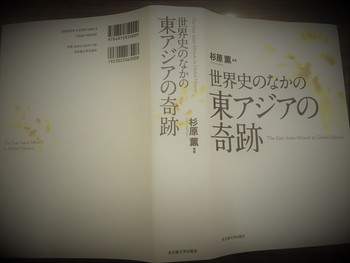
「長崎の原爆の記憶と対話をする」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月21日18:37
今日は、2年生の長崎修学旅行のために事前学習を行いました。
まずは、校長による「30分でおさらいする日本近代史」。中学で学んだ知識をもとに「なぜ列強は植民地支配を進めたのか」「なぜ戦争の呼称が“事変”になったのか」「なぜ日本はアメリカに宣戦布告したのか」「なぜ広島と長崎に原爆が落とされたのか」を考えました。すべての「なぜ」が実は一続きにつながっています。
そして長崎からお招きした田平由布子さんに「長崎原爆交流者証言講話」をしていただきました。
生存するヒバクシャが少なくなる中で、若い世代がヒバク体験を継承して高校生に伝える活動をしています。
田平さんもそのおひとりで、享年77歳でお亡くなりになった吉田勲さんの体験(記憶・生き方)を、自分のお仕事と両立させながら、語り継いでおられます。実は昨年度も田平さんは蘇南高校にお越しいただきました。
私は田平さんの講話をとても心待ちにしていました。記憶を語り継ぐということは、どのようにして可能になるのかということを、私自身が深く考える機会になるからです。
戦争経験者が少なくなっていくなかで、①映像や音声で伝えるという方法がありますが受け手が受動的な消費者になるおそれがあります。②演劇のように第三者が演じるという方法がありますが虚構と事実の境界がとても曖昧になります。
田平さんが「語り継ぎ」をしているのは、①でも②でもありません。吉田さんの記憶に懸命に手を伸ばそうとし、その記憶と対話をしている田平さんご自身のことが、私たちの心に刻印づけられながら、吉田さんの記憶が語られるのです。つまり、田平さんと私たちが、ともに吉田さんの記憶に手を伸ばそうとする「対話空間」になる。
――③第三者が記憶を守り、対話をしようとする空間を共有して、聞き手も対話に参加する。
そんな「語り継ぎ」の方法であると言えましょう。
田平さんが試行錯誤していることを、私があえて理論化してみました。
今年も生徒たちが夢中になって「ことば」を聞き、考え、心を動かし、田平さんに語りかけていました。

まずは、校長による「30分でおさらいする日本近代史」。中学で学んだ知識をもとに「なぜ列強は植民地支配を進めたのか」「なぜ戦争の呼称が“事変”になったのか」「なぜ日本はアメリカに宣戦布告したのか」「なぜ広島と長崎に原爆が落とされたのか」を考えました。すべての「なぜ」が実は一続きにつながっています。
そして長崎からお招きした田平由布子さんに「長崎原爆交流者証言講話」をしていただきました。
生存するヒバクシャが少なくなる中で、若い世代がヒバク体験を継承して高校生に伝える活動をしています。
田平さんもそのおひとりで、享年77歳でお亡くなりになった吉田勲さんの体験(記憶・生き方)を、自分のお仕事と両立させながら、語り継いでおられます。実は昨年度も田平さんは蘇南高校にお越しいただきました。
私は田平さんの講話をとても心待ちにしていました。記憶を語り継ぐということは、どのようにして可能になるのかということを、私自身が深く考える機会になるからです。
戦争経験者が少なくなっていくなかで、①映像や音声で伝えるという方法がありますが受け手が受動的な消費者になるおそれがあります。②演劇のように第三者が演じるという方法がありますが虚構と事実の境界がとても曖昧になります。
田平さんが「語り継ぎ」をしているのは、①でも②でもありません。吉田さんの記憶に懸命に手を伸ばそうとし、その記憶と対話をしている田平さんご自身のことが、私たちの心に刻印づけられながら、吉田さんの記憶が語られるのです。つまり、田平さんと私たちが、ともに吉田さんの記憶に手を伸ばそうとする「対話空間」になる。
――③第三者が記憶を守り、対話をしようとする空間を共有して、聞き手も対話に参加する。
そんな「語り継ぎ」の方法であると言えましょう。
田平さんが試行錯誤していることを、私があえて理論化してみました。
今年も生徒たちが夢中になって「ことば」を聞き、考え、心を動かし、田平さんに語りかけていました。
「先生と生徒の歌声と演奏がスマイルを届ける」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月20日18:46
今日は、体育館でミニコンサートを全校で鑑賞しました。
合唱コンクールを夏休み明けのコロナ第5波のために中止にせざるをえなかったので、「100を0にしない」という本校の方針のもと、代替企画として実施したものです。
まずは音楽担当の原先生が登場して「オ・ソレ・ミオ」を独唱。声楽が専門の原先生が、イタリアのカンツォーネを披露してくれ、その歌声に生徒たちは驚嘆していました。
ついでコロナ禍のために発表の機会がなくなってしまっていた音楽部の生徒たちが、練習の成果を次々と披露してくれました。テーマは「恋」。それぞれの曲がストーリーのようにつながっていて、コンサートの構成にも生徒たちが細やかな工夫をしてくれたことがわかります。全校の生徒が手拍子をしたりして、音楽部の生徒と心を一つにしてコンサートを楽しみました。
アンコールの声に、生徒たちが「スマイル」を歌ってくれました。
「すぐスマイルするべきだ/子供じゃないからね」というフレーズが体育館に響いて、コンサートは幕を閉じました。
音楽部の皆さん、原先生、素敵なコンサートを本当にありがとうございました。
合唱コンクールを夏休み明けのコロナ第5波のために中止にせざるをえなかったので、「100を0にしない」という本校の方針のもと、代替企画として実施したものです。
まずは音楽担当の原先生が登場して「オ・ソレ・ミオ」を独唱。声楽が専門の原先生が、イタリアのカンツォーネを披露してくれ、その歌声に生徒たちは驚嘆していました。
ついでコロナ禍のために発表の機会がなくなってしまっていた音楽部の生徒たちが、練習の成果を次々と披露してくれました。テーマは「恋」。それぞれの曲がストーリーのようにつながっていて、コンサートの構成にも生徒たちが細やかな工夫をしてくれたことがわかります。全校の生徒が手拍子をしたりして、音楽部の生徒と心を一つにしてコンサートを楽しみました。
アンコールの声に、生徒たちが「スマイル」を歌ってくれました。
「すぐスマイルするべきだ/子供じゃないからね」というフレーズが体育館に響いて、コンサートは幕を閉じました。
音楽部の皆さん、原先生、素敵なコンサートを本当にありがとうございました。
「文化財としての郷土食を未来に伝える」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月19日14:15
今日は、2年生の選択講座「フードデザイン」(半場先生)の授業で、木曽福祉保健事務所と連携した郷土食の学習「食の支援講座」を行いました。
この木曽地域は、それぞれの地区に昔から伝わる独自な料理・食材の種類がとても豊かです。この地域でしか味わえないような料理もたくさんあります。
こうした料理は、美術品や舞台芸術とならぶ「文化財」だと私は考えます。この文化財は、大勢の若者が実際に作ってみることで、その魅力を知り、自らも作り手となることで、未来に継承されていくものです。
今日は、河野さん、矢澤さん、麦島さんという地域の大人の皆さんから、本校生徒が、荏胡麻の白和えとか、けんちん汁、芋のころ煮を教えていただきました。芋は、本当は、南木曽の蘭(あららぎ)地区に伝わる在来種を使うのですが、今回はシーズン外なので、じゃがいもで代用しました。
私も試食させていただきましたが、一言で言えば、料亭の味。上品で野菜のうまみがとてもよく引き出されています。祖先からずっと引き継がれてきた郷土食には、ひとびとの知恵が「味」の形で凝縮しているのです。
「やってみると自分でもできるとわかった」「自分の家の味と違うのだけれども、この味付けもいい」といった感想を、生徒はリフレクションで語り合ったのでした。
私からは、「これ、文化財だよ」とメッセージ。
追伸
講師のひとり矢澤さんが、「若い先生たちにも郷土食を知ってほしいから」と、南木曽ならではの料理を届けてくださいました。
「からすみ」:南木曽では米粉で作る桃の節句のお菓子のことなのです。絶品。
「あかたつの漬物」:いもの茎の漬物。これがまた爽快な食感と味。いもは素揚げにして活用。
「そばいなり」:揚げのなかにそばを入れて、カラフルに飾る。とても華やか。
ここでしか食べられない文化財なのです。とてもおいしかったです。ごちそうさまでした。

この木曽地域は、それぞれの地区に昔から伝わる独自な料理・食材の種類がとても豊かです。この地域でしか味わえないような料理もたくさんあります。
こうした料理は、美術品や舞台芸術とならぶ「文化財」だと私は考えます。この文化財は、大勢の若者が実際に作ってみることで、その魅力を知り、自らも作り手となることで、未来に継承されていくものです。
今日は、河野さん、矢澤さん、麦島さんという地域の大人の皆さんから、本校生徒が、荏胡麻の白和えとか、けんちん汁、芋のころ煮を教えていただきました。芋は、本当は、南木曽の蘭(あららぎ)地区に伝わる在来種を使うのですが、今回はシーズン外なので、じゃがいもで代用しました。
私も試食させていただきましたが、一言で言えば、料亭の味。上品で野菜のうまみがとてもよく引き出されています。祖先からずっと引き継がれてきた郷土食には、ひとびとの知恵が「味」の形で凝縮しているのです。
「やってみると自分でもできるとわかった」「自分の家の味と違うのだけれども、この味付けもいい」といった感想を、生徒はリフレクションで語り合ったのでした。
私からは、「これ、文化財だよ」とメッセージ。
追伸
講師のひとり矢澤さんが、「若い先生たちにも郷土食を知ってほしいから」と、南木曽ならではの料理を届けてくださいました。
「からすみ」:南木曽では米粉で作る桃の節句のお菓子のことなのです。絶品。
「あかたつの漬物」:いもの茎の漬物。これがまた爽快な食感と味。いもは素揚げにして活用。
「そばいなり」:揚げのなかにそばを入れて、カラフルに飾る。とても華やか。
ここでしか食べられない文化財なのです。とてもおいしかったです。ごちそうさまでした。
「経営ビジネス系列の生徒たちが商品開発に取り組む」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月18日16:05
3年の「経営ビジネス系列」には、「商品開発」と「広告と販売促進」という科目があり、これを選択した生徒たちが、担当の久保田先生の指導の下で文字通り商品開発に取り組んでいます。
今年度は、南木曽駅前の老舗の菓子店である蔦屋さんの全面的なご支援をいただき、木曽谷南部の特産品を活用して、若い購買層を獲得するような和菓子の商品開発に取り組んでいます。
原料の選定から調理方法の開発、パッケージの制作までを一貫して実践してみるのです。
このほど、生徒たちが試作品を示しながら商品開発計画を発表する中間報告会を開催しました。審査員は、蔦屋さんのご夫婦です。
荏胡麻を用いた最中であるとか、五幣餅と和菓子のコラボであるとか、生徒が考案した製品が発表され、蔦屋さんが和菓子職人として長年培ってきた知見をもとに、生徒の思いもよらないことを次々と指摘して教えてくださります。
地域の大人が持っている知恵が、いかに深いものかを生徒が実感する機会となりました。まさに地域に生きる方々が「先生」なのです。
生徒たちはこれから企画をさらに練り直し、パッケージの制作を行い、蔦屋さんに製造・販売していただけることを目指します。

今年度は、南木曽駅前の老舗の菓子店である蔦屋さんの全面的なご支援をいただき、木曽谷南部の特産品を活用して、若い購買層を獲得するような和菓子の商品開発に取り組んでいます。
原料の選定から調理方法の開発、パッケージの制作までを一貫して実践してみるのです。
このほど、生徒たちが試作品を示しながら商品開発計画を発表する中間報告会を開催しました。審査員は、蔦屋さんのご夫婦です。
荏胡麻を用いた最中であるとか、五幣餅と和菓子のコラボであるとか、生徒が考案した製品が発表され、蔦屋さんが和菓子職人として長年培ってきた知見をもとに、生徒の思いもよらないことを次々と指摘して教えてくださります。
地域の大人が持っている知恵が、いかに深いものかを生徒が実感する機会となりました。まさに地域に生きる方々が「先生」なのです。
生徒たちはこれから企画をさらに練り直し、パッケージの制作を行い、蔦屋さんに製造・販売していただけることを目指します。

「新しい生徒会のスローガンは“革進”」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年10月15日15:17
昨日、生徒総会が体育館で行われ、3年生から1・2年生へ生徒会体制の引継ぎが正式になされました。
新生徒会長の上野さんから次のような「施政方針演説」がなされました。
①新しいスローガンは「革進」とする。生徒が主体的に発言し、よりよい学校にするために改革を進めていこう。そのためには、ひとりひとりの当事者意識が大切である。
②生徒がボランティアなどで地域社会に出向き、地域の皆さんとのつながりを一層築こう。
③生徒の意見がさまざまなところで反映していくように、意見集約の方法を工夫していきたい。
折しも国政選挙の時期なのですが、蘇南高校生徒会は明確な方針をかかげることになりました。聞いていた3年生からは、「ボランティアの計画はどのように構想しているのか」など、鋭い質問が出され、生徒会執行部が丁寧に答弁をしていました。
最後に私からは、引退する3年生執行部が「ファミリー」を方針に掲げてコロナ禍を乗り越えてきたことへの感謝の言葉を述べました。
蘇南高校の次の新しい時代が、始まりました。

新生徒会長の上野さんから次のような「施政方針演説」がなされました。
①新しいスローガンは「革進」とする。生徒が主体的に発言し、よりよい学校にするために改革を進めていこう。そのためには、ひとりひとりの当事者意識が大切である。
②生徒がボランティアなどで地域社会に出向き、地域の皆さんとのつながりを一層築こう。
③生徒の意見がさまざまなところで反映していくように、意見集約の方法を工夫していきたい。
折しも国政選挙の時期なのですが、蘇南高校生徒会は明確な方針をかかげることになりました。聞いていた3年生からは、「ボランティアの計画はどのように構想しているのか」など、鋭い質問が出され、生徒会執行部が丁寧に答弁をしていました。
最後に私からは、引退する3年生執行部が「ファミリー」を方針に掲げてコロナ禍を乗り越えてきたことへの感謝の言葉を述べました。
蘇南高校の次の新しい時代が、始まりました。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長



