「さらにここまでできるということに出会う喜び」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月30日19:35
今日は、2年の経営ビジネス系列の「商品開発」という授業のまとめがありました。これは本当にワクワクする学びでした。
「商品開発」の受講生徒は、これまで「木曽・中津川の特産品をいかしたヴィーガン向け商品を開発する」という共通テーマのもと、開発コンセプトを練り上げ、試作品を作り、それを検討の結果を経て作り直して、最終プレゼンテーションを行いました。
今日の「まとめ」の授業は、その最終プレゼンテーションの講師をつとめていただいた、専門学校未来ビジネスカレッジ・パティシエ・ブーランジェ学科長の古川博徳先生が、3つの優秀企画を選び、その内容を専門学校の教え子の皆さんと試作・検討しながら改良し、「これだったら市場化できるのではないか」というレベルに完成させて、実物を見ながら講義をしてくださったのです。
生徒も私も、プロの指導はこのようなレベルなのかと感嘆しながら、授業を受けました。
たとえば、採用された企画のひとつに「栗のタルト」(生徒の命名はマロマロンタルト)があったのですが、グルテンフリーとか卵・牛乳がNGという条件のもと、米粉とか栗のペーストを使っていたために、味はともかく、固いという難点がありました。そこで古川さんと教え子の皆さんは、米粉に長芋とおからを加え、栗には寒天を加えてみたというのです。そうすることで、外国人観光客に「和」をさらに強調する商品になれたし、予想外の結果としてアレルギー体質の方にも食べていただける商品になる可能性が出てきたのでした。
他に今日の授業で取り上げていただいたのは、「そばろーる」「あいすぼー わっふる」「柿其味噌ドレッシング」です。講義のあと、古川先生と教え子の皆さんに作っていただいた、グレードアップした商品を全員で(私も!)試食をしました。知的な喜びと食の楽しさをともに味わうぜいたくなひとときです。
今日のあらためての私の発見は、生徒が精一杯作りあげた探究の成果を、上級学校の方々がバトンを受け取って「さらにここまでできる」というその先を見せてくれる学びは本当に素晴らしいということでした。学びの成果の未来の可能性まで知ることができるのですから。
専門学校未来ビジネスカレッジの古川先生、そして田中校長先生、教え子の皆さん、ご指導をいただき、本当にありがとうございました。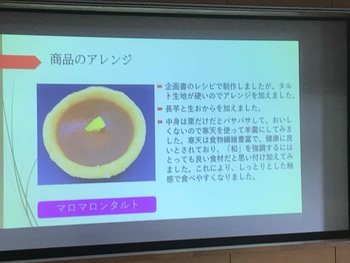
「商品開発」の受講生徒は、これまで「木曽・中津川の特産品をいかしたヴィーガン向け商品を開発する」という共通テーマのもと、開発コンセプトを練り上げ、試作品を作り、それを検討の結果を経て作り直して、最終プレゼンテーションを行いました。
今日の「まとめ」の授業は、その最終プレゼンテーションの講師をつとめていただいた、専門学校未来ビジネスカレッジ・パティシエ・ブーランジェ学科長の古川博徳先生が、3つの優秀企画を選び、その内容を専門学校の教え子の皆さんと試作・検討しながら改良し、「これだったら市場化できるのではないか」というレベルに完成させて、実物を見ながら講義をしてくださったのです。
生徒も私も、プロの指導はこのようなレベルなのかと感嘆しながら、授業を受けました。
たとえば、採用された企画のひとつに「栗のタルト」(生徒の命名はマロマロンタルト)があったのですが、グルテンフリーとか卵・牛乳がNGという条件のもと、米粉とか栗のペーストを使っていたために、味はともかく、固いという難点がありました。そこで古川さんと教え子の皆さんは、米粉に長芋とおからを加え、栗には寒天を加えてみたというのです。そうすることで、外国人観光客に「和」をさらに強調する商品になれたし、予想外の結果としてアレルギー体質の方にも食べていただける商品になる可能性が出てきたのでした。
他に今日の授業で取り上げていただいたのは、「そばろーる」「あいすぼー わっふる」「柿其味噌ドレッシング」です。講義のあと、古川先生と教え子の皆さんに作っていただいた、グレードアップした商品を全員で(私も!)試食をしました。知的な喜びと食の楽しさをともに味わうぜいたくなひとときです。
今日のあらためての私の発見は、生徒が精一杯作りあげた探究の成果を、上級学校の方々がバトンを受け取って「さらにここまでできる」というその先を見せてくれる学びは本当に素晴らしいということでした。学びの成果の未来の可能性まで知ることができるのですから。
専門学校未来ビジネスカレッジの古川先生、そして田中校長先生、教え子の皆さん、ご指導をいただき、本当にありがとうございました。
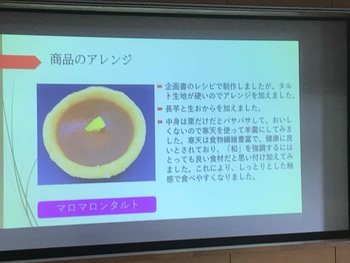
「3年総合研究発表会の2次予選をおこなう」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月27日20:53
今日は、3年生が「総合研究」(週3時間)の授業で取り組んできた課題研究の成果を発表し合う2次予選会でした。
1次予選には3年生全員が参加し、その中から選抜された9作品が2次予選会に進んだのです。力作ぞろいのなかで9作品を選ぶのは、なかなか大変でしたが、生徒の投票と教員の投票をもとに、選考委員会で厳正に審査をした結果です。この中から4作品がさらに選抜されて、12月11日(金)の課題研究発表会(本選)にのぞみます。
実は、今日はどうしても出席しなければならない対面の会議があって長野市に出張だったので、私が2次予選会を見るのは、月曜日になります。録画されたものをきちんと見る予定です。(今日の写真は、予選会のものがないので、帰り道の姨捨(おばすて)PAからの善光寺平の夜景です。きれいでした。)
2次予選に参加する9組の生徒たち全員に、1次予選の発表を受けての改善点について、校長面談をおこなってアドバイスしてあります。共通している点は、次のようなことでした。
(1)冒頭の問題設定(仮説)と末尾の考察(検証結果)が、じゅうぶん対応していないので、これを考え直すこと。
(2)考察の社会的意義を多角的に深めていくこと。
(3)参照、引用したものについて出典を明らかにするとともに、オリジナルに作成したものについてはそのプロセスをもっと明らかにすること。
(4)検証が不十分な点があるので、再検証をすること。(条件設定を厳密にして検証をすること。)
(5)全国で同じような実践がないかを調査し、自分の独創性が唯一無二なのか確認すること。
(6)人の心をつかまえる表現・文体を目指すこと。
(7)あなたの研究成果は実に面白い!
以上です。(7)を除いて、まさに今、自分が必死の思いで書いている研究論文にもあてはまることであり、自分が苦しみながら取り組んでいるからこそ、生徒に実感を込めてアドバイスをしたくなるのです。
さあ、生徒たちがどのように伸びてくれたのかを楽しみにしつつ、週明けに録画を再生してみたいと思っています。

1次予選には3年生全員が参加し、その中から選抜された9作品が2次予選会に進んだのです。力作ぞろいのなかで9作品を選ぶのは、なかなか大変でしたが、生徒の投票と教員の投票をもとに、選考委員会で厳正に審査をした結果です。この中から4作品がさらに選抜されて、12月11日(金)の課題研究発表会(本選)にのぞみます。
実は、今日はどうしても出席しなければならない対面の会議があって長野市に出張だったので、私が2次予選会を見るのは、月曜日になります。録画されたものをきちんと見る予定です。(今日の写真は、予選会のものがないので、帰り道の姨捨(おばすて)PAからの善光寺平の夜景です。きれいでした。)
2次予選に参加する9組の生徒たち全員に、1次予選の発表を受けての改善点について、校長面談をおこなってアドバイスしてあります。共通している点は、次のようなことでした。
(1)冒頭の問題設定(仮説)と末尾の考察(検証結果)が、じゅうぶん対応していないので、これを考え直すこと。
(2)考察の社会的意義を多角的に深めていくこと。
(3)参照、引用したものについて出典を明らかにするとともに、オリジナルに作成したものについてはそのプロセスをもっと明らかにすること。
(4)検証が不十分な点があるので、再検証をすること。(条件設定を厳密にして検証をすること。)
(5)全国で同じような実践がないかを調査し、自分の独創性が唯一無二なのか確認すること。
(6)人の心をつかまえる表現・文体を目指すこと。
(7)あなたの研究成果は実に面白い!
以上です。(7)を除いて、まさに今、自分が必死の思いで書いている研究論文にもあてはまることであり、自分が苦しみながら取り組んでいるからこそ、生徒に実感を込めてアドバイスをしたくなるのです。
さあ、生徒たちがどのように伸びてくれたのかを楽しみにしつつ、週明けに録画を再生してみたいと思っています。

「南木曽町観光協会にモニュメントを寄贈する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月26日20:34
コロナ臨時休校や集中豪雨を乗り越えて、7月中旬に蘇峡祭(文化祭)を生徒がやりとげたとき、生徒たちは「苦しい時に自分たちだけが楽しむという姿勢ではなく、みんなで力を合わせて南木曽町に貢献できるモニュメントを作ろう」と話し合い、巨大パズル型のモニュメント観光案内板を作成しました。
ダンボール紙を切り出して組み立てて、そこに南木曽町の代表的な観光名所を描きこみ、開祭式で披露しました。その後、生徒会執行部の代替わりがあり、新しいメンバーで不十分だったところを手直しし、このほど完成したのです。
今日、軽トラック3台に積載したパズルのピースを妻籠宿の南木曽町観光協会に運び、贈呈式を行いました。生徒会長の澤渡さんと副会長の藤本さんから樋口事務局長さん(本校同窓会長でもあります)にモニュメントを受け取っていただき、励ましの言葉をいただきました。澤渡さんは、試行錯誤を重ねて苦労して作ったものであり、文化祭を通じて社会貢献がしたかったとの思いをあいさつのなかで語りました。
ところが…! 深刻なトラブルが発生。モニュメントが収まるはずだった観光協会の建物の天井につかえてしまったのです。やむなく玄関先に組み立てて記念撮影をし、建物の中では分解した状態でとりあえず展示することとしました。時を見て、上下の部分をカットして寸法を縮める作業をするかなどを検討していきます。
学校のなかでは普通のサイズだと思っていたのですが、学校の外の空間に出ると、結構大きなものを作ったのだと、自分たちのやったことをあらためて認識できました。
とまれ、この夏の生徒たちの努力の結晶が、妻籠宿のまんなかで輝くことを祈りたいと思います。

ダンボール紙を切り出して組み立てて、そこに南木曽町の代表的な観光名所を描きこみ、開祭式で披露しました。その後、生徒会執行部の代替わりがあり、新しいメンバーで不十分だったところを手直しし、このほど完成したのです。
今日、軽トラック3台に積載したパズルのピースを妻籠宿の南木曽町観光協会に運び、贈呈式を行いました。生徒会長の澤渡さんと副会長の藤本さんから樋口事務局長さん(本校同窓会長でもあります)にモニュメントを受け取っていただき、励ましの言葉をいただきました。澤渡さんは、試行錯誤を重ねて苦労して作ったものであり、文化祭を通じて社会貢献がしたかったとの思いをあいさつのなかで語りました。
ところが…! 深刻なトラブルが発生。モニュメントが収まるはずだった観光協会の建物の天井につかえてしまったのです。やむなく玄関先に組み立てて記念撮影をし、建物の中では分解した状態でとりあえず展示することとしました。時を見て、上下の部分をカットして寸法を縮める作業をするかなどを検討していきます。
学校のなかでは普通のサイズだと思っていたのですが、学校の外の空間に出ると、結構大きなものを作ったのだと、自分たちのやったことをあらためて認識できました。
とまれ、この夏の生徒たちの努力の結晶が、妻籠宿のまんなかで輝くことを祈りたいと思います。

「ヒノキの節の美しさを味わう」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月25日20:31
今日は、本校のOBで英語の非常勤講師をおつとめいただいたこともある林俊男さんが来校され、コミュニティと高校の連携の在り方とか、地域の魅力をいかした英語の学習方法など、さまざまなことを意見交換しました。アメリカでお仕事をされてきた林さんならではの知見を伺いました。(記念写真のときだけマスクを外しています。)
そして、なんと、林さんの制作した「檜節(ひぶし)アート」の作品を3点、寄贈していただきました。林さん、本当にありがとうございます。
校長室や玄関ロビーなどに、南木曽ならではの木曽五木にかかわるものがほしいと思っていたところだったのです。実は私の二人の祖父は林業と桶製造業にそれぞれ携わっていました。樹木に私が憧れるのは、昔、私の家の居間には、いつも樹木の香りがあったからなのだと思います。(幼少の頃の私は、祖父の手に刺さった樹木の棘を抜くことが日課でした。)
「檜節(ひぶし)アート」とは、建築材としては歓迎されない、ヒノキの節をむしろ積極的にいかしてプレートに切り出し、そこに手書きの漢字をのせ、さらに島崎藤村や宮沢賢治の「ことば」を彼らの「筆跡」とともにプリントするアートです。藤村も賢治もとても味わいのある字を書きますから、実にヒノキの表面に映えます。
そして何といってもヒノキの節の美しいこと!
「生命の混沌」とも言うべき渦巻きから、木曽のヒノキならではの密度の濃い年輪が流れるように放射されていきます。その一すじ一すじを見つめて、見飽きません。まるで大宇宙の銀河系のすがたを見ているかのよう。その節から年輪が流れ出すところに、「郷」(ふるさと)、「凛」(りん)などの文字が刻まれています。
もちろんヒノキの透き通るような香りも漂います。時間のたつのを忘れてヒノキの年輪と描かれた文字を見つめては、木曽のヒノキの「声」を聞いているような気がしたのでした。
樹木に満ちあふれたふるさとって、すばらしいですよね。

そして、なんと、林さんの制作した「檜節(ひぶし)アート」の作品を3点、寄贈していただきました。林さん、本当にありがとうございます。
校長室や玄関ロビーなどに、南木曽ならではの木曽五木にかかわるものがほしいと思っていたところだったのです。実は私の二人の祖父は林業と桶製造業にそれぞれ携わっていました。樹木に私が憧れるのは、昔、私の家の居間には、いつも樹木の香りがあったからなのだと思います。(幼少の頃の私は、祖父の手に刺さった樹木の棘を抜くことが日課でした。)
「檜節(ひぶし)アート」とは、建築材としては歓迎されない、ヒノキの節をむしろ積極的にいかしてプレートに切り出し、そこに手書きの漢字をのせ、さらに島崎藤村や宮沢賢治の「ことば」を彼らの「筆跡」とともにプリントするアートです。藤村も賢治もとても味わいのある字を書きますから、実にヒノキの表面に映えます。
そして何といってもヒノキの節の美しいこと!
「生命の混沌」とも言うべき渦巻きから、木曽のヒノキならではの密度の濃い年輪が流れるように放射されていきます。その一すじ一すじを見つめて、見飽きません。まるで大宇宙の銀河系のすがたを見ているかのよう。その節から年輪が流れ出すところに、「郷」(ふるさと)、「凛」(りん)などの文字が刻まれています。
もちろんヒノキの透き通るような香りも漂います。時間のたつのを忘れてヒノキの年輪と描かれた文字を見つめては、木曽のヒノキの「声」を聞いているような気がしたのでした。
樹木に満ちあふれたふるさとって、すばらしいですよね。

「教え子にバトンを渡す」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月22日19:26
出版社の編集者や研究者の方々から「東大の教養学部報に名前が出ていたよ」と最近よくメールをいただいています。
東大教養学部で哲学を研究している藤岡俊博さんが、同僚たちの書いた『東大連続講義・歴史学の思考法』(東京大学出版会)の書評の中で、私との思い出を書いているのです。藤岡さんは手紙を添えて、教養学部報を私に送ってくれました。そのくだりを引用します。
「最後に粗末な個人史に触れるのをお許しいただきたい。二十年前、文科三類に入学した当初の私は、高校の恩師である小川幸司先生に憧れ(先生は現在、長野県蘇南高等学校長で、歴史教育に関して積極的に発言されている)、西洋史学科への進学を考えていた。が、当時は歴史教科書をめぐる喧騒の真っ只中で、自己の顕揚と他者の軽視のために歴史を利用するひとたちを前に、私は歴史学に携わる気概をついにもてなかった。本書を通じて歴史学の思考法を学んでいたら、そして本書に示される先生方の「歴史への真摯さ」に接していれば、進路は違っていたのだろうか。歴史の食卓に「鱈・レバー」は並ばないと言うが、本書は私に、自分に訪れなかった過去を、別の誰かの未来として夢想する喜びを与えてくれる。」
出会った教え子はみんなが大切なことは言うまでもありませんが、誰かが歴史学を研究する人になってほしいという願いが、私にもないわけではありません。高校という学び舎の中で、対立する歴史認識の中で言説の正しさの根拠になりうるものはあるのかなど、多くのことを真摯に語り合った教え子が、藤岡さんでした。
西洋史学科に進まなかった藤岡さんは、レヴィナスの哲学についての優れた研究書を出版し、先ごろレヴィナスの主著『全体性と無限』の個人訳(レヴィナスの息遣いが聞こえるような素晴らしい訳!)を世に問いました。私自身の歴史研究の根底をなす「他者とはどのような存在なのか」という問いに、藤岡さんは「応答」を投げかけてくれます。教え子にバトンを渡すということは、同じ道に進むということではなくて、教え子が自分の先生になっていくことなのだと思います。
藤岡さんの書評の結びを、少し改作して私の思いを表現しますね。
「歴史の食卓に「鱈・レバー」は並ばないと言うが、「教え子」は私に、自分に訪れなかった過去を、別の誰かの未来として夢想する喜びを与えてくれる。」

東大教養学部で哲学を研究している藤岡俊博さんが、同僚たちの書いた『東大連続講義・歴史学の思考法』(東京大学出版会)の書評の中で、私との思い出を書いているのです。藤岡さんは手紙を添えて、教養学部報を私に送ってくれました。そのくだりを引用します。
「最後に粗末な個人史に触れるのをお許しいただきたい。二十年前、文科三類に入学した当初の私は、高校の恩師である小川幸司先生に憧れ(先生は現在、長野県蘇南高等学校長で、歴史教育に関して積極的に発言されている)、西洋史学科への進学を考えていた。が、当時は歴史教科書をめぐる喧騒の真っ只中で、自己の顕揚と他者の軽視のために歴史を利用するひとたちを前に、私は歴史学に携わる気概をついにもてなかった。本書を通じて歴史学の思考法を学んでいたら、そして本書に示される先生方の「歴史への真摯さ」に接していれば、進路は違っていたのだろうか。歴史の食卓に「鱈・レバー」は並ばないと言うが、本書は私に、自分に訪れなかった過去を、別の誰かの未来として夢想する喜びを与えてくれる。」
出会った教え子はみんなが大切なことは言うまでもありませんが、誰かが歴史学を研究する人になってほしいという願いが、私にもないわけではありません。高校という学び舎の中で、対立する歴史認識の中で言説の正しさの根拠になりうるものはあるのかなど、多くのことを真摯に語り合った教え子が、藤岡さんでした。
西洋史学科に進まなかった藤岡さんは、レヴィナスの哲学についての優れた研究書を出版し、先ごろレヴィナスの主著『全体性と無限』の個人訳(レヴィナスの息遣いが聞こえるような素晴らしい訳!)を世に問いました。私自身の歴史研究の根底をなす「他者とはどのような存在なのか」という問いに、藤岡さんは「応答」を投げかけてくれます。教え子にバトンを渡すということは、同じ道に進むということではなくて、教え子が自分の先生になっていくことなのだと思います。
藤岡さんの書評の結びを、少し改作して私の思いを表現しますね。
「歴史の食卓に「鱈・レバー」は並ばないと言うが、「教え子」は私に、自分に訪れなかった過去を、別の誰かの未来として夢想する喜びを与えてくれる。」

「枝分かれするような夢をもつ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月19日20:08
2年生は修学旅行が無事に終わり、いよいよ3年生に向けて自分のキャリアデザインを深めていく時期になってきました。そのスタートラインの意識付けとして、今日の6限の「産業社会と人間」の授業で私が講話をしました。
「どんな職業につきたいのか」を早めに決めることが、努力をいち早く重ねられることになるから望ましいという、学校現場でよく見られる発想は、一面では真理かもしれないけれども、他面では間違っていると私は考えています。人生の夢や目標は単一でもないし、不変でもない。
私自身のキャリアデザインの軌跡を振り返りながら、次のようなことを生徒に問題提起しました。
(1)「枝分かれするような夢」をもとう。それは「大きな夢」(生きる方針)と「具体的な夢」から構成される。たとえば、「世界とつながる・世界の文化を楽しむ」という「大きな夢」があって、それを実現するために、研究者・アナウンサー・映画評論家・高校教員・作家などの「具体的な夢」がある。つまり、「大きな夢」を持っていると、「具体的な夢」が豊かになっていく。
(2)3段階で夢を語れるようになろう。
①まず、高校時代の学びのプロセスを語る。
➁次に、その結果、身についた力を語る。
③そして、その力をつかって追いかけたい夢を語る。
具体例
〈ありがちな語り方〉私は小さい頃からお菓子作りが好きで、将来、パティシエになりたいと思っています。
〈蘇南高校の生徒に求める語り方〉私は高校の課題研究でカロリーの低いケーキは可能かということを研究し、家庭科の食物分野も一生懸命勉強したので、栄養成分とおいしさの双方を大切にする判断力が身に付きました。この力を使い、私は人々の生活の豊かさに貢献するために、女性も男性もカロリー過多を心配しないで食べられるケーキを作るパティシエになる…という夢を追いかけたい。
⇒こう語れる人は、おそらくパティシエだけでなく、食品工場で働くとか、福祉施設で働くとか、いろいろな夢が枝分かれして見えてくるはずなのです。
そんなキャリアデザインを一緒に楽しんでいこうねと、2年生に呼びかけたのでした。

「どんな職業につきたいのか」を早めに決めることが、努力をいち早く重ねられることになるから望ましいという、学校現場でよく見られる発想は、一面では真理かもしれないけれども、他面では間違っていると私は考えています。人生の夢や目標は単一でもないし、不変でもない。
私自身のキャリアデザインの軌跡を振り返りながら、次のようなことを生徒に問題提起しました。
(1)「枝分かれするような夢」をもとう。それは「大きな夢」(生きる方針)と「具体的な夢」から構成される。たとえば、「世界とつながる・世界の文化を楽しむ」という「大きな夢」があって、それを実現するために、研究者・アナウンサー・映画評論家・高校教員・作家などの「具体的な夢」がある。つまり、「大きな夢」を持っていると、「具体的な夢」が豊かになっていく。
(2)3段階で夢を語れるようになろう。
①まず、高校時代の学びのプロセスを語る。
➁次に、その結果、身についた力を語る。
③そして、その力をつかって追いかけたい夢を語る。
具体例
〈ありがちな語り方〉私は小さい頃からお菓子作りが好きで、将来、パティシエになりたいと思っています。
〈蘇南高校の生徒に求める語り方〉私は高校の課題研究でカロリーの低いケーキは可能かということを研究し、家庭科の食物分野も一生懸命勉強したので、栄養成分とおいしさの双方を大切にする判断力が身に付きました。この力を使い、私は人々の生活の豊かさに貢献するために、女性も男性もカロリー過多を心配しないで食べられるケーキを作るパティシエになる…という夢を追いかけたい。
⇒こう語れる人は、おそらくパティシエだけでなく、食品工場で働くとか、福祉施設で働くとか、いろいろな夢が枝分かれして見えてくるはずなのです。
そんなキャリアデザインを一緒に楽しんでいこうねと、2年生に呼びかけたのでした。

「生徒製作の来客用傘立てを設置する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月18日21:06
3年生の総合研究の成果報告第3弾です。
学校で末永く使用できる備品を自分たちで製作するというコンセプトで、なんと「来客用傘立て」を生徒たちが寄贈してくれたのです。拮石さん、牧野さん、原さん、徳原さんの4名が、設計からはじめて金属部品の切断・溶接・研磨を丁寧に行い、最後は塗装をして、見事な「傘立て」を仕上げました。触ったときにケガをしないように溶接部の研磨を特に注意して行ったとのこと。素敵な仕上がりの「傘立て」を早速、来客用玄関に設置しました。
大切に使わせていただきます。本当にありがとう!
自分で原材料から製品を作るとき、その製品がどのような工夫の積み重ねで成立するものなのかがよくわかります。買って使うだけでは絶対にわかりません。「ものづくり」の魅力は、「もの」自体の奥深さを知り、自分自身でもその奥深さを創造できるところになるのでしょう。
玄関の「傘立て」は、生徒のワクワク感の表現です。

学校で末永く使用できる備品を自分たちで製作するというコンセプトで、なんと「来客用傘立て」を生徒たちが寄贈してくれたのです。拮石さん、牧野さん、原さん、徳原さんの4名が、設計からはじめて金属部品の切断・溶接・研磨を丁寧に行い、最後は塗装をして、見事な「傘立て」を仕上げました。触ったときにケガをしないように溶接部の研磨を特に注意して行ったとのこと。素敵な仕上がりの「傘立て」を早速、来客用玄関に設置しました。
大切に使わせていただきます。本当にありがとう!
自分で原材料から製品を作るとき、その製品がどのような工夫の積み重ねで成立するものなのかがよくわかります。買って使うだけでは絶対にわかりません。「ものづくり」の魅力は、「もの」自体の奥深さを知り、自分自身でもその奥深さを創造できるところになるのでしょう。
玄関の「傘立て」は、生徒のワクワク感の表現です。

「失われつつある里山の恵みを新たな料理方法にいかす」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月17日17:47
3年生の総合研究が、まとめにむけて追い込みをかけています。以前はコロナ禍のなかの学習の遅れについて地域の子どもたちのサポートに取り組んでいる生徒の研究実践を紹介しましたが、他にも面白い研究が様々にあります。
かつては南木曽の地のいたるところに出会えたのに、今はほとんど見かけなくなった植物があるということを知った長岡さんは、野原や河川敷などをフィールドワークして希少植物を採取し、それを食材として活用する新たな方法を開発しようとしました。具体的には自然酵母を培養して、それをもとに新しいパンを開発するという研究です。調理室のなかに酵母を培養する彼の(一見あやしげな)壜が並び、ホームベーカリー2台が彼専用で持ち込まれ、どうやったらパンになるのかの試行錯誤が行われました。
そうして、ようやくふっくらとしたパンが焼きあがったのです。私も早速試食をしました。おお、なんと! 野草としてのニホンハッカを酵母化したパンからは、ほのかなハッカの香りが口の中に広がり、味も素晴らしい。お金を払ってでも食べたい味のパン!
これは結構な発明ではないだろうかと、私も色々調べると、北海道の北見でハッカを使ったパンを名物にしているお店があり、製造方法はまったく違います。ハッカの香りを焼いたときに失わないよう、苦労して開発したとのこと。
長岡さんが開発したのは、ハッカの香りがやわらかく口の中に広がり、なぜハッカが希少種になってしまったかという日本の里山の危機を考えるきっかけになる、ハッカパンです。ちなみにカワラナデシコパンも出来て、これも素晴らしい。
本当の意味での「豊かな自然の恵み」を味わうことができました。長岡さん、ありがとう!

かつては南木曽の地のいたるところに出会えたのに、今はほとんど見かけなくなった植物があるということを知った長岡さんは、野原や河川敷などをフィールドワークして希少植物を採取し、それを食材として活用する新たな方法を開発しようとしました。具体的には自然酵母を培養して、それをもとに新しいパンを開発するという研究です。調理室のなかに酵母を培養する彼の(一見あやしげな)壜が並び、ホームベーカリー2台が彼専用で持ち込まれ、どうやったらパンになるのかの試行錯誤が行われました。
そうして、ようやくふっくらとしたパンが焼きあがったのです。私も早速試食をしました。おお、なんと! 野草としてのニホンハッカを酵母化したパンからは、ほのかなハッカの香りが口の中に広がり、味も素晴らしい。お金を払ってでも食べたい味のパン!
これは結構な発明ではないだろうかと、私も色々調べると、北海道の北見でハッカを使ったパンを名物にしているお店があり、製造方法はまったく違います。ハッカの香りを焼いたときに失わないよう、苦労して開発したとのこと。
長岡さんが開発したのは、ハッカの香りがやわらかく口の中に広がり、なぜハッカが希少種になってしまったかという日本の里山の危機を考えるきっかけになる、ハッカパンです。ちなみにカワラナデシコパンも出来て、これも素晴らしい。
本当の意味での「豊かな自然の恵み」を味わうことができました。長岡さん、ありがとう!

「税に関する作文で木曽税務署長賞をいただく」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月16日17:48
令和2年度「税に関する高校生の作文」にて木曽税務署長賞を本校2年生の森さんが受賞し、本日、河原署長さんより表彰状をいただきました。本校の生徒が賞をいただくのは、本当にうれしいことです。わざわざお越しいただいた河原署長さん、瀬在係長さんに心より感謝申し上げます。
森さんの作文は、税金の必要性を日常生活で実感しにくいのは、用途が国民全体に向けているからだと気づき、身近なものにどれだけ税金が使われていて、それを自分たちが実費で負担するとすればどれだけの額になるのかを調べたという内容です。見えていないものを理解することによって、ことがらの本質を把握するというのは、学ぶことの本質だと、森さんの作文を読んであらためて私は実感しました。
署長さんから教えてもらったのですが、表彰状は国立印刷局の製造によるもので、紙の中央下部に燦然と記載されています。さすが・・・と感嘆。
ちなみに私の専門の世界史教育で言うと、教科書に出てきて生徒が暗記させられる税の知識と言うと、「租庸調」とか「10分の1税」とか、「庶民はそれで苦しんだのです」というような内容ばかり。たとえば、イギリスの「ゆりかごから墓場まで」という福祉理念が、どのような租税や民間からの寄付金で成り立ってきたのかなどの「制度を支えるための努力」について、高校世界史ではあまり教えてきませんでした。
本当は、その成果を実現するためのプロセスについて考えるところに、学びの意義があるはずなのです。

森さんの作文は、税金の必要性を日常生活で実感しにくいのは、用途が国民全体に向けているからだと気づき、身近なものにどれだけ税金が使われていて、それを自分たちが実費で負担するとすればどれだけの額になるのかを調べたという内容です。見えていないものを理解することによって、ことがらの本質を把握するというのは、学ぶことの本質だと、森さんの作文を読んであらためて私は実感しました。
署長さんから教えてもらったのですが、表彰状は国立印刷局の製造によるもので、紙の中央下部に燦然と記載されています。さすが・・・と感嘆。
ちなみに私の専門の世界史教育で言うと、教科書に出てきて生徒が暗記させられる税の知識と言うと、「租庸調」とか「10分の1税」とか、「庶民はそれで苦しんだのです」というような内容ばかり。たとえば、イギリスの「ゆりかごから墓場まで」という福祉理念が、どのような租税や民間からの寄付金で成り立ってきたのかなどの「制度を支えるための努力」について、高校世界史ではあまり教えてきませんでした。
本当は、その成果を実現するためのプロセスについて考えるところに、学びの意義があるはずなのです。

「長崎修学旅行から全員が笑顔で戻ってくる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年11月13日18:06
本日、2年生全員が長崎修学旅行から元気な笑顔で戻ってきました。
今朝の検温では全員平熱の状態かつ元気であり、安心して帰りの飛行機に搭乗することができました。
4日間の旅は、たくさんの生徒の成長した姿に出会うことができました。3日目の夜、ホテルに帰ってきて少し体調不安があった生徒は、夜のハウステンボスのイリュミネーションの見学に外出できませんでした。しかし班の仲間たちが彼の淋しさを埋め合わせるだけのおみやげを買ってきました。互いに支え合いながら、生徒たちは旅を進めていきました。
困ったときのリカバリーにおいても、一段大人に近づいた生徒たちの姿を随所に見ることができました。やはり旅は、人間を成長させる絶好の機会なのです。
「100を0にしない」ことを、みんなの力で今回も成し遂げることができました。
2年生の生徒の皆さん、お疲れさまでした。お帰りなさい。
そしてコロナ禍のなか学校を信頼していただき、お子さんを旅行に出していただいた、保護者の皆様、本当にありがとうございました。全員の保護者の皆様から同意書が出てきたことで、私たちは絶対にこの旅を成功させるのだという決意をもちました。
今回の旅のプランニングとリスクマネジメントを綿密に行ってくださった東武トップツアーズ伊那支店の河合支店長様にも心より感謝申し上げます。コロナ時代に観光産業が人々に安全安心な旅の夢を提供していくということは、このような緻密で膨大な努力の上に成り立つことなのだと、今回、私は実感しました。観光産業の皆さんに、私は尊敬の念をもちます。
最後に、旅のエンディングについての報告です。セントレア空港に帰着して、終わりのセレモニーを予定どおり終えようとしたとき、生徒の代表がサプライズで引率教員への感謝の思いをスピーチしてくれました。
教員も「蘇南高校でこの時代にこの生徒たちと一緒に旅ができた幸せ」をかみしめたのです。

今朝の検温では全員平熱の状態かつ元気であり、安心して帰りの飛行機に搭乗することができました。
4日間の旅は、たくさんの生徒の成長した姿に出会うことができました。3日目の夜、ホテルに帰ってきて少し体調不安があった生徒は、夜のハウステンボスのイリュミネーションの見学に外出できませんでした。しかし班の仲間たちが彼の淋しさを埋め合わせるだけのおみやげを買ってきました。互いに支え合いながら、生徒たちは旅を進めていきました。
困ったときのリカバリーにおいても、一段大人に近づいた生徒たちの姿を随所に見ることができました。やはり旅は、人間を成長させる絶好の機会なのです。
「100を0にしない」ことを、みんなの力で今回も成し遂げることができました。
2年生の生徒の皆さん、お疲れさまでした。お帰りなさい。
そしてコロナ禍のなか学校を信頼していただき、お子さんを旅行に出していただいた、保護者の皆様、本当にありがとうございました。全員の保護者の皆様から同意書が出てきたことで、私たちは絶対にこの旅を成功させるのだという決意をもちました。
今回の旅のプランニングとリスクマネジメントを綿密に行ってくださった東武トップツアーズ伊那支店の河合支店長様にも心より感謝申し上げます。コロナ時代に観光産業が人々に安全安心な旅の夢を提供していくということは、このような緻密で膨大な努力の上に成り立つことなのだと、今回、私は実感しました。観光産業の皆さんに、私は尊敬の念をもちます。
最後に、旅のエンディングについての報告です。セントレア空港に帰着して、終わりのセレモニーを予定どおり終えようとしたとき、生徒の代表がサプライズで引率教員への感謝の思いをスピーチしてくれました。
教員も「蘇南高校でこの時代にこの生徒たちと一緒に旅ができた幸せ」をかみしめたのです。
カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長



