「2年越しの離任式と自由の女神」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月30日17:20
今日は、2学期制をとる本校の終・始業式でした。一年の折り返し地点です。
久しぶりの体育館での対面行事として、①校長講話、②絵画贈呈式、③先生方からの呼びかけ、の三つのパートで構成しました。
今日のメインは、絵画贈呈式です。本校OBで元福島中学校長(現木曽町中学校)の岡田政晴先生は、ご退職後に本校の非常勤講師をつとめていただいていました。しかし令和2年6月より療養生活を余儀なくされ、離任式もできないまま、教壇から離れました。
半身不随で趣味の絵筆も握れなくなった岡田先生は、リハビリを重ねて、やがて動くほうの指を使って絵画の制作を再開します。お身体の不自由さは、想像力がどんどんカバーするようになりました。そしてこのほど蘇南高校の玄関から眺めた南木曽岳の風景を描いた「母校に栄誉あれ」という6号の作品を寄贈したいと、先生から温かなお言葉をいただいたのです。
そこで今日は、絵画贈呈式(兼2年越しの離任式)を行いました。車いすの岡田先生が、生徒たちに蘇南高校の大切な思い出を語って下さり、生徒会長の亀山さんが「不自由さを克服していった先生の生き方に後輩として学びたい」という感謝のことばと花束を贈りました。
そして全校生徒が花道をつくり、岡田先生を満場の拍手でお送りしました。



次に、今日の校長講話は、「うつむいて静かに考えることの意味」というタイトルで、本校の前庭にたたずむ彫刻家の勝野眞言先生の作品「律」が、なぜ目を閉じてうつむいているのか(多くの高校の銅像は空や彼方を仰ぎ見ているのに・・・)について考えました。英語で言えば、thinkではなく、considerの姿がそこにあるのではないか。considerの語源をふりかえるならば、じっくり考えるとは、星々を見渡しながら、次にうつむいて自分自身のことを見つめることなのでしょう。
それは、第二次世界大戦中に短い生涯をかけぬけた哲学者シモーヌ・ヴェイユが、「自由」とは、目的と手段に関する多くの選択肢について自らの意思で熟考していくことだと述べたことに重なるのではないか。作品「律」は、蘇南高校にとっての「自由」の象徴なのだと、生徒に語りかけてみました。
私の原稿は、こちらです。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220930_kouwa.pdf
岡田先生、勝野先生という大先輩と大切な対話ができた一日でした。

久しぶりの体育館での対面行事として、①校長講話、②絵画贈呈式、③先生方からの呼びかけ、の三つのパートで構成しました。
今日のメインは、絵画贈呈式です。本校OBで元福島中学校長(現木曽町中学校)の岡田政晴先生は、ご退職後に本校の非常勤講師をつとめていただいていました。しかし令和2年6月より療養生活を余儀なくされ、離任式もできないまま、教壇から離れました。
半身不随で趣味の絵筆も握れなくなった岡田先生は、リハビリを重ねて、やがて動くほうの指を使って絵画の制作を再開します。お身体の不自由さは、想像力がどんどんカバーするようになりました。そしてこのほど蘇南高校の玄関から眺めた南木曽岳の風景を描いた「母校に栄誉あれ」という6号の作品を寄贈したいと、先生から温かなお言葉をいただいたのです。
そこで今日は、絵画贈呈式(兼2年越しの離任式)を行いました。車いすの岡田先生が、生徒たちに蘇南高校の大切な思い出を語って下さり、生徒会長の亀山さんが「不自由さを克服していった先生の生き方に後輩として学びたい」という感謝のことばと花束を贈りました。
そして全校生徒が花道をつくり、岡田先生を満場の拍手でお送りしました。


次に、今日の校長講話は、「うつむいて静かに考えることの意味」というタイトルで、本校の前庭にたたずむ彫刻家の勝野眞言先生の作品「律」が、なぜ目を閉じてうつむいているのか(多くの高校の銅像は空や彼方を仰ぎ見ているのに・・・)について考えました。英語で言えば、thinkではなく、considerの姿がそこにあるのではないか。considerの語源をふりかえるならば、じっくり考えるとは、星々を見渡しながら、次にうつむいて自分自身のことを見つめることなのでしょう。
それは、第二次世界大戦中に短い生涯をかけぬけた哲学者シモーヌ・ヴェイユが、「自由」とは、目的と手段に関する多くの選択肢について自らの意思で熟考していくことだと述べたことに重なるのではないか。作品「律」は、蘇南高校にとっての「自由」の象徴なのだと、生徒に語りかけてみました。
私の原稿は、こちらです。https://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/pdf/20220930_kouwa.pdf
岡田先生、勝野先生という大先輩と大切な対話ができた一日でした。
「校長、3回目のモデルになる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月29日14:14
玄関ロビーに展示されている美術作品のコーナーには、私の顔をデッサンした作品の一角があります。校長が3回目のモデルになりました。
吉田先生の命を受けて(!)、顔写真を撮影し、それをもとに生徒たちがデッサンをしてくれたのです。さすがに長時間モデルとしてじっとしていることはできないので、その点ではほっとしているのですが、それでも自分の顔がずらっと並んでいるのを見るのは、かなり恥ずかしい。
小川の顔が、草間彌生の「増殖する水玉」のように見えてくるのも面白いです。
岸田劉生の「麗子像」のように不思議な雰囲気だと言えば、うぬぼれるなと叱られるでしょう。
当然ながら、ひとりひとり私の顔のどこの部分に注目しているかが異なっているわけで、私の専門の歴史学と交錯させると、同じ歴史事象を見ていても、そこからどのような歴史叙述をくみたてるかが百家争鳴になるのは当然なのだと言えましょう。
描いてくれた1年生の皆さんには、ただただ感謝の言葉しかありません。こんな特徴のないモデルを、よくぞ作品に昇華してくれました。
本当にありがとう!

吉田先生の命を受けて(!)、顔写真を撮影し、それをもとに生徒たちがデッサンをしてくれたのです。さすがに長時間モデルとしてじっとしていることはできないので、その点ではほっとしているのですが、それでも自分の顔がずらっと並んでいるのを見るのは、かなり恥ずかしい。
小川の顔が、草間彌生の「増殖する水玉」のように見えてくるのも面白いです。
岸田劉生の「麗子像」のように不思議な雰囲気だと言えば、うぬぼれるなと叱られるでしょう。
当然ながら、ひとりひとり私の顔のどこの部分に注目しているかが異なっているわけで、私の専門の歴史学と交錯させると、同じ歴史事象を見ていても、そこからどのような歴史叙述をくみたてるかが百家争鳴になるのは当然なのだと言えましょう。
描いてくれた1年生の皆さんには、ただただ感謝の言葉しかありません。こんな特徴のないモデルを、よくぞ作品に昇華してくれました。
本当にありがとう!
「見えないことを大切にする」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月28日16:22
蘇南高校は、南木曽岳をのぞむ天白の丘に、大きな鳥がまさに羽ばたこうとしているような形で校舎が建てられています。鵬翼(ほうよく)という言葉がまさにぴったりな校舎です。
昇降口の下駄箱もすべて美しい木製になっていて、本校舎は木の温かさに満ちています。
ところが一点だけ、わが校舎には大きな欠陥がありました。最も以前に建てられていた商業棟の避難階段が壁面や手すりの老朽化により、立入禁止状態になっていたのです。いざというときの避難階段が使えないということは、昨年度に総合探究で防災をテーマにしていた3年生から「とてもまずいことだ」と指摘されていました。(当然消防署からも指摘されてきました。)私は応急措置として、避難梯子を設置して使用するための訓練をしてきました。
今年度、特別予算が配当されて松瀬工務店さんに改修工事をお願いした結果、見違えるようなきれいな階段に生まれ変わることができました。
これで私は、堂々と鵬翼の校舎のすべてを誇れるようになりました。何とうれしいことでしょうか。松瀬さん、本当にありがとうございました。
生徒にとってはほとんど見えていない、隠れた場所の整備になります。
でもこうしたところを丁寧に維持管理していくことで、学校は学校としての輝きを保ち続けるのだと思っています。
サンテグジュペリの「星の王子さま」が語ったように、「大切なことは目には見えない」のです。

昇降口の下駄箱もすべて美しい木製になっていて、本校舎は木の温かさに満ちています。
ところが一点だけ、わが校舎には大きな欠陥がありました。最も以前に建てられていた商業棟の避難階段が壁面や手すりの老朽化により、立入禁止状態になっていたのです。いざというときの避難階段が使えないということは、昨年度に総合探究で防災をテーマにしていた3年生から「とてもまずいことだ」と指摘されていました。(当然消防署からも指摘されてきました。)私は応急措置として、避難梯子を設置して使用するための訓練をしてきました。
今年度、特別予算が配当されて松瀬工務店さんに改修工事をお願いした結果、見違えるようなきれいな階段に生まれ変わることができました。
これで私は、堂々と鵬翼の校舎のすべてを誇れるようになりました。何とうれしいことでしょうか。松瀬さん、本当にありがとうございました。
生徒にとってはほとんど見えていない、隠れた場所の整備になります。
でもこうしたところを丁寧に維持管理していくことで、学校は学校としての輝きを保ち続けるのだと思っています。
サンテグジュペリの「星の王子さま」が語ったように、「大切なことは目には見えない」のです。
「生徒たちがヴァイオリンを奏でる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月27日16:47
2年の「音楽表現基礎」という授業では、夏休み明けからヴァイオリンの演奏を学んできました。
もちろん生徒たちは、初めてこの楽器にふれることになりますし、実際に使う学期は専門の業者からレンタルしています。
ヴァイオリンを左肩に乗せて、姿勢を整え、原先生のレッスンを受けていきます。私が参観した時には「きらきら星」を演奏できるようになっていて、大したものだと感心させられました。
もちろん生徒たちは様々な苦労と格闘していて、女子は「楽器が重いです!」と言いながら頑張っています。私は教室のうしろで目を閉じながら生徒たちの奏でるヴァイオリンの音色をしばし楽しみました。
様々な楽器の魅力に気づくことは、きっと人生を豊かにしてくれるでしょう。
実は、本校では、来週、鍵盤ハーモニカの演奏家(!)のはざまゆかさんをお招きしてコンサートを開催します。芸術の秋を思い切り楽しむ計画なのです。

もちろん生徒たちは、初めてこの楽器にふれることになりますし、実際に使う学期は専門の業者からレンタルしています。
ヴァイオリンを左肩に乗せて、姿勢を整え、原先生のレッスンを受けていきます。私が参観した時には「きらきら星」を演奏できるようになっていて、大したものだと感心させられました。
もちろん生徒たちは様々な苦労と格闘していて、女子は「楽器が重いです!」と言いながら頑張っています。私は教室のうしろで目を閉じながら生徒たちの奏でるヴァイオリンの音色をしばし楽しみました。
様々な楽器の魅力に気づくことは、きっと人生を豊かにしてくれるでしょう。
実は、本校では、来週、鍵盤ハーモニカの演奏家(!)のはざまゆかさんをお招きしてコンサートを開催します。芸術の秋を思い切り楽しむ計画なのです。
「普段見られない風景のなかに身をおいて」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月26日20:46
今日から本校は、第3回定期考査。2学期制をとっているので、前期をしめくくる試験です。
一日時計の針を戻して、昨日の山登りのことを報告します。
三連休に相次いで台風が襲来したのですが、25日(日)はようやく晴れ間が見えそうな天気予報だったので、厚い雲がたれこめるなか、伊那谷の吉田山(1450m)を目指しました。二日後に83歳になる父と一緒です。
吉田山は、飯田市の北にある高森町の代表的な里山で、三角形の端正な山容をしています。私は松川高校時代に毎朝、朝日に照らされるこの山を眺めながら自動車を走らせていました。
今回は十数年ぶりの再訪で、伐採されて眺望が良くなったという評判の山頂がとても楽しみでした。登り2時間、やせ尾根を注意しながらひと登りすると、「おおっ」と思わず歓声をあげました。それまでの厚い雲と霧がなくなっていて、天竜川とその向こうにそびえる仙丈ケ岳・北岳・間ノ岳・農鳥岳・塩見岳の絶景が広がっていたからです。
南アルプスの雄大な山々の姿を見て、「ああこれを延々と飯田高校の生徒たちと縦走したなあ」と大鹿村の登山口から歩き出し、二日目の夜に甲府の夜景(!)をみおろして感動したことを思い出しました。
汗をかいて身体を動かし、普段見られない風景のなかに身をおくことの爽快感を、あらためて味わった一日でした。
ついでに山頂一帯には山ほどの山栗が落ちていて、夕食の食材にすべく「痛ッ」と何度も叫びながら、栗拾いにも夢中になりました。

一日時計の針を戻して、昨日の山登りのことを報告します。
三連休に相次いで台風が襲来したのですが、25日(日)はようやく晴れ間が見えそうな天気予報だったので、厚い雲がたれこめるなか、伊那谷の吉田山(1450m)を目指しました。二日後に83歳になる父と一緒です。
吉田山は、飯田市の北にある高森町の代表的な里山で、三角形の端正な山容をしています。私は松川高校時代に毎朝、朝日に照らされるこの山を眺めながら自動車を走らせていました。
今回は十数年ぶりの再訪で、伐採されて眺望が良くなったという評判の山頂がとても楽しみでした。登り2時間、やせ尾根を注意しながらひと登りすると、「おおっ」と思わず歓声をあげました。それまでの厚い雲と霧がなくなっていて、天竜川とその向こうにそびえる仙丈ケ岳・北岳・間ノ岳・農鳥岳・塩見岳の絶景が広がっていたからです。
南アルプスの雄大な山々の姿を見て、「ああこれを延々と飯田高校の生徒たちと縦走したなあ」と大鹿村の登山口から歩き出し、二日目の夜に甲府の夜景(!)をみおろして感動したことを思い出しました。
汗をかいて身体を動かし、普段見られない風景のなかに身をおくことの爽快感を、あらためて味わった一日でした。
ついでに山頂一帯には山ほどの山栗が落ちていて、夕食の食材にすべく「痛ッ」と何度も叫びながら、栗拾いにも夢中になりました。
「前のめりになって考えたくなる問いを授業でかかげる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月22日18:10
この9月は、本校の先生たち全員の授業を参観してきました。
授業の前半か後半か、あらかじめ希望を聞いておき、その授業で生徒の努力を評価するルーブリックをどのように作成したかを提出してもらっています。
授業を参観していくと、生徒たちの知的成長にあらためて感動しますし、先生方ひとりひとりの成長もひしひしと感じて嬉しい思いがしています。
たとえば、地歴公民科の鷹野先生の2年「日本史A」の授業では、「日清戦争・日露戦争を防ぐことができたのはどの時点か」という問いについて、生徒たちが仮説をたて、タブレットパソコンに入力して、友人同士で対話をしました。
「藩閥政治を温存した大日本帝国憲法の成立」をあげた生徒もいれば、「甲申政変」によって朝鮮半島の政治に日本が大きく関与したことをあげた生徒もいます。それぞれが自分の言葉で、なぜこの歴史事象を重視するのかを説明し、そのことが日清戦争・日露戦争のさまざまな特徴と深く関係していることが、生徒たちに共有されていきました。
対話が活発になるためには、前のめりになって考えたくなる「問い」を設定することが必要です。そうした「問い」を考えられるようになること、そして生徒たちの発言をすくいあげて新たな認識の深まりを実現することが、教師の腕の見せ所と言えましょう。
生徒たちの対話の姿にも、先生の「問い」のうまさにも、感心したひとときでした。

授業の前半か後半か、あらかじめ希望を聞いておき、その授業で生徒の努力を評価するルーブリックをどのように作成したかを提出してもらっています。
授業を参観していくと、生徒たちの知的成長にあらためて感動しますし、先生方ひとりひとりの成長もひしひしと感じて嬉しい思いがしています。
たとえば、地歴公民科の鷹野先生の2年「日本史A」の授業では、「日清戦争・日露戦争を防ぐことができたのはどの時点か」という問いについて、生徒たちが仮説をたて、タブレットパソコンに入力して、友人同士で対話をしました。
「藩閥政治を温存した大日本帝国憲法の成立」をあげた生徒もいれば、「甲申政変」によって朝鮮半島の政治に日本が大きく関与したことをあげた生徒もいます。それぞれが自分の言葉で、なぜこの歴史事象を重視するのかを説明し、そのことが日清戦争・日露戦争のさまざまな特徴と深く関係していることが、生徒たちに共有されていきました。
対話が活発になるためには、前のめりになって考えたくなる「問い」を設定することが必要です。そうした「問い」を考えられるようになること、そして生徒たちの発言をすくいあげて新たな認識の深まりを実現することが、教師の腕の見せ所と言えましょう。
生徒たちの対話の姿にも、先生の「問い」のうまさにも、感心したひとときでした。

「岐阜県立恵那南高校の校長先生と学校経営について交流する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月21日19:34
今日は、岐阜県恵那市の明智町にある、岐阜県立恵那南高校に学校視察を行いました。
これからの蘇南高校をブラッシュアップすべく、他県の先進的な取組(特に学校経営・地域連携)を学んでいくためです。今回は、南木曽町の向井教育長さんと末松教育次長補佐さんと一緒に視察を行いました。
恵那南高校さんは、全校の生徒数が本校とほぼ同じ。そして総合学科。地域のなかで学ぶ教育を特に重視されており、生徒の多様な進路実現をはかっている点も本校と共通しています。恵那から伸びているローカル鉄道「明知鉄道」の終着駅にあたる明智町の町のサイズは、南木曽町よりやや大きいくらいで、ほぼ同じです。
生徒の皆さんが一生懸命学んでいる授業の様子を参観させていただくとともに、デュアルシステムの構築とか明智町における小中校の連携、地元企業とタイアップした教育など、本校の参考にしたい取り組みについて、高橋校長先生・柴教頭先生から丁寧に教えていただきました。
「是非、これからも交流を深めさせていただければありがたいです」とお願いして、高橋校長先生と校門のところで記念撮影をしました。
自動車で1時間くらいのところ(長野県側の隣の木曽青峰高校までとほぼ同じ時間!)に、かくも共通する教育理念を親しく交流できる高校が存在していることを知り、私はとても嬉しい思いがしました。(さらには恵那南高校の地歴公民科の先生が、私の著書の読者であることを教えていただき、感激しました。)
今日が最初の種まきであり、この出会いの芽を大きく育てていきたいと思っています。
高橋先生、柴先生、なにとぞよろしくお願いいたします。

これからの蘇南高校をブラッシュアップすべく、他県の先進的な取組(特に学校経営・地域連携)を学んでいくためです。今回は、南木曽町の向井教育長さんと末松教育次長補佐さんと一緒に視察を行いました。
恵那南高校さんは、全校の生徒数が本校とほぼ同じ。そして総合学科。地域のなかで学ぶ教育を特に重視されており、生徒の多様な進路実現をはかっている点も本校と共通しています。恵那から伸びているローカル鉄道「明知鉄道」の終着駅にあたる明智町の町のサイズは、南木曽町よりやや大きいくらいで、ほぼ同じです。
生徒の皆さんが一生懸命学んでいる授業の様子を参観させていただくとともに、デュアルシステムの構築とか明智町における小中校の連携、地元企業とタイアップした教育など、本校の参考にしたい取り組みについて、高橋校長先生・柴教頭先生から丁寧に教えていただきました。
「是非、これからも交流を深めさせていただければありがたいです」とお願いして、高橋校長先生と校門のところで記念撮影をしました。
自動車で1時間くらいのところ(長野県側の隣の木曽青峰高校までとほぼ同じ時間!)に、かくも共通する教育理念を親しく交流できる高校が存在していることを知り、私はとても嬉しい思いがしました。(さらには恵那南高校の地歴公民科の先生が、私の著書の読者であることを教えていただき、感激しました。)
今日が最初の種まきであり、この出会いの芽を大きく育てていきたいと思っています。
高橋先生、柴先生、なにとぞよろしくお願いいたします。
「余の辞書に休校ということばはない」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月20日18:15
大型で強い勢力をもつ台風14号が最接近したことにより、JR中央西線が夕方16時まで計画運休となりました。
これまで多くの高校生はこのようなとき、「やったー、休校っ!」と、歓声をあげてきました。
しかし(!)、本校では昨晩のうちに「ではオンライン教育に切り替えます」と全生徒に連絡しました。そして実際、今日は朝のホームルームから6時間目まで時間割通りに授業をしました。ナポレオンの「余の辞書に不可能ということばはない」にならえば、「余の辞書に休校ということばはない」(!)のです。
生徒たちからのブーイングが聞こえてきそうですが、あえて説明をします。
(1)学びを止めないことが大切。来週は定期考査なのです。
(2)台風のコースは、地球の状態によるものなので、繰り返す可能性があります。休校が重なってしまい、休日を登校日にしないためにも、授業ができるときはやります。
(3)職員が学校に来られない(来るのがとても危険)ならば躊躇せずに休校にします。今回はそれほどの予想でもありませんでした。
午後には学校評議員会があり、委員の皆さんとオンライン授業の様子を参観してまわりました。一生懸命学んでいる生徒の様子(そして工夫してオンライン授業をしている先生たちの様子)に、委員の皆さんもとても感心してくださいました。
あわせて学校評議員会では、生徒代表による探究活動の中間報告や、新生徒会長亀山さんのスピーチをオンラインで行いました。
今日の学校評議員会のテーマは、「キャリア教育のあり方」でした。地域の代表の皆さん、中学校やPTAの代表の皆さんからとても有意義なアドバイスをいただいて、私たち教員もたくさんの学びを重ねることができました。(委員の皆様、本当にありがとうございました。)
明日は、校舎の中に生徒の皆さんの元気な声がみちあふれることでしょう。
皆さんをお待ちしています。

これまで多くの高校生はこのようなとき、「やったー、休校っ!」と、歓声をあげてきました。
しかし(!)、本校では昨晩のうちに「ではオンライン教育に切り替えます」と全生徒に連絡しました。そして実際、今日は朝のホームルームから6時間目まで時間割通りに授業をしました。ナポレオンの「余の辞書に不可能ということばはない」にならえば、「余の辞書に休校ということばはない」(!)のです。
生徒たちからのブーイングが聞こえてきそうですが、あえて説明をします。
(1)学びを止めないことが大切。来週は定期考査なのです。
(2)台風のコースは、地球の状態によるものなので、繰り返す可能性があります。休校が重なってしまい、休日を登校日にしないためにも、授業ができるときはやります。
(3)職員が学校に来られない(来るのがとても危険)ならば躊躇せずに休校にします。今回はそれほどの予想でもありませんでした。
午後には学校評議員会があり、委員の皆さんとオンライン授業の様子を参観してまわりました。一生懸命学んでいる生徒の様子(そして工夫してオンライン授業をしている先生たちの様子)に、委員の皆さんもとても感心してくださいました。
あわせて学校評議員会では、生徒代表による探究活動の中間報告や、新生徒会長亀山さんのスピーチをオンラインで行いました。
今日の学校評議員会のテーマは、「キャリア教育のあり方」でした。地域の代表の皆さん、中学校やPTAの代表の皆さんからとても有意義なアドバイスをいただいて、私たち教員もたくさんの学びを重ねることができました。(委員の皆様、本当にありがとうございました。)
明日は、校舎の中に生徒の皆さんの元気な声がみちあふれることでしょう。
皆さんをお待ちしています。
「島崎藤村生誕150周年の記念映画を観て」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月19日12:04
今日は、飯田のセンゲキシネマズで、映画『破戒』を観ました。
島崎藤村生誕150周年の今年、60年ぶりに東映が『破戒』の再映画化に挑戦したのです。
明治維新で四民平等の世の中になったとはいえ、新平民とされた被差別部落出身の人々への酷い差別は続き、主人公の瀬川丑松は、「隠せ」という父からの戒めをかたく守りながら飯山の尋常小学校の教壇に立ちますが、やがて出自を同僚に暴かれそうになります。苦しむ丑松は、平等な社会を目指して戦う人々の姿に限りない共感を寄せ、やがて教壇で自分が部落出身であることを告白して、学校を去るというストーリーです。
日本社会に部落解放の思想が広まるにつれ、主人公が出自を隠していたことを生徒に詫びて、教職を去るという小説の「敗北の結末」に大きな批判が寄せられるようになります。『破戒』は忘却された小説のひとつになっていきました。
でも主人公のモデル・大江磯吉が、私の家のある飯田の出身ということもあり、私はこの小説にずっと関心を寄せてきました。飯田高校の時には生徒たちに小説の紹介もしました。
私にとって目の覚めるような思いがしたのは、評論家の宮崎学さんの『近代の奈落』(解放出版社)の『破戒』論です。宮崎さんは、藤村は解放運動を実践しようとしたのではなく、主人公の悲しみと勇気に寄り添ってこの小説を書いたのであり、その観点でこれを読めば、生徒に隠しごとをしていた自分を詫びる丑松の姿は、単なる敗北ではないと論じたのです。
今回の前田和男監督のこの映画も、子どもたちに詫びる瀬川丑松を、未来に向けて真摯に歩き出す青年の希望として描いています。
私は心から感動しました。まさに現代に『破戒』が見事に再生したと思いました。
藤村にゆかりのあるわが南木曽町で、是非とも上映会をしたいものです。
追伸
写真は、十川信介『島崎藤村』(ミネルヴァ書房)のなかの『破戒』初版の表紙です。(藤村記念館提供)
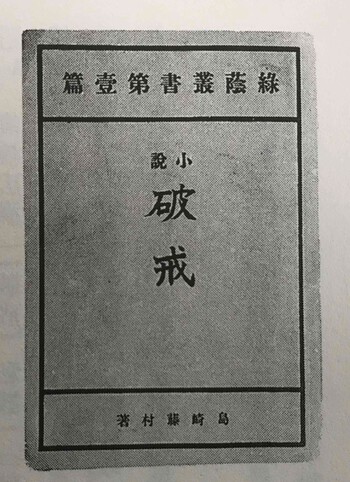
島崎藤村生誕150周年の今年、60年ぶりに東映が『破戒』の再映画化に挑戦したのです。
明治維新で四民平等の世の中になったとはいえ、新平民とされた被差別部落出身の人々への酷い差別は続き、主人公の瀬川丑松は、「隠せ」という父からの戒めをかたく守りながら飯山の尋常小学校の教壇に立ちますが、やがて出自を同僚に暴かれそうになります。苦しむ丑松は、平等な社会を目指して戦う人々の姿に限りない共感を寄せ、やがて教壇で自分が部落出身であることを告白して、学校を去るというストーリーです。
日本社会に部落解放の思想が広まるにつれ、主人公が出自を隠していたことを生徒に詫びて、教職を去るという小説の「敗北の結末」に大きな批判が寄せられるようになります。『破戒』は忘却された小説のひとつになっていきました。
でも主人公のモデル・大江磯吉が、私の家のある飯田の出身ということもあり、私はこの小説にずっと関心を寄せてきました。飯田高校の時には生徒たちに小説の紹介もしました。
私にとって目の覚めるような思いがしたのは、評論家の宮崎学さんの『近代の奈落』(解放出版社)の『破戒』論です。宮崎さんは、藤村は解放運動を実践しようとしたのではなく、主人公の悲しみと勇気に寄り添ってこの小説を書いたのであり、その観点でこれを読めば、生徒に隠しごとをしていた自分を詫びる丑松の姿は、単なる敗北ではないと論じたのです。
今回の前田和男監督のこの映画も、子どもたちに詫びる瀬川丑松を、未来に向けて真摯に歩き出す青年の希望として描いています。
私は心から感動しました。まさに現代に『破戒』が見事に再生したと思いました。
藤村にゆかりのあるわが南木曽町で、是非とも上映会をしたいものです。
追伸
写真は、十川信介『島崎藤村』(ミネルヴァ書房)のなかの『破戒』初版の表紙です。(藤村記念館提供)
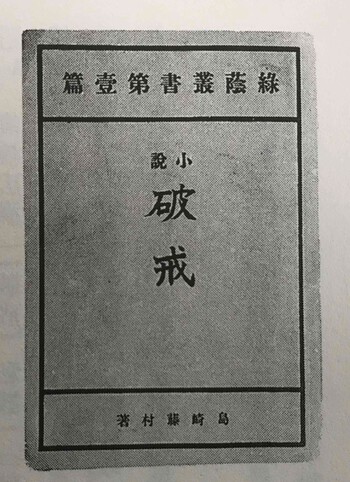
「暴力の満ち溢れる世界に身を置いて」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月18日15:23
松本深志高校時代に私の世界史講座の生徒であり、現在は東京大学でフランス哲学を研究されている藤岡俊博さんが、新著を出版されました。
伊達聖伸・藤岡俊博編『「暴力」から読み解く現代世界』(東京大学出版会)です。
藤岡さんによる巻頭論文「いま『暴力』を考えるために」が、暴力の定義、これまでの暴力論、暴力を見つめるときの視点について、手際よく、そして鋭角的に論じられています。ベンヤミンの法措定的暴力と法維持的暴力という視点に、自己防衛の権利としての暴力とか構造的暴力という視点を交錯させることで、藤岡さんは「暴力」論を深く掘り下げていきます。
続く各論では、フランスの政教分離、ウクライナ戦争、ミャンマーの国軍、在日朝鮮人差別、アメリカのBLMなど、最もホットなテーマがたてられています。
今回も藤岡さんからたくさんのことを学ばせていただきました。
私は、これまでの歴史教育では、暴力そのものの分析が回避されてきたことに大きな問題意識をもってきました。「暴力はいけない」「戦争はいけない」という平和教育が表面的なものにとどまると、石川啄木のいう「揮発性の言葉」のようになって、なぜ人類の歴史の中にかくも可視的・不可視的に暴力が満ち溢れてきたのか、そしてその暴力に対抗するにはどのような抵抗が可能なのかということを深く考える機会を失ってきたように思います。
一方でフランス革命のような遠い世界の革命行為は賛美しつつ、打ちこわしや米騒動、安保闘争のような近い世界の民衆騒擾には同情と危険視のアンビバレンツなまなざしを向けるといった、情緒的な暴力への対峙の仕方が繰り返されてきたように思います。
改めて藤岡さんたちの研究成果を歴史教育にどのように摂取していくかを、私自身の課題として考えていきたいと決意しています。
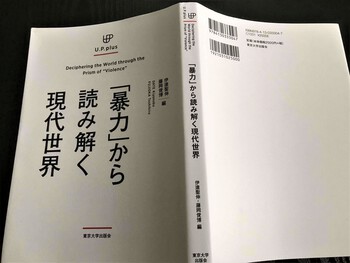
伊達聖伸・藤岡俊博編『「暴力」から読み解く現代世界』(東京大学出版会)です。
藤岡さんによる巻頭論文「いま『暴力』を考えるために」が、暴力の定義、これまでの暴力論、暴力を見つめるときの視点について、手際よく、そして鋭角的に論じられています。ベンヤミンの法措定的暴力と法維持的暴力という視点に、自己防衛の権利としての暴力とか構造的暴力という視点を交錯させることで、藤岡さんは「暴力」論を深く掘り下げていきます。
続く各論では、フランスの政教分離、ウクライナ戦争、ミャンマーの国軍、在日朝鮮人差別、アメリカのBLMなど、最もホットなテーマがたてられています。
今回も藤岡さんからたくさんのことを学ばせていただきました。
私は、これまでの歴史教育では、暴力そのものの分析が回避されてきたことに大きな問題意識をもってきました。「暴力はいけない」「戦争はいけない」という平和教育が表面的なものにとどまると、石川啄木のいう「揮発性の言葉」のようになって、なぜ人類の歴史の中にかくも可視的・不可視的に暴力が満ち溢れてきたのか、そしてその暴力に対抗するにはどのような抵抗が可能なのかということを深く考える機会を失ってきたように思います。
一方でフランス革命のような遠い世界の革命行為は賛美しつつ、打ちこわしや米騒動、安保闘争のような近い世界の民衆騒擾には同情と危険視のアンビバレンツなまなざしを向けるといった、情緒的な暴力への対峙の仕方が繰り返されてきたように思います。
改めて藤岡さんたちの研究成果を歴史教育にどのように摂取していくかを、私自身の課題として考えていきたいと決意しています。
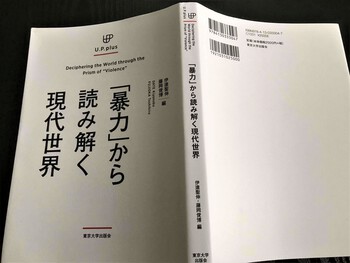
カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長



