「小中学校の保護者の皆さんが蘇南高校を実際に見学する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月30日15:54
今日は、木曽郡PTA連合会の子育て委員会の皆さんが、蘇南高校の見学に来てくださいました。今回が3年目になりますが、小中学校の保護者の皆さんに本校を知っていただく大切な機会です。北は木祖村、南が地元南木曽町まで14名の方々が、本校に足を運んでくださったのです。
私の方から「蘇南高校の学校づくり“ジャンプ期”」というタイトルで、この3年間の本校の教育実践をどのように積み上げてきたのかを報告しました。そして生徒会長の亀山さんから、現在の生徒会の活動について、3年生の松下さん・三石さんから総合探究の研究発表について、それぞれプレゼンを行いました。
その後、校内の授業風景を見学していただきました。英語のディベートをする風景、工業の製図をひく光景、簿記の複雑な仕組みを学ぶ風景、さまざまです。


一連の学校見学のしめくくりとして、参加者のグループ討論とシェアをしました。
「子どもたちの発表を聞いて、エネルギッシュなところに感心しました。」
「先生と生徒たちの関係がとても密接であることがよくわかりました。」
「地元にいながら高校生の具体的な様子を初めて知ることができてよかったです。」
「生徒たちがこんなにいきいきと探究していたことを家族に伝えたい。」
などのご感想をいただき、本当にうれしく思いました。
今の蘇南高校のいきいきとした学びの様子を知っていただけた半日でした。
お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。
なお、本校は随時中学生の皆さんの個別学校見学を受け付けていますので、お気軽にお越しください。
私の方から「蘇南高校の学校づくり“ジャンプ期”」というタイトルで、この3年間の本校の教育実践をどのように積み上げてきたのかを報告しました。そして生徒会長の亀山さんから、現在の生徒会の活動について、3年生の松下さん・三石さんから総合探究の研究発表について、それぞれプレゼンを行いました。
その後、校内の授業風景を見学していただきました。英語のディベートをする風景、工業の製図をひく光景、簿記の複雑な仕組みを学ぶ風景、さまざまです。


一連の学校見学のしめくくりとして、参加者のグループ討論とシェアをしました。
「子どもたちの発表を聞いて、エネルギッシュなところに感心しました。」
「先生と生徒たちの関係がとても密接であることがよくわかりました。」
「地元にいながら高校生の具体的な様子を初めて知ることができてよかったです。」
「生徒たちがこんなにいきいきと探究していたことを家族に伝えたい。」
などのご感想をいただき、本当にうれしく思いました。
今の蘇南高校のいきいきとした学びの様子を知っていただけた半日でした。
お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。
なお、本校は随時中学生の皆さんの個別学校見学を受け付けていますので、お気軽にお越しください。
「3年生が記者会見用のバックパネルを制作しています」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月29日15:54
本校の経営・ビジネス系列の3年「商品開発」の授業では、今年度、バックパネルの開発に取り組んでいます。
インターネットでの会議や発信が多くなってきた現在、その画面の背景になるパネルを制作しようとするわけです。もちろん対面の会議でもパネルを正面に置けばアクセントをつけられます。

私も楯先生が担当する「商品開発」の授業を参観しましたが、①スクール・アイデンティティは何か、②カリキュラムの特色とそれを表現する方法は何か、③スクール・カラーは何か、など多様な観点を組み合わせて、試行錯誤しながら、ひとりひとりが自分だけのバックパネルを開発しました。
現在は、全校投票を行い、最終決定に向けて動いています。
これからの時代、オンラインによる会議や情報発信の場は増えていくいっぽうだと思います。
生徒たちが作ったバックパネルが実際に使用できるときが楽しみです。

インターネットでの会議や発信が多くなってきた現在、その画面の背景になるパネルを制作しようとするわけです。もちろん対面の会議でもパネルを正面に置けばアクセントをつけられます。
私も楯先生が担当する「商品開発」の授業を参観しましたが、①スクール・アイデンティティは何か、②カリキュラムの特色とそれを表現する方法は何か、③スクール・カラーは何か、など多様な観点を組み合わせて、試行錯誤しながら、ひとりひとりが自分だけのバックパネルを開発しました。
現在は、全校投票を行い、最終決定に向けて動いています。
これからの時代、オンラインによる会議や情報発信の場は増えていくいっぽうだと思います。
生徒たちが作ったバックパネルが実際に使用できるときが楽しみです。
「『岩波講座世界歴史』の第11巻を出版します」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月26日19:42
このたび岩波書店から『岩波講座世界歴史11 構造化される世界――14~19世紀』を刊行しました。
全24巻のうち、私が責任編集を担当したのが第1巻と、この第11巻になります。東京大学の島田竜登先生に編集協力という形で多大なご協力をいただきました。
タイトルにあるように時間軸をモンゴル帝国から帝国主義の時代までの600年という長大なスパンにし、空間軸を地球全体に広げて、「近世の世界史」のなかに「世界の構造」をどのように見出していくのかということを考察しました。
私は編集に徹したので文章は書いていないのですが、力作揃いの内容になっていると思っています。
(内容の一部、敬称略)
・島田竜登「構造化される世界」
・山下範久「14~19世紀におけるパワーポリティクス」
・守川知子「宗派化する世界」
・ルシオ・デ・ソウザ/岡美穂子「奴隷たちの世界史」
・山崎岳「アジア海域における近世的国際秩序の形成」
・関哲行「近世スペインのユダヤ人とコンベルソ」
・小林和夫「商品連鎖のなかの西アフリカ」
・大橋厚子「東南アジアにおける植民地型政府投資の光と影」
・永島剛「感染症・検疫・国際社会」
・矢部正明「グローバル・ヒストリーと歴史教育」
・ほかにコラム(林裕文「東北地方のグローカル・ヒストリーとしての歴史実践」など)
たとえば、600年にわたる近世グローバル・ヒストリーの分析視点の提示(島田論文)、オスマン朝とサファヴィー朝の抗争と徳川政権の宗教政策の比較(守川論文)、奴隷たちの世界史の提示――そのなかで、たとえば、日本の戦国時代に捕虜となった人々が奴隷として売却されリスボンやメキシコシティなどで生きたことの実証(ソウザ/岡論文)、オランダがジャワでおこなった強制栽培制度を植民地型政府投資としてとらえて各国の公共政策との比較の視座をつくる(大橋論文)、高校のグローバル・ヒストリーの変遷の分析(矢部論文)、東北地方の近世と世界に連関を題材にした授業実践(林コラム)など、高校の歴史教育にかかわる方々にとっても、きっと大きな学びが得られるはずです。
スケールの大きな論文を書くために、それぞれの執筆者が多大なエネルギーを注いできました。私自身もかなりの時間をかけて編集してきました。
いつでも本を刊行するときは、大きな緊張感に包まれています。
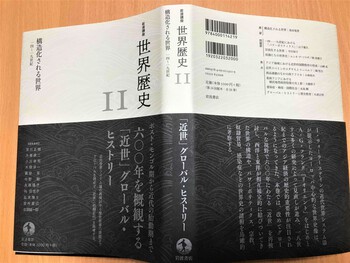
全24巻のうち、私が責任編集を担当したのが第1巻と、この第11巻になります。東京大学の島田竜登先生に編集協力という形で多大なご協力をいただきました。
タイトルにあるように時間軸をモンゴル帝国から帝国主義の時代までの600年という長大なスパンにし、空間軸を地球全体に広げて、「近世の世界史」のなかに「世界の構造」をどのように見出していくのかということを考察しました。
私は編集に徹したので文章は書いていないのですが、力作揃いの内容になっていると思っています。
(内容の一部、敬称略)
・島田竜登「構造化される世界」
・山下範久「14~19世紀におけるパワーポリティクス」
・守川知子「宗派化する世界」
・ルシオ・デ・ソウザ/岡美穂子「奴隷たちの世界史」
・山崎岳「アジア海域における近世的国際秩序の形成」
・関哲行「近世スペインのユダヤ人とコンベルソ」
・小林和夫「商品連鎖のなかの西アフリカ」
・大橋厚子「東南アジアにおける植民地型政府投資の光と影」
・永島剛「感染症・検疫・国際社会」
・矢部正明「グローバル・ヒストリーと歴史教育」
・ほかにコラム(林裕文「東北地方のグローカル・ヒストリーとしての歴史実践」など)
たとえば、600年にわたる近世グローバル・ヒストリーの分析視点の提示(島田論文)、オスマン朝とサファヴィー朝の抗争と徳川政権の宗教政策の比較(守川論文)、奴隷たちの世界史の提示――そのなかで、たとえば、日本の戦国時代に捕虜となった人々が奴隷として売却されリスボンやメキシコシティなどで生きたことの実証(ソウザ/岡論文)、オランダがジャワでおこなった強制栽培制度を植民地型政府投資としてとらえて各国の公共政策との比較の視座をつくる(大橋論文)、高校のグローバル・ヒストリーの変遷の分析(矢部論文)、東北地方の近世と世界に連関を題材にした授業実践(林コラム)など、高校の歴史教育にかかわる方々にとっても、きっと大きな学びが得られるはずです。
スケールの大きな論文を書くために、それぞれの執筆者が多大なエネルギーを注いできました。私自身もかなりの時間をかけて編集してきました。
いつでも本を刊行するときは、大きな緊張感に包まれています。
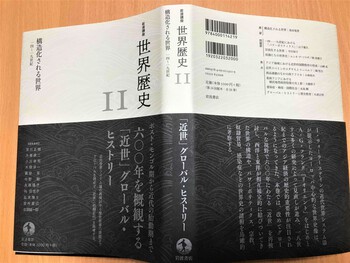
「青山学院大学大学院の授業を担当する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月25日20:15
昨日、11月24日(木)の夜、青山学院大学大学院の授業をゲスト講師として担当しました。直前まで蘇南高校で仕事をしていたので、オンラインで院生の皆さんとつながっての授業です。春にも講義をしているので今年度2度目の登板。
『岩波講座世界歴史01世界史とは何か』に感染症の世界史に関するご論文をいただいた飯島渉先生からの要請なので、必死に準備して臨みました。
今回は演習形式で、こんなことを院生さんたちと語り合いました。
「主体的・対話的で深い授業」が目指されているとはいえ、現在の高校の世界史の授業では、教科書に書いてあることが「問い」として投げかけられ、「ディスカッションしてみよう」と言われがちです。生徒からすれば「それ、教えてくれた方が効率的じゃない?」というのが本音です。
そのようなありきたりの「問い」(before)を、教科書的な歴史認識とか一般的な歴史の見方を「再考する」ことになって、「新しい見方をしている自分と出会う」ことになるような「問い」(after)に作り替えてみましょう。
これが事前に私が院生たちに出した課題です。
昨晩は、各自が考えた「beforeの問い」と「afterの問い」を発表して、それを互いに批評し合ってみました。
難しい課題を出してしまったかなと心配していましたが、さすが青学の皆さん、すばらしい「問い」を続々と考えてくれて、私自身が大いに刺激を受けました。
90分の授業があっという間に経ってしまい、あせりながら、私自身の「問い」の作り方の観点をお話してしめくくりました。
院生さんたちの瑞々しい知性に脱帽です。

『岩波講座世界歴史01世界史とは何か』に感染症の世界史に関するご論文をいただいた飯島渉先生からの要請なので、必死に準備して臨みました。
今回は演習形式で、こんなことを院生さんたちと語り合いました。
「主体的・対話的で深い授業」が目指されているとはいえ、現在の高校の世界史の授業では、教科書に書いてあることが「問い」として投げかけられ、「ディスカッションしてみよう」と言われがちです。生徒からすれば「それ、教えてくれた方が効率的じゃない?」というのが本音です。
そのようなありきたりの「問い」(before)を、教科書的な歴史認識とか一般的な歴史の見方を「再考する」ことになって、「新しい見方をしている自分と出会う」ことになるような「問い」(after)に作り替えてみましょう。
これが事前に私が院生たちに出した課題です。
昨晩は、各自が考えた「beforeの問い」と「afterの問い」を発表して、それを互いに批評し合ってみました。
難しい課題を出してしまったかなと心配していましたが、さすが青学の皆さん、すばらしい「問い」を続々と考えてくれて、私自身が大いに刺激を受けました。
90分の授業があっという間に経ってしまい、あせりながら、私自身の「問い」の作り方の観点をお話してしめくくりました。
院生さんたちの瑞々しい知性に脱帽です。

「二つの高校から視察に来ていただき、自分の鉄則を振り返る」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月24日20:38
今日は、二つの高校から蘇南高校に学校視察に来ていただきました。定期考査の最終日なので、授業の様子を見ていただけなかったのが残念ですが、本校のカリキュラム・マネジメントの取組をお話ししました。
まず、富山県立富山いずみ高校の古澤先生と平野先生です。大きな総合学科であり、多くの生徒さんが進学する高校の若い先生方と「生徒の成長を励ます学習評価」や「地域のなかに生徒が出ていく課題探究」をめぐって対話をさせていただきました。共通する課題意識も多く、私たちも励まされた思いです。

夕方にいらっしゃったのが、長野県伊那弥生ケ丘高校のファー先生と竹松先生です。お二人とは「生徒の成長を励ます学習評価」を中心テーマにして、かなり突っ込んだ対話をさせていただきました。実は、竹松先生と私は、かつて松川高校で一緒に担任をしてたくさんの学校改革を楽しみながら実践した関係です。松川高校の日々のおかげで今の私があると言えます。

こうして学校訪問をいただくことで、私自身もまた他校の実践に学び、蘇南高校をさらにバージョンアップしていくためのヒントをもらう経験ができます。
本当にうれしいことでした。
少しだけ昔話をすると、松川高校の竹松先生との日々から私が学んで、今も実践していることがいくつかあります。
○目の前の一人の生徒に語ることばは、その後ろに全校生徒がいると思って、ことばを考えるべき。
○悩んでいる生徒、道に迷う生徒を見つけたときに、どのように支援するかの方法はそのときどきに違うとしても、ただ一つ共通しているのは、「まあいいか」と絶対に思わず、チームとして見守ること。
今日、お越しくださった四人の先生方、本当にありがとうございました!
まず、富山県立富山いずみ高校の古澤先生と平野先生です。大きな総合学科であり、多くの生徒さんが進学する高校の若い先生方と「生徒の成長を励ます学習評価」や「地域のなかに生徒が出ていく課題探究」をめぐって対話をさせていただきました。共通する課題意識も多く、私たちも励まされた思いです。

夕方にいらっしゃったのが、長野県伊那弥生ケ丘高校のファー先生と竹松先生です。お二人とは「生徒の成長を励ます学習評価」を中心テーマにして、かなり突っ込んだ対話をさせていただきました。実は、竹松先生と私は、かつて松川高校で一緒に担任をしてたくさんの学校改革を楽しみながら実践した関係です。松川高校の日々のおかげで今の私があると言えます。
こうして学校訪問をいただくことで、私自身もまた他校の実践に学び、蘇南高校をさらにバージョンアップしていくためのヒントをもらう経験ができます。
本当にうれしいことでした。
少しだけ昔話をすると、松川高校の竹松先生との日々から私が学んで、今も実践していることがいくつかあります。
○目の前の一人の生徒に語ることばは、その後ろに全校生徒がいると思って、ことばを考えるべき。
○悩んでいる生徒、道に迷う生徒を見つけたときに、どのように支援するかの方法はそのときどきに違うとしても、ただ一つ共通しているのは、「まあいいか」と絶対に思わず、チームとして見守ること。
今日、お越しくださった四人の先生方、本当にありがとうございました!
「そして校長、武士になる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月23日13:00
今日は、日本遺産「妻籠宿」の一大イベント「文化文政風俗絵巻之行列」が3年ぶりに復活しました。
南木曽の人々が江戸時代の衣装をみにまとい、妻籠宿を華やかに練り歩くのです。先頭には太鼓叩き、瓦版配りが舞い、代官とそれを警護する武士、旅人、宿場の人々、木曽馬に乗った花嫁・・・と、まさにタイムスリップした人々が、宿場町を半日かけて行進していきます。

私は、町長さんと地方振興局長さん扮する代官を警護する「武士」となりました。
もう私は、このために蘇南高校の校長になったと言っても過言ではないのです!(「高文連演劇専門部会長」以上に、この「武士」という肩書にしびれます。)昨晩は興奮して眠れず、怒涛の2週間の疲れもふきとばし、今日は「武士」として生きました。
あいにくの冷たい雨でしたが、薄暗い妻籠宿はことのほか美しく、一生の思い出になるでしょう。

できればこのまま衣装をお借りして、明日の昇降口で生徒たちを迎えたかった。
「おぬしは、何者だ。どのような夢を持っているのか、言うてみよ。」と、刀に手をかけながら、ひとりひとりに語りかけたかった。
妻籠を愛する会の皆様、南木曽町の皆様、お越しくださった皆様、本当にありがとうございました!
南木曽の人々が江戸時代の衣装をみにまとい、妻籠宿を華やかに練り歩くのです。先頭には太鼓叩き、瓦版配りが舞い、代官とそれを警護する武士、旅人、宿場の人々、木曽馬に乗った花嫁・・・と、まさにタイムスリップした人々が、宿場町を半日かけて行進していきます。
私は、町長さんと地方振興局長さん扮する代官を警護する「武士」となりました。
もう私は、このために蘇南高校の校長になったと言っても過言ではないのです!(「高文連演劇専門部会長」以上に、この「武士」という肩書にしびれます。)昨晩は興奮して眠れず、怒涛の2週間の疲れもふきとばし、今日は「武士」として生きました。
あいにくの冷たい雨でしたが、薄暗い妻籠宿はことのほか美しく、一生の思い出になるでしょう。
できればこのまま衣装をお借りして、明日の昇降口で生徒たちを迎えたかった。
「おぬしは、何者だ。どのような夢を持っているのか、言うてみよ。」と、刀に手をかけながら、ひとりひとりに語りかけたかった。
妻籠を愛する会の皆様、南木曽町の皆様、お越しくださった皆様、本当にありがとうございました!
「浜松で講演をして一般道で南木曽に戻る冒険をする」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月22日20:53
今日は、静岡県西部社会科教育研究会で講演をするために浜松市立高校に伺いました。
昨日(東北大学の講演)と今日は、土日の演劇県大会の振替休なのです。とはいえ、朝にどうしても会っておきたい何人かの生徒に声をかけてから、浜松に向かいました。「おはよう」という挨拶だけなんですが・・・。
今日の講演は、これまで歴史教育の対話を重ねてきた、松井秀明さんや良知永行さんからの要請です。「「歴史総合」の授業をデザインするための基礎考察」というタイトルで、対話を有意味にするための「問い」をどのように作ればよいのかという報告をさせていただきました。
講演後の静岡の先生方との対話がとても有意義で、とりわけ「そのような問いをどうやったら、思いつくのか?」という質問には、はっとさせられました。
そうです!多くの皆さんにアクセス可能な「問いの発想方法」を提示する必要があるのです!今、書いている岩波新書に盛り込むべき必須の内容だと気づきました。
松井先生の「生徒がわくわくして身近に考えたくなるような問いでないと、いけないですよね」というご意見に、私も心から同感なのです。


あっという間の楽しいひとときのあと、私はある仮説の証明を試しました。
仮説とは、「南木曽の隣町の隣町が浜松市なので、浜松市から一般道で南木曽に帰ってきても近いはず。」というもの。
というわけで、三ケ日から三遠南信道で愛知県の奥三河の夜道を走り、鳳来峡→東栄町→豊根村をくねくね走り続けたところで力尽き、温泉で休養しました。
再起をはかり長野県に入ったものの、新野峠→売木峠→平谷峠→治部坂峠→寒原峠→清内路峠と六つの峠を(タヌキを轢きそうになりながら)走り続け、必死の思いで南木曽に帰ってきました。おそるべし、信州の地形の険しさ!
所要時間4時間。でもうな重を食べた時間と温泉につかった時間を含みます(笑)。高速道路を使った往路と大して変わりはありません。
仮説は正しかった! 松井さん、良知さん、また、語り合いましょう。
でも冬は絶対に無理なコースでした。
昨日(東北大学の講演)と今日は、土日の演劇県大会の振替休なのです。とはいえ、朝にどうしても会っておきたい何人かの生徒に声をかけてから、浜松に向かいました。「おはよう」という挨拶だけなんですが・・・。
今日の講演は、これまで歴史教育の対話を重ねてきた、松井秀明さんや良知永行さんからの要請です。「「歴史総合」の授業をデザインするための基礎考察」というタイトルで、対話を有意味にするための「問い」をどのように作ればよいのかという報告をさせていただきました。
講演後の静岡の先生方との対話がとても有意義で、とりわけ「そのような問いをどうやったら、思いつくのか?」という質問には、はっとさせられました。
そうです!多くの皆さんにアクセス可能な「問いの発想方法」を提示する必要があるのです!今、書いている岩波新書に盛り込むべき必須の内容だと気づきました。
松井先生の「生徒がわくわくして身近に考えたくなるような問いでないと、いけないですよね」というご意見に、私も心から同感なのです。
あっという間の楽しいひとときのあと、私はある仮説の証明を試しました。
仮説とは、「南木曽の隣町の隣町が浜松市なので、浜松市から一般道で南木曽に帰ってきても近いはず。」というもの。
というわけで、三ケ日から三遠南信道で愛知県の奥三河の夜道を走り、鳳来峡→東栄町→豊根村をくねくね走り続けたところで力尽き、温泉で休養しました。
再起をはかり長野県に入ったものの、新野峠→売木峠→平谷峠→治部坂峠→寒原峠→清内路峠と六つの峠を(タヌキを轢きそうになりながら)走り続け、必死の思いで南木曽に帰ってきました。おそるべし、信州の地形の険しさ!
所要時間4時間。でもうな重を食べた時間と温泉につかった時間を含みます(笑)。高速道路を使った往路と大して変わりはありません。
仮説は正しかった! 松井さん、良知さん、また、語り合いましょう。
でも冬は絶対に無理なコースでした。
「東北大学のセミナーでどきどきしながら講演をする」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月21日20:27
今日は、東北大学の高度教養教育・学生支援機構のウェビナー「IDE大学セミナー 学生の目を社会に開く――大学によるエンゲージメントの新展開」に、講演者のひとりとして参加しました。
開会あいさつ 大野英男さん(東北大総長)
趣旨説明 米澤彰純さん(東北大)
基調講演 吉田文さん(早稲田大)「翻弄を跳ね返す学生:大学と企業の狭間で」
講演1 小川幸司「高校生は、今、世界をどう学び、大学教育に、何を求めているのか?」
講演2 西村幹子さん(国際基督教大)「サービスラーニングで国際社会とともに学ぶ学生たち」
講演3 髙橋修一郎さん(リバネス代表取締役社長CEO)「ベンチャー企業からみた日本の大学教育」
コメント 濱中淳子さん(早稲田大)
閉会挨拶 滝澤博胤さん(東北大副学長)
私は、①「主体的・対話的で深い学び」への学びの改革が進められているといっても、「話し合ってそれで終わり」という形式的な学びが広がりつつあるのではないか、②そのことが、高校時代の学びへの満足感があまり高まっていないとか、大学の専門教育への関心が薄いといった高校生の意識調査結果につながっているのではないか、③今、必要なのは、高大連携の中で教科教育が「知の理論」を模索すべきではないのか、④それによって文科省や県教委から指示された「学びの改革」ではなく、内発的な学びの展開をすべきではないのか・・・といったことを報告しました。
ドキドキしながら登壇したのですが、論点が他の講演者と次々とつながりあい、私自身もこれから取り組むべきことがいくつか見えてきた、とても貴重な学びの経験をしました。
この問題関心や実践の重なり合いには、とても勇気づけられました。高校で私が試行錯誤していることは、大学の先生方も、企業の経営者も、同じように試行錯誤しておられるのだということに気づかされました。
思い切って社会に出て、さまざまな方々と「対話」をすることで、自分自身の「立ち位置」を獲得できるようになる・・・そんなことを改めて実感したのでした。
セミナーに誘っていただいた東北大学の米澤先生、一緒に登壇してくださった先生方、本当にありがとうございました。

開会あいさつ 大野英男さん(東北大総長)
趣旨説明 米澤彰純さん(東北大)
基調講演 吉田文さん(早稲田大)「翻弄を跳ね返す学生:大学と企業の狭間で」
講演1 小川幸司「高校生は、今、世界をどう学び、大学教育に、何を求めているのか?」
講演2 西村幹子さん(国際基督教大)「サービスラーニングで国際社会とともに学ぶ学生たち」
講演3 髙橋修一郎さん(リバネス代表取締役社長CEO)「ベンチャー企業からみた日本の大学教育」
コメント 濱中淳子さん(早稲田大)
閉会挨拶 滝澤博胤さん(東北大副学長)
私は、①「主体的・対話的で深い学び」への学びの改革が進められているといっても、「話し合ってそれで終わり」という形式的な学びが広がりつつあるのではないか、②そのことが、高校時代の学びへの満足感があまり高まっていないとか、大学の専門教育への関心が薄いといった高校生の意識調査結果につながっているのではないか、③今、必要なのは、高大連携の中で教科教育が「知の理論」を模索すべきではないのか、④それによって文科省や県教委から指示された「学びの改革」ではなく、内発的な学びの展開をすべきではないのか・・・といったことを報告しました。
ドキドキしながら登壇したのですが、論点が他の講演者と次々とつながりあい、私自身もこれから取り組むべきことがいくつか見えてきた、とても貴重な学びの経験をしました。
この問題関心や実践の重なり合いには、とても勇気づけられました。高校で私が試行錯誤していることは、大学の先生方も、企業の経営者も、同じように試行錯誤しておられるのだということに気づかされました。
思い切って社会に出て、さまざまな方々と「対話」をすることで、自分自身の「立ち位置」を獲得できるようになる・・・そんなことを改めて実感したのでした。
セミナーに誘っていただいた東北大学の米澤先生、一緒に登壇してくださった先生方、本当にありがとうございました。

「今日も出張をして土日は大会の審査員を務めます」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月18日18:33
昨日の長野市での県校長会から夜10時に一旦、南木曽に戻りました。
今朝は蘇南高校に出勤して、先生方との打ち合わせを1時間半ばかりのあいだに次々と行い、10時半頃、また出発。塩尻志学館高校で行われた中信地区校長会に出席しました。人事異動のこと、コロナ第8波への対応など、地区校長会で打ち合わせることも多くなってきています。
17時に会議が終了してから、松本市のキッセイ文化ホールに移動しました。高文連演劇専門部の県大会のリハーサルが行われているのです。明日・明後日の二日間の県大会は、3年ぶりに部員の関係者・県内の演劇部員に限って観客を受け入れ、有観客の中での開催となります。もちろんコロナの状況が厳しいので、あらゆるところに神経をとがらせています。
万一、部員の感染によって上演できなくなった学校には、ビデオ上映の形での発表を許可しています。有観客の発表とビデオ上映の発表の間に有利・不利をつくらないよう、3名の審査員のなかの一人に会長である私が就きます。
今週は、北海道出張から始まって、とにかく忙しく過ごしました。でも、まだまだ道半ば。
明日からの県大会の運営を、心を込めて行いたいと思っています。
ちなみに今晩はさすがに南木曽に戻ることをあきらめ、浅間温泉に宿泊します。

今朝は蘇南高校に出勤して、先生方との打ち合わせを1時間半ばかりのあいだに次々と行い、10時半頃、また出発。塩尻志学館高校で行われた中信地区校長会に出席しました。人事異動のこと、コロナ第8波への対応など、地区校長会で打ち合わせることも多くなってきています。
17時に会議が終了してから、松本市のキッセイ文化ホールに移動しました。高文連演劇専門部の県大会のリハーサルが行われているのです。明日・明後日の二日間の県大会は、3年ぶりに部員の関係者・県内の演劇部員に限って観客を受け入れ、有観客の中での開催となります。もちろんコロナの状況が厳しいので、あらゆるところに神経をとがらせています。
万一、部員の感染によって上演できなくなった学校には、ビデオ上映の形での発表を許可しています。有観客の発表とビデオ上映の発表の間に有利・不利をつくらないよう、3名の審査員のなかの一人に会長である私が就きます。
今週は、北海道出張から始まって、とにかく忙しく過ごしました。でも、まだまだ道半ば。
明日からの県大会の運営を、心を込めて行いたいと思っています。
ちなみに今晩はさすがに南木曽に戻ることをあきらめ、浅間温泉に宿泊します。
「新潟県の二つの高校の教頭先生と地域連携の未来を語り合う」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年11月17日17:25
今日は、新潟県中条高校の高見教頭先生と新潟県小出高校の鈴木教頭先生が、遠路はるばる蘇南高校に視察にお越しくださいました。
授業参観のあと、総合学科・進路指導・ICT教育の担当の教員が本校の取組をお話しし、後半は私がこの3年間の学校づくりと本校が大切にしていることについて説明して、意見交換をしました。
実は、今日の私は、県校長会秋季総会に出席しており、終日、長野市に身をおいていました。でもせっかくお二人が来てくださったので、校長会のほうは早退して、表参道の「もんぜんぷら座」の会議室に移動して、オンライン対話を行いました。
中条高校は胎内市にある110周年の伝統校であり、探究教養コースと地域産業コースを設置しています。小出高校は越後三山を望む魚沼市の素晴らしい環境にたつ高校で、地域との連携を大切にしつつ、9割の生徒が進学をしています。
お二人の教頭先生はともに地歴公民科で、拙著を読んでおられ、私はとても感激しました。さらに高見先生は、ともに県教育委員会の代表として総務省の「領土教育」の研修会(北方領土や尖閣諸島を学ぶという研修会で、結構、内容が充実していました)に参加した仲であることを思い出し、思わず「おおっ」と歓声をあげたのでした。
せっかくのこの出会いを、今後の交流につなげていきましょう、と語り合いました。(いつか新潟県に講演に行きますねと約束しました。)
私たちが語り合ったのは、地域と密に連携する高校の未来像についてです。未来の希望を語り合う仲間が増えていくことは何という喜びでしょうか。
高見先生、鈴木先生、これからもどうかよろしくお願いいたします。
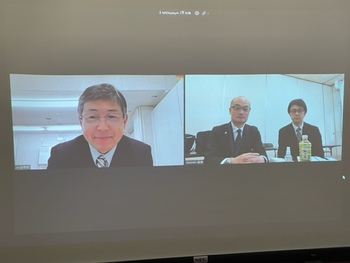
授業参観のあと、総合学科・進路指導・ICT教育の担当の教員が本校の取組をお話しし、後半は私がこの3年間の学校づくりと本校が大切にしていることについて説明して、意見交換をしました。
実は、今日の私は、県校長会秋季総会に出席しており、終日、長野市に身をおいていました。でもせっかくお二人が来てくださったので、校長会のほうは早退して、表参道の「もんぜんぷら座」の会議室に移動して、オンライン対話を行いました。
中条高校は胎内市にある110周年の伝統校であり、探究教養コースと地域産業コースを設置しています。小出高校は越後三山を望む魚沼市の素晴らしい環境にたつ高校で、地域との連携を大切にしつつ、9割の生徒が進学をしています。
お二人の教頭先生はともに地歴公民科で、拙著を読んでおられ、私はとても感激しました。さらに高見先生は、ともに県教育委員会の代表として総務省の「領土教育」の研修会(北方領土や尖閣諸島を学ぶという研修会で、結構、内容が充実していました)に参加した仲であることを思い出し、思わず「おおっ」と歓声をあげたのでした。
せっかくのこの出会いを、今後の交流につなげていきましょう、と語り合いました。(いつか新潟県に講演に行きますねと約束しました。)
私たちが語り合ったのは、地域と密に連携する高校の未来像についてです。未来の希望を語り合う仲間が増えていくことは何という喜びでしょうか。
高見先生、鈴木先生、これからもどうかよろしくお願いいたします。
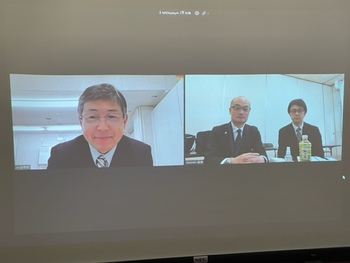
カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長



