「月岡先生&音楽部ミニコンサートを楽しむ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月30日09:02
蘇南高校は、コロナ禍であっても「100を0にしない」という方針で歩んでいますが、昨日、合唱コンクールの代替行事として「月岡先生&音楽部ミニコンサート」を開催しました。合唱コンクールは芸術に親しみ、クラスの団結をはかる大切な行事なのですが、専門家の分析・提言などをみると左右に1m以上離れ、前後に2m以上離れて練習するのが望ましいとのことで、普段の教室の練習環境でこれを実現するのは困難であると判断しました。
しかし「0にしない」ために、音楽に親しむ代替行事をしたいと望んでいたところ、後期の音楽の授業の新しい講師として、東京から月岡先生が赴任してくださったというわけなのです。
月岡穂波先生は音楽大学を卒業後、サクソフォンの個人演奏家として活躍しているのですが、このコロナ禍のなか、郷里の長野県で音楽の先生を求めている私たちの願いにこたえて、蘇南高校講師に赴任していただいたのです。
ミニコンサートは、発表の機会を失っている音楽部にも登場してもらう構想のもと、月岡先生のソロでの2曲に続き、月岡先生と音楽部のコラボでの3曲が演奏されました。
月岡先生のサックス演奏が始まると、その美しい音色に私も全校生徒も心をゆさぶられました。圧倒的な迫力です。演奏後にお礼の言葉を述べた生徒会長がいみじくも語ったように、「ここが体育館であることを忘れて聞き入っていたひととき」になりました。
音楽部の生徒たちの演奏も、月岡先生の力にしっかり支えられて、聴衆の心にまっすぐに届く素敵なものになりました。最後の曲は、副顧問の鈴木先生も演奏に参加し、まさに全員でつくりあげるステージに! 生徒たちにとっても一生の思い出になるでしょう。
このコンサートを行うには、セッティング図からタイムスケジュール表まで綿密な裏方の準備がありました。それをてきぱきこなす月岡先生に私はあらためて感心しました。そして音響操作は工業科の太田先生が担当。演劇を専門にしてきた私から見ても、太田先生の裏方の力はとても大きい。音楽室からの機材運搬は、教員総出によります。
「100を0にしない」思いによって、みんなでつくる温かなコンサートでした。

しかし「0にしない」ために、音楽に親しむ代替行事をしたいと望んでいたところ、後期の音楽の授業の新しい講師として、東京から月岡先生が赴任してくださったというわけなのです。
月岡穂波先生は音楽大学を卒業後、サクソフォンの個人演奏家として活躍しているのですが、このコロナ禍のなか、郷里の長野県で音楽の先生を求めている私たちの願いにこたえて、蘇南高校講師に赴任していただいたのです。
ミニコンサートは、発表の機会を失っている音楽部にも登場してもらう構想のもと、月岡先生のソロでの2曲に続き、月岡先生と音楽部のコラボでの3曲が演奏されました。
月岡先生のサックス演奏が始まると、その美しい音色に私も全校生徒も心をゆさぶられました。圧倒的な迫力です。演奏後にお礼の言葉を述べた生徒会長がいみじくも語ったように、「ここが体育館であることを忘れて聞き入っていたひととき」になりました。
音楽部の生徒たちの演奏も、月岡先生の力にしっかり支えられて、聴衆の心にまっすぐに届く素敵なものになりました。最後の曲は、副顧問の鈴木先生も演奏に参加し、まさに全員でつくりあげるステージに! 生徒たちにとっても一生の思い出になるでしょう。
このコンサートを行うには、セッティング図からタイムスケジュール表まで綿密な裏方の準備がありました。それをてきぱきこなす月岡先生に私はあらためて感心しました。そして音響操作は工業科の太田先生が担当。演劇を専門にしてきた私から見ても、太田先生の裏方の力はとても大きい。音楽室からの機材運搬は、教員総出によります。
「100を0にしない」思いによって、みんなでつくる温かなコンサートでした。

「長崎から来た平和の語り部と生徒たちとの対話」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月29日15:47
いよいよ2年生の長崎修学旅行が再来週に近づいてきました。
昨日は、長崎平和推進協会「家族・交流証言者」の田平由布子さんにはるばる長崎からお越しいただき、2時間続きの平和学習を行いました。
一言で言えば、とても感動的で濃密な2時間になったのです。
まず、「語り部」のイメージとは全く違う20代前半の女性の登場に一同(私も)驚きました。
「私は、長崎で生まれ育ち、平和教育を受けてきたのですが、当時は核問題、原爆のことに全く関心がありませんでした。原爆資料館に行ったという記録があるのですが、記憶がありません。」「平和学習とは毎年同じことを学んで退屈だし、自分とは関係がないと思っていました。そんな私が『語り部』につながる核兵器の勉強を始めたきっかけは…」という語り口ですから、私たちも思わず身体を乗り出して聞いてしまいます。
日常生活の目線で「平和学習」をとらえなおしていくことの大切さをあらためて考えさせられました。
田平さんは、3年前にお亡くなりになった吉田勲さんという被爆者の体験を語り継いでおられます。戦争体験者の高齢化により、記憶の継承が困難になっていくなかで、田平さんのような、後に続く世代が「語り継ぐ」という方法があるのだと知りました。その場合、私は当初、田平さんが証言を俳優のように丁寧に朗読している(演じている)と思っていました。
ところが田平さんは、最後の結論のところを録音テープで流し、それが機材の不調で途切れがちになったとき、「結論だけは吉田さんの肉声で聞いてほしかったのですが、やはり私がしゃべります。でも吉田さんの声は、息継ぎの場所も含めて暗記しているので、私の再現を聞いてください。」と、田平さんの語りを続けました。
そのとき私は気づいたのです。これは吉田さんの証言を田平さんが細部まで「再現」しようとしているうえに、田平さんの「思いが乗っている」から私たちの心を揺さぶるのだと。
戦争の記憶を語り継ぐことに、ひとすじの希望が見えたひとときでした。
1時間の講演の後、田平さんと生徒たちとのクエスチョンタイムが、なんと1時間続きました。まあよく質問の出てくること。しかもそれぞれがとても深い意味のある質問でした。「核抑止力とは何か」「キューバ危機で抑止論が破綻したら世界はどうなっていたか」などなど。
生徒たちの心が揺さぶられたからこそ、濃密な対話へと発展したのだと思います。
この学びをもとに実際に長崎の地に立って、蘇南高校生がどんなことを考えるのか。コロナ禍のなかの修学旅行が、いよいよ幕をあけます。

昨日は、長崎平和推進協会「家族・交流証言者」の田平由布子さんにはるばる長崎からお越しいただき、2時間続きの平和学習を行いました。
一言で言えば、とても感動的で濃密な2時間になったのです。
まず、「語り部」のイメージとは全く違う20代前半の女性の登場に一同(私も)驚きました。
「私は、長崎で生まれ育ち、平和教育を受けてきたのですが、当時は核問題、原爆のことに全く関心がありませんでした。原爆資料館に行ったという記録があるのですが、記憶がありません。」「平和学習とは毎年同じことを学んで退屈だし、自分とは関係がないと思っていました。そんな私が『語り部』につながる核兵器の勉強を始めたきっかけは…」という語り口ですから、私たちも思わず身体を乗り出して聞いてしまいます。
日常生活の目線で「平和学習」をとらえなおしていくことの大切さをあらためて考えさせられました。
田平さんは、3年前にお亡くなりになった吉田勲さんという被爆者の体験を語り継いでおられます。戦争体験者の高齢化により、記憶の継承が困難になっていくなかで、田平さんのような、後に続く世代が「語り継ぐ」という方法があるのだと知りました。その場合、私は当初、田平さんが証言を俳優のように丁寧に朗読している(演じている)と思っていました。
ところが田平さんは、最後の結論のところを録音テープで流し、それが機材の不調で途切れがちになったとき、「結論だけは吉田さんの肉声で聞いてほしかったのですが、やはり私がしゃべります。でも吉田さんの声は、息継ぎの場所も含めて暗記しているので、私の再現を聞いてください。」と、田平さんの語りを続けました。
そのとき私は気づいたのです。これは吉田さんの証言を田平さんが細部まで「再現」しようとしているうえに、田平さんの「思いが乗っている」から私たちの心を揺さぶるのだと。
戦争の記憶を語り継ぐことに、ひとすじの希望が見えたひとときでした。
1時間の講演の後、田平さんと生徒たちとのクエスチョンタイムが、なんと1時間続きました。まあよく質問の出てくること。しかもそれぞれがとても深い意味のある質問でした。「核抑止力とは何か」「キューバ危機で抑止論が破綻したら世界はどうなっていたか」などなど。
生徒たちの心が揺さぶられたからこそ、濃密な対話へと発展したのだと思います。
この学びをもとに実際に長崎の地に立って、蘇南高校生がどんなことを考えるのか。コロナ禍のなかの修学旅行が、いよいよ幕をあけます。

「予定調和の防災訓練にしない」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月28日18:00
ストーブ使用を前にして、今日は、木曽消防署南分署さんに来ていただき、防災訓練をおこないました。地震と火災が起こったことを想定しての避難の訓練です。
学校の防災訓練というのが形式的なものになりがちだという問題意識をもっていたので、次のことを改革しました。
第一に、これは「教員のための訓練」である。出火場所を避けて生徒を安全に移動させ、授業担当者が責任をもって点呼をし、報告すべきこと。(避難したらHRごとに並び替えて点呼をとるのでは意味がない。授業担当者が責任を持つ。)
第二に、生徒にとっては、災害が起こるとどのような事態になるかを想像し、今できる予防措置を考えるとともに、過去の災害体験者の経験から学ぶ機会とする。そのためには校長講話をきちんと組み立ててじっくり話をする。
校長講話では、まず、阪神・淡路大震災のニュース映像を視聴しました。今の高校生の年代にとっては、もう歴史年表の中の出来事です。そして精神科医の中井久夫の著書『災害がほんとうに襲った時』(みすず書房)や林 春男ほか編『防災の決め手「災害エスノグラフィー」』(NHK出版)などをもとにしながら、どのような悲劇が起こり、救助や被災者支援を行う人々がどのような「想定外」の困難に直面したかを考えました。
中井久夫が書いている、「有効なことをなしえたものは、すべて、自分でその時点で最良と思う行動を自己の責任において行ったものであった」という経験は、未来に向かって語り継いでいくべきものです。誰かが指示を出してくれる。誰かが何かをしてくれる。そうやって誰かを待つのではなく、自分で判断して自分から動いた者が、その事態をのりこえたのだというのです。
「ブリコラージュをしていこう」と私がコロナ禍のなかで生徒に語ってきたこととつながるように思いました。(講話の内容はHPに載せました。)
消防署さんと今日の反省を振り返りました。やってみて課題が次々と浮かび上がってきました。どのように点呼を早めていくのか。どのように校舎の外に迅速に出るのか。誰もが緊急放送を操作できるようにするにはどうするか・・・などです。
「想定外だからできなかった」という言い訳をすることだけは、断じてしたくありません。
「災害後」というのは、「災害間」である(次の災害までのインターバルでしかない)という考え方を心にとめ、危機管理システムを磨いていこうと決意した一日でした。

学校の防災訓練というのが形式的なものになりがちだという問題意識をもっていたので、次のことを改革しました。
第一に、これは「教員のための訓練」である。出火場所を避けて生徒を安全に移動させ、授業担当者が責任をもって点呼をし、報告すべきこと。(避難したらHRごとに並び替えて点呼をとるのでは意味がない。授業担当者が責任を持つ。)
第二に、生徒にとっては、災害が起こるとどのような事態になるかを想像し、今できる予防措置を考えるとともに、過去の災害体験者の経験から学ぶ機会とする。そのためには校長講話をきちんと組み立ててじっくり話をする。
校長講話では、まず、阪神・淡路大震災のニュース映像を視聴しました。今の高校生の年代にとっては、もう歴史年表の中の出来事です。そして精神科医の中井久夫の著書『災害がほんとうに襲った時』(みすず書房)や林 春男ほか編『防災の決め手「災害エスノグラフィー」』(NHK出版)などをもとにしながら、どのような悲劇が起こり、救助や被災者支援を行う人々がどのような「想定外」の困難に直面したかを考えました。
中井久夫が書いている、「有効なことをなしえたものは、すべて、自分でその時点で最良と思う行動を自己の責任において行ったものであった」という経験は、未来に向かって語り継いでいくべきものです。誰かが指示を出してくれる。誰かが何かをしてくれる。そうやって誰かを待つのではなく、自分で判断して自分から動いた者が、その事態をのりこえたのだというのです。
「ブリコラージュをしていこう」と私がコロナ禍のなかで生徒に語ってきたこととつながるように思いました。(講話の内容はHPに載せました。)
消防署さんと今日の反省を振り返りました。やってみて課題が次々と浮かび上がってきました。どのように点呼を早めていくのか。どのように校舎の外に迅速に出るのか。誰もが緊急放送を操作できるようにするにはどうするか・・・などです。
「想定外だからできなかった」という言い訳をすることだけは、断じてしたくありません。
「災害後」というのは、「災害間」である(次の災害までのインターバルでしかない)という考え方を心にとめ、危機管理システムを磨いていこうと決意した一日でした。

「古典はやはり自分で読んでこそ偉大さがわかる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月27日20:29
今日は、学校管理者の労働安全衛生に係る研修会で、終日、総合教育センターに出張でした。
そこで時計の針を戻して、この土日の読書について書きます。
私のような世界史の教師は、よく自分が読んでもないのに「この時代のこの著作は世界史上、画期的で…」などと授業で解説をしがちです。私はそういう語り口が嫌で、なるべく自分で読んで、自分の言葉で「世界の名著」を授業で分析してきました。それでも未読の「名著」は多くて、その代表が、古代ローマ帝国末期のキリスト教神学者アウグスティヌスの『神の国』でした。膨大な分量であるうえに、神学の議論についていけないと思っていたからです。
しかし、今、執筆中の論文で、アウグスティヌスに言及することを避けて通れなくなり、誰かのアウグスティヌス論ではなく、自分であたるしかないと、土曜日に『神の国』を読み始めました。ところがこれが実に面白いのです。見事に「はまり」、夢中になって読み進め、上下二巻、二段組、計1600ページを日曜日の夜に完読しました。
なんでもっと早く読まなかったのだろうと、後悔することしきりです。
ラテン語の原題は De Civitate Dei 、つまり「神の国」というより「神の市民共同体(キヴィタス)」。世界史の教科書には、滅びゆくローマ帝国のような「地上の国」とは異なって、「神の国」は永遠だと論じた、などと解説されているのですが、アウグスティヌスは、こう語っているのだとわかりました。
人間の「高慢さ」によって動かされてきた歴史上の国家(「地上の国」)の歴史のなかにも、神への信仰に裏付けられた「愛」によってむすばれている「神の市民共同体」が受け継がれてきており、それはどんなに「地上の国」が滅亡しても、簡単には滅ばない。必ず未来に向かって発展していくだろう。
その「神の市民共同体」では人間をどのように見つめるのかという例として、彼が冒頭でとりあげるのは、戦争で性暴力の犠牲となった女性に対して、恥ずべき罪を犯したと決めつけないような人間の見方をすることでした。ゲルマン民族のローマ侵攻で現実に起こっていた女性の悲劇をまのあたりにしたからのことでしょう。
今から1600年前の著作の問題意識の何と普遍的なことか!
「名著」がなぜ「名著」なのかは、自分で読んでこそわかるのだと、あらためて思ったのでした。
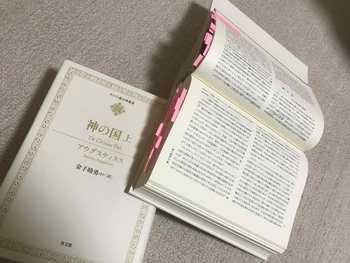
そこで時計の針を戻して、この土日の読書について書きます。
私のような世界史の教師は、よく自分が読んでもないのに「この時代のこの著作は世界史上、画期的で…」などと授業で解説をしがちです。私はそういう語り口が嫌で、なるべく自分で読んで、自分の言葉で「世界の名著」を授業で分析してきました。それでも未読の「名著」は多くて、その代表が、古代ローマ帝国末期のキリスト教神学者アウグスティヌスの『神の国』でした。膨大な分量であるうえに、神学の議論についていけないと思っていたからです。
しかし、今、執筆中の論文で、アウグスティヌスに言及することを避けて通れなくなり、誰かのアウグスティヌス論ではなく、自分であたるしかないと、土曜日に『神の国』を読み始めました。ところがこれが実に面白いのです。見事に「はまり」、夢中になって読み進め、上下二巻、二段組、計1600ページを日曜日の夜に完読しました。
なんでもっと早く読まなかったのだろうと、後悔することしきりです。
ラテン語の原題は De Civitate Dei 、つまり「神の国」というより「神の市民共同体(キヴィタス)」。世界史の教科書には、滅びゆくローマ帝国のような「地上の国」とは異なって、「神の国」は永遠だと論じた、などと解説されているのですが、アウグスティヌスは、こう語っているのだとわかりました。
人間の「高慢さ」によって動かされてきた歴史上の国家(「地上の国」)の歴史のなかにも、神への信仰に裏付けられた「愛」によってむすばれている「神の市民共同体」が受け継がれてきており、それはどんなに「地上の国」が滅亡しても、簡単には滅ばない。必ず未来に向かって発展していくだろう。
その「神の市民共同体」では人間をどのように見つめるのかという例として、彼が冒頭でとりあげるのは、戦争で性暴力の犠牲となった女性に対して、恥ずべき罪を犯したと決めつけないような人間の見方をすることでした。ゲルマン民族のローマ侵攻で現実に起こっていた女性の悲劇をまのあたりにしたからのことでしょう。
今から1600年前の著作の問題意識の何と普遍的なことか!
「名著」がなぜ「名著」なのかは、自分で読んでこそわかるのだと、あらためて思ったのでした。
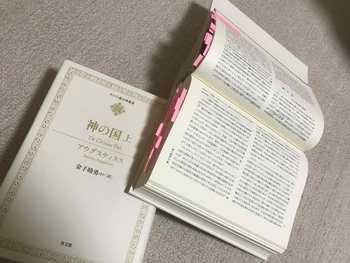
「初任の先生の研究授業をみんなで参観する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月26日21:19
今日は、今年度、長野県の教員に採用された先生の研究授業を行いました。
本校は、地理的に都市部から離れた場所に立地しているために、初任校として赴任する先生がとても多いのが特徴です。教員生活の船出をした先生方は、この後の長い教員生活の「礎」を私たちと一緒に作り上げることになります。
私にとって、生徒ひとりひとりがとても大切であるのと同様に、先生方ひとりひとりも、かけがえのない大切な存在です。
ゆえに私は、初任の先生方の授業を折々に見せてもらっては、いいところ、改善した方がいいところなどを対話しています。今日研究授業を行った先生の授業も、繰り返し見せてもらって、よりよい授業とは何かについて一緒に考えてきました。
今日の研究授業は、3年の選択科目「政治・経済」で「消費者問題」がテーマでした。先生は、電子黒板を使いながら、わかりやすく簡潔に説明をするとともに、単元の大切なテーマについてグループディスカッションをして、その気づきを授業の推進力にしていきます。生徒たちもディスカッションに慣れてきていて、多少抽象的なお題であっても躊躇せずに考察を進め、一番大切だと思った内容をリフレクションタイムで発表していきます。
夏休み前に比べると目覚ましく授業の内容が深くなってきたことに、私は感心させられました。先生も生徒もともに進歩しているのです。心の中で、「いいねえ」「うまくなったねえ」と呟きながら1時間の授業を参観したのでした。
昨日の日曜日の夕方のことです。私が仕事をするために学校に出勤すると、ひとりで黙々と研究授業の準備をしている先生の姿がありました。明日にかける意気込みをそのときにひしひしと感じました。
先週の職員会で、私は、「初任者の研究授業は、その先生にとって一生の思い出になる大切な機会なので、そのとき授業のない人は、ぜひ、みてアドバイスをしましょう」と呼びかけました。
教室のうしろにびっしりと埋まった同僚たちの列は、全身全霊をこめて授業を行う初任の先生の「未来」へのエールでもありました。

本校は、地理的に都市部から離れた場所に立地しているために、初任校として赴任する先生がとても多いのが特徴です。教員生活の船出をした先生方は、この後の長い教員生活の「礎」を私たちと一緒に作り上げることになります。
私にとって、生徒ひとりひとりがとても大切であるのと同様に、先生方ひとりひとりも、かけがえのない大切な存在です。
ゆえに私は、初任の先生方の授業を折々に見せてもらっては、いいところ、改善した方がいいところなどを対話しています。今日研究授業を行った先生の授業も、繰り返し見せてもらって、よりよい授業とは何かについて一緒に考えてきました。
今日の研究授業は、3年の選択科目「政治・経済」で「消費者問題」がテーマでした。先生は、電子黒板を使いながら、わかりやすく簡潔に説明をするとともに、単元の大切なテーマについてグループディスカッションをして、その気づきを授業の推進力にしていきます。生徒たちもディスカッションに慣れてきていて、多少抽象的なお題であっても躊躇せずに考察を進め、一番大切だと思った内容をリフレクションタイムで発表していきます。
夏休み前に比べると目覚ましく授業の内容が深くなってきたことに、私は感心させられました。先生も生徒もともに進歩しているのです。心の中で、「いいねえ」「うまくなったねえ」と呟きながら1時間の授業を参観したのでした。
昨日の日曜日の夕方のことです。私が仕事をするために学校に出勤すると、ひとりで黙々と研究授業の準備をしている先生の姿がありました。明日にかける意気込みをそのときにひしひしと感じました。
先週の職員会で、私は、「初任者の研究授業は、その先生にとって一生の思い出になる大切な機会なので、そのとき授業のない人は、ぜひ、みてアドバイスをしましょう」と呼びかけました。
教室のうしろにびっしりと埋まった同僚たちの列は、全身全霊をこめて授業を行う初任の先生の「未来」へのエールでもありました。

「総合研究のPBLで中学生の学習サポートを始めた生徒たち」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月23日22:53
本校では、総合的な探究(学習)の時間が、3年生の金曜日の4・5・6限に「総合研究」という名称で設置されています。もちろん1・2年次での「産業社会と人間」でも課題研究を進めていますから、探究学習にあてる時間は3年間を通じてかなり多いのです。
この「総合研究」が、12月の課題研究発表会に向けて最後のラストスパートにかかっています。
生徒たちは、社会の課題を何らかの実践によって解決しようとしているのですが、その取組が実に面白い。社会課題解決のプロジェクト型学習(PBL)を彼らなりに懸命に追求しているのです。
たとえば、昨日から、南木曽中学校の3年生の朝の自習に「学習サポーター」として入った生徒がいます。伊藤さん、鈴木さんの二人は、コロナ臨時休校の際に県内公立高校がどのような対応をしたのかを聞き取り調査をし、本校の対応と比較しながら、これからの教育に必要な学習支援のあり方を考えました。
次いで、公立中学のコロナ臨時休校で直面した教育課題についてインタビュー取材し、高校生としてコロナ臨時休校の経験から得たものを地元の中学生に還元できないかということを考えたのです。そして中学生の学習サポートを「対面」で行い、その経験をもとにオンラインでの学習サポートとしてどのようなことが可能かを考察していくというプロジェクトをたてました。
二人は南木曽中学校の上田校長先生に、中学生の学習支援をさせていただけないかと直訴し、校長先生、学年の先生方の温かな応援をいただき、「学習サポーター」として任命していただいたわけなのです。二人は蘇南高校内でサポーターの輪を広げようと呼びかけています。
まず初回は、2人だけで、南木曽中学を訪問しました。
校長室で上田校長先生より「学習サポーター」の任命を受け、会場となる図書館に向かいます。なんと20名をこえる3年生が自習をしています。挨拶をして、「わからないところを聞いてください」と声がけをします。でもそこに大きな壁。中学生も初対面の高校生にすぐに質問なんてできるわけがありません。どの生徒にどのタイミングで声がけをして、教えてあげるのがよいのか。こちらからアクションをしてあげるのが大切だと二人は気づきます。
私は二人の姿を見て、ふと気づいたことがあります。二人は、自分がうまく教えられるかドキドキしながら、中学生の質問に向き合っていました。中学生が「ここがわからない」と思うことについて、「わからないと思うのは当然だよね」という雰囲気がありました。そのことが学ぶ安心感をつくりだしていました。
教員が子どもたちに教え込む時に「こんなこともわからないのか」という上から目線になりがちなものが、この二人にはありません。・・・ああ、メンターというのは、こういうことなのか、と私はあらためて再発見したような気がしました。
二人は大学受験の直前です。本来は自分のことで精一杯なはずなのですが、それでも学習サポーターのPBLを全力でやろうとしています。
こういう学びの姿勢こそ、未来にきっともっと大きな花を咲かせるのだろうと、私は二人を見守っています。
そして学習サポーターの「下駄箱」(=承認された居場所)を用意してくださった南木曽中学校さんの優しさが、心にしみました。本当にありがとうございます。

この「総合研究」が、12月の課題研究発表会に向けて最後のラストスパートにかかっています。
生徒たちは、社会の課題を何らかの実践によって解決しようとしているのですが、その取組が実に面白い。社会課題解決のプロジェクト型学習(PBL)を彼らなりに懸命に追求しているのです。
たとえば、昨日から、南木曽中学校の3年生の朝の自習に「学習サポーター」として入った生徒がいます。伊藤さん、鈴木さんの二人は、コロナ臨時休校の際に県内公立高校がどのような対応をしたのかを聞き取り調査をし、本校の対応と比較しながら、これからの教育に必要な学習支援のあり方を考えました。
次いで、公立中学のコロナ臨時休校で直面した教育課題についてインタビュー取材し、高校生としてコロナ臨時休校の経験から得たものを地元の中学生に還元できないかということを考えたのです。そして中学生の学習サポートを「対面」で行い、その経験をもとにオンラインでの学習サポートとしてどのようなことが可能かを考察していくというプロジェクトをたてました。
二人は南木曽中学校の上田校長先生に、中学生の学習支援をさせていただけないかと直訴し、校長先生、学年の先生方の温かな応援をいただき、「学習サポーター」として任命していただいたわけなのです。二人は蘇南高校内でサポーターの輪を広げようと呼びかけています。
まず初回は、2人だけで、南木曽中学を訪問しました。
校長室で上田校長先生より「学習サポーター」の任命を受け、会場となる図書館に向かいます。なんと20名をこえる3年生が自習をしています。挨拶をして、「わからないところを聞いてください」と声がけをします。でもそこに大きな壁。中学生も初対面の高校生にすぐに質問なんてできるわけがありません。どの生徒にどのタイミングで声がけをして、教えてあげるのがよいのか。こちらからアクションをしてあげるのが大切だと二人は気づきます。
私は二人の姿を見て、ふと気づいたことがあります。二人は、自分がうまく教えられるかドキドキしながら、中学生の質問に向き合っていました。中学生が「ここがわからない」と思うことについて、「わからないと思うのは当然だよね」という雰囲気がありました。そのことが学ぶ安心感をつくりだしていました。
教員が子どもたちに教え込む時に「こんなこともわからないのか」という上から目線になりがちなものが、この二人にはありません。・・・ああ、メンターというのは、こういうことなのか、と私はあらためて再発見したような気がしました。
二人は大学受験の直前です。本来は自分のことで精一杯なはずなのですが、それでも学習サポーターのPBLを全力でやろうとしています。
こういう学びの姿勢こそ、未来にきっともっと大きな花を咲かせるのだろうと、私は二人を見守っています。
そして学習サポーターの「下駄箱」(=承認された居場所)を用意してくださった南木曽中学校さんの優しさが、心にしみました。本当にありがとうございます。

「判断力を丁寧に育成するために」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月22日20:37
今年度、蘇南高校は、全国工業高等学校長協会(全工協)の評価手法研究に関わる実践研究校に指定していただき、新しい授業評価のカリキュラムを開発しています。
今日は、その第1回研究授業を実施し、工業科の藤城先生が新たな試みの授業を行い、全工協の運営委員である小山宣樹先生に指導助言をいただきながら、研修を深めました。
藤城先生は、まず地元企業・官公庁に「今の時代に入社(入庁)する若者に身に付けておいてほしい資質・能力は何か」を尋ねるアンケートをとりました。木曽郡南部・中津川の30社近くから回答をいただきました。アンケートに項目としてあげた資質・能力は、文部科学省が学習指導要領で重視しているもののほか、OECDの「学びのコンパス」などを参考にしています。
私たちは、自己肯定感、自己効力感、協調性などが多数になるのではないかと思っていたのですが、最も多くあげられたのは、「判断力」でした。最初、意外に思ったのですが、考えてみれば、唯一解のない現実の中で蓋然性の高い最適解を判断していく「判断力」こそ、コロナ禍のなかで私たちに日々問われているものなのです。
しかし学習指導要領で「思考力・判断力・表現力」の育成が大切だと言うとき、思考力と表現力の育成については詳しく構想されている一方で、判断力はブラックボックスになっているきらいがあります。
そこで藤城先生は、判断力を育てるために単元を「3ステップ」で進めるカリキュラムを考え、まずは第一ステップ、次に第二ステップ、そして第三ステップに進みながら、この単元の目標の判断力を見につける組み立てにしました。スモールステップこそ学びの「手すり」です。
今日は、その第一ステップだったのです。授業の冒頭で、「何のために今日の授業をするのか」を説明し、授業の終わりでルーブリック表を使って自己評価をして「目標がどの程度達成できたか」を自己評価しました。
何のために今日の学びがあったのかが、生徒にとってきわめて明瞭になり、とても学びやすい、腑に落ちる授業になったのだと思います。
小山先生からは、「評価というのは特別なことではなく、私たちは日々の授業で何らかの評価を生徒に無意識のうちにやっている。そしてそれがときに生徒を傷つける。ならば生徒を伸ばす評価を自覚的に考え、生徒自身が自分のことを、自信をもって評価できるような授業を創造していくことが大切ではないか」という助言をいただきました。
心にしみる助言でした。
「先生の授業で判断力を育てるカリキュラムって、どうなりますか」と私は最近、いろんな先生と対話を重ねています。これはそれぞれの教科をメタレベルで見つめ直す、いい機会になっています。
唯一解ではなく、最適解をどう判断するかという知的回路が教科ごとにさまざまなのです。多くの要素が複雑にからみあう工業科は、最適解の思考が多いです。理科であれば、生物にその要素が多くなりますが、それでも参照データから最適解はしぼりこまれそうです。地歴公民科の最適解の根拠は多岐にわたり、往々にして倫理的根拠が連動してきそうです。国語科は、限定されたテキストのコンテキストを対象にするため、意外と最適解という発想がうまれにくいということもわかってきました。
複数の教員で「判断力」育成の試みを行い、それをつなぎあわせれば、魅力的な「タペストリー」ができるかもしれません。それが学問の多元性をメタレベルで理解できるような「タペストリー」になれば、学校の「知の魅力」が構造的にわかるかもしれないと、ワクワクしています。

今日は、その第1回研究授業を実施し、工業科の藤城先生が新たな試みの授業を行い、全工協の運営委員である小山宣樹先生に指導助言をいただきながら、研修を深めました。
藤城先生は、まず地元企業・官公庁に「今の時代に入社(入庁)する若者に身に付けておいてほしい資質・能力は何か」を尋ねるアンケートをとりました。木曽郡南部・中津川の30社近くから回答をいただきました。アンケートに項目としてあげた資質・能力は、文部科学省が学習指導要領で重視しているもののほか、OECDの「学びのコンパス」などを参考にしています。
私たちは、自己肯定感、自己効力感、協調性などが多数になるのではないかと思っていたのですが、最も多くあげられたのは、「判断力」でした。最初、意外に思ったのですが、考えてみれば、唯一解のない現実の中で蓋然性の高い最適解を判断していく「判断力」こそ、コロナ禍のなかで私たちに日々問われているものなのです。
しかし学習指導要領で「思考力・判断力・表現力」の育成が大切だと言うとき、思考力と表現力の育成については詳しく構想されている一方で、判断力はブラックボックスになっているきらいがあります。
そこで藤城先生は、判断力を育てるために単元を「3ステップ」で進めるカリキュラムを考え、まずは第一ステップ、次に第二ステップ、そして第三ステップに進みながら、この単元の目標の判断力を見につける組み立てにしました。スモールステップこそ学びの「手すり」です。
今日は、その第一ステップだったのです。授業の冒頭で、「何のために今日の授業をするのか」を説明し、授業の終わりでルーブリック表を使って自己評価をして「目標がどの程度達成できたか」を自己評価しました。
何のために今日の学びがあったのかが、生徒にとってきわめて明瞭になり、とても学びやすい、腑に落ちる授業になったのだと思います。
小山先生からは、「評価というのは特別なことではなく、私たちは日々の授業で何らかの評価を生徒に無意識のうちにやっている。そしてそれがときに生徒を傷つける。ならば生徒を伸ばす評価を自覚的に考え、生徒自身が自分のことを、自信をもって評価できるような授業を創造していくことが大切ではないか」という助言をいただきました。
心にしみる助言でした。
「先生の授業で判断力を育てるカリキュラムって、どうなりますか」と私は最近、いろんな先生と対話を重ねています。これはそれぞれの教科をメタレベルで見つめ直す、いい機会になっています。
唯一解ではなく、最適解をどう判断するかという知的回路が教科ごとにさまざまなのです。多くの要素が複雑にからみあう工業科は、最適解の思考が多いです。理科であれば、生物にその要素が多くなりますが、それでも参照データから最適解はしぼりこまれそうです。地歴公民科の最適解の根拠は多岐にわたり、往々にして倫理的根拠が連動してきそうです。国語科は、限定されたテキストのコンテキストを対象にするため、意外と最適解という発想がうまれにくいということもわかってきました。
複数の教員で「判断力」育成の試みを行い、それをつなぎあわせれば、魅力的な「タペストリー」ができるかもしれません。それが学問の多元性をメタレベルで理解できるような「タペストリー」になれば、学校の「知の魅力」が構造的にわかるかもしれないと、ワクワクしています。

「澄み切った秋晴れのなか、ソバを収穫する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月21日14:28
今日も木曽谷は雲ひとつない最高の秋晴れです。
2年の経営ビジネス系列の「課題研究」の授業では、本校OBの早川さんから畑をご提供いただき、ソバの栽培、収穫、加工を生徒たちが実習する学習をおこなっています。県木曽農業農村支援センター、南木曽町役場、JAなどの皆様からのご指導をいただきながら、今日はソバの収穫を行いました。
鎌で刈り取ったソバを束ねて縛り、それをトラックに積んでいきます。いっぱいに積んだ後は、落穂拾いを行います。南木曽岳が青空に映える木曽川西岸の畑で、生徒たちは笑顔で汗を流していました。
ソバの収量はその年の天候に大きく左右されます。今年は雨が多かったためか、雑草の背丈が高くなってしまい、例年よりも収穫量が減りそうです。それでもトラックいっぱいの刈り取ったソバを別の場所に運び、はぜ掛けをしていただきました。
家で収穫した経験があるかと生徒に聞いたところ、家の前の家庭菜園の野菜を採って台所に運んだという経験はあるようです。でも播種をして一面に実った農産物を収穫するという経験は初めてとのこと。「いのち」をいかし、その「いのち」に自分の「いのち」がいかされるという、日々のいとなみをあらためて自覚する格好の学びになりました。
早川さんの上の畑では、野沢菜の芽が顔を出していました。
厳しい冬に向かうこの時期に、すくすくと成長していくのは、人間だけではないのですね。

2年の経営ビジネス系列の「課題研究」の授業では、本校OBの早川さんから畑をご提供いただき、ソバの栽培、収穫、加工を生徒たちが実習する学習をおこなっています。県木曽農業農村支援センター、南木曽町役場、JAなどの皆様からのご指導をいただきながら、今日はソバの収穫を行いました。
鎌で刈り取ったソバを束ねて縛り、それをトラックに積んでいきます。いっぱいに積んだ後は、落穂拾いを行います。南木曽岳が青空に映える木曽川西岸の畑で、生徒たちは笑顔で汗を流していました。
ソバの収量はその年の天候に大きく左右されます。今年は雨が多かったためか、雑草の背丈が高くなってしまい、例年よりも収穫量が減りそうです。それでもトラックいっぱいの刈り取ったソバを別の場所に運び、はぜ掛けをしていただきました。
家で収穫した経験があるかと生徒に聞いたところ、家の前の家庭菜園の野菜を採って台所に運んだという経験はあるようです。でも播種をして一面に実った農産物を収穫するという経験は初めてとのこと。「いのち」をいかし、その「いのち」に自分の「いのち」がいかされるという、日々のいとなみをあらためて自覚する格好の学びになりました。
早川さんの上の畑では、野沢菜の芽が顔を出していました。
厳しい冬に向かうこの時期に、すくすくと成長していくのは、人間だけではないのですね。

「強歩大会のかわりにクラスマッチを行いました」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月20日18:15
まさに秋晴れという素晴らしい天気のもと、全校クラスマッチを実施しました。本来は、強歩大会の予定だったのですが、生徒同士の間隔を一定に保つことが出来ないことや、山間地の道路を走るときにクマとの遭遇の可能性を否定できないことから、体育館でバドミントン、グラウンドでソフトボールを競技するクラスマッチに変更したのでした。多くの生徒にとっては、強歩大会よりもクラスマッチのほうを歓迎しています。
学年に関係なく全校のクラスが総当たりになるのですが、生徒たちはそれぞれ笑顔でスポーツを楽しんでいました。
本校の生徒たちは、文化祭もそうですが、このような行事のときに、お互いを支え合って、やさしく楽しく楽しむことができます。穏やかな笑い声と掛け声があちこちから聞こえてくる、とても明るい一日でした。
ところで、先週の金曜日午後に設置されたグラウンドに下りていく手すりですが、これが生徒たちに好評で、何人もの生徒から「これいいですね。前は怖かったですから。」と声をかけてもらいました。階段のまんなかに手すりが出来たために、右側を登って、左側を降りるという人の流れもスムースになり、すれ違いざまの衝突のおそれもなくなりました。
クラスマッチに間に合うように工事を施工したので、早速、手すりが重宝されている様子を見ることができ、私もとても嬉しくなりました。

学年に関係なく全校のクラスが総当たりになるのですが、生徒たちはそれぞれ笑顔でスポーツを楽しんでいました。
本校の生徒たちは、文化祭もそうですが、このような行事のときに、お互いを支え合って、やさしく楽しく楽しむことができます。穏やかな笑い声と掛け声があちこちから聞こえてくる、とても明るい一日でした。
ところで、先週の金曜日午後に設置されたグラウンドに下りていく手すりですが、これが生徒たちに好評で、何人もの生徒から「これいいですね。前は怖かったですから。」と声をかけてもらいました。階段のまんなかに手すりが出来たために、右側を登って、左側を降りるという人の流れもスムースになり、すれ違いざまの衝突のおそれもなくなりました。
クラスマッチに間に合うように工事を施工したので、早速、手すりが重宝されている様子を見ることができ、私もとても嬉しくなりました。

「振替休日は東山魁夷の絵画を」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月19日20:01
今日の本校は、振替休日でした。
飯田の自宅から昼頃、天白住宅に戻ってくると、「おお」と思わず声をあげてしまいました。中央アルプスの峻厳な峰々が、純白の姿になっているではありませんか。純白のアルプスと、深い緑とパッチワークのように紅葉色が散らされた木曽の里山とのコントラストが美しい季節になりました。
ここのところ休日の私は、ひたすら歴史研究の論文を書いています。もうとにかく、ひたすらです。この3週間で400字詰め換算50枚分くらいの文章を書きました。でもまだ3合目。今まで登ったことのない急斜面を必死に登っている気分です。
夕方前、少し息抜きをしようと思い、岐阜県中津川市山口にある「東山魁夷心の旅路館」に行きました。住宅から車で15分ほどのところに東山魁夷の美術館があるのです。何という幸せ!
東山は学生時代に木曽川に沿って北上し、テントに泊まりながら、御嶽山登山をしています。旅の途中、山口に来たときに激しい夕立にあって農家にかけこんだ彼は、その家で親切なもてなしを受け、木曽谷の人々の素朴な生活と自然の雄大さに心をうたれます。のちに風景画家として歩むことになる東山の大切な原体験だったと言います。
今、開催中の展示企画は「旅――巡り合い」で、北欧やドイツの静謐な風景を描いた絵画や、鑑真和上が生まれ育った中国の山水風景を描いた絵画などと巡り合うことが出来ました。
深くどこまでもつづく森が、透みきった湖の面にあざやかに映し出されている絵画を見ながら、この湖の面のような論文を、どうやったら書けるのだろうかと考えています。

飯田の自宅から昼頃、天白住宅に戻ってくると、「おお」と思わず声をあげてしまいました。中央アルプスの峻厳な峰々が、純白の姿になっているではありませんか。純白のアルプスと、深い緑とパッチワークのように紅葉色が散らされた木曽の里山とのコントラストが美しい季節になりました。
ここのところ休日の私は、ひたすら歴史研究の論文を書いています。もうとにかく、ひたすらです。この3週間で400字詰め換算50枚分くらいの文章を書きました。でもまだ3合目。今まで登ったことのない急斜面を必死に登っている気分です。
夕方前、少し息抜きをしようと思い、岐阜県中津川市山口にある「東山魁夷心の旅路館」に行きました。住宅から車で15分ほどのところに東山魁夷の美術館があるのです。何という幸せ!
東山は学生時代に木曽川に沿って北上し、テントに泊まりながら、御嶽山登山をしています。旅の途中、山口に来たときに激しい夕立にあって農家にかけこんだ彼は、その家で親切なもてなしを受け、木曽谷の人々の素朴な生活と自然の雄大さに心をうたれます。のちに風景画家として歩むことになる東山の大切な原体験だったと言います。
今、開催中の展示企画は「旅――巡り合い」で、北欧やドイツの静謐な風景を描いた絵画や、鑑真和上が生まれ育った中国の山水風景を描いた絵画などと巡り合うことが出来ました。
深くどこまでもつづく森が、透みきった湖の面にあざやかに映し出されている絵画を見ながら、この湖の面のような論文を、どうやったら書けるのだろうかと考えています。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長



