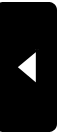「グラウンドに下りていく急傾斜の階段に手すりを付ける」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月16日18:57
ここのところ、プチ施設改修ラッシュです。
今日、業者に入ってもらったのは、体育館前の駐車場からグラウンドにおりていく階段に手すりを設置する工事でした。丘を造成して建設された蘇南高校は、グラウンドが最も手前の低いところにあり、次いで体育館、その上に本館というように、インカ帝国の遺跡マチュピチュのように階段状に建物が配置されています。
その体育館からグラウンドにおりていく階段が、約40段、一直線なのです。今年の職員団体と私との交渉のなかで、体育の教員から「あそこは危ないと思うのですが…」という提言がありました。翌日、現場を見てみると、山登りを重ねてきた私でも一瞬たじろぐ急傾斜です。
よく半世紀以上、生徒たちはこの階段を何もつかまらずに上り下りしてきたなと思うのですが、考えてみれば、私の生まれた茅野市の家でも、昔は階段がかなり急なことが当たり前だったような気がします。
今回、階段のまんなかに一本の手すりが設置されたのですが、材質にも工夫してあって、冬に素手で触っても大丈夫なように金属が樹脂でコーティングされています。
早速、階段をくだってみました。まだコンクリート部分が固まっていないので手すりに触れることはできませんが、気持の面でも随分と斜度が緩やかに感じられました。
ふと思ったのですが、私たちが「学ぶ」ということは、急な階段を上り下りするようなものかもしれません。だとすれば、それを緩やかに思えるような「手すり」にあたるものは何だろうかと、私たちはたえず工夫をしていくべきなのでしょう。
余分な恐怖心など持たないようにするための温かい「手すり」とは何だろうかを考え、実践していきたいと思います。

今日、業者に入ってもらったのは、体育館前の駐車場からグラウンドにおりていく階段に手すりを設置する工事でした。丘を造成して建設された蘇南高校は、グラウンドが最も手前の低いところにあり、次いで体育館、その上に本館というように、インカ帝国の遺跡マチュピチュのように階段状に建物が配置されています。
その体育館からグラウンドにおりていく階段が、約40段、一直線なのです。今年の職員団体と私との交渉のなかで、体育の教員から「あそこは危ないと思うのですが…」という提言がありました。翌日、現場を見てみると、山登りを重ねてきた私でも一瞬たじろぐ急傾斜です。
よく半世紀以上、生徒たちはこの階段を何もつかまらずに上り下りしてきたなと思うのですが、考えてみれば、私の生まれた茅野市の家でも、昔は階段がかなり急なことが当たり前だったような気がします。
今回、階段のまんなかに一本の手すりが設置されたのですが、材質にも工夫してあって、冬に素手で触っても大丈夫なように金属が樹脂でコーティングされています。
早速、階段をくだってみました。まだコンクリート部分が固まっていないので手すりに触れることはできませんが、気持の面でも随分と斜度が緩やかに感じられました。
ふと思ったのですが、私たちが「学ぶ」ということは、急な階段を上り下りするようなものかもしれません。だとすれば、それを緩やかに思えるような「手すり」にあたるものは何だろうかと、私たちはたえず工夫をしていくべきなのでしょう。
余分な恐怖心など持たないようにするための温かい「手すり」とは何だろうかを考え、実践していきたいと思います。

「新生徒会のスローガンは『ファミリー』」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月15日22:16
今日は、第2回生徒総会が体育館で開催されました。3年生の生徒会執行部が、各委員会活動や蘇峡祭の反省を行い、今日をもって退任して2年生の新執行部にバトンタッチしました。
伊藤会長、尾上副会長をはじめ、引退する3年生たちの成長した姿を見ると、これで退任することが、私には何とも淋しくてたまりません。しかし、当の3年生たちは進学・就職の私見の真っただ中なので、生徒総会を運営することも必死でしょう。
新しく生徒会長になった澤渡さんからは、新生徒会のスローガンを「ファミリー」にしたいという宣言がなされました。
「ファミリー」のように気軽にさまざまなことを話し合える生徒会にしたい。「ファミリー」のように先輩からの思いを受け継いでいく生徒会にしたい。「ファミリー」のきずなを校内だけにとどめておくのではなくて、地域に広げていくような生徒会にしたい。・・・そんな抱負が新生徒会長から語られたのでした。
本校にふさわしいスローガンを掲げてくれた…と、私はこれまた胸がいっぱいになります。
ときにぶつかりあいながらも、対話を重ね、互いに支え合っていくような学校を、生徒たちも目指しています。
新しい生徒会執行部を見守りながら、私は朝も昼も晩も3年生の受験指導に奔走しています。

伊藤会長、尾上副会長をはじめ、引退する3年生たちの成長した姿を見ると、これで退任することが、私には何とも淋しくてたまりません。しかし、当の3年生たちは進学・就職の私見の真っただ中なので、生徒総会を運営することも必死でしょう。
新しく生徒会長になった澤渡さんからは、新生徒会のスローガンを「ファミリー」にしたいという宣言がなされました。
「ファミリー」のように気軽にさまざまなことを話し合える生徒会にしたい。「ファミリー」のように先輩からの思いを受け継いでいく生徒会にしたい。「ファミリー」のきずなを校内だけにとどめておくのではなくて、地域に広げていくような生徒会にしたい。・・・そんな抱負が新生徒会長から語られたのでした。
本校にふさわしいスローガンを掲げてくれた…と、私はこれまた胸がいっぱいになります。
ときにぶつかりあいながらも、対話を重ね、互いに支え合っていくような学校を、生徒たちも目指しています。
新しい生徒会執行部を見守りながら、私は朝も昼も晩も3年生の受験指導に奔走しています。

「満洲移民の語り部と生徒との対話」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月14日21:56
9月17日に本校で、満洲移民体験者の可児力一郎さんと私のコラボレーションによる人権講話を行ったと、このブログでも報告しました。
私の講話では、アジア・太平洋戦争の「終戦」において、忘れ去られていて、戦争が終わらなかった人々がいるということを、生徒に問題提起しました。それは南樺太でなおソ連軍との戦争に巻き込まれた人々であり、満洲に取り残されて、自決したり多くの犠牲を出しながら帰国を目指した人々であったりしたわけです。
人間の存在を「忘れる」ということの意味を、生徒に問いかけました。そして満洲の地獄絵図を生きのびた可児さんからは、その過酷な経験のなかでどのような「希望の言葉」をつかんだのかを話していただきました。
人権講話の後、生徒が可児さんへのメッセージを書いています。もちろんこのメッセージを可児さんにお送りしました。
たとえば、3年生のひとりはこう書いています。
「この講話をきき、玉音放送により“戦争は終わった”と伝えられたにもかかわらず、忘れ去られ、戦争を続けることになってしまった人たちの存在を初めて知りました。このことを聞くまで、『玉音放送が流れた後は戦争はなく、自決とかもなく、平和になった』とずっと信じていたので、激しい衝撃を受けました。半ばおどしとほぼ変わらない方法で満州へ送られ、そして悲惨な体験をした恐怖は、想像すらできないほど大きいものだと思います。
それでも、一部の中国人から優しくしてもらった体験を大切に思い、今日のように人へ伝える可児さんの強さを心から尊敬します。この話は、コロナの差別にも通じるものがあると思います。もし、もしもクラスの人がコロナにかかった場合は、差別は絶対にしない。どう思える講話でした。」
どんな困難な状況であっても人の優しさを信じるとか、「忘れられた人」を作ってはならないとか、生徒たちは様々なことを考えたようです。
そして歴史の事件、過去の悲しみ、今目の前にある勇気・・・そういった世界で出会ったことと、自分の生き方を結びつけていく生徒たちは、「希望」そのものだと思うのです。

私の講話では、アジア・太平洋戦争の「終戦」において、忘れ去られていて、戦争が終わらなかった人々がいるということを、生徒に問題提起しました。それは南樺太でなおソ連軍との戦争に巻き込まれた人々であり、満洲に取り残されて、自決したり多くの犠牲を出しながら帰国を目指した人々であったりしたわけです。
人間の存在を「忘れる」ということの意味を、生徒に問いかけました。そして満洲の地獄絵図を生きのびた可児さんからは、その過酷な経験のなかでどのような「希望の言葉」をつかんだのかを話していただきました。
人権講話の後、生徒が可児さんへのメッセージを書いています。もちろんこのメッセージを可児さんにお送りしました。
たとえば、3年生のひとりはこう書いています。
「この講話をきき、玉音放送により“戦争は終わった”と伝えられたにもかかわらず、忘れ去られ、戦争を続けることになってしまった人たちの存在を初めて知りました。このことを聞くまで、『玉音放送が流れた後は戦争はなく、自決とかもなく、平和になった』とずっと信じていたので、激しい衝撃を受けました。半ばおどしとほぼ変わらない方法で満州へ送られ、そして悲惨な体験をした恐怖は、想像すらできないほど大きいものだと思います。
それでも、一部の中国人から優しくしてもらった体験を大切に思い、今日のように人へ伝える可児さんの強さを心から尊敬します。この話は、コロナの差別にも通じるものがあると思います。もし、もしもクラスの人がコロナにかかった場合は、差別は絶対にしない。どう思える講話でした。」
どんな困難な状況であっても人の優しさを信じるとか、「忘れられた人」を作ってはならないとか、生徒たちは様々なことを考えたようです。
そして歴史の事件、過去の悲しみ、今目の前にある勇気・・・そういった世界で出会ったことと、自分の生き方を結びつけていく生徒たちは、「希望」そのものだと思うのです。
「今日の写真は私の仕事部屋の本棚です」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月13日20:59
今日は、私の自宅の仕事部屋の本棚の写真です。スライド式の本棚や普通の本棚が、このほかにも別のところにおいてあるのですが、写真の本棚に、最も使う書籍を置いてあります。
ここ3年間くらいで20万円ほど投資して書籍を電子ファイル化して減らしたので、これでも本棚はすっきりしたほうなのです。地震が来たら最もまずい空間なのですが、論文は、やはりこの部屋で書くのが一番です。
どの本がどこにあるかは、一応記憶しています。自分の大脳に接続しているもうひとつの神経系のような存在が、この本棚です。

ここ3年間くらいで20万円ほど投資して書籍を電子ファイル化して減らしたので、これでも本棚はすっきりしたほうなのです。地震が来たら最もまずい空間なのですが、論文は、やはりこの部屋で書くのが一番です。
どの本がどこにあるかは、一応記憶しています。自分の大脳に接続しているもうひとつの神経系のような存在が、この本棚です。
「学校評価のなかの生徒からの要望を実現していく」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月12日18:09
上半期の保護者・生徒・職員の「学校評価」をまとめたのですが、その内容は職員会で共有するとともに、ひとりひとりの職員との面談によって、寄せられた要望に下半期でどう応えていくかを検討しています。
生徒の要望のなかに、こんな声がありました。
トイレの個室に音の出る装置がほしい、と。・・・なるほどなあと、書いた生徒の気持がよくわかるような気がしました。大人の中には、そんなこと気にするなという人もいるかもしれませんが、私は気になる生徒の側に立ちたいと思います。(県教育委員会に勤めていた時、県庁のトイレが、改修されたとはいえ、流れる音があまりに小さいことに、デリカシーがないなと思っていたのです。)
というわけで、事務室の職員に製品の調査をしてもらい、これなら予算内で購入できるとわかったので、すぐに調達をした次第。まあ、事務室の仕事の早いこと!
今週中にすべての蘇南高校のトイレの個室には、流音発生器が設置されます。
生徒の願いに応える学校、やさしいトイレのある学校を目指します。

生徒の要望のなかに、こんな声がありました。
トイレの個室に音の出る装置がほしい、と。・・・なるほどなあと、書いた生徒の気持がよくわかるような気がしました。大人の中には、そんなこと気にするなという人もいるかもしれませんが、私は気になる生徒の側に立ちたいと思います。(県教育委員会に勤めていた時、県庁のトイレが、改修されたとはいえ、流れる音があまりに小さいことに、デリカシーがないなと思っていたのです。)
というわけで、事務室の職員に製品の調査をしてもらい、これなら予算内で購入できるとわかったので、すぐに調達をした次第。まあ、事務室の仕事の早いこと!
今週中にすべての蘇南高校のトイレの個室には、流音発生器が設置されます。
生徒の願いに応える学校、やさしいトイレのある学校を目指します。

「読売新聞全国版に蘇南高校の取組を紹介していただきました」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月09日18:45
本日の『読売新聞』13面「学ぶ育む」の特集記事「遠隔授業の技術『対面』にも活用」にて、蘇南高校の取組を取り上げていただきました。
記事の主な内容は、私立かえつ有明中学・高校(東京)のすぐれた教育実践についてなのですが、それに補足する内容として、蘇南高校がコロナ臨時休校の遠隔教育の経験を7月の集中豪雨休校の際に応用できたとか、1年の「産業社会と人間」の探究学習で、東京とオンラインで結んで講演・インタビューを実施したなどの取組が紹介されています。
本校の教育実践を全国紙でも取り上げていただけたことは、とても嬉しいことです。
実は、明日は土曜日に中学生や保護者の皆さんに向けて授業公開をするために登校日だったのですが、台風14号の接近により交通障害が予想され、臨時休校とします。今回は職員の安全確保もはからねばなりませんので、申し訳ありませんが、オンライン授業はありません。
台風による被害が起こらないことを祈りつつ、明日は職員住宅で待機をします。

記事の主な内容は、私立かえつ有明中学・高校(東京)のすぐれた教育実践についてなのですが、それに補足する内容として、蘇南高校がコロナ臨時休校の遠隔教育の経験を7月の集中豪雨休校の際に応用できたとか、1年の「産業社会と人間」の探究学習で、東京とオンラインで結んで講演・インタビューを実施したなどの取組が紹介されています。
本校の教育実践を全国紙でも取り上げていただけたことは、とても嬉しいことです。
実は、明日は土曜日に中学生や保護者の皆さんに向けて授業公開をするために登校日だったのですが、台風14号の接近により交通障害が予想され、臨時休校とします。今回は職員の安全確保もはからねばなりませんので、申し訳ありませんが、オンライン授業はありません。
台風による被害が起こらないことを祈りつつ、明日は職員住宅で待機をします。

「雑誌『世界』に書評論文を発表しました」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月08日20:28
今日発売の総合雑誌『世界』11月号(岩波書店発行)に、私が書いた書評論文が掲載されました。今朝の『朝日新聞』2面に出た岩波書店の広告にも名前が入っていたので、昼間の校長会で「論文書いたの?」と話しかけられて嬉しい思いをしたのでした。
論文のタイトルは「〈語り〉から〈対話〉へ~「1945ひろしまタイムライン」問題が問いかけるもの」…。6ページの中で、保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』、菅豊・北條勝貴編『パブリック・ヒストリー』、バフチン『ドストエフスキーの詩学』の3冊をつないで思索を展開してみました。「1945ひろしまタイムライン」問題とは、この夏に社会問題化した、被爆者の記録を高校生たちがツイッター表現にリライトした際に、ヘイトにつながる表現がうまれてしまったという一件です。
高校時代に背伸びして読んでいた『思想』とか『世界』に、高校で教員をしながら自分が文章を寄せることになろうとは、夢にも思いませんでした。いつまでも生徒とともに「学び続ける」教員でいたいので、『世界』編集部からお声をかけていただいたのは、このうえない幸せでした。
私のこの書評論文も、多くの方々との「対話」の成果です。今回は、特に私の敬愛する編集者との「対話」によって、書評の鋭角性が生まれたのではないかと思っています。私一人の力では到底書けません。
もしよろしければ、お読みいただければ幸いです。
蘇南高校の皆さんは、昇降口ロビーに展示しておきますね。
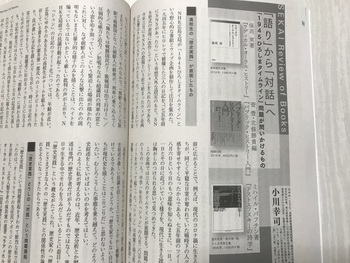
論文のタイトルは「〈語り〉から〈対話〉へ~「1945ひろしまタイムライン」問題が問いかけるもの」…。6ページの中で、保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』、菅豊・北條勝貴編『パブリック・ヒストリー』、バフチン『ドストエフスキーの詩学』の3冊をつないで思索を展開してみました。「1945ひろしまタイムライン」問題とは、この夏に社会問題化した、被爆者の記録を高校生たちがツイッター表現にリライトした際に、ヘイトにつながる表現がうまれてしまったという一件です。
高校時代に背伸びして読んでいた『思想』とか『世界』に、高校で教員をしながら自分が文章を寄せることになろうとは、夢にも思いませんでした。いつまでも生徒とともに「学び続ける」教員でいたいので、『世界』編集部からお声をかけていただいたのは、このうえない幸せでした。
私のこの書評論文も、多くの方々との「対話」の成果です。今回は、特に私の敬愛する編集者との「対話」によって、書評の鋭角性が生まれたのではないかと思っています。私一人の力では到底書けません。
もしよろしければ、お読みいただければ幸いです。
蘇南高校の皆さんは、昇降口ロビーに展示しておきますね。
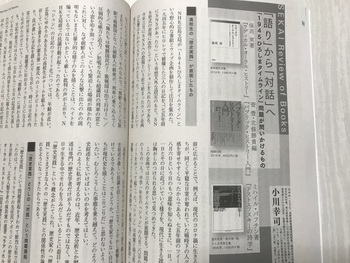
「木曽の伝統のろくろ工芸の技を学ぶ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月07日21:18
南木曽が世界に誇る技が、ろくろ工芸です。木をろくろによって回し、刃をあててくりぬいて器を作る木地師(きじし)たちが、この地で活躍してきました。
蘇南高校には二人の伝統工芸士が、芸術科(美術)の非常勤講師として、毎年、生徒にろくろ工芸を教えてくださっています。
今日は、小椋一男さん、酒井高男さん両先生の授業開きが、2年生を対象に実施されました。木曽・中津川地域に住んでいるとはいえ、電動のろくろを間近で見るのは、多くの生徒たちにとって初めてです。代表の生徒が、先生のサポートを受けながら、勢いよく回転する木材に刃をあてて造形をしていくと、周囲から歓声があがります。最後に先生が刃をあてて自在に美しいフォルムを作り出すと、もっと大きな歓声があがりました。
生徒は、これからろくろ工芸の技を学び、いくつかの作品を作っていきます。
本校に赴任してから、私は我が家を少しずつ南木曽のろくろ工芸品で飾りつつあります。フォルムも美しいし、感触、使い勝手が抜群で、これまた歓声をあげながら使っています。
自分の住んでいる地域にこのような奥深い技があるのだということに、生徒はきっと感動するはずです。そして材料となる木の多彩な美しさと出会うでしょう。
私も生徒に混じって何か作品を作りたいと、ひそかに願っています。

蘇南高校には二人の伝統工芸士が、芸術科(美術)の非常勤講師として、毎年、生徒にろくろ工芸を教えてくださっています。
今日は、小椋一男さん、酒井高男さん両先生の授業開きが、2年生を対象に実施されました。木曽・中津川地域に住んでいるとはいえ、電動のろくろを間近で見るのは、多くの生徒たちにとって初めてです。代表の生徒が、先生のサポートを受けながら、勢いよく回転する木材に刃をあてて造形をしていくと、周囲から歓声があがります。最後に先生が刃をあてて自在に美しいフォルムを作り出すと、もっと大きな歓声があがりました。
生徒は、これからろくろ工芸の技を学び、いくつかの作品を作っていきます。
本校に赴任してから、私は我が家を少しずつ南木曽のろくろ工芸品で飾りつつあります。フォルムも美しいし、感触、使い勝手が抜群で、これまた歓声をあげながら使っています。
自分の住んでいる地域にこのような奥深い技があるのだということに、生徒はきっと感動するはずです。そして材料となる木の多彩な美しさと出会うでしょう。
私も生徒に混じって何か作品を作りたいと、ひそかに願っています。

「生徒の授業評価をもとにした教員面談」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月06日21:06
以前にこのブログで報告したように、毎年行っている生徒の授業評価について、具体的な評価項目を生徒の意見を聞きながら作りかえました。それをもとに授業評価アンケートをすべての授業で実施したのです。
今は、その集計データをもとに、本校の教員ひとりひとりと面談を行っています。どの項目について評価値が低くなっているのか、その原因は何か、評価値をあげていくためにはどうすべきか、などについて対話をしています。自由記述の内容にも生徒の思いが込められているので、丁寧に読んでいきます。
なかには、先生のねらいがうまく生徒に伝わっていないケースもありますし、生徒のほうがもう少し慣れていけば、授業の意図が実現するだろうというケースもあります。しかし多くの場合は、生徒の指摘する課題は、先生が修正していくべきものと言えます。
ちょうど生徒の皆さんが成績表をもらうときに担任と面談をするように、私も教員全員と丁寧に面談をしています。
やはり多くの先生に共通した課題は、いかに生徒の対話的な学びを実現していくか、いかに深い学びを実現していくかです。まさに教えることは学ぶことから始まります。日々の研鑽を積み重ねていきたいと思います。

今は、その集計データをもとに、本校の教員ひとりひとりと面談を行っています。どの項目について評価値が低くなっているのか、その原因は何か、評価値をあげていくためにはどうすべきか、などについて対話をしています。自由記述の内容にも生徒の思いが込められているので、丁寧に読んでいきます。
なかには、先生のねらいがうまく生徒に伝わっていないケースもありますし、生徒のほうがもう少し慣れていけば、授業の意図が実現するだろうというケースもあります。しかし多くの場合は、生徒の指摘する課題は、先生が修正していくべきものと言えます。
ちょうど生徒の皆さんが成績表をもらうときに担任と面談をするように、私も教員全員と丁寧に面談をしています。
やはり多くの先生に共通した課題は、いかに生徒の対話的な学びを実現していくか、いかに深い学びを実現していくかです。まさに教えることは学ぶことから始まります。日々の研鑽を積み重ねていきたいと思います。

「ミクロコスモスへのまなざし」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年10月05日22:43
今月から校長室ギャラリーは、草間彌生のエッチング「幻の野」を飾っています。草間彌生を楽しめる校長室にしてみたのです。
この作品、以前に松本市美術館の企画展でも見ましたが、いかんせん草間彌生ワールド全開の大作のはざまに咲いた、スミレのようなものでした。しかしこの作品が単体として展示されていると、あらためて作品の魅力が際立ってきます。
草間作品に頻繁に登場する「カボチャ」だけでなく、この作品にはブドウ、クリ、カブなどさまざまな果物・野菜が登場します。ちょっとポップで明るい作品なので、その昔、私は一目で気に入って知り合いのギャラリーから購入したのでした。
そしてこの作品の果物・野菜は、やはり微細な幾何学模様に彩られており、たとえばブドウの一粒一粒の微細な網の目を凝視していると、その深淵に吸い込まれていきそうな錯覚に陥ります。
神は細部に宿る・・・とか、マクロコスモスがミクロコスモスと重なり合うという発想が、ヨーロッパにはありますが、まさにミクロコスモスの細部の中に無限大の宇宙を感じさせるのが、草間ワールドです。
この作品をじっと覗き込む生徒が出てくることを楽しみにしています。

この作品、以前に松本市美術館の企画展でも見ましたが、いかんせん草間彌生ワールド全開の大作のはざまに咲いた、スミレのようなものでした。しかしこの作品が単体として展示されていると、あらためて作品の魅力が際立ってきます。
草間作品に頻繁に登場する「カボチャ」だけでなく、この作品にはブドウ、クリ、カブなどさまざまな果物・野菜が登場します。ちょっとポップで明るい作品なので、その昔、私は一目で気に入って知り合いのギャラリーから購入したのでした。
そしてこの作品の果物・野菜は、やはり微細な幾何学模様に彩られており、たとえばブドウの一粒一粒の微細な網の目を凝視していると、その深淵に吸い込まれていきそうな錯覚に陥ります。
神は細部に宿る・・・とか、マクロコスモスがミクロコスモスと重なり合うという発想が、ヨーロッパにはありますが、まさにミクロコスモスの細部の中に無限大の宇宙を感じさせるのが、草間ワールドです。
この作品をじっと覗き込む生徒が出てくることを楽しみにしています。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長