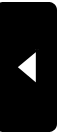「いのちの舞い降りる瞬間をひたすら待つ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月16日19:20
私は大学を卒業して初めて勤めた豊科高校で、何が何だかわからぬまま演劇部の顧問になりました。最初は副顧問でしたが、やがて正顧問となり、舞台づくりにのめりこんでいきます。
豊高演劇部でたくさんの素晴らしい生徒たちと出会いました。
そのなかで、やがて美術の創作に夢中になっていった人もいます。石に「いのち」を描く独自の作風を確立している浜昼顔さんです。
Facebookで彼女の作品を見て「大したものだ」と感心して、あるミュージアムで実際の作品を見て深く心を動かされました。それは、丸いすべすべの石にとまって羽を休めている蝶々(多分ミヤマカラスアゲハ)の絵でした。超微細に描きこまれた蝶々の「いのち」は、作家が何日も何日もただひたすらに「いのち」を描き続けたことを、私に想像させました。
浜昼顔さんに「買いたい」と懇願して、蝶々の絵画を入手しました。
先週から校長室の大きなテーブルのまんなかに飾っています。来室者の多くが、本物の蝶々だと思って一瞬驚き、感心して蝶々を見つめています。
高校時代の浜昼顔さんと一緒に創った舞台は、噂の「青木さんちの奥さん」を若者たちが必死に待つというただそれだけの演劇でした。ひたすら待つ。でも奥さんは最後まで来ないのです。ベケットの「ゴドー」の青春版ですね。
私は蝶々の作品を見ては、「いのち」が舞い降りることをひたすら待って、絵筆を動かしている浜昼顔さんのことを思い浮かべ、前に進む勇気をもらっています。

豊高演劇部でたくさんの素晴らしい生徒たちと出会いました。
そのなかで、やがて美術の創作に夢中になっていった人もいます。石に「いのち」を描く独自の作風を確立している浜昼顔さんです。
Facebookで彼女の作品を見て「大したものだ」と感心して、あるミュージアムで実際の作品を見て深く心を動かされました。それは、丸いすべすべの石にとまって羽を休めている蝶々(多分ミヤマカラスアゲハ)の絵でした。超微細に描きこまれた蝶々の「いのち」は、作家が何日も何日もただひたすらに「いのち」を描き続けたことを、私に想像させました。
浜昼顔さんに「買いたい」と懇願して、蝶々の絵画を入手しました。
先週から校長室の大きなテーブルのまんなかに飾っています。来室者の多くが、本物の蝶々だと思って一瞬驚き、感心して蝶々を見つめています。
高校時代の浜昼顔さんと一緒に創った舞台は、噂の「青木さんちの奥さん」を若者たちが必死に待つというただそれだけの演劇でした。ひたすら待つ。でも奥さんは最後まで来ないのです。ベケットの「ゴドー」の青春版ですね。
私は蝶々の作品を見ては、「いのち」が舞い降りることをひたすら待って、絵筆を動かしている浜昼顔さんのことを思い浮かべ、前に進む勇気をもらっています。
「今日はおおいに寝不足です」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月15日18:23
天気予報ではまったく言われなかった局所的な大雨が、南木曽では連続しています。全国で同じような状態になっていることでしょう。
夜7時から9時までのあいだに豪雨で中央西線が運転見合わせになることが頻発していて、そのたびに8時台の電車に乗って帰る生徒がいないかの確認に奔走しています。いったん運転見合わせになると、運転再開は雨が止んで路線の点検を終えてからになるので、とても時間がかかります。中央西線は無人駅が多く、南木曽駅でも委託職員が夜にはいなくなるので、運転見合わせによって生徒が駅で孤立しかねません。
今朝も夜明け前にかなりの激しい雨が降りました。屋根を打つ激しい音に目が覚めてしまい、このままだとJRが運転見合わせになるだろうと、心配で眠れなくなりました。やはり早朝に運転見合わせの情報が、登録してあるツイッターから流されて、学校全体をオンライン授業に切り替えるべきか注意しながら推移を見守りました。結果的に6時台に運転再開に至り一安心でした。
おそるべき豪雨の頻発に警戒しながら、日々の校長の仕事をしています。

夜7時から9時までのあいだに豪雨で中央西線が運転見合わせになることが頻発していて、そのたびに8時台の電車に乗って帰る生徒がいないかの確認に奔走しています。いったん運転見合わせになると、運転再開は雨が止んで路線の点検を終えてからになるので、とても時間がかかります。中央西線は無人駅が多く、南木曽駅でも委託職員が夜にはいなくなるので、運転見合わせによって生徒が駅で孤立しかねません。
今朝も夜明け前にかなりの激しい雨が降りました。屋根を打つ激しい音に目が覚めてしまい、このままだとJRが運転見合わせになるだろうと、心配で眠れなくなりました。やはり早朝に運転見合わせの情報が、登録してあるツイッターから流されて、学校全体をオンライン授業に切り替えるべきか注意しながら推移を見守りました。結果的に6時台に運転再開に至り一安心でした。
おそるべき豪雨の頻発に警戒しながら、日々の校長の仕事をしています。
「タンポポの花の奥行を見つめる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月14日21:26
現在、昇降口ロビーには、美術の授業で生徒たちが制作した様々な作品が展示されています。
たとえば、切り絵。花々の美しいフォルムと色彩がとても繊細に切り出されています。黒の部分がうまくつながるように作っていますし、花が自然の神秘ともいうべき存在であることがよくわかります。ヨーロッパ中世では、バラが神の象徴でした。生徒の作品を見ながら、タンポポもバラのような奥行がある花だと再発見しました。


たとえば、切り絵。花々の美しいフォルムと色彩がとても繊細に切り出されています。黒の部分がうまくつながるように作っていますし、花が自然の神秘ともいうべき存在であることがよくわかります。ヨーロッパ中世では、バラが神の象徴でした。生徒の作品を見ながら、タンポポもバラのような奥行がある花だと再発見しました。
「就職試験に臨むときに胸に秘めるもの」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月13日18:04
今週末からの就職試験を前にして、9月12日(月)の放課後に「就職試験出陣式」をおこないました。
試験に臨む生徒たちが大講義室に集まり、私からの激励とアドバイスを受け止めました。
そして生徒代表の橋本さんが、私の前に立って、決意表明をしてくれました。――これまでの自分たちの学びの軌跡をふりかえって未来を展望するとともに、その学びを支えてくれた周囲の人々への感謝の気持ちを胸に秘めて、就職試験に臨みたいという、決意表明でした。
これだけしっかりした決意表明ができるのならば、きっとうまくいくだろうと、私は確信しました。
最後に二人の担任が前に立って、「ガンバロー」コールをしました。生徒たちはちょっと照れくさいですが、人生初めての「ガンバロー」でした。
本校は、今週をコロナ予防重点週間として、受験生が安心して試験に臨めるように、全校で感染予防に気を付けています。
「就職試験を前にした皆さん、君たちは私の自慢の生徒です。きっとうまくいく!」

試験に臨む生徒たちが大講義室に集まり、私からの激励とアドバイスを受け止めました。
そして生徒代表の橋本さんが、私の前に立って、決意表明をしてくれました。――これまでの自分たちの学びの軌跡をふりかえって未来を展望するとともに、その学びを支えてくれた周囲の人々への感謝の気持ちを胸に秘めて、就職試験に臨みたいという、決意表明でした。
これだけしっかりした決意表明ができるのならば、きっとうまくいくだろうと、私は確信しました。
最後に二人の担任が前に立って、「ガンバロー」コールをしました。生徒たちはちょっと照れくさいですが、人生初めての「ガンバロー」でした。
本校は、今週をコロナ予防重点週間として、受験生が安心して試験に臨めるように、全校で感染予防に気を付けています。
「就職試験を前にした皆さん、君たちは私の自慢の生徒です。きっとうまくいく!」

「重要文化財・桃介橋の100周年を生徒と記念する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月12日20:04
今日は、1年生全員が桃介橋と桃介記念館のフィールドワークをしました。国の重要文化財に指定されている桃介橋は、福沢諭吉の娘婿の福沢桃介が水力発電施設の建設資材を運ぶために木曽川にかけた、全長約250メートルの巨大な木造の吊橋です。そして、桃介記念館は、桃介がパートナーの女優・川上貞奴とともに発電所建設を指揮する拠点とした別荘です。
今年は桃介橋が完成してなんと100周年(!)になります。
まずは、校長が桃介橋と桃介記念館についての講義をしました。
(1)ドローンの空撮を見るとわかるように、桃介橋は木曽川幅の最も広いところに斜めに架けられた空前のスケールをもっている。ニューヨークのブルックリン橋をモデルにしているとも言われ、世界的に注目される建築様式である。南木曽駅に連結する高さにあり、発電所建設の物資を運ぶ鉄道(!)が木造の吊り橋の上を走っていた。
(2)福沢桃介は、木曽川の水力発電所の建物にヨーロッパの建築様式をとりいれた。須原発電所はライン古城、柿其水道橋はローマの水道橋、読書発電所はパリのアール・デコ式というように、世界の文化が木曽で楽しめる。

(3)福沢桃介のパートナーである川上貞奴は、別荘からバイクにのって発電所に出向き、男たちを指揮する「新しい女性」だった。木曽路に忽然とうまれたヨーロッパ風の別荘は、新しい生き方をうんでいた。
(4)福沢桃介は軍部の植民地拡大政策に批判的だった。信濃毎日新聞を追われた桐生悠々を支えたのが桃介だった。このような歴史をもつ桃介橋100周年を記念して、自分たちがどんな未来を築いていくかを考えていこう。

このあと生徒たちは、桃介橋や桃介記念館を班ごとに訪問し、フィールド・ワーク・ノートに記録をしました。
「とても面白いです」と目を輝かせて、生徒が感想を言ってくれました。
そうでしょう。私たちの生きている場所の「記憶の地層」を掘っていくと、過去の人々の素晴らしい軌跡と出会えるのです。蘇南高校の桃介橋100周年記念の一日でした。
今年は桃介橋が完成してなんと100周年(!)になります。
まずは、校長が桃介橋と桃介記念館についての講義をしました。
(1)ドローンの空撮を見るとわかるように、桃介橋は木曽川幅の最も広いところに斜めに架けられた空前のスケールをもっている。ニューヨークのブルックリン橋をモデルにしているとも言われ、世界的に注目される建築様式である。南木曽駅に連結する高さにあり、発電所建設の物資を運ぶ鉄道(!)が木造の吊り橋の上を走っていた。
(2)福沢桃介は、木曽川の水力発電所の建物にヨーロッパの建築様式をとりいれた。須原発電所はライン古城、柿其水道橋はローマの水道橋、読書発電所はパリのアール・デコ式というように、世界の文化が木曽で楽しめる。
(3)福沢桃介のパートナーである川上貞奴は、別荘からバイクにのって発電所に出向き、男たちを指揮する「新しい女性」だった。木曽路に忽然とうまれたヨーロッパ風の別荘は、新しい生き方をうんでいた。
(4)福沢桃介は軍部の植民地拡大政策に批判的だった。信濃毎日新聞を追われた桐生悠々を支えたのが桃介だった。このような歴史をもつ桃介橋100周年を記念して、自分たちがどんな未来を築いていくかを考えていこう。
このあと生徒たちは、桃介橋や桃介記念館を班ごとに訪問し、フィールド・ワーク・ノートに記録をしました。
「とても面白いです」と目を輝かせて、生徒が感想を言ってくれました。
そうでしょう。私たちの生きている場所の「記憶の地層」を掘っていくと、過去の人々の素晴らしい軌跡と出会えるのです。蘇南高校の桃介橋100周年記念の一日でした。
「奇跡のような窯変がうまれたドラマを作家に夢中に質問する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月09日16:45
まず、ここのところの持病(尿管結石)の問題について温かなお言葉をたくさんの方々からいただき、本当にありがとうございました。おかげさまで今日出張を控えて校内で仕事をしていたところ、結石が身体の外に出たので、これで回復すると思います。(治る瞬間がわかる病気というのも珍しいですね。)
出張をとりやめて、とてもいいことがありました。
実は、本校の今の校舎が完成した1988年のことですが、前庭にブロンズ像が置かれました。本校OBの彫刻家・勝野眞言先生が第17回日本彫刻会展で日彫賞を受賞された作品「律」です。勝野先生は、2019年の日展彫刻の部で文部科学大臣賞を受賞され、熊本の崇城大学芸術学部長としても活躍されています。その勝野先生が、ぶらりと蘇南高校を訪ねてきてくださいました。
前庭の「律」は、自分を律しようとしたときの「戸惑いや不安のまざった内省」を見事に表現した作品だと私は見てきました。単純な希望の表現ではなく、陰影をまじえた希望の表現であることが、蘇南高校のキャンパスの宝物なのです。

先生は熊本で白磁の人物像を造形されておられます。フィンランドなどで展示されてきた作品のカタログを拝見しながら、勝野先生と芸術についての対話をひとしきり夢中になってさせていただきました。
白磁の作品は、窯のなかで焼くさいの方法を多様に工夫していくことで、神の恩寵としか言いようのない色合い・フォルムの窯変が生まれます。その奇跡のような窯変がうまれたドラマを、私は勝野先生に夢中になって聞き出していました。
いつか私も作品とじかに対面したいと強く思います。そしていつか生徒たちにも対面できる機会があればいいのにと、夢を抱きました。
南木曽町をはじめとする世界の人々が、この地で生まれ育った芸術家の作品をこの地で感じることが出来たら、どんなに幸せなことだろうかと、また私の夢がひとつできました。
勝野先生、本当にありがとうございました。
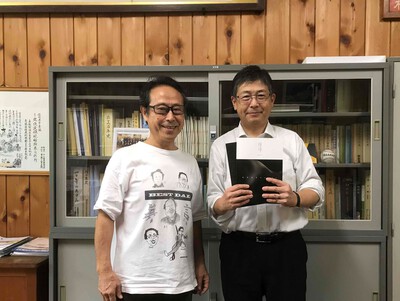
出張をとりやめて、とてもいいことがありました。
実は、本校の今の校舎が完成した1988年のことですが、前庭にブロンズ像が置かれました。本校OBの彫刻家・勝野眞言先生が第17回日本彫刻会展で日彫賞を受賞された作品「律」です。勝野先生は、2019年の日展彫刻の部で文部科学大臣賞を受賞され、熊本の崇城大学芸術学部長としても活躍されています。その勝野先生が、ぶらりと蘇南高校を訪ねてきてくださいました。
前庭の「律」は、自分を律しようとしたときの「戸惑いや不安のまざった内省」を見事に表現した作品だと私は見てきました。単純な希望の表現ではなく、陰影をまじえた希望の表現であることが、蘇南高校のキャンパスの宝物なのです。
先生は熊本で白磁の人物像を造形されておられます。フィンランドなどで展示されてきた作品のカタログを拝見しながら、勝野先生と芸術についての対話をひとしきり夢中になってさせていただきました。
白磁の作品は、窯のなかで焼くさいの方法を多様に工夫していくことで、神の恩寵としか言いようのない色合い・フォルムの窯変が生まれます。その奇跡のような窯変がうまれたドラマを、私は勝野先生に夢中になって聞き出していました。
いつか私も作品とじかに対面したいと強く思います。そしていつか生徒たちにも対面できる機会があればいいのにと、夢を抱きました。
南木曽町をはじめとする世界の人々が、この地で生まれ育った芸術家の作品をこの地で感じることが出来たら、どんなに幸せなことだろうかと、また私の夢がひとつできました。
勝野先生、本当にありがとうございました。
「痛みも忘れるひとときを経験する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月08日19:59
「生徒の地域ボランティアは、しばしばやりっぱなしになっています。町のあちこちにいいものを寄贈しても、点検・維持していくシステムがないから、朽ち果てていくだけになってしまっています。この現状を変えたい。」
「高校の学びで大切なのは、社会に出ていくときのためのコミュニケーション能力のための育成と、生徒の価値観の尊重であると思います。それが蘇南高校で実現するための生徒会活動をつくっていくべきです。」
・・・と、職員会で校長が学校経営方針を語っているようなことばですが、これらはすべて今日の「生徒会選挙」のなかで生徒が立候補演説で語ったことばの一部です。
今日は、新しい生徒会執行部を決める立会演説会と選挙がありました。蘇南高校は、生徒会長・副会長2名・会計2名・議長・副議長・蘇峡祭実行係長・副係長・監査の10名が選挙で選ばれるのです。それぞれに応援演説があり、しかも今回は蘇峡祭実行副係長が複数の立候補になったので、22名が演説をする壮観でした。
そして一人一人の演説が内容的にも表現的にもすぐれたもので、私は心から感心したのでした。
実は持病の尿管結石がとても痛くなってしまい、大きな病院に行って検査を受けました。薬をもらって午後、ようやく学校に戻ると夕方の立会演説会に間に合いました。
本当に痛みも忘れるひとときでした。
ずっと聞いていたかった!

「高校の学びで大切なのは、社会に出ていくときのためのコミュニケーション能力のための育成と、生徒の価値観の尊重であると思います。それが蘇南高校で実現するための生徒会活動をつくっていくべきです。」
・・・と、職員会で校長が学校経営方針を語っているようなことばですが、これらはすべて今日の「生徒会選挙」のなかで生徒が立候補演説で語ったことばの一部です。
今日は、新しい生徒会執行部を決める立会演説会と選挙がありました。蘇南高校は、生徒会長・副会長2名・会計2名・議長・副議長・蘇峡祭実行係長・副係長・監査の10名が選挙で選ばれるのです。それぞれに応援演説があり、しかも今回は蘇峡祭実行副係長が複数の立候補になったので、22名が演説をする壮観でした。
そして一人一人の演説が内容的にも表現的にもすぐれたもので、私は心から感心したのでした。
実は持病の尿管結石がとても痛くなってしまい、大きな病院に行って検査を受けました。薬をもらって午後、ようやく学校に戻ると夕方の立会演説会に間に合いました。
本当に痛みも忘れるひとときでした。
ずっと聞いていたかった!

「木曽路はすべて山の中であるが、脇道に入るとハワイもある」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月07日20:00
今日は、1年生のキャリア学習の一環として、マウカラニゴートファームの三輪さんに講演をしていただきました。
海外留学を楽しんだ高校・短大時代があり、就職した後にもっと学びたいという思いがわいて、ハワイ大学に進学します。帰国後に就職するも、さらに自分の夢をおいかけて地域おこし協力隊員になり、やがて南木曽町にヤギ牧場を創設。・・・波乱万丈の三輪さんの半生(1/3生)を伺いながら、学ぶことの意義とか夢をカタチにすることの素晴らしさを生徒は学びました。
1年生はこれまで自分史を作成することによって、自分の強みがどのようなところにあり、周囲の人々にどのように支えられて生きてきたのかを振り返りました。これからは、この日本社会や世界で生きる様々な魅力ある大人たちと出会い、「人生の幅」を見つめていきます。
今日の三輪さんの講演は、その最初となる記念すべき学びでした。
牧場の名前となっているマウカラニとは、ハワイ語で、「山側の+広い空」という意味です。南木曽から飯田に向かう清内路街道を、妻籠宿から蘭(あららぎ)の集落を抜けて木地師の里に向かう途中、北側に入る細い道をしばらく登っていくと、突然、広い空が開けて、ヤギたちが悠然と草を食んでいる牧場が出現します。
「ポツンと一軒家」の取材に来ないかなあと私は待っているのです。
ハワイ仕込みのヤギ・チーズは、三輪さんがヤギの健康管理からはじまって本当に丹精込めて作っているもので、すばらしい味です。ちなみに9月は牧場でアーティストをお招きしてのイベントが目白押しです。
「木曽路はすべて山の中である」と島崎藤村は『夜明け前』の冒頭に書きました。現代風に書き直すと、「木曽路はすべて山の中であるが、脇道に入るとハワイもある」なのです。

海外留学を楽しんだ高校・短大時代があり、就職した後にもっと学びたいという思いがわいて、ハワイ大学に進学します。帰国後に就職するも、さらに自分の夢をおいかけて地域おこし協力隊員になり、やがて南木曽町にヤギ牧場を創設。・・・波乱万丈の三輪さんの半生(1/3生)を伺いながら、学ぶことの意義とか夢をカタチにすることの素晴らしさを生徒は学びました。
1年生はこれまで自分史を作成することによって、自分の強みがどのようなところにあり、周囲の人々にどのように支えられて生きてきたのかを振り返りました。これからは、この日本社会や世界で生きる様々な魅力ある大人たちと出会い、「人生の幅」を見つめていきます。
今日の三輪さんの講演は、その最初となる記念すべき学びでした。
牧場の名前となっているマウカラニとは、ハワイ語で、「山側の+広い空」という意味です。南木曽から飯田に向かう清内路街道を、妻籠宿から蘭(あららぎ)の集落を抜けて木地師の里に向かう途中、北側に入る細い道をしばらく登っていくと、突然、広い空が開けて、ヤギたちが悠然と草を食んでいる牧場が出現します。
「ポツンと一軒家」の取材に来ないかなあと私は待っているのです。
ハワイ仕込みのヤギ・チーズは、三輪さんがヤギの健康管理からはじまって本当に丹精込めて作っているもので、すばらしい味です。ちなみに9月は牧場でアーティストをお招きしてのイベントが目白押しです。
「木曽路はすべて山の中である」と島崎藤村は『夜明け前』の冒頭に書きました。現代風に書き直すと、「木曽路はすべて山の中であるが、脇道に入るとハワイもある」なのです。

「第一志望の大学に合格することの意味を考える」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月06日20:53
今日の放課後は、大学入学共通テストの出願説明会を行いました。
共通テストを受験する生徒たちが大講義室に集まり、私からの校長講話を聞いたあとで、具体的な出願手続きの打ち合わせをしたのです。
この説明会の場に立つと、いよいよ3年生の進学受験のシーズンが幕をあけると実感し、気持ちが一段と引き締まります。
私からは受験生たちに二つのアドバイスをしました。
その1。高校までは、君たちが何かの失敗をしても、誰かがカバーをしてくれる。けれども高校から先の世界は、ミスをしたら自分で責任をとらねばならない。大学では授業の登録の期限に遅れるとか、卒業論文の提出に遅れるとか、言い訳が一切通じない。だから大学入試の出願については、ミスのないように十分気を付けてほしい。
その2。君たちが第一志望の大学に合格することは、人生の「目標」ではない。蘇南高校で君たちが考えてきた「目標」は、もっと大きなことだ。すなわち「人のいのちを支える」とか「人のくらしを豊かにする」とかの人生のスタンスのことだ。
それに対して第一志望の大学に合格することは目標にいたるための「手段」にすぎない。「手段」はつねに複数のものがあるはずである。だから第一志望の大学に行けなくても、人生はいくらでも輝く。「目標」達成のために、志望を変えることもありうる。
君たちには第一志望を目指して猛烈に頑張ってほしいが、いつも心の片隅に「目標」と「手段」は違うということを心にとどめておいてほしい。
このようなことを3年生に語りかけました。
実は、今年度の私は二つの大学で、ゲスト講師として講義を担当しています。いつか大学で蘇南高校生と再会できたらどんなに幸せだろうかと想像しています。

共通テストを受験する生徒たちが大講義室に集まり、私からの校長講話を聞いたあとで、具体的な出願手続きの打ち合わせをしたのです。
この説明会の場に立つと、いよいよ3年生の進学受験のシーズンが幕をあけると実感し、気持ちが一段と引き締まります。
私からは受験生たちに二つのアドバイスをしました。
その1。高校までは、君たちが何かの失敗をしても、誰かがカバーをしてくれる。けれども高校から先の世界は、ミスをしたら自分で責任をとらねばならない。大学では授業の登録の期限に遅れるとか、卒業論文の提出に遅れるとか、言い訳が一切通じない。だから大学入試の出願については、ミスのないように十分気を付けてほしい。
その2。君たちが第一志望の大学に合格することは、人生の「目標」ではない。蘇南高校で君たちが考えてきた「目標」は、もっと大きなことだ。すなわち「人のいのちを支える」とか「人のくらしを豊かにする」とかの人生のスタンスのことだ。
それに対して第一志望の大学に合格することは目標にいたるための「手段」にすぎない。「手段」はつねに複数のものがあるはずである。だから第一志望の大学に行けなくても、人生はいくらでも輝く。「目標」達成のために、志望を変えることもありうる。
君たちには第一志望を目指して猛烈に頑張ってほしいが、いつも心の片隅に「目標」と「手段」は違うということを心にとどめておいてほしい。
このようなことを3年生に語りかけました。
実は、今年度の私は二つの大学で、ゲスト講師として講義を担当しています。いつか大学で蘇南高校生と再会できたらどんなに幸せだろうかと想像しています。

「献血とは幸せの一部を分けて差し上げること」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年09月05日20:04
日本社会では若年層の献血する人が減ってきていて、このままいくと輸血する血液が足りなくなるのではないかという危惧が専門家のあいだで語られています。そこで蘇南高校では今日、献血セミナーを行いました。まずは献血の意義について学んでおこうという企画です。
私自身は校長会で出張していたので、今日の以下の学びの報告は、杉山教頭先生から行います。
本日は、長野県赤十字血液センターの村上純子様を講師に迎え、「血液セミナー」を行いました。
献血の意義だけでなく、血液の種類や必要性、血管の仕組みなど、多岐にわたってお話をいただきました。特に、日本で使われている輸血の8割が病気の方で、毎日3,000人が必要としていること、そのためには毎日1,500人に献血してもらわなければならないことなど、はじめて知ることが多く、生徒たちもメモを取って聞き入っていました。
村上先生は「献血とは、幸い健康に恵まれている人が、「幸せ」の一部を輸血を必要としている方々に分けて差し上げるボランティア活動です。」とお話しされ、献血はれっきとしたボランティア活動ですと強調されていました。
最後に、生徒代表の亀山さんがお礼の言葉のなかで、「松本を訪れたときは、是非献血センターに足を運びたい」と語りました。
蘇南高校までお越しくださった長野県赤十字血液センターの皆様、本当にありがとうございました。

私自身は校長会で出張していたので、今日の以下の学びの報告は、杉山教頭先生から行います。
本日は、長野県赤十字血液センターの村上純子様を講師に迎え、「血液セミナー」を行いました。
献血の意義だけでなく、血液の種類や必要性、血管の仕組みなど、多岐にわたってお話をいただきました。特に、日本で使われている輸血の8割が病気の方で、毎日3,000人が必要としていること、そのためには毎日1,500人に献血してもらわなければならないことなど、はじめて知ることが多く、生徒たちもメモを取って聞き入っていました。
村上先生は「献血とは、幸い健康に恵まれている人が、「幸せ」の一部を輸血を必要としている方々に分けて差し上げるボランティア活動です。」とお話しされ、献血はれっきとしたボランティア活動ですと強調されていました。
最後に、生徒代表の亀山さんがお礼の言葉のなかで、「松本を訪れたときは、是非献血センターに足を運びたい」と語りました。
蘇南高校までお越しくださった長野県赤十字血液センターの皆様、本当にありがとうございました。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長