「歴史のなかの音に思いをはせる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年11月06日22:41
笹本正治さんの『歴史のなかの音――音がつなぐ日本人の感性』(三弥井書店、2021年)を夢中になって読みました。
この本のテーマは、「音」です。それはお寺の梵鐘の音であったり、神社の鰐口の音であったりします。また、太鼓やほら貝の音が論じられるかと思えば、高野辰之の「春の小川」の音について論がたてられます。
「音」のありようが今とは全く異なっていた中世の人々の世界が、明らかにされます。
中世の人々にとって自分たちの住む世界の周囲はすべて「他界」であり、自分たちの世界は常に他界の神仏によってコントロールされていると考えられていました。鰐口や梵鐘などの音は、人間と他界を結びつける手段でもあったのでした。
このことをベースにしておくと、各地に伝わる「音」をめぐる謎めいた伝承の意味がわかってきます。この本は「夜泣き石」とか「竜宮からやってきた鐘」などの私たちが見聞きしたことのある伝承を鮮やかに読み解いていきます。(笹本さんの本を読むといつも世界の見方が豊かになります。)
歴史をその時代の人々の生きていた世界の文脈にそって読み解いていくことで、今の私たちとは全く異なる中世の人々の世界観や日常感覚が、浮かび上がってきます。そして音が氾濫して、芸術の音以外は心を動かさなくなっている現代人の姿が、あらためて見えてくるのでした。
私は、「聞く」ことを特に重視したパスカルの『パンセ』を連想したのでした。「信仰とは聞くによる」とパスカルは書きました。パスカルの「聞く」という行為は、宇宙の沈黙にじっと耳を傾けるような姿勢でもあります。
見ることや話すことが優位に立つ現代社会の中で、音に耳を澄ますことの意味を改めて考えていきたいと思ったのでした。
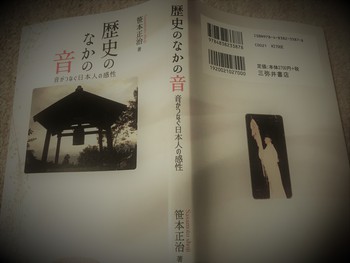
この本のテーマは、「音」です。それはお寺の梵鐘の音であったり、神社の鰐口の音であったりします。また、太鼓やほら貝の音が論じられるかと思えば、高野辰之の「春の小川」の音について論がたてられます。
「音」のありようが今とは全く異なっていた中世の人々の世界が、明らかにされます。
中世の人々にとって自分たちの住む世界の周囲はすべて「他界」であり、自分たちの世界は常に他界の神仏によってコントロールされていると考えられていました。鰐口や梵鐘などの音は、人間と他界を結びつける手段でもあったのでした。
このことをベースにしておくと、各地に伝わる「音」をめぐる謎めいた伝承の意味がわかってきます。この本は「夜泣き石」とか「竜宮からやってきた鐘」などの私たちが見聞きしたことのある伝承を鮮やかに読み解いていきます。(笹本さんの本を読むといつも世界の見方が豊かになります。)
歴史をその時代の人々の生きていた世界の文脈にそって読み解いていくことで、今の私たちとは全く異なる中世の人々の世界観や日常感覚が、浮かび上がってきます。そして音が氾濫して、芸術の音以外は心を動かさなくなっている現代人の姿が、あらためて見えてくるのでした。
私は、「聞く」ことを特に重視したパスカルの『パンセ』を連想したのでした。「信仰とは聞くによる」とパスカルは書きました。パスカルの「聞く」という行為は、宇宙の沈黙にじっと耳を傾けるような姿勢でもあります。
見ることや話すことが優位に立つ現代社会の中で、音に耳を澄ますことの意味を改めて考えていきたいと思ったのでした。
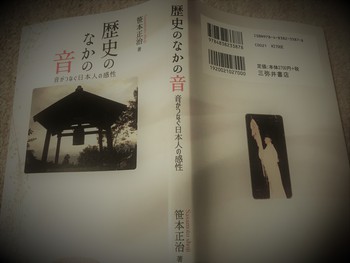
カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長


