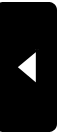「自由な時間をいかすために」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月18日10:44
今日は、本来ならば土曜日で蘇南高校はお休みなのですが、生徒の皆さんにとっては曜日の違いがない生活になってしまいました。そこで、私も皆さんにあわせて、ブログを書きますので、おつきあいください。
今日は「自由な時間をいかすために」というメッセージです。
家にいざるをえなくなって、したいことが何もできないという状況なのですが、こういうときこそ「家にいてもできること」をポジティブに取り組んでいこう、と全校放送で呼びかけましたよね。
例えば、ですよ。
家にいながらでも「旅」ができます。
手順その1 今の自分の精神状況や知的好奇心で、見てみたい場所を
想像してみましょう。
手順その2 スマホでキーワード検索してみましょう。
「世界 絶景」などはよくあるパターン
「世界 最もおそろしい 風景」とか
「日本 元気がでる 場所」
あるいは、好きなものを入れてもいいですよ。
「日本 野球 大人気の場所」
あるいは、変化球で
「日本 最も人気のない 場所」とか。
→この場合、ヒットするのは、やや違ったテーマになってく
る。それで新たな発見が生まれる。(最も人気のない場所を宣
伝するサイトなんてあるわけないですよね。)
手順その3 ヒットしたサイトを楽しみましょう。おお、こんな風景
があるのか。こんな場所があるのか、と絶対に驚きますよ。…
ただし、ここで終わらせてはいけない。そこから一歩、進むこ
とがポイントです。
手順その4 その場所の地名とか住所を紙に控えておく。また、その
場所に行った人の感想の中で、最も印象に残った言葉を書き
出しておく。
手順その5 ヤフーマップとかグーグルマップを開いて、その場所が
どこに存在していて、自分の住んでいるところからどのくらい
離れているかを調べてみる。
手順その6 国内だったら、ヤフーの路線検索とかNAVITIMEの検索
を開いて、そこに行くまでにはどんな手段で何時間かかり、交
通費がいくらかかるかを調べる。海外だったら、その国に行く
までの飛行機代や時間がいくらかかるかを調べる。先ほどのメ
モに、調べたことを書き足してみる。その国に旅するときの注
意事項とか、その国の料理・宗教・政治の様子などを調べると
なおよい。
…ここまでやることで、「ホントに行ってみたいな」という気持ちになってくる。これが大切! これで今日、あなたがやったことは、単なるネットサーフィンではなくて、「探究」をしたことになる。
誰か友達と調べたことを報告し合えると、さらに面白くなるでしょう。
皆さんは、自宅にいたとしても、世界のなかで遊ぶことができます。「いつかここに行ってみよう」と「未来」のことを自分の心に「書く」ことができます。自宅にいるからできることです。
休み明けの校長主催の「ブリコラージュ賞」の個人部門に、こんな面白い旅先を見つけたという報告を応募してもいいですよ。
今日の写真は、12月にウィーンに行ったときのものです。(絶対にもう一度行きたい場所です。)
皆さん、心の中で旅をしよう!

今日は「自由な時間をいかすために」というメッセージです。
家にいざるをえなくなって、したいことが何もできないという状況なのですが、こういうときこそ「家にいてもできること」をポジティブに取り組んでいこう、と全校放送で呼びかけましたよね。
例えば、ですよ。
家にいながらでも「旅」ができます。
手順その1 今の自分の精神状況や知的好奇心で、見てみたい場所を
想像してみましょう。
手順その2 スマホでキーワード検索してみましょう。
「世界 絶景」などはよくあるパターン
「世界 最もおそろしい 風景」とか
「日本 元気がでる 場所」
あるいは、好きなものを入れてもいいですよ。
「日本 野球 大人気の場所」
あるいは、変化球で
「日本 最も人気のない 場所」とか。
→この場合、ヒットするのは、やや違ったテーマになってく
る。それで新たな発見が生まれる。(最も人気のない場所を宣
伝するサイトなんてあるわけないですよね。)
手順その3 ヒットしたサイトを楽しみましょう。おお、こんな風景
があるのか。こんな場所があるのか、と絶対に驚きますよ。…
ただし、ここで終わらせてはいけない。そこから一歩、進むこ
とがポイントです。
手順その4 その場所の地名とか住所を紙に控えておく。また、その
場所に行った人の感想の中で、最も印象に残った言葉を書き
出しておく。
手順その5 ヤフーマップとかグーグルマップを開いて、その場所が
どこに存在していて、自分の住んでいるところからどのくらい
離れているかを調べてみる。
手順その6 国内だったら、ヤフーの路線検索とかNAVITIMEの検索
を開いて、そこに行くまでにはどんな手段で何時間かかり、交
通費がいくらかかるかを調べる。海外だったら、その国に行く
までの飛行機代や時間がいくらかかるかを調べる。先ほどのメ
モに、調べたことを書き足してみる。その国に旅するときの注
意事項とか、その国の料理・宗教・政治の様子などを調べると
なおよい。
…ここまでやることで、「ホントに行ってみたいな」という気持ちになってくる。これが大切! これで今日、あなたがやったことは、単なるネットサーフィンではなくて、「探究」をしたことになる。
誰か友達と調べたことを報告し合えると、さらに面白くなるでしょう。
皆さんは、自宅にいたとしても、世界のなかで遊ぶことができます。「いつかここに行ってみよう」と「未来」のことを自分の心に「書く」ことができます。自宅にいるからできることです。
休み明けの校長主催の「ブリコラージュ賞」の個人部門に、こんな面白い旅先を見つけたという報告を応募してもいいですよ。
今日の写真は、12月にウィーンに行ったときのものです。(絶対にもう一度行きたい場所です。)
皆さん、心の中で旅をしよう!
「あらためて『私はここにいるよ』」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月17日10:00
国の全国を対象とした「緊急事態宣言」発令を受けての蘇南高校の対応は、ホームページに校長からのお知らせとして掲載しました。このブログでは、私たちの「生きる姿勢」について書きます。
Zoomを導入するはずだったホームルームは、ゴールデンウィークまではオクレンジャーでの双方向のやりとりにします。学習課題には、今の時代における各自の生き方を考えてもらうような課題を出すことにしました。
相談体制は、さらに充実をはかるために、「気軽な電話窓口」にカウンセラーへの相談日を設けました。困ったら、不安になったら、いつでも本校に電話をかけてくださいね。
ホームページの「校長あいさつ」に、私の好きな言葉を紹介しています。
「私はここにいるよ」という言葉です。
これは、第二次世界大戦中のナチスドイツのユダヤ人大虐殺のさなかに、アウシュヴィッツ絶滅収容所から奇跡的にいきのびたフランクルという精神医学者が、その体験記『夜と霧』のなかで紹介している言葉です。重い病で死を前にした孤独な女性が、フランクルに次のように話しかけたと言うのです。病室の窓から見える木が、自分に声をかけてくれる。「私はここにいるよ。私は“いのち”だよ。」と。
ホームページの「あいさつ」に書いていないことを少し言うと、「私はここにいるよ」をドイツ語で言うと「イッヒ・ビン・ダア」です。「私は“いのち”だよ」のドイツ語が「イッヒ・ビン・ダ(ア)ス・レーベン」。つまり「私はここにいるよ。私は“いのち”だよ。」をドイツ語で一気に言うと、「イッヒ・ビン・ダア」が2回繰り返され、そのすぐあとに「ダ(ア)ス・レーベン」=「いのち」という言葉が、まるで花が咲くように響くのです。
私たち教職員は、蘇南高校の生徒ひとりひとりの「私はここにいるよ」の声を聞くように、みんなを大切にしたいです。なぜならば、どんな人でも(その人が自分自身のことを嫌いであったとしても)、ひとりひとりには、“咲く花”のように必ず素敵な魅力があるからです。
実は、緊急事態宣言が出されるなどとは想像していなかった、昨日の朝、蘇南高校に出勤すると、満開の桜が散り始めていて、高校につづく坂道にも花びらが絨毯のように散らばっていました。まだ木に咲いている花も、地面にしきつめられた花びらも、すべてが「私はここにいるよ」と言っているようでした。
日本全国に緊急事態宣言が出されたとしても、ひとりひとりの「私はここにいるよ」の魅力は、今までと変わりません。
「私はここにいるよ。私は“いのち”だよ。」…この声を大切にすることが、いつも私たちの原点です。

Zoomを導入するはずだったホームルームは、ゴールデンウィークまではオクレンジャーでの双方向のやりとりにします。学習課題には、今の時代における各自の生き方を考えてもらうような課題を出すことにしました。
相談体制は、さらに充実をはかるために、「気軽な電話窓口」にカウンセラーへの相談日を設けました。困ったら、不安になったら、いつでも本校に電話をかけてくださいね。
ホームページの「校長あいさつ」に、私の好きな言葉を紹介しています。
「私はここにいるよ」という言葉です。
これは、第二次世界大戦中のナチスドイツのユダヤ人大虐殺のさなかに、アウシュヴィッツ絶滅収容所から奇跡的にいきのびたフランクルという精神医学者が、その体験記『夜と霧』のなかで紹介している言葉です。重い病で死を前にした孤独な女性が、フランクルに次のように話しかけたと言うのです。病室の窓から見える木が、自分に声をかけてくれる。「私はここにいるよ。私は“いのち”だよ。」と。
ホームページの「あいさつ」に書いていないことを少し言うと、「私はここにいるよ」をドイツ語で言うと「イッヒ・ビン・ダア」です。「私は“いのち”だよ」のドイツ語が「イッヒ・ビン・ダ(ア)ス・レーベン」。つまり「私はここにいるよ。私は“いのち”だよ。」をドイツ語で一気に言うと、「イッヒ・ビン・ダア」が2回繰り返され、そのすぐあとに「ダ(ア)ス・レーベン」=「いのち」という言葉が、まるで花が咲くように響くのです。
私たち教職員は、蘇南高校の生徒ひとりひとりの「私はここにいるよ」の声を聞くように、みんなを大切にしたいです。なぜならば、どんな人でも(その人が自分自身のことを嫌いであったとしても)、ひとりひとりには、“咲く花”のように必ず素敵な魅力があるからです。
実は、緊急事態宣言が出されるなどとは想像していなかった、昨日の朝、蘇南高校に出勤すると、満開の桜が散り始めていて、高校につづく坂道にも花びらが絨毯のように散らばっていました。まだ木に咲いている花も、地面にしきつめられた花びらも、すべてが「私はここにいるよ」と言っているようでした。
日本全国に緊急事態宣言が出されたとしても、ひとりひとりの「私はここにいるよ」の魅力は、今までと変わりません。
「私はここにいるよ。私は“いのち”だよ。」…この声を大切にすることが、いつも私たちの原点です。

「再びのブリコラージュをします」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月16日17:41
安倍首相が「緊急事態宣言」を日本全国に拡大する方針をかためました。
これを受けて、本校の予定していた第2登校日については、家庭学習の課題の内容も含めて、明日、あらためてお伝えします。
このようなときですが、あえて、今日一日、蘇南高校の教職員がどのように生きていたかを報告させてください。
今日は、朝からずっと、自宅にいざるをえない生徒の皆さんを蘇南高校が支援する指導体制を、グレードアップさせる準備を全職員で行ってきました。
高校の一日の日課の中で、どの時間が一番大切なのかということは、人によって異なるでしょう。しかし、今の状況においては、一番大切なのはホームルームであると私たちは考えました。担任が、クラス全員が揃っているかを確認して、話しかけること。そしてクラスメートどうしが語り合うこと。ときに、たわいもない雑談に笑うこと。こうした「対話」が高校生活のすべての土台です。
昨日、ひとつのクラスでスマホを使ったオンラインのホームルームを試行してみました。登校できない中津川の生徒とクラスを結んだのです。慣れるまでにはとまどいがあるかもしれませんが、高校生活の土台を守っていくために、私たちはオンライン・ホームルームを全校で実施することにしました。
あわせて、パソコンやスマホを利用したオンライン学習を取り入れることにしました。今、日本全国でオンライン学習が試みられています。オンライン学習によって、勉強はやりやすくなるでしょう。しかしオンライン学習は決して万能ではありません。ついていけない人、飽きてくる人、なじめない人もでてくるかもしれません。ゆえにフォローアップ体制が必要です。
今日は、朝から晩まで先生方はめいっぱい動き回り、新しい指導体制の準備に汗を流していました。こうした新しいオンライン・ホームルームなどについて、第2登校日で生徒の皆さんと準備しようと思っていたのです。(もちろん登校できない中津川の生徒の皆さんにどう伝えるかについても、新たな工夫を考えていました。)
そんな第2登校日について、「緊急事態宣言」という新たな事態を受けて、考え直していかなければなりません。私たち教職員が、「ブリコラージュ」(目の前の課題に自分の知識と経験を総動員して乗り越えること)をするときです。
しっかり考えて、明日には皆さんにお伝えしますので、少しお待ちください。
これを受けて、本校の予定していた第2登校日については、家庭学習の課題の内容も含めて、明日、あらためてお伝えします。
このようなときですが、あえて、今日一日、蘇南高校の教職員がどのように生きていたかを報告させてください。
今日は、朝からずっと、自宅にいざるをえない生徒の皆さんを蘇南高校が支援する指導体制を、グレードアップさせる準備を全職員で行ってきました。
高校の一日の日課の中で、どの時間が一番大切なのかということは、人によって異なるでしょう。しかし、今の状況においては、一番大切なのはホームルームであると私たちは考えました。担任が、クラス全員が揃っているかを確認して、話しかけること。そしてクラスメートどうしが語り合うこと。ときに、たわいもない雑談に笑うこと。こうした「対話」が高校生活のすべての土台です。
昨日、ひとつのクラスでスマホを使ったオンラインのホームルームを試行してみました。登校できない中津川の生徒とクラスを結んだのです。慣れるまでにはとまどいがあるかもしれませんが、高校生活の土台を守っていくために、私たちはオンライン・ホームルームを全校で実施することにしました。
あわせて、パソコンやスマホを利用したオンライン学習を取り入れることにしました。今、日本全国でオンライン学習が試みられています。オンライン学習によって、勉強はやりやすくなるでしょう。しかしオンライン学習は決して万能ではありません。ついていけない人、飽きてくる人、なじめない人もでてくるかもしれません。ゆえにフォローアップ体制が必要です。
今日は、朝から晩まで先生方はめいっぱい動き回り、新しい指導体制の準備に汗を流していました。こうした新しいオンライン・ホームルームなどについて、第2登校日で生徒の皆さんと準備しようと思っていたのです。(もちろん登校できない中津川の生徒の皆さんにどう伝えるかについても、新たな工夫を考えていました。)
そんな第2登校日について、「緊急事態宣言」という新たな事態を受けて、考え直していかなければなりません。私たち教職員が、「ブリコラージュ」(目の前の課題に自分の知識と経験を総動員して乗り越えること)をするときです。
しっかり考えて、明日には皆さんにお伝えしますので、少しお待ちください。
「終わりでなく、明日につなぐ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月15日21:17
今日は、3年生の分散登校日で、家庭学習の課題の点検・解説や、総合研究の打ち合わせをしました。3年生の元気な声を聞くと、校舎全体がいつもより一層明るく見えてきます。
午後の職員会の冒頭で、昨日のバドミントン部作成のYoutube動画を職員みんなで鑑賞。このブログでは公開できないのが残念なのですが、実によくできています。トランプの演説に、勝手に自分たちのメッセージを字幕でつけているのですが、要所要所で英語と日本語を一致させている。occurを「お母(かあ)」とか。ひとりひとりの「自主練」の姿に、職員も大いに笑い、そして大いに勇気づけられました。字幕には「先生たちも頑張って!」と映し出され、私は二度目の大感動。
さて、そんな午後、高体連から今年度の地区大会を中止するとの通知がきました。すでに、あるいはこれから、顧問から生徒に、このあまりに悲しい現実を伝えます。自分たちに何の落ち度もないのに、自分が目標にしてきた大会に出場することもできないのです。生徒の皆さんの願いを叶えられなくて、ただただ申し訳ない思いでいっぱいです。
ただ、先生たちとこんなことを語り合いました。これで「終わり」にはしたくないですよね。自宅で待機しているうちに、何となく自分の部活が「終わり」になったには、したくない。国体予選のような別の大会の可能性があるかもしれない。学校が再開されたときに、何かの試合を自分たちで企画することができるかもしれない。100が0になるのでなくて、0ではないけれども50や60にできる方法はきっとある。ブリコラージュできるはず。
だから、今は、自分の自主練をあくまで続けることをしてほしいです。「今できること」を続けてほしい。そして学校で再び部活のみんなと会えたとき、自分の打ち込んだ部活動を、次はあなたに託すと後輩に「つないで」ほしいです。
自分の大切なことを「終わり」にしてはいけない。自分の未来や後輩たちに「つなぐ」ことで部活動をしめくくってほしい。蘇南高校の生徒にそう語りかけます。
夕方、先生たちが分担して校舎のあちこちを消毒して回りました。この作業も30分以上かかります。次の登校日に生徒を迎え入れるためです。
木曽保健所管内でも陽性の事例が発生したとのニュースも届きました。
生徒と同じように、私たち教職員も蘇南高校を明日に「つなぐ」覚悟です。

午後の職員会の冒頭で、昨日のバドミントン部作成のYoutube動画を職員みんなで鑑賞。このブログでは公開できないのが残念なのですが、実によくできています。トランプの演説に、勝手に自分たちのメッセージを字幕でつけているのですが、要所要所で英語と日本語を一致させている。occurを「お母(かあ)」とか。ひとりひとりの「自主練」の姿に、職員も大いに笑い、そして大いに勇気づけられました。字幕には「先生たちも頑張って!」と映し出され、私は二度目の大感動。
さて、そんな午後、高体連から今年度の地区大会を中止するとの通知がきました。すでに、あるいはこれから、顧問から生徒に、このあまりに悲しい現実を伝えます。自分たちに何の落ち度もないのに、自分が目標にしてきた大会に出場することもできないのです。生徒の皆さんの願いを叶えられなくて、ただただ申し訳ない思いでいっぱいです。
ただ、先生たちとこんなことを語り合いました。これで「終わり」にはしたくないですよね。自宅で待機しているうちに、何となく自分の部活が「終わり」になったには、したくない。国体予選のような別の大会の可能性があるかもしれない。学校が再開されたときに、何かの試合を自分たちで企画することができるかもしれない。100が0になるのでなくて、0ではないけれども50や60にできる方法はきっとある。ブリコラージュできるはず。
だから、今は、自分の自主練をあくまで続けることをしてほしいです。「今できること」を続けてほしい。そして学校で再び部活のみんなと会えたとき、自分の打ち込んだ部活動を、次はあなたに託すと後輩に「つないで」ほしいです。
自分の大切なことを「終わり」にしてはいけない。自分の未来や後輩たちに「つなぐ」ことで部活動をしめくくってほしい。蘇南高校の生徒にそう語りかけます。
夕方、先生たちが分担して校舎のあちこちを消毒して回りました。この作業も30分以上かかります。次の登校日に生徒を迎え入れるためです。
木曽保健所管内でも陽性の事例が発生したとのニュースも届きました。
生徒と同じように、私たち教職員も蘇南高校を明日に「つなぐ」覚悟です。

「生徒も動いていた」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月14日19:34
臨時休業に入るにあたって、生徒には、「部活動が自粛と言っても、家でできる個人の活動をみんなで横につなげれば、何かができる。素晴らしい取り組みには、校長主催の『ブリコラージュ賞』を贈る。」と校長講話で訴えました。授業も生徒会も部活動も「パッケージ」として支えてあげたいというのが、本校の方針です。
でも、生徒はやっているのかなあと、実は心配していました。
すると、今朝、今井先生が「バドミントン部の生徒たちが、これを先生たちに見てほしいと言っています」とスマホをもって校長室に来てくれました。
Youtubeの動画なのですが、なんと、トランプ大統領の映像を加工して、困難な時代に生きる自分たちの思いを宣言し、ついで一人ひとりの部員の自主練の光景がユーモアたっぷりに展開します。さらには自分の家で、それぞれの部員が遠く離れたところに置いたマグカップにシャトルを打ち込む様子が、次々に映し出されてきます。
その喜び方に、ひとりひとりの個性が見事に浮かび上がっている。何度も苦労した末に命中して大喜びする人。たった一度で決めて、きょとんとする人。命中したのに静かに喜ぶ人。卒業した先輩まで映像に参加して、シャトルを打ち込んでいます。
思わず、私も大笑いしながら夢中になって見ていました。個人の活動を見事に横につないで、日々のなかで楽しみと努力を創造しているのです。
そして最後にテロップ。
「#コロナに負けるな!」「#One蘇南!」
格好いいねえ。さすが蘇南高校の生徒です!

でも、生徒はやっているのかなあと、実は心配していました。
すると、今朝、今井先生が「バドミントン部の生徒たちが、これを先生たちに見てほしいと言っています」とスマホをもって校長室に来てくれました。
Youtubeの動画なのですが、なんと、トランプ大統領の映像を加工して、困難な時代に生きる自分たちの思いを宣言し、ついで一人ひとりの部員の自主練の光景がユーモアたっぷりに展開します。さらには自分の家で、それぞれの部員が遠く離れたところに置いたマグカップにシャトルを打ち込む様子が、次々に映し出されてきます。
その喜び方に、ひとりひとりの個性が見事に浮かび上がっている。何度も苦労した末に命中して大喜びする人。たった一度で決めて、きょとんとする人。命中したのに静かに喜ぶ人。卒業した先輩まで映像に参加して、シャトルを打ち込んでいます。
思わず、私も大笑いしながら夢中になって見ていました。個人の活動を見事に横につないで、日々のなかで楽しみと努力を創造しているのです。
そして最後にテロップ。
「#コロナに負けるな!」「#One蘇南!」
格好いいねえ。さすが蘇南高校の生徒です!

「再び動き始める、そして第一歩はこれ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月13日18:47
今日は、「蘇南高校の保護者の皆様」への校長メッセージという形で書かせてください。
【岐阜県の非常事態宣言を受けて】
4月10日からの長野県立高校の臨時休業に対して、私たち蘇南高校では、多面的で丁寧な生徒への支援策を考えていたわけですが、まさにその初日に岐阜県から非常事態宣言が出され、岐阜県から通学する生徒の皆さんが分散登校できないことになってしまいました。
そこで本日、4月13日、この事態に対応した支援策をたてました。具体的には、教材については郵送することとし、その解説授業については、インターネットを使った映像配信とLINEや電話等による補充説明によって対応していきます。具体的な説明については、明日以降、各学年より情報発信をいたします。
【これからの蘇南高校の学びの土台】
さて、今日、私から蘇南高校のすべての保護者の皆様に申し上げたいことがあります。
私たちが、お子さんへの支援策として、第一に考えたいことは、「自分と他者の『いのち』を大切にすること」と「孤独に苦しむことを回避すること」です。この土台が基本となり、お子さんの日々の学びを構築していきたいと考えています。
【「見えない敵」との闘い方を「見える化」する】
まず、「自分と他者の『いのち』を大切にすること」ですが、ウイルスという「見えない敵」との闘い方をできるだけ「見える化」することが大切だと考えました。「三密」の回避が政府からも強調されていますが、もし、体調の心配な家族が出た場合や、緊急事態宣言地域に関係した家族がいる場合(これらは十分起こりえます)の対処方法を「見える化」することが、私たちがウイルスとどう戦うべきかを教えてくれます。様々な解説のなかで、茅野市役所のホームページに掲載されている諏訪中央病院の玉井医師の解説が、詳しくわかりやすいので、紹介します。本校の対応もこれに学んでいきます。是非、目をとおしていただければ、幸いです。家族の「いのち」を守るために、ご覧ください。
https://www.city.chino.lg.jp/site/korona/corona-setsumei.html
【孤独におちいることの回避】
もうひとつの「孤独に苦しむことを回避すること」ですが、お子さんに対しては、予定通り、全家庭への担任・副担任からの電話や、「気軽な電話窓口」の開設を行います。
【力を合わせて一緒に頑張りましょう】
そして今日は、保護者の皆様に「一緒に頑張りましょう」という思いをこめて、私自身が最近とても感動した音楽を紹介いたします。曲を作ったのは、私の高校時代の同級生のヤジマハジメくんが現役で組んでいるバンド「やじばん」です。映像の仕事と音楽をこよなく愛するハジメくんは、いつも教育関係者とはまったく違う言葉を私にかけてきます。(高校とは、そのような雑多な友人と出会える、かけがえのない場所です。)
昨日、目の前の壁をこえる方法を教員住宅で必死に考えている私に「これでも聴いて元気を出してくれ」と、ハジメくんは「ゴッド・パイル」という自作の曲をインターネットで送ってきてくれました。彼が、諏訪の御柱祭をイメージして創った曲なのですが、私には、未来がまったく見通せない状況に陥っていても、「我が子には幸せでいてほしい」と願う、保護者の皆様と私たち教員の「共通の思い」を歌った曲に思えてなりません。「森から里に下る樅の木」とは、「未来に歩んでいく子どもたちそのもの」であると私は受け止めました。
そこでハジメくんの快諾を得て、曲「ゴッド・パイル」を「蘇南応援メッセージ」第1号として、ここに紹介させていただきます。
お聴きいただければ、うれしいです。
「The God’s Pile 〜ゴッド・パイル〜」
作詞:ヤジマハジメ
作曲:やじばん
編曲:やじばん
ああ、春の囁きが、森の果てに満ちる頃、
その子らの歌声が、冬の壁を打ち破る。
あの森の樅の木が、坂を下(くだ)り神となる。
その子らの歌声が、風と雲の色を変えて行く。
吹けよ、風。呼べよ、花。
降りつのるその思いが今、
荒くれた魂に、乗って 、この世に響く声となってゆく。
ああ神さまお願いだ。この子らをいつまでも笑わせてくれ。
ああ神さまお願いだ。この風をこの空を美しく永らえてくれ。
ああ、勝どきの歌声が、里の春を渡る時、
生けるものの喜びが、森を染めて花となる。
神の杭は森を出で、滔々と人の河を越ゆ。
生けるものの喜びが、歌の花と咲き、薫り、飛ぶ。
ゆくな、時。うつろうな、歌。
降りつのるその思いが今、
やがて来る夏空に向かい急ぐように風と吹いてゆく。
ああ神さまお願いだ。この子らをいつまでも笑わせてくれ。
ああ神さまお願いだ。この風をこの空を美しく永らえてくれ。
ゆくな、時。うつろうな、歌。
降りつのるその思いが今、
やがて来る夏空に向かい急ぐように風と吹いてゆく。
ああ神さまお願いだ。この子らをいつまでも笑わせてくれ。
ああ神さまお願いだ。この風をこの空を美しく永らえてくれ。
ああ、春の囁きが、
森の果てに満ちる頃、
やがて来る夏空に向かい
急ぐように風と吹いてゆく・・・
https://www.youtube.com/watch?v=3jWoxqWCXwo

【岐阜県の非常事態宣言を受けて】
4月10日からの長野県立高校の臨時休業に対して、私たち蘇南高校では、多面的で丁寧な生徒への支援策を考えていたわけですが、まさにその初日に岐阜県から非常事態宣言が出され、岐阜県から通学する生徒の皆さんが分散登校できないことになってしまいました。
そこで本日、4月13日、この事態に対応した支援策をたてました。具体的には、教材については郵送することとし、その解説授業については、インターネットを使った映像配信とLINEや電話等による補充説明によって対応していきます。具体的な説明については、明日以降、各学年より情報発信をいたします。
【これからの蘇南高校の学びの土台】
さて、今日、私から蘇南高校のすべての保護者の皆様に申し上げたいことがあります。
私たちが、お子さんへの支援策として、第一に考えたいことは、「自分と他者の『いのち』を大切にすること」と「孤独に苦しむことを回避すること」です。この土台が基本となり、お子さんの日々の学びを構築していきたいと考えています。
【「見えない敵」との闘い方を「見える化」する】
まず、「自分と他者の『いのち』を大切にすること」ですが、ウイルスという「見えない敵」との闘い方をできるだけ「見える化」することが大切だと考えました。「三密」の回避が政府からも強調されていますが、もし、体調の心配な家族が出た場合や、緊急事態宣言地域に関係した家族がいる場合(これらは十分起こりえます)の対処方法を「見える化」することが、私たちがウイルスとどう戦うべきかを教えてくれます。様々な解説のなかで、茅野市役所のホームページに掲載されている諏訪中央病院の玉井医師の解説が、詳しくわかりやすいので、紹介します。本校の対応もこれに学んでいきます。是非、目をとおしていただければ、幸いです。家族の「いのち」を守るために、ご覧ください。
https://www.city.chino.lg.jp/site/korona/corona-setsumei.html
【孤独におちいることの回避】
もうひとつの「孤独に苦しむことを回避すること」ですが、お子さんに対しては、予定通り、全家庭への担任・副担任からの電話や、「気軽な電話窓口」の開設を行います。
【力を合わせて一緒に頑張りましょう】
そして今日は、保護者の皆様に「一緒に頑張りましょう」という思いをこめて、私自身が最近とても感動した音楽を紹介いたします。曲を作ったのは、私の高校時代の同級生のヤジマハジメくんが現役で組んでいるバンド「やじばん」です。映像の仕事と音楽をこよなく愛するハジメくんは、いつも教育関係者とはまったく違う言葉を私にかけてきます。(高校とは、そのような雑多な友人と出会える、かけがえのない場所です。)
昨日、目の前の壁をこえる方法を教員住宅で必死に考えている私に「これでも聴いて元気を出してくれ」と、ハジメくんは「ゴッド・パイル」という自作の曲をインターネットで送ってきてくれました。彼が、諏訪の御柱祭をイメージして創った曲なのですが、私には、未来がまったく見通せない状況に陥っていても、「我が子には幸せでいてほしい」と願う、保護者の皆様と私たち教員の「共通の思い」を歌った曲に思えてなりません。「森から里に下る樅の木」とは、「未来に歩んでいく子どもたちそのもの」であると私は受け止めました。
そこでハジメくんの快諾を得て、曲「ゴッド・パイル」を「蘇南応援メッセージ」第1号として、ここに紹介させていただきます。
お聴きいただければ、うれしいです。
「The God’s Pile 〜ゴッド・パイル〜」
作詞:ヤジマハジメ
作曲:やじばん
編曲:やじばん
ああ、春の囁きが、森の果てに満ちる頃、
その子らの歌声が、冬の壁を打ち破る。
あの森の樅の木が、坂を下(くだ)り神となる。
その子らの歌声が、風と雲の色を変えて行く。
吹けよ、風。呼べよ、花。
降りつのるその思いが今、
荒くれた魂に、乗って 、この世に響く声となってゆく。
ああ神さまお願いだ。この子らをいつまでも笑わせてくれ。
ああ神さまお願いだ。この風をこの空を美しく永らえてくれ。
ああ、勝どきの歌声が、里の春を渡る時、
生けるものの喜びが、森を染めて花となる。
神の杭は森を出で、滔々と人の河を越ゆ。
生けるものの喜びが、歌の花と咲き、薫り、飛ぶ。
ゆくな、時。うつろうな、歌。
降りつのるその思いが今、
やがて来る夏空に向かい急ぐように風と吹いてゆく。
ああ神さまお願いだ。この子らをいつまでも笑わせてくれ。
ああ神さまお願いだ。この風をこの空を美しく永らえてくれ。
ゆくな、時。うつろうな、歌。
降りつのるその思いが今、
やがて来る夏空に向かい急ぐように風と吹いてゆく。
ああ神さまお願いだ。この子らをいつまでも笑わせてくれ。
ああ神さまお願いだ。この風をこの空を美しく永らえてくれ。
ああ、春の囁きが、
森の果てに満ちる頃、
やがて来る夏空に向かい
急ぐように風と吹いてゆく・・・
https://www.youtube.com/watch?v=3jWoxqWCXwo

「準備万端と思っていたら、すぐ『次の手』が必要になった」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月10日21:24
臨時休校の第一日目は、まず職員朝会から始まりました。県教委からの指示など多くの連絡の前に、昨日のフェイスブックの私の投稿にいただいた、尊敬する医師(教え子というより友人)からの温かなコメントを紹介。学力保障も大切だけれど、第一は「孤独の回避」という私たちの方針は、このように医療の最前線に立つ方に応援していただけました、と。
次いで、朝9時半から先生方全員が、生徒のいない校舎を清掃。来週の分散登校に来る生徒をきれいな校舎で迎えたいという思いです。
そのあとは分散登校のさいの学習指導の準備、工業科・商業科・英語科などの各種検定の指導をどうするかの打ち合わせ、文化祭の準備をこの状態でどう進めていくかの打ち合わせを重ねます。あわせて南木曽町への蘇南高校の今をどうお知らせしていくかについても会議。校長室に入れかわり、立ちかわり。それぞれの先生方が一生懸命考えています。
午後に満開の桜をホームページにアップして、「分散登校での再会を待っています」というメッセージを掲載しました。来週には生徒に会えるという期待感。
…と、そこへ、岐阜県が県独自の「非常事態宣言」を発令したとのニュース。通勤・通院等以外の不要不急の外出を避けてほしいという岐阜県民への切実な要請です。
わが蘇南高校の3分の1の生徒は、岐阜県中津川市から通学してきています。先生方の4分の1も中津川からの通勤。「蘇南」という言葉には、南木曽だけでなく木曽地方と中津川市の「みんなの学校」という意味があると入学式で言ったばかり。南木曽と中津川は、生活圏が密接につながっています。でもこのような切迫した状況になると、ふだんはまったく意識しない県境が、物理的な壁のように見えてきます。
しかし、こうなった以上、中津川の生徒には、自宅待機をお願いしなければなりません。緊急職員会を夕方5時に行い、オクレンジャーでその旨を生徒・保護者の皆さんに伝えました。
それから分散登校で学ぶはずだった内容を、どう中津川の生徒に伝えるのかの検討を始めました。
土日で練って、来週には生徒たちに伝える予定です。
実は、この1週間、蘇南高校の先生方も私も全力疾走してきたので、「今日は少し早く帰って、体を休めましょう」と、私は朝会で呼びかけたのでした。もうそれが遠い昔の出来事のよう。
でも一日の最後に、大事なことに気付きました。
そもそも私たちが第一に大切にしようと思っていたのは、「孤独の回避」なのです。全員に電話をかける。相談の窓口を全学年で開設する。それには、県境など何も関係ない。その大黒柱は揺るがないのです。
それを堅持しながら、「次の手」「その次の手」を土日に考え抜き、また、月曜日に先生方とディスカッションしようと思っています。

次いで、朝9時半から先生方全員が、生徒のいない校舎を清掃。来週の分散登校に来る生徒をきれいな校舎で迎えたいという思いです。
そのあとは分散登校のさいの学習指導の準備、工業科・商業科・英語科などの各種検定の指導をどうするかの打ち合わせ、文化祭の準備をこの状態でどう進めていくかの打ち合わせを重ねます。あわせて南木曽町への蘇南高校の今をどうお知らせしていくかについても会議。校長室に入れかわり、立ちかわり。それぞれの先生方が一生懸命考えています。
午後に満開の桜をホームページにアップして、「分散登校での再会を待っています」というメッセージを掲載しました。来週には生徒に会えるという期待感。
…と、そこへ、岐阜県が県独自の「非常事態宣言」を発令したとのニュース。通勤・通院等以外の不要不急の外出を避けてほしいという岐阜県民への切実な要請です。
わが蘇南高校の3分の1の生徒は、岐阜県中津川市から通学してきています。先生方の4分の1も中津川からの通勤。「蘇南」という言葉には、南木曽だけでなく木曽地方と中津川市の「みんなの学校」という意味があると入学式で言ったばかり。南木曽と中津川は、生活圏が密接につながっています。でもこのような切迫した状況になると、ふだんはまったく意識しない県境が、物理的な壁のように見えてきます。
しかし、こうなった以上、中津川の生徒には、自宅待機をお願いしなければなりません。緊急職員会を夕方5時に行い、オクレンジャーでその旨を生徒・保護者の皆さんに伝えました。
それから分散登校で学ぶはずだった内容を、どう中津川の生徒に伝えるのかの検討を始めました。
土日で練って、来週には生徒たちに伝える予定です。
実は、この1週間、蘇南高校の先生方も私も全力疾走してきたので、「今日は少し早く帰って、体を休めましょう」と、私は朝会で呼びかけたのでした。もうそれが遠い昔の出来事のよう。
でも一日の最後に、大事なことに気付きました。
そもそも私たちが第一に大切にしようと思っていたのは、「孤独の回避」なのです。全員に電話をかける。相談の窓口を全学年で開設する。それには、県境など何も関係ない。その大黒柱は揺るがないのです。
それを堅持しながら、「次の手」「その次の手」を土日に考え抜き、また、月曜日に先生方とディスカッションしようと思っています。

「準備していたことを、いよいよ始める」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年04月09日21:56
長野県では、4月10日から2週間を「感染対策強化月間」と位置づけ、全県立高校を4月24日(金)まで臨時休業とすることになりました。今回は新年度のスタートの時期ですから、学校生活に対する影響は断然大きくなると言わざるをえません。
蘇南高校では、4月3日の職員研修会のさいに、先生方がみんなで考えたことをもとに、生徒の学業・メンタル・特別活動等を“多面的に”支えるための方策をとることにします。
その1。学習支援については、課題をスモールステップ(2週間を3期間に区分しました)で学び、分散登校によって、その都度、丁寧に振り返ることとしました。分散登校は学年別とし、せっかく登校した生徒に全教員が関われるようにしました。生徒が、「こういうふうにやっていくんだ」という実感をもって学んでいけるようにしようと思います。この方式を2週間行い、この間に次のステージとしてe-ラーニングとの組み合わせを研究します。
その2。相談体制を構築しました。やや日数の多い第2期には、担任・副担任ですべての生徒に電話をかけて声がけをする予定です。また、「蘇南高校・気軽な電話窓口」を開設し、相談したいこと、普通におしゃべりがしたいことを受け付け、全学年の教員が当番を組みました。一斉休業の最大の課題は、学力低下ではなく、「生徒の孤立」だという未来予測に基づいています。雑談を作り出すことに価値があります。
その3。生徒会活動や部活動について、休業期間中は自粛となりますが、自宅にいる状態で、生徒会とか部活動とかのメンバーが情報交換しながらできる「個人の活動」に、是非取り組むよう、呼びかけました。今日の放課後は、その打ち合わせをする姿があちこちにありました。一斉休業があけたら、校長主催の「ブリコラージュ賞」に、休業中の取組を応募しようと呼びかけました。
その4。そのほかの細かな配慮を伝えました。夏の水泳は中止するので水着は買わなくていい。定期券の払い戻し方法。PTA総会の延期。生活指導の要点(とくにSNS)。家計が急変した家庭への支援制度の連絡。
18時頃、教員のチームが汗を流して全校舎のドアノブ、スイッチ、手すりを消毒しています。先生方は、それが終わってから第2期の課題の作成に尽力することになります。
先生方が倒れるようなことがあってはいけないと、強く思う今日です。
今日の全校放送で、私が生徒に訴えたのは、次のようなことでした。
「ただ、何となく一斉休校に巻き込まれて、何となく孤独になって、日々ぼうっと生きて…、というのはやめよう。一斉休校になっても、できることはたくさんある。自分のもっている知識・経験を総動員して、未来のために、今できることを精いっぱいやろう。それができるようになったならば、この一斉休業を、プラスの経験にできる! 蘇南高校は負けない!」
それで、一斉休業の直前の日の最後に何が起こったかというと、19時少し前、藤城先生が、校舎の前の桜のライトアップをしてくれたのです。木曽川にのぞむ谷の中に見事に満開の桜が浮かび上がりました。この風景、私は一生、忘れないでしょう。

蘇南高校では、4月3日の職員研修会のさいに、先生方がみんなで考えたことをもとに、生徒の学業・メンタル・特別活動等を“多面的に”支えるための方策をとることにします。
その1。学習支援については、課題をスモールステップ(2週間を3期間に区分しました)で学び、分散登校によって、その都度、丁寧に振り返ることとしました。分散登校は学年別とし、せっかく登校した生徒に全教員が関われるようにしました。生徒が、「こういうふうにやっていくんだ」という実感をもって学んでいけるようにしようと思います。この方式を2週間行い、この間に次のステージとしてe-ラーニングとの組み合わせを研究します。
その2。相談体制を構築しました。やや日数の多い第2期には、担任・副担任ですべての生徒に電話をかけて声がけをする予定です。また、「蘇南高校・気軽な電話窓口」を開設し、相談したいこと、普通におしゃべりがしたいことを受け付け、全学年の教員が当番を組みました。一斉休業の最大の課題は、学力低下ではなく、「生徒の孤立」だという未来予測に基づいています。雑談を作り出すことに価値があります。
その3。生徒会活動や部活動について、休業期間中は自粛となりますが、自宅にいる状態で、生徒会とか部活動とかのメンバーが情報交換しながらできる「個人の活動」に、是非取り組むよう、呼びかけました。今日の放課後は、その打ち合わせをする姿があちこちにありました。一斉休業があけたら、校長主催の「ブリコラージュ賞」に、休業中の取組を応募しようと呼びかけました。
その4。そのほかの細かな配慮を伝えました。夏の水泳は中止するので水着は買わなくていい。定期券の払い戻し方法。PTA総会の延期。生活指導の要点(とくにSNS)。家計が急変した家庭への支援制度の連絡。
18時頃、教員のチームが汗を流して全校舎のドアノブ、スイッチ、手すりを消毒しています。先生方は、それが終わってから第2期の課題の作成に尽力することになります。
先生方が倒れるようなことがあってはいけないと、強く思う今日です。
今日の全校放送で、私が生徒に訴えたのは、次のようなことでした。
「ただ、何となく一斉休校に巻き込まれて、何となく孤独になって、日々ぼうっと生きて…、というのはやめよう。一斉休校になっても、できることはたくさんある。自分のもっている知識・経験を総動員して、未来のために、今できることを精いっぱいやろう。それができるようになったならば、この一斉休業を、プラスの経験にできる! 蘇南高校は負けない!」
それで、一斉休業の直前の日の最後に何が起こったかというと、19時少し前、藤城先生が、校舎の前の桜のライトアップをしてくれたのです。木曽川にのぞむ谷の中に見事に満開の桜が浮かび上がりました。この風景、私は一生、忘れないでしょう。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長