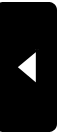「きそじんの卵たち」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月17日17:23
木曽地域の企業・団体で働いている皆さんが、「どんな仕事をしているのか」「その仕事を選んだ理由は何か」「何をやりがい・大切にしているのか」などについて、インタビューしようという学びを1年生が進めてきました。「ふるさと探究学」のプログラムです。
地元企業の方に話を伺う機会は、小学校・中学校でもあるわけですが、今回は木祖村から南木曽町まで木曽地域全域にわたって22の企業・団体に生徒たちが自らアポイントメントをとり、Zoomでつながっていただき、インタビューを試みました。
その学んだ内容を「輝礎人(きそじん)」という冊子にまとめ、今日はさらにポスターセッションという形で、なるべくたくさんのインタビュー結果を聞き、その内容について質問して対話を行うという「シェアする学び」を行いました。「輝礎人」というネーミングは担当の太田先生によるものです。(私は拍手を贈りました。)
そして私が本当に驚いたことに、生徒たちがいきいきとプレゼンを行い、それに対して聞き手が丁寧な質問を返して対話が深まっていくのでした。「ああ、うちの生徒たちは、高校一年生で対話の作法とその意義をわがものとしつつある」…そう私は確信し、感無量になりました。
対話の基礎にあるのは、気づくことの喜びです。
まさに「輝礎人」の卵たちです。

地元企業の方に話を伺う機会は、小学校・中学校でもあるわけですが、今回は木祖村から南木曽町まで木曽地域全域にわたって22の企業・団体に生徒たちが自らアポイントメントをとり、Zoomでつながっていただき、インタビューを試みました。
その学んだ内容を「輝礎人(きそじん)」という冊子にまとめ、今日はさらにポスターセッションという形で、なるべくたくさんのインタビュー結果を聞き、その内容について質問して対話を行うという「シェアする学び」を行いました。「輝礎人」というネーミングは担当の太田先生によるものです。(私は拍手を贈りました。)
そして私が本当に驚いたことに、生徒たちがいきいきとプレゼンを行い、それに対して聞き手が丁寧な質問を返して対話が深まっていくのでした。「ああ、うちの生徒たちは、高校一年生で対話の作法とその意義をわがものとしつつある」…そう私は確信し、感無量になりました。
対話の基礎にあるのは、気づくことの喜びです。
まさに「輝礎人」の卵たちです。
「ベネッセSTEAMフェスタの代表チームに選ばれる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月16日17:55
3月14日(日)に全国の中学・高校32校150名がオンラインでつながって、「実社会の課題解決につながる研究」の成果を発表する、「ベネッセSTEAMフェスタ」が開かれました。
教科横断的な探究学習を意味する「STEAM(スティーム、science/technologyなどの頭文字からの造語)」を掲げたこの大会は、まさに東日本大震災の年から始まったので、今回で10回目。
この節目の大会に、蘇南高校は初めて参加しました。
3月21日(日)13:00から、代表11チームが発表する「ベネッセSTEAMフェスタ2021」が全国公開(オンライン)されます。なんと本校生徒がその代表11チームのひとつとして発表する機会をこのほど与えていただいたのです。
ソーシャルイノベーション部門に応募した2年生のチーム「がくたとめい」による「南木曽ねこ認知度100%計画」という研究発表です。インターネットにつながれば、誰でもライブ配信を視聴できますので、是非、ご覧ください。フェスタの開催要項や視聴方法は、下記のハイパーリンクにてどうぞ。https://steamfesta.benesse.co.jp/s/pc/top.html
蘇南高校の課題研究は3年次に行うので、2年生のこの時期は、1月から3月にかけて取り組んだ「課題研究のテーマをどのように見つけてきたか」という中間発表です。これをもとに「がくたとめい」チームは、3年生の学びをスタートさせることになります。本校の生徒が全国の場での発表の機会をいただけたのは、地域の魅力をうけつぎ、発展させようとして、地域のたくさんの大人たちと出会い、面白がって課題研究を進めていることが伝わったからであろうと思っています。
「がくたとめい」チームは、あらためて21日に向けてプレゼンのブラッシュアップをはかっています。「南木曽ねこ」(知らない人は天然記念物の猫だと思うでしょう)を未来に受け継ぐべく、生徒たちは試行錯誤を繰り返しながら考察を進めています。
全国の大勢の方々にむかって「南木曽ねこ」の魅力と可能性が伝わるよう、「がくたとめい」の「南木曽ねこ物語・序章」が幕をあけます。

教科横断的な探究学習を意味する「STEAM(スティーム、science/technologyなどの頭文字からの造語)」を掲げたこの大会は、まさに東日本大震災の年から始まったので、今回で10回目。
この節目の大会に、蘇南高校は初めて参加しました。
3月21日(日)13:00から、代表11チームが発表する「ベネッセSTEAMフェスタ2021」が全国公開(オンライン)されます。なんと本校生徒がその代表11チームのひとつとして発表する機会をこのほど与えていただいたのです。
ソーシャルイノベーション部門に応募した2年生のチーム「がくたとめい」による「南木曽ねこ認知度100%計画」という研究発表です。インターネットにつながれば、誰でもライブ配信を視聴できますので、是非、ご覧ください。フェスタの開催要項や視聴方法は、下記のハイパーリンクにてどうぞ。https://steamfesta.benesse.co.jp/s/pc/top.html
蘇南高校の課題研究は3年次に行うので、2年生のこの時期は、1月から3月にかけて取り組んだ「課題研究のテーマをどのように見つけてきたか」という中間発表です。これをもとに「がくたとめい」チームは、3年生の学びをスタートさせることになります。本校の生徒が全国の場での発表の機会をいただけたのは、地域の魅力をうけつぎ、発展させようとして、地域のたくさんの大人たちと出会い、面白がって課題研究を進めていることが伝わったからであろうと思っています。
「がくたとめい」チームは、あらためて21日に向けてプレゼンのブラッシュアップをはかっています。「南木曽ねこ」(知らない人は天然記念物の猫だと思うでしょう)を未来に受け継ぐべく、生徒たちは試行錯誤を繰り返しながら考察を進めています。
全国の大勢の方々にむかって「南木曽ねこ」の魅力と可能性が伝わるよう、「がくたとめい」の「南木曽ねこ物語・序章」が幕をあけます。

「開拓者精神の具現化を目指して」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月15日21:38
今日は、1・2年生の成績処理や来年度に向けての膨大な準備を一生懸命進める一日でした。
先生たちが次々に校長室にやってきて様々な打ち合わせを行い、家に帰ってきたのが21時でした。(校長ブログもいつになく遅い時間の投稿です。)なぜそんなにたくさんのことがあるのかというと、「少し先の未来」を見越して、今、手を打っておきたいからです。たとえば、11月の修学旅行の計画について、コロナ感染症の状況を予想してどう変更を加えるかとか、3年間の「探究的な学び」のプログラムに一貫した流れを作ったのですが、よりいっそう魅力的な学びにするためにどう改良を加えるとか、考えるべき課題が次々に出てきます。
先生たちがその課題に次々と気づき、原案を作って、校長室にやってきます。それを先生たちと対話をしながらブラッシュアップしていくわけです。
今日は、ランチをとる30分と夕方のウェブ会議の90分を除いて、一日中、対話をしていました。
本校の建学の精神は、「開拓者精神の具現化」です。私は生徒たちに、「開拓者とは未来を予想して、今の努力をする人のことだ」といつも語りかけてきました。私たち教職員も「開拓者」でありたいと、いつも考えています。

先生たちが次々に校長室にやってきて様々な打ち合わせを行い、家に帰ってきたのが21時でした。(校長ブログもいつになく遅い時間の投稿です。)なぜそんなにたくさんのことがあるのかというと、「少し先の未来」を見越して、今、手を打っておきたいからです。たとえば、11月の修学旅行の計画について、コロナ感染症の状況を予想してどう変更を加えるかとか、3年間の「探究的な学び」のプログラムに一貫した流れを作ったのですが、よりいっそう魅力的な学びにするためにどう改良を加えるとか、考えるべき課題が次々に出てきます。
先生たちがその課題に次々と気づき、原案を作って、校長室にやってきます。それを先生たちと対話をしながらブラッシュアップしていくわけです。
今日は、ランチをとる30分と夕方のウェブ会議の90分を除いて、一日中、対話をしていました。
本校の建学の精神は、「開拓者精神の具現化」です。私は生徒たちに、「開拓者とは未来を予想して、今の努力をする人のことだ」といつも語りかけてきました。私たち教職員も「開拓者」でありたいと、いつも考えています。
「笠松山から白銀の南アルプスを眺める」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月14日12:35
今日は低気圧が通過した後の澄みわたった青空だったので、飯田市の笠松山(1271m)に登りました。そもそも我が家は笠松山ろくの扇状地に立地しているので、まさに故郷の山です。
隣の風越山が飯田市のシンボルになっているのに比べると笠松山は無名の山なのですが、実は、山頂からの眺望は、ここがダントツ。仙丈ケ岳から光岳・池口岳までの長大な南アルプスが一望できる稀有な場所なのでした。(当然、中央アルプスの高山の上に行けばいいわけですが、白銀のアルプスを里山で見られるのはここ。)
写真は、左から小河内岳、荒川岳、赤石岳、聖岳とつながっています。南アルプスはとにかくひとつひとつの山が大きく、登るのに時間がかかります。
「山のあなたの空遠く」(ブッセ)という詩句を思い出すような伊那谷の風景を飽かずに眺め続けたのでした。

隣の風越山が飯田市のシンボルになっているのに比べると笠松山は無名の山なのですが、実は、山頂からの眺望は、ここがダントツ。仙丈ケ岳から光岳・池口岳までの長大な南アルプスが一望できる稀有な場所なのでした。(当然、中央アルプスの高山の上に行けばいいわけですが、白銀のアルプスを里山で見られるのはここ。)
写真は、左から小河内岳、荒川岳、赤石岳、聖岳とつながっています。南アルプスはとにかくひとつひとつの山が大きく、登るのに時間がかかります。
「山のあなたの空遠く」(ブッセ)という詩句を思い出すような伊那谷の風景を飽かずに眺め続けたのでした。
「『岩波講座世界歴史』第3期のこと」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月12日20:46
岩波書店のホームページに、『岩波講座世界歴史』全24巻の刊行を10月から始めることが告知されています。元日の新聞の全面広告についで、編集委員と全巻構成が具体的に発表されたことになります。
今回は、同名のシリーズの第3期にあたり、これまで四半世紀ごとに刊行されてきました。1960年代から1970年代にかけて刊行された第一期(写真の本)は、私が生まれたころの全集ですが、その重厚感は圧倒的です。私の教員生活の初期に刊行された第二期は、研究の深まりを反映して、地域別だけではない世界横断的な構成をとった全集です。
そして今回の第3期では、私が「第1巻」の責任編集をつとめる予定です。この一年間は、学校での仕事以外は、この仕事に没頭してきました。
その際、「一高校教師」の自分がこの仕事をしていいのか、自分が引き受ける意味はどこにあるのか、このことをいつも問い続けてきました。(当然、世の中からも厳しく問われるのだと思っています。)
具体的な内容については、これから順次、岩波書店のホームページにて告知されていきます。

今回は、同名のシリーズの第3期にあたり、これまで四半世紀ごとに刊行されてきました。1960年代から1970年代にかけて刊行された第一期(写真の本)は、私が生まれたころの全集ですが、その重厚感は圧倒的です。私の教員生活の初期に刊行された第二期は、研究の深まりを反映して、地域別だけではない世界横断的な構成をとった全集です。
そして今回の第3期では、私が「第1巻」の責任編集をつとめる予定です。この一年間は、学校での仕事以外は、この仕事に没頭してきました。
その際、「一高校教師」の自分がこの仕事をしていいのか、自分が引き受ける意味はどこにあるのか、このことをいつも問い続けてきました。(当然、世の中からも厳しく問われるのだと思っています。)
具体的な内容については、これから順次、岩波書店のホームページにて告知されていきます。
「大きな物語と小さな物語」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月11日17:53
今日も入試業務のため教職員以外は校舎内立入禁止でした。緊張した静かな一日でした。
14時46分に東日本大震災によって生まれた数多くの悲しみに思いをいたし、教職員全員で南木曽岳の彼方の東北の地に向かって黙とうを捧げました。
今月下旬の終業式では、私から生徒たちに「大きな物語」と「小さな物語」という講話をするつもりです。とかく私たちは、大きな悲しみをのりこえて復興に向かうという「大きな物語」を定型化して、その枠組みの中で世界を見つめ、人を応援しつつ自分自身のカタルシスを得るということをしがちです。
しかし東日本大震災で失われた「いのち」と、現在進行形で生き続けている「いのち」の「小さな物語」は、その定型化されたストーリーにはおさまりきれない具体的な表情や多様な出来事に彩られているはずなのです。その無数の「小さな物語」は、私にとまどいや、絶望や、自己批判のような痛みを迫るかもしれない。そんな「小さな物語」にたえず眼差しを注げるような人間でありたいと思います。
本校の玄関ホールには、「父に捧ぐ」と題された大きなフレスコ画が飾られています。校舎改築の時に、本校OBの三浦秀喜さんがこの素敵な作品を寄贈してくださったのだと同窓会報に記録されています。
「小さな物語」を前にして、ただただ、祈っている人間の姿が描かれているような気がして、今日はしばらくこの絵の前に佇んでいました。

14時46分に東日本大震災によって生まれた数多くの悲しみに思いをいたし、教職員全員で南木曽岳の彼方の東北の地に向かって黙とうを捧げました。
今月下旬の終業式では、私から生徒たちに「大きな物語」と「小さな物語」という講話をするつもりです。とかく私たちは、大きな悲しみをのりこえて復興に向かうという「大きな物語」を定型化して、その枠組みの中で世界を見つめ、人を応援しつつ自分自身のカタルシスを得るということをしがちです。
しかし東日本大震災で失われた「いのち」と、現在進行形で生き続けている「いのち」の「小さな物語」は、その定型化されたストーリーにはおさまりきれない具体的な表情や多様な出来事に彩られているはずなのです。その無数の「小さな物語」は、私にとまどいや、絶望や、自己批判のような痛みを迫るかもしれない。そんな「小さな物語」にたえず眼差しを注げるような人間でありたいと思います。
本校の玄関ホールには、「父に捧ぐ」と題された大きなフレスコ画が飾られています。校舎改築の時に、本校OBの三浦秀喜さんがこの素敵な作品を寄贈してくださったのだと同窓会報に記録されています。
「小さな物語」を前にして、ただただ、祈っている人間の姿が描かれているような気がして、今日はしばらくこの絵の前に佇んでいました。
「桃介橋が架かる町で学ぶこと」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月10日14:06
今日は、後期選抜の2日目で面接検査でした。予定通り、すべての検査日程を終えました。3月19日が入学予定者の発表になります。
入試業務の期間中は、原則として教職員以外は校舎に入ることができません。来客のいない校長室のテーブルの上には、本校の同窓会が1980年代から90年代にかけて発行した同窓会報『鵬翼』が積まれています。副会長の楯盛親さんからお借りしているもので、とにかく内容が面白く、私は読みふけってきました。封筒に入る四つ折りのサイズで、表紙の写真を見るだけでも本校と南木曽町の歩みがよくわかります。
たとえば、1993年冬号の写真は、復元がなしとげられた桃介橋を本校の女生徒が渡ろうとしているところ。ピッカピカの桃介橋にも驚きますが、女生徒のスカート丈の長さにも「!」です。その前年の1992年冬号の写真は、朽ち果てて横転寸前の桃介橋の風景です。編集者は、この2枚を対比して後世に残そうとしたのでしょう。
桃介橋は、電力王と言われ、木曽川の電源開発を進めた福沢桃介(福沢諭吉の娘婿)が架けた吊り橋で、現在は国の重要文化財に指定されています。木曽川の最も幅の広いところに、わざと目立つように斜めに架けられているこの橋は、険阻な南木曾岳をバックにして青空に映える、本当に美しい建造物です。
町の人々の熱意ある運動によりこの橋が後世に残され、その橋の上の本校に高校生たちが集ってくる。
この「絵のような風景」を大切にしていこうと改めて思ったのでした。

入試業務の期間中は、原則として教職員以外は校舎に入ることができません。来客のいない校長室のテーブルの上には、本校の同窓会が1980年代から90年代にかけて発行した同窓会報『鵬翼』が積まれています。副会長の楯盛親さんからお借りしているもので、とにかく内容が面白く、私は読みふけってきました。封筒に入る四つ折りのサイズで、表紙の写真を見るだけでも本校と南木曽町の歩みがよくわかります。
たとえば、1993年冬号の写真は、復元がなしとげられた桃介橋を本校の女生徒が渡ろうとしているところ。ピッカピカの桃介橋にも驚きますが、女生徒のスカート丈の長さにも「!」です。その前年の1992年冬号の写真は、朽ち果てて横転寸前の桃介橋の風景です。編集者は、この2枚を対比して後世に残そうとしたのでしょう。
桃介橋は、電力王と言われ、木曽川の電源開発を進めた福沢桃介(福沢諭吉の娘婿)が架けた吊り橋で、現在は国の重要文化財に指定されています。木曽川の最も幅の広いところに、わざと目立つように斜めに架けられているこの橋は、険阻な南木曾岳をバックにして青空に映える、本当に美しい建造物です。
町の人々の熱意ある運動によりこの橋が後世に残され、その橋の上の本校に高校生たちが集ってくる。
この「絵のような風景」を大切にしていこうと改めて思ったのでした。
「後期選抜の学力検査がおこなわれる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月09日16:09
今日は、後期選抜の学力検査でした。全日程を予定どおりに終了し、帰宅する受検生を見送りました。
学力検査が行われている時間は、校長室から「全員が本来の自分の力を発揮できますように」と祈ることしかできません。我が子が高校入試や大学入試に臨んでいる親御さんは、もっと切実に祈るような思いでいることでしょう。親としての自分の「あの頃」のことを思い返した一日でもありました。
本校の後期選抜は、明日の面接検査に続きます。
受検生の皆さん、体調に気をつけて、明日も元気な姿を見せてくださいね!

学力検査が行われている時間は、校長室から「全員が本来の自分の力を発揮できますように」と祈ることしかできません。我が子が高校入試や大学入試に臨んでいる親御さんは、もっと切実に祈るような思いでいることでしょう。親としての自分の「あの頃」のことを思い返した一日でもありました。
本校の後期選抜は、明日の面接検査に続きます。
受検生の皆さん、体調に気をつけて、明日も元気な姿を見せてくださいね!
「卒業式の風景・番外編」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月08日14:39
今日は、後期選抜直前の閉庁日(長野県立高校一斉の対応)です。
土曜日に書ききれなかったことを二つ、報告させてください。
ひとつめ。卒業式会場の体育館に3年生が入場してくると、在校生が作成したビデオメッセージを大きなスクリーンにながしました。3年生ひとりひとりの顔写真が映し出され、その名前を在校生が2人1組で大きな声で呼ぶというスタイルで、在校生が卒業生全員を紹介するビデオでした。生徒会のスローガン「ファミリー」のような温かさにあふれたオープニングでした。
ふたつめ。私の式辞では、アフガニスタンで井戸を掘って人々のいのちを支え続けた中村哲さんが著書の中で紹介しているエピソードを紹介しました。(中田正一さんの文章を中村さんが引用しているくだり。)
――ある時、三人の若者が山の中で吹雪にあい、遭難しそうになった。C君はぐったりして動けなくなった。とほうにくれたA君、B君のうち、A君は頭の良い人で、「このままでは皆が危ない。ぼくが一人でさきにようすを見てくる」といって二人をおいて身軽に行ってしまった。
ところが、待てど暮らせどもどってこない。残されたB君は、「まあ仕方がない。ともかく凍えるよりは」と、たおれたC君を背にしてとぼとぼと雪の中を歩きはじめた。さいわいB君もC君も救助隊に助けられたが、途中で彼が遭遇したのは、なんと先に一人で進んだA君の死体だった。その時、B君が電光のようにさとったことがある。「ぼくはC君を助けるつもりで歩いていた。だが、じつは背にしたC君の体の温もりであたためあい、自分も凍えずに助かったのだ。」
私はこうつづけました。
私たち、蘇南高校の教員は、皆さんを背負っているつもりだったが、実は皆さんの温もりにあたためられてきた。親御さんはもっと同じことを思っているはず。これからは、皆さんが誰かを背負い、そのぬくもりで皆さんが幸せになってほしい。そうすれば、「いのちのリレー」になるんじゃないかな。

土曜日に書ききれなかったことを二つ、報告させてください。
ひとつめ。卒業式会場の体育館に3年生が入場してくると、在校生が作成したビデオメッセージを大きなスクリーンにながしました。3年生ひとりひとりの顔写真が映し出され、その名前を在校生が2人1組で大きな声で呼ぶというスタイルで、在校生が卒業生全員を紹介するビデオでした。生徒会のスローガン「ファミリー」のような温かさにあふれたオープニングでした。
ふたつめ。私の式辞では、アフガニスタンで井戸を掘って人々のいのちを支え続けた中村哲さんが著書の中で紹介しているエピソードを紹介しました。(中田正一さんの文章を中村さんが引用しているくだり。)
――ある時、三人の若者が山の中で吹雪にあい、遭難しそうになった。C君はぐったりして動けなくなった。とほうにくれたA君、B君のうち、A君は頭の良い人で、「このままでは皆が危ない。ぼくが一人でさきにようすを見てくる」といって二人をおいて身軽に行ってしまった。
ところが、待てど暮らせどもどってこない。残されたB君は、「まあ仕方がない。ともかく凍えるよりは」と、たおれたC君を背にしてとぼとぼと雪の中を歩きはじめた。さいわいB君もC君も救助隊に助けられたが、途中で彼が遭遇したのは、なんと先に一人で進んだA君の死体だった。その時、B君が電光のようにさとったことがある。「ぼくはC君を助けるつもりで歩いていた。だが、じつは背にしたC君の体の温もりであたためあい、自分も凍えずに助かったのだ。」
私はこうつづけました。
私たち、蘇南高校の教員は、皆さんを背負っているつもりだったが、実は皆さんの温もりにあたためられてきた。親御さんはもっと同じことを思っているはず。これからは、皆さんが誰かを背負い、そのぬくもりで皆さんが幸せになってほしい。そうすれば、「いのちのリレー」になるんじゃないかな。
「3年生60名が世界に飛翔する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年03月06日12:29
自分が生きている時代と真剣に向き合った人は、何歳であるかに関係なく、ずっと心に残るであろう「ことば」をうみだします。
令和2年卒業式が、南木曽町の向井町長さん、伊藤教育長さんのご臨席と保護者、在校生全員の出席を得て、とっても温かく素敵なセレモニーとして開催することができました。卒業式では、前生徒会長の伊藤さんが、三つのことを私たちに語りかけました。
高校時代に自分が学んだことの第一は、「挑戦してみること」の大切さだ。チャレンジすれば、新たな気づきと出会いが生まれて、自分がこんなふうに生きてみたいという思いがわいてくる。今、自分は「教育」についてもっと学び、「子どもたち」を支えて生きていきたいと考えている。
学んだことの第二は、「日常」というものの大切さだ。コロナで自分たちの生活は大きく変化したけれど、それがゆえに「学校に行く」ということのかけがえのなさを私たちは思い知った。文化祭のテーマ「青春と一瞬」にこめたように、日常の一瞬一瞬をいとおしいと思った、あの感覚を自分は一生忘れないでいたい。
第三は在校生へのメッセージとして、「こんな時代」であるからこそ、「自分ができること」を見つけていこうと言いたい。そうすることで「一瞬」を大切にしていこう。
伊藤さんの「答辞」の要旨です。
蘇南高校から、私たちの誇る卒業生たちが世界に乗り出していきます。
とってもさびしいというのが本音ですが、卒業生たちのこれからの「挑戦」と「日常」に幸多からんことを心から祈りたいと思います。
「卒業、ほんとうにおめでとう!」

令和2年卒業式が、南木曽町の向井町長さん、伊藤教育長さんのご臨席と保護者、在校生全員の出席を得て、とっても温かく素敵なセレモニーとして開催することができました。卒業式では、前生徒会長の伊藤さんが、三つのことを私たちに語りかけました。
高校時代に自分が学んだことの第一は、「挑戦してみること」の大切さだ。チャレンジすれば、新たな気づきと出会いが生まれて、自分がこんなふうに生きてみたいという思いがわいてくる。今、自分は「教育」についてもっと学び、「子どもたち」を支えて生きていきたいと考えている。
学んだことの第二は、「日常」というものの大切さだ。コロナで自分たちの生活は大きく変化したけれど、それがゆえに「学校に行く」ということのかけがえのなさを私たちは思い知った。文化祭のテーマ「青春と一瞬」にこめたように、日常の一瞬一瞬をいとおしいと思った、あの感覚を自分は一生忘れないでいたい。
第三は在校生へのメッセージとして、「こんな時代」であるからこそ、「自分ができること」を見つけていこうと言いたい。そうすることで「一瞬」を大切にしていこう。
伊藤さんの「答辞」の要旨です。
蘇南高校から、私たちの誇る卒業生たちが世界に乗り出していきます。
とってもさびしいというのが本音ですが、卒業生たちのこれからの「挑戦」と「日常」に幸多からんことを心から祈りたいと思います。
「卒業、ほんとうにおめでとう!」
カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長