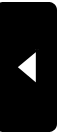「紙はないけれども賞状を授与したい」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月17日20:32
インターハイ予選の結果を校長に報告してねと、顧問を通じて生徒に伝えています。
特にこれで部活動に区切りをつけることになる3年生が「今のこの時点で考えていること」を語り、そのことばを受け止めることが、校長の役割だと思うからです。
まず、女子バレーボール部の全学年17名が訪ねて来てくれました。1回戦で敗れたものの、1セット目が「6対25」だったのに対し、2セット目は「23対25」と接戦の末の惜敗でした。
「大会で20点をとったのは初めてです。マネージャーとして、スコアを記録するのが本当に楽しかった。そんな経験が最後にできました。」(古川さん)
「大会では一人一人の役割をきちんと果たすことができたんだなって思いました。」(宮下さん)
「20点までとれるほど自分たちのチームが成長できたことがわかって、本当にうれしかった。選手権までもう少し続けたい。」(青沼さん)
「ここまで出来たことに対して、みんなにただただ感謝の思いでいっぱいです。1年生が加わって、みんなで努力をしてきたこの2カ月が、私にとって本当に『楽しい』日々でした。」(垣内さん)
彼女たちは、練習をすることが本当に「楽しい」2カ月を積み重ね、最後の大会で、記録を書き残すことが生まれて初めて「楽しい」経験を味わったのです。
今日は、大雨の一日でしたが、彼女たちと対話をした私の心は快晴になりました。
紙はないけれども賞状を授与したくなり、今日の私の記録を書き記したのでした。

特にこれで部活動に区切りをつけることになる3年生が「今のこの時点で考えていること」を語り、そのことばを受け止めることが、校長の役割だと思うからです。
まず、女子バレーボール部の全学年17名が訪ねて来てくれました。1回戦で敗れたものの、1セット目が「6対25」だったのに対し、2セット目は「23対25」と接戦の末の惜敗でした。
「大会で20点をとったのは初めてです。マネージャーとして、スコアを記録するのが本当に楽しかった。そんな経験が最後にできました。」(古川さん)
「大会では一人一人の役割をきちんと果たすことができたんだなって思いました。」(宮下さん)
「20点までとれるほど自分たちのチームが成長できたことがわかって、本当にうれしかった。選手権までもう少し続けたい。」(青沼さん)
「ここまで出来たことに対して、みんなにただただ感謝の思いでいっぱいです。1年生が加わって、みんなで努力をしてきたこの2カ月が、私にとって本当に『楽しい』日々でした。」(垣内さん)
彼女たちは、練習をすることが本当に「楽しい」2カ月を積み重ね、最後の大会で、記録を書き残すことが生まれて初めて「楽しい」経験を味わったのです。
今日は、大雨の一日でしたが、彼女たちと対話をした私の心は快晴になりました。
紙はないけれども賞状を授与したくなり、今日の私の記録を書き記したのでした。
「バドミントン中信大会三日目が終わる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月16日20:07
今日は、大会長をつとめている、バドミントンのインターハイ予選・中信地区大会の三日目でした。勝ち進んできている選手たちなので、どの高校の選手たちもそれぞれに目を見張るプレーをしています。ひたむきに努力している高校生の姿は、それだけでひとつのドラマのようです。
コロナに対する厳戒態勢をとり、細部に神経をとがらせて大会運営をしてくださった専門委員の皆さんや各校の顧問の皆さん、中信高体連の皆さんに、心から感謝を申し上げます。そして本校の生徒たちが、この大会に出場することを支えてくださった保護者・南木曽町社会体育のコーチ・下宿経営の皆様、そして南木曽町の皆様、本当にありがとうございました。
すべての試合が終わり、入賞者に私から賞状を授与しました。ひとりひとりのまなざしに正対して「おめでとう」と声をかけました。
本校バドミントン部の上位入賞結果は、以下のとおりとなりました。
・学校対抗戦 男子優勝・女子優勝
・ダブルス男子 1位(森・三石)2位(有賀伊・有賀詩)3位(藤森・下平)
・ダブルス女子 1位(小澤・後藤)
・シングルス男子 1位(森)2位(三石)3位(有賀詩)
・シングルス女子 1位(小澤)2位(後藤)
自分と闘いながら懸命に努力した生徒たち「全員」に、心を込めて拍手をおくります!

コロナに対する厳戒態勢をとり、細部に神経をとがらせて大会運営をしてくださった専門委員の皆さんや各校の顧問の皆さん、中信高体連の皆さんに、心から感謝を申し上げます。そして本校の生徒たちが、この大会に出場することを支えてくださった保護者・南木曽町社会体育のコーチ・下宿経営の皆様、そして南木曽町の皆様、本当にありがとうございました。
すべての試合が終わり、入賞者に私から賞状を授与しました。ひとりひとりのまなざしに正対して「おめでとう」と声をかけました。
本校バドミントン部の上位入賞結果は、以下のとおりとなりました。
・学校対抗戦 男子優勝・女子優勝
・ダブルス男子 1位(森・三石)2位(有賀伊・有賀詩)3位(藤森・下平)
・ダブルス女子 1位(小澤・後藤)
・シングルス男子 1位(森)2位(三石)3位(有賀詩)
・シングルス女子 1位(小澤)2位(後藤)
自分と闘いながら懸命に努力した生徒たち「全員」に、心を込めて拍手をおくります!

「悲しみに思いをいたしながら試合にのぞむ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月14日20:54
今日は、インターハイ予選中信地区大会のバドミントンの大会長として、信州スカイパーク体育館に一日つめました。
コロナ禍の中なので、感染予防対策を幾重にもとり、先生方はとても神経を使いながら大会運営をしています。スコアをつける用箋挟み、ペン、イス、あらゆるものを、そのたびにアルコール消毒をしました。フロアはいくつかの扉を全開にして、風が通るようになっています。感染予防のためにやむをえない措置です。
開会式で選手宣誓をしたのは、蘇南高校の森さんでした。校長室の掃除をしてくれている彼と、あらためてコートで向かい合うので、それだけで胸が熱くなります。
さらに私が心を動かされたのは、このような状況下で大会に参加できることになったことへの感謝の思いを忘れずに試合に臨みたいということと、昨年の大会に出られなかった先輩の悲しみに思いをいたしながら試合に臨みたいということを、森さんが宣誓したからです。生徒たちが、たくさんのものを背負ってこのコートに立っているのだということを、あらためて感じました。
他校の皆さんの思いも同じであったことでしょう。
本日は、学校対抗戦だったのですが、男女ともに蘇南高校が優勝しました。
生徒たちのプレイはすがすがしく、力強いものでした。

コロナ禍の中なので、感染予防対策を幾重にもとり、先生方はとても神経を使いながら大会運営をしています。スコアをつける用箋挟み、ペン、イス、あらゆるものを、そのたびにアルコール消毒をしました。フロアはいくつかの扉を全開にして、風が通るようになっています。感染予防のためにやむをえない措置です。
開会式で選手宣誓をしたのは、蘇南高校の森さんでした。校長室の掃除をしてくれている彼と、あらためてコートで向かい合うので、それだけで胸が熱くなります。
さらに私が心を動かされたのは、このような状況下で大会に参加できることになったことへの感謝の思いを忘れずに試合に臨みたいということと、昨年の大会に出られなかった先輩の悲しみに思いをいたしながら試合に臨みたいということを、森さんが宣誓したからです。生徒たちが、たくさんのものを背負ってこのコートに立っているのだということを、あらためて感じました。
他校の皆さんの思いも同じであったことでしょう。
本日は、学校対抗戦だったのですが、男女ともに蘇南高校が優勝しました。
生徒たちのプレイはすがすがしく、力強いものでした。
「いくつもの課題を同時並行で進める」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月13日20:06
昨日は、万一の事態に備えてのオンライン教育の環境整備を行いましたが、職員会ではそれと並行していくつかのことを進めていこうと確認しました。
(1)グランドデザインを刷新する。とくに「生徒育成方針」(このような生徒を育てたいという目標)は、このコロナ禍を乗り越えてくるなかで、従来の観念的なものから具体的なものに焦点化してきています。それをグランドデザインの核にしようと考えています。
(2)大学進学に向けての支援体制をブラッシュアップするために、家庭学習と授業・補習とのサイクルをより明確にしていくことに取り組みたいと思います。
(3)就職の支援については、来月に木曽地域の企業・団体の方々を本校にお招きし、校内で企業説明会を大規模に開催することを企画しています。
(4)探究学習を支えていただく地域連携のコンソーシアムに、これまでの南木曽町の方々に加え、大桑村と中津川市の方々にも入っていただき、生徒が地域で学ぶフィールドを拡大していくことを計画しています。
これらはすべてつながっていて、「未来の自分」を豊かに「想像」することを楽しみ、それを「創造」(現実化)につなげていくというコンセプトです。その際、多くの他者と対話し、心動かされる経験をし、やがて他者のために何かをしようと思考し、行動していってほしいと思うのです。
今日は、大桑村のコンソーシアム委員について打ち合わせのアポをとり、就労支援について「ともに」さんと打ち合わせをし、中信地区校長会に向かいました。
明日からは生徒たちがインターハイ予選に向かいます。

(1)グランドデザインを刷新する。とくに「生徒育成方針」(このような生徒を育てたいという目標)は、このコロナ禍を乗り越えてくるなかで、従来の観念的なものから具体的なものに焦点化してきています。それをグランドデザインの核にしようと考えています。
(2)大学進学に向けての支援体制をブラッシュアップするために、家庭学習と授業・補習とのサイクルをより明確にしていくことに取り組みたいと思います。
(3)就職の支援については、来月に木曽地域の企業・団体の方々を本校にお招きし、校内で企業説明会を大規模に開催することを企画しています。
(4)探究学習を支えていただく地域連携のコンソーシアムに、これまでの南木曽町の方々に加え、大桑村と中津川市の方々にも入っていただき、生徒が地域で学ぶフィールドを拡大していくことを計画しています。
これらはすべてつながっていて、「未来の自分」を豊かに「想像」することを楽しみ、それを「創造」(現実化)につなげていくというコンセプトです。その際、多くの他者と対話し、心動かされる経験をし、やがて他者のために何かをしようと思考し、行動していってほしいと思うのです。
今日は、大桑村のコンソーシアム委員について打ち合わせのアポをとり、就労支援について「ともに」さんと打ち合わせをし、中信地区校長会に向かいました。
明日からは生徒たちがインターハイ予選に向かいます。
「オンライン教育に備えた接続確認をする」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月12日20:11
今日は日課を一部変更して、生徒のICT環境の接続確認を行いました。
明日も学校は普通に登校日なのですが、「万一」の事態に備えて、オンライン教育によって家庭にいる生徒と私たちがつながるための準備です。
生徒はそれぞれのホームルーム教室にいて、Zoomで職員室の私たちの講話や説明を電子黒板に映し出す形です。
まず、私から、コロナ変異株がこれまでのウイルスとどのように違うのかについて、再度、呼びかけをしました。ここ数日、報道番組で解説されている変異株の特徴をしっかり理解したうえで、学校活動を組み立てていかなければならないと考えるからです。
次いで、生徒指導主事から、本校の教室がフリーWi-fi環境になったことと、フィルターがかかっているけれども、学習環境の充実のためのものであるという趣旨を心にとめて活用してほしいと話をしました。
そしてGoogle-Classroomに接続しての授業聴講や課題提出などを確認してみました。Zoomについてはこれまでも使用してきていたので、2・3年生にとっては簡単な復習です。
最後に担任が別室に行き、あえてZoomHRを行ってしめくくりました。
放課後は、職員会の後、あらためて全職員がGoogle-Classroomを操作できるよう、研修を行いました。
定期考査の試験づくり、インターハイ予選に向けての最終調整、文化祭の準備など、たくさんのことと並行しながらの「万一」のときの態勢づくりです。
生徒の皆さんが心配しないように、困らないようにするために、教職員が奮起した一日でした。

明日も学校は普通に登校日なのですが、「万一」の事態に備えて、オンライン教育によって家庭にいる生徒と私たちがつながるための準備です。
生徒はそれぞれのホームルーム教室にいて、Zoomで職員室の私たちの講話や説明を電子黒板に映し出す形です。
まず、私から、コロナ変異株がこれまでのウイルスとどのように違うのかについて、再度、呼びかけをしました。ここ数日、報道番組で解説されている変異株の特徴をしっかり理解したうえで、学校活動を組み立てていかなければならないと考えるからです。
次いで、生徒指導主事から、本校の教室がフリーWi-fi環境になったことと、フィルターがかかっているけれども、学習環境の充実のためのものであるという趣旨を心にとめて活用してほしいと話をしました。
そしてGoogle-Classroomに接続しての授業聴講や課題提出などを確認してみました。Zoomについてはこれまでも使用してきていたので、2・3年生にとっては簡単な復習です。
最後に担任が別室に行き、あえてZoomHRを行ってしめくくりました。
放課後は、職員会の後、あらためて全職員がGoogle-Classroomを操作できるよう、研修を行いました。
定期考査の試験づくり、インターハイ予選に向けての最終調整、文化祭の準備など、たくさんのことと並行しながらの「万一」のときの態勢づくりです。
生徒の皆さんが心配しないように、困らないようにするために、教職員が奮起した一日でした。

「時代の風を読む」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月11日18:43
今日もおだやかな日常が流れていきました。南木曽の山々の新緑がまぶしいくらいに輝いています。放課後に友人たちと楽しそうに語り合っている生徒の笑顔もまた、輝いて見えます。
とはいえ、COVID-19の変異株の猛威は、長野県でも深刻な状態になりつつあります。
南木曽で学園生活を送っていると、世の中の雰囲気に気づくのが遅れてしまうこともありうるので、今日の帰りのSHRでは、あらためて感染予防の要点を全クラスで確認しました。
そして、いつ本校が臨時休校の事態になっても、オンライン教育に切り替えられるように、明日は日課変更を行って、6・7限目に家庭での授業の受信方法の確認をしておくことにしました。ZoomとGoogle-Classroomを併用しながら、学校と生徒の皆さんがいつでもつながっていられるようにする覚悟です。
本校のスローガン「開拓者精神」について、私はことあるごとに、「未来の人々の幸せを想像して努力すること」だと生徒に語りかけてきました。
教職員の側には「時代の風を読んで先手を打つこと」だと語りかけてきました。厳しい時代だからこそ、時代の風をどう読むか、自分たちが常に試されています。

とはいえ、COVID-19の変異株の猛威は、長野県でも深刻な状態になりつつあります。
南木曽で学園生活を送っていると、世の中の雰囲気に気づくのが遅れてしまうこともありうるので、今日の帰りのSHRでは、あらためて感染予防の要点を全クラスで確認しました。
そして、いつ本校が臨時休校の事態になっても、オンライン教育に切り替えられるように、明日は日課変更を行って、6・7限目に家庭での授業の受信方法の確認をしておくことにしました。ZoomとGoogle-Classroomを併用しながら、学校と生徒の皆さんがいつでもつながっていられるようにする覚悟です。
本校のスローガン「開拓者精神」について、私はことあるごとに、「未来の人々の幸せを想像して努力すること」だと生徒に語りかけてきました。
教職員の側には「時代の風を読んで先手を打つこと」だと語りかけてきました。厳しい時代だからこそ、時代の風をどう読むか、自分たちが常に試されています。
「インターハイ予選に向けて」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月10日17:36
今週末からインターハイ予選地区大会が本格的に始まります。(一部の種目はすでに始まっています。)
昨年度の今頃は、臨時休校の真っ只中にインターハイの中止が決まり、3年生を中心に生徒たちは大きく落胆していました。今年度は、何とか生徒たちの努力の成果を発揮する舞台を守っていこうと地区大会が準備されてきました。
先週の金曜日には、壮行会を実施しました。大きな声では歌えないけれども、十分に距離を取り合いながら応援歌を歌い、エールの拍手を贈りました。全校のみんなが選手を見つめています。
生徒会長は、今年度の生徒会のテーマである「ファミリー」に関連付けて、「私たちみんながファミリーとして皆さんを応援している」と、激励の言葉を語りかけました。
私からは、「現代の日本ではオリンピックに対する世論の雰囲気を見ればわかるように、手放しでスポーツが応援される時代ではない。そのような状況下で、多くの方々から支えられて皆さんのインターハイ予選がある。感謝の気持ちを忘れないようにしよう」と、あえて厳しい現実を語りかけました。
選手の健闘を心から祈っています。そして何とか無事に地区大会が開かれてほしいと、文字通り「祈る」日々です。

昨年度の今頃は、臨時休校の真っ只中にインターハイの中止が決まり、3年生を中心に生徒たちは大きく落胆していました。今年度は、何とか生徒たちの努力の成果を発揮する舞台を守っていこうと地区大会が準備されてきました。
先週の金曜日には、壮行会を実施しました。大きな声では歌えないけれども、十分に距離を取り合いながら応援歌を歌い、エールの拍手を贈りました。全校のみんなが選手を見つめています。
生徒会長は、今年度の生徒会のテーマである「ファミリー」に関連付けて、「私たちみんながファミリーとして皆さんを応援している」と、激励の言葉を語りかけました。
私からは、「現代の日本ではオリンピックに対する世論の雰囲気を見ればわかるように、手放しでスポーツが応援される時代ではない。そのような状況下で、多くの方々から支えられて皆さんのインターハイ予選がある。感謝の気持ちを忘れないようにしよう」と、あえて厳しい現実を語りかけました。
選手の健闘を心から祈っています。そして何とか無事に地区大会が開かれてほしいと、文字通り「祈る」日々です。

「探究イノベーションの試み」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月07日18:01
今日の3年生の「総合探究」(金曜日の午後3時間連続)では、「探究イノベーション」という試みを行いました。
個人または班で、担当の教員の指導を受けながら、地域や日本社会の課題解決を探究しているのですが、教員のほうのバイアスとか視野の狭さに、生徒の探究が制約されてしまう恐れがあります。生徒と教員の距離が近い本校は、余計にその恐れがあります。
そこで今年は、担当ではない教員のところに生徒が行って、自分の研究の進捗状況をプレゼンし、アドバイスをもらうという機会を何回か設けることにしました。なづけて「探究イノベーション」です。
外からの刺激で、自分を見つめ直し、探究の革新をはかっていこうという企画です。
校長室には、防災の探究を進めている3人が来ました。プレゼンを聞くと、さまざまな試行錯誤が伺えて、とても面白い。
蘇南高校は高台にあるのですが、中学校や教職員寮のある沼田地区は木曽川河畔なので、どうしても洪水警報の際に避難することが必要になります。ところがそのためには木曽川や伊勢小屋沢の橋を渡らないといけません。避難に遅れると取り残される危険があります。
昔は沼田地区から蘇南高校の高台に登る避難路(山道)があったと聞いて、それを復活させようと、生徒たちは森林の藪の中に突入したのだそうです。途中で崩落している個所に出くわし、ときに(少し)滑落し、ほうほうのていで高台に登って来たのでした。お年寄りにはとてもこれを使うのは無理だとわかり、やはり早めの避難こそ大事と考えるにいたっています。ちなみに冒険のプロセスを動画に撮影しているところも、さすが。
身体を張って「安全な避難」を実現するためにはどうしたらよいかを探究する生徒の話を聞いて、私からもいくつかのアドバイスをしたのでした。
「探究イノベーション」は、生徒の探究をアカデミックな研究にリンクさせる視点をアドバイスできればいいという願いもあります。
学校を上げて生徒の探究を支援していくことを、大切にしていきたいと思っています。

個人または班で、担当の教員の指導を受けながら、地域や日本社会の課題解決を探究しているのですが、教員のほうのバイアスとか視野の狭さに、生徒の探究が制約されてしまう恐れがあります。生徒と教員の距離が近い本校は、余計にその恐れがあります。
そこで今年は、担当ではない教員のところに生徒が行って、自分の研究の進捗状況をプレゼンし、アドバイスをもらうという機会を何回か設けることにしました。なづけて「探究イノベーション」です。
外からの刺激で、自分を見つめ直し、探究の革新をはかっていこうという企画です。
校長室には、防災の探究を進めている3人が来ました。プレゼンを聞くと、さまざまな試行錯誤が伺えて、とても面白い。
蘇南高校は高台にあるのですが、中学校や教職員寮のある沼田地区は木曽川河畔なので、どうしても洪水警報の際に避難することが必要になります。ところがそのためには木曽川や伊勢小屋沢の橋を渡らないといけません。避難に遅れると取り残される危険があります。
昔は沼田地区から蘇南高校の高台に登る避難路(山道)があったと聞いて、それを復活させようと、生徒たちは森林の藪の中に突入したのだそうです。途中で崩落している個所に出くわし、ときに(少し)滑落し、ほうほうのていで高台に登って来たのでした。お年寄りにはとてもこれを使うのは無理だとわかり、やはり早めの避難こそ大事と考えるにいたっています。ちなみに冒険のプロセスを動画に撮影しているところも、さすが。
身体を張って「安全な避難」を実現するためにはどうしたらよいかを探究する生徒の話を聞いて、私からもいくつかのアドバイスをしたのでした。
「探究イノベーション」は、生徒の探究をアカデミックな研究にリンクさせる視点をアドバイスできればいいという願いもあります。
学校を上げて生徒の探究を支援していくことを、大切にしていきたいと思っています。
「山笑う」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年05月06日16:57
ゴールデンウィークあけの学校は、温かな陽気にめぐまれ、開け放たれた教室のドアから生徒たちの明るい声が響いていました。この時代状況の中で、生徒たちが元気に登校してくれるというそのことが、本当にうれしく、感動的に思えます。
蘇南高校をとりまく南木曽町の風景は、山々の新緑・花々が、澄んだ青空のもとに照らし出されて輝き、目を見張るような美しさです。
「山笑う」という俳句の季語を思わず口ずさみます。
「故郷(ふるさと)や どちらをみても 山笑ふ」(正岡子規)
私は一時期、子規を読みあさって、子規庵やお墓などあちこちを旅しました。故郷の心包まれる風景を秀逸に表現しており、感服する作品です。
「腹に在る 家動かして 山笑ふ」(高浜虚子)
今日は、この句の「家」が「学校」そのものです。
雄大で繊細な自然に囲まれて生活できることの喜びをかみしめます。この日々の中で自分がどんな「ことば」を紡ぐのか、あらためて心して生きていこうと思いました。

蘇南高校をとりまく南木曽町の風景は、山々の新緑・花々が、澄んだ青空のもとに照らし出されて輝き、目を見張るような美しさです。
「山笑う」という俳句の季語を思わず口ずさみます。
「故郷(ふるさと)や どちらをみても 山笑ふ」(正岡子規)
私は一時期、子規を読みあさって、子規庵やお墓などあちこちを旅しました。故郷の心包まれる風景を秀逸に表現しており、感服する作品です。
「腹に在る 家動かして 山笑ふ」(高浜虚子)
今日は、この句の「家」が「学校」そのものです。
雄大で繊細な自然に囲まれて生活できることの喜びをかみしめます。この日々の中で自分がどんな「ことば」を紡ぐのか、あらためて心して生きていこうと思いました。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長