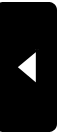「互いの学びを評価し合うことができるか」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月15日18:28
今日は、工業科の藤城先生のプレ研究授業を行いました。本校は、全国工業高等学校長協会の評価実践の研究校になっています。
昨年度は、ルーブリックやアセスメントを活用して、生徒が自分の学びと成長の様子をふりかえることができる「自己評価」を活用して、生徒たちが自信をもって学ぶことを支援しました。
今年度は、生徒たちがお互いの学びに温かな評価をしあえるような授業づくりを、テーマの一つにしています。「相互評価」の導入です。そのためには、常日頃のクラスの「人間関係づくり」も大切になってきますし、お互いの学びに温かであり、かつ的を射たコメントをする「人生の習慣」が必要になってきます。
今日の藤城先生の授業は、現在のエネルギー危機・環境問題を見すえて、50年後の日本のエネルギーのあり方について提言をしようというものでした。3班にわかれて、生徒たちがプレゼンテーションを行い、それに対して同時並行的に、聞く側の生徒がパソコンの「ジャムボード」を使ってコメントを入力し、それをもとに対話を試みるというものでした。
生徒たちの鋭い問いかけに感心し、これならば「相互評価」に挑戦できるのではないかと思ったのでした。
授業後の研究会では、協会の小山先生と湯澤先生から丁寧なアドバイスをいただきました。
評価というものを、生徒たちが自分の学習をふりかえって、さらに成長するためにはどうすればいいかを具体的に考えられるような「チャンス」にしたい(単なる評定のラベリングにしないようにする)と改めて思いました。

昨年度は、ルーブリックやアセスメントを活用して、生徒が自分の学びと成長の様子をふりかえることができる「自己評価」を活用して、生徒たちが自信をもって学ぶことを支援しました。
今年度は、生徒たちがお互いの学びに温かな評価をしあえるような授業づくりを、テーマの一つにしています。「相互評価」の導入です。そのためには、常日頃のクラスの「人間関係づくり」も大切になってきますし、お互いの学びに温かであり、かつ的を射たコメントをする「人生の習慣」が必要になってきます。
今日の藤城先生の授業は、現在のエネルギー危機・環境問題を見すえて、50年後の日本のエネルギーのあり方について提言をしようというものでした。3班にわかれて、生徒たちがプレゼンテーションを行い、それに対して同時並行的に、聞く側の生徒がパソコンの「ジャムボード」を使ってコメントを入力し、それをもとに対話を試みるというものでした。
生徒たちの鋭い問いかけに感心し、これならば「相互評価」に挑戦できるのではないかと思ったのでした。
授業後の研究会では、協会の小山先生と湯澤先生から丁寧なアドバイスをいただきました。
評価というものを、生徒たちが自分の学習をふりかえって、さらに成長するためにはどうすればいいかを具体的に考えられるような「チャンス」にしたい(単なる評定のラベリングにしないようにする)と改めて思いました。

「就職試験出陣式をひらく」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月14日19:22
いよいよ明後日から就職試験が解禁となります。本校でも3分の1の生徒が就職試験に臨みます。
今日の放課後、出陣式を開催しました。
まず、私から生徒たちに激励の言葉を贈りました。
第一に、就職試験で皆さん個人の努力ではどうすることもできないこと(例えば家庭環境であるとか容姿であるとか)を問われて、それで合否が左右されることは、あってはならない。万一、そのようなことがあればすぐに報告してほしい、とアドバイスをしました。
第二に、前の日まで面接練習など、徹底した努力を積み重ねよう。これでもかというくらい努力をすれば、当日は落ち着いて試験に臨むことができる、とアドバイスしました。人事を尽くして天命を待つ、です。
次いで、代表の生徒が、私に向って決意表明をしてくれました。とても力強い言葉で、私は「これなら大丈夫だ」と心の中でつぶやきました。最後に「ガンバロー・コール」を、コロナ対策のために、ポーズのみで行いました。
本校の生徒たちの魅力と可能性が、企業の皆様の心に届くことを祈っています。
生徒の皆さん、普段の自分をそのまま相手に伝えればよいので、自信をもって、試験に臨んでください!

今日の放課後、出陣式を開催しました。
まず、私から生徒たちに激励の言葉を贈りました。
第一に、就職試験で皆さん個人の努力ではどうすることもできないこと(例えば家庭環境であるとか容姿であるとか)を問われて、それで合否が左右されることは、あってはならない。万一、そのようなことがあればすぐに報告してほしい、とアドバイスをしました。
第二に、前の日まで面接練習など、徹底した努力を積み重ねよう。これでもかというくらい努力をすれば、当日は落ち着いて試験に臨むことができる、とアドバイスしました。人事を尽くして天命を待つ、です。
次いで、代表の生徒が、私に向って決意表明をしてくれました。とても力強い言葉で、私は「これなら大丈夫だ」と心の中でつぶやきました。最後に「ガンバロー・コール」を、コロナ対策のために、ポーズのみで行いました。
本校の生徒たちの魅力と可能性が、企業の皆様の心に届くことを祈っています。
生徒の皆さん、普段の自分をそのまま相手に伝えればよいので、自信をもって、試験に臨んでください!
「どろぼう草が活躍する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月13日19:33
今月は、教職員が相互に授業を参観し合って学ぶ、授業研究月間となっています。
通常日課になったこともあり、今日から私も様々な授業に後ろの座席から参加させてもらっています。
教職員がよりよい授業をつくるには、さらにどのような点に留意していけばよいかというアドバイスをしたいと思って参観するわけですが、しばしば「学ぶこと」を純粋に楽しんでいます。
たとえば、今日の2年「音楽表現基礎」では、コロナ対策をふまえて、「涙そうそう」をハンドベルで演奏していました。原先生は、この曲のリズムやメロディーに実に繊細な仕掛けが施されていることを教えながら、ハンドベルの練習を促していきます。
この曲が、なぜこんなにも心を打つのかの理由が、私にもわかったように思えました。
同じく2年の「科学と人間生活」では、窒素同化を学ぶ中で、根粒菌を実際に観察しました。大ベテランの白金先生が教室に持ち込んだのは、なんと大量の「ヌスビトハギ」! わが飯田では「どろぼう草」と呼ばれて忌み嫌われている植物です。なにしろ秋に草刈りをすると果実の破片がズボンにびっしり貼り付いて、私たちをいらつかせるのですから。
しかし、白金先生が授業のために巨大化を許した「どろぼう草」が、今日は大活躍でした。

通常日課になったこともあり、今日から私も様々な授業に後ろの座席から参加させてもらっています。
教職員がよりよい授業をつくるには、さらにどのような点に留意していけばよいかというアドバイスをしたいと思って参観するわけですが、しばしば「学ぶこと」を純粋に楽しんでいます。
たとえば、今日の2年「音楽表現基礎」では、コロナ対策をふまえて、「涙そうそう」をハンドベルで演奏していました。原先生は、この曲のリズムやメロディーに実に繊細な仕掛けが施されていることを教えながら、ハンドベルの練習を促していきます。
この曲が、なぜこんなにも心を打つのかの理由が、私にもわかったように思えました。
同じく2年の「科学と人間生活」では、窒素同化を学ぶ中で、根粒菌を実際に観察しました。大ベテランの白金先生が教室に持ち込んだのは、なんと大量の「ヌスビトハギ」! わが飯田では「どろぼう草」と呼ばれて忌み嫌われている植物です。なにしろ秋に草刈りをすると果実の破片がズボンにびっしり貼り付いて、私たちをいらつかせるのですから。
しかし、白金先生が授業のために巨大化を許した「どろぼう草」が、今日は大活躍でした。
「雑誌『木曽人』でバドミントン部が紹介されています」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月10日15:57
フリーペーパー『木曽人』(季刊)は、木曽地域の魅力的な人々を紹介していて、私は毎号を楽しみにしています。
今回発行された第28号には、「学び舎の風景」というコーナーがあって、本校のバドミントン部の生徒たちがとりあげられています。
インターハイに出場する直前の取材だったので、大会にのぞむ意気込みについてのインタビューが中心なのですが、生徒たちの熱い思いと明るい表情が掲載されていますので、是非、お読みいただければ幸いです。

今回発行された第28号には、「学び舎の風景」というコーナーがあって、本校のバドミントン部の生徒たちがとりあげられています。
インターハイに出場する直前の取材だったので、大会にのぞむ意気込みについてのインタビューが中心なのですが、生徒たちの熱い思いと明るい表情が掲載されていますので、是非、お読みいただければ幸いです。

「丸木俊の少女像を飾る」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月08日14:25
今日から本校は通常日課(50分授業×6コマ)としながら、県教育委員会の方針により部活動と生徒会活動の原則禁止を続けて、学校生活をいとなんでいます。
校長室の入り口の横に設けている「校長室ギャラリー」は、丸木俊(1912-2000)「おしゃれの少女 ソフィア 文字の日」という版画を展示しています。私が持っている丸木作品は2点あり、そのうちのひとつです。
北海道出身の丸木俊は、夫の丸木位里と制作した「原爆の図」が有名です。一方で、多くの絵本の挿絵とか華麗な版画作品も数多く残しています。展示している「おしゃれの少女 ソフィア 文字の日」も、鮮やかな色彩が目をひく作品です。
曇りがちの天気が続いているのですが、すぐれたアートを鑑賞して、心を明るくしていきたいものです。

校長室の入り口の横に設けている「校長室ギャラリー」は、丸木俊(1912-2000)「おしゃれの少女 ソフィア 文字の日」という版画を展示しています。私が持っている丸木作品は2点あり、そのうちのひとつです。
北海道出身の丸木俊は、夫の丸木位里と制作した「原爆の図」が有名です。一方で、多くの絵本の挿絵とか華麗な版画作品も数多く残しています。展示している「おしゃれの少女 ソフィア 文字の日」も、鮮やかな色彩が目をひく作品です。
曇りがちの天気が続いているのですが、すぐれたアートを鑑賞して、心を明るくしていきたいものです。
「第2回ブリコラージュ賞を呼びかける」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月07日14:43
本校は、今日まで短縮日課で、明日から通常日課となります。ただし部活動は、長野県教育委員会の方針により、大会直前のクラブ以外は禁止です。
今日の帰りのホームルームの時間に、校長の放送講話を行いました。①コロナについての改めての注意喚起、②オンライン学習に生徒がいかに頑張ったかについての評価、③第2回ブリコラージュ賞、④先日の代行バスを走らせるにあたっての人々の努力への感謝…の4点についてです。
①について言うと、本校の生徒のうち、2回または1回のワクチン接種を済ませた人は6割、10月末までに接種予定の人を入れると8割になります。木曽・中津川地域では接種が進んでいることがわかります。(もちろん接種しない人への配慮もしたスマホによる調査の結果です。)
今日、私が生徒に語ったのは、2回接種をしてもコロナにかかる場合があるし、そのときに症状は比較的軽いけれども、口から出るウイルスの量は未接種の人と差がないという研究結果が出ているということ。つまり、ワクチン接種はコロナ予防である一方で、よりうつし易くなっている面もあるのです。だから感染予防が引き続き大切。
③の第2回ブリコラージュ賞について言うと、自宅にいる時間が長くなるのならば、それを逆手にとって、今しかできないことに取り組んで応募しようという、校長主催のコンクールです。
今日も、こんなことをやっていますとか、こんなことをやってみたいと、校長室に来て話してくれる生徒がいました。
――いいねえ、ぜひ、取り組んでね。…と、励ましています。
前庭の植栽は、紅葉が始まっています。急な秋の気配を楽しみつつ、コロナ禍のなかの対面授業を注意深く進めています。

今日の帰りのホームルームの時間に、校長の放送講話を行いました。①コロナについての改めての注意喚起、②オンライン学習に生徒がいかに頑張ったかについての評価、③第2回ブリコラージュ賞、④先日の代行バスを走らせるにあたっての人々の努力への感謝…の4点についてです。
①について言うと、本校の生徒のうち、2回または1回のワクチン接種を済ませた人は6割、10月末までに接種予定の人を入れると8割になります。木曽・中津川地域では接種が進んでいることがわかります。(もちろん接種しない人への配慮もしたスマホによる調査の結果です。)
今日、私が生徒に語ったのは、2回接種をしてもコロナにかかる場合があるし、そのときに症状は比較的軽いけれども、口から出るウイルスの量は未接種の人と差がないという研究結果が出ているということ。つまり、ワクチン接種はコロナ予防である一方で、よりうつし易くなっている面もあるのです。だから感染予防が引き続き大切。
③の第2回ブリコラージュ賞について言うと、自宅にいる時間が長くなるのならば、それを逆手にとって、今しかできないことに取り組んで応募しようという、校長主催のコンクールです。
今日も、こんなことをやっていますとか、こんなことをやってみたいと、校長室に来て話してくれる生徒がいました。
――いいねえ、ぜひ、取り組んでね。…と、励ましています。
前庭の植栽は、紅葉が始まっています。急な秋の気配を楽しみつつ、コロナ禍のなかの対面授業を注意深く進めています。
「本島和人さんの満洲移民研究書を読む」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月05日08:49
飯田市歴史研究所の本島和人さんが、『滿洲移民・青少年義勇軍の研究――長野県下の国策遂行』(吉川弘文館、1万円)を出版されました。私は深い感銘をもって読み終えました。見事な業績と言えましょう。
歴史教育の見地から本書の意義を述べます。
第一に、全国一、満洲移民をうみだした長野県の中でも中心的な役割を果たした下伊那地方において、移民を送り出すことの困難さ、壁があったということを本書が明らかにしていることです。それは複数の思惑による送出方法の競合という政策立案者側の問題もありました。しかし、一番に注目すべきは、人々の間に呼びかけに応じないという「非協力」の論理があったということを、川路村の事例を丹念に分析しながら明らかにしていることです。どんなに移民を要請されても従わなかった「生活者の論理」とも言えましょう。
普通の人々の生活者の抵抗に着目することこそ、主権者として市民がどう生きるかを問うことにつながると思うのです。抵抗する側の「多様な」論理を分析することこそ、これまでの歴史教育に不足しがちであったテーマです。
第二に、バス乗り遅れるなという「バスの論理」が満洲移民を推進したのだという仮説に一定の評価を与えながらも、それでは歴史の解明にならないという姿勢を示している点です。私はこの点に大いに共感します。「バスの論理」があったにせよ、政策を推進して人々を満洲に送った「送りだした主体」がいるわけで、その人々の行為を解明しないと「送り出した主体」もまた騙されていたという論理で免責されかねない。
そして「送り出した主体」として本書は、教育者たちの責任、政治家の責任、行政を担う公務員の責任を克明に明らかにしていきます。そしてまた彼らが自らの責任に十分向き合うことをしてこなかったことを、厳しく見つめています。さりながら本書の筆致は、彼らの罪状を暴露して告発するというスタイルではなく、彼らの弱さを自分たちに通じる弱さとして見つめる反省的なまなざしのもとにあるために、断罪スタイルの本になっていない。
その研究者としての姿勢にも私は深く共感しています。
本書に登場する人々は、国や県の進める政策に抱いた「違和感」を自分の「立場の責任」によって覆い隠して、人々を満洲に送り出していきました。
では、私はどう生きるべきか。本書の描く歴史は自分自身を問い直すことを求めています。

歴史教育の見地から本書の意義を述べます。
第一に、全国一、満洲移民をうみだした長野県の中でも中心的な役割を果たした下伊那地方において、移民を送り出すことの困難さ、壁があったということを本書が明らかにしていることです。それは複数の思惑による送出方法の競合という政策立案者側の問題もありました。しかし、一番に注目すべきは、人々の間に呼びかけに応じないという「非協力」の論理があったということを、川路村の事例を丹念に分析しながら明らかにしていることです。どんなに移民を要請されても従わなかった「生活者の論理」とも言えましょう。
普通の人々の生活者の抵抗に着目することこそ、主権者として市民がどう生きるかを問うことにつながると思うのです。抵抗する側の「多様な」論理を分析することこそ、これまでの歴史教育に不足しがちであったテーマです。
第二に、バス乗り遅れるなという「バスの論理」が満洲移民を推進したのだという仮説に一定の評価を与えながらも、それでは歴史の解明にならないという姿勢を示している点です。私はこの点に大いに共感します。「バスの論理」があったにせよ、政策を推進して人々を満洲に送った「送りだした主体」がいるわけで、その人々の行為を解明しないと「送り出した主体」もまた騙されていたという論理で免責されかねない。
そして「送り出した主体」として本書は、教育者たちの責任、政治家の責任、行政を担う公務員の責任を克明に明らかにしていきます。そしてまた彼らが自らの責任に十分向き合うことをしてこなかったことを、厳しく見つめています。さりながら本書の筆致は、彼らの罪状を暴露して告発するというスタイルではなく、彼らの弱さを自分たちに通じる弱さとして見つめる反省的なまなざしのもとにあるために、断罪スタイルの本になっていない。
その研究者としての姿勢にも私は深く共感しています。
本書に登場する人々は、国や県の進める政策に抱いた「違和感」を自分の「立場の責任」によって覆い隠して、人々を満洲に送り出していきました。
では、私はどう生きるべきか。本書の描く歴史は自分自身を問い直すことを求めています。
「最終バスを見送る」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月03日13:00
8月14日の豪雨から不通になっていた中央西線の南木曽~上松間が、今日の始発から開通しました。
昨晩、最後の代行バスが出発することを見送ろうと、夜の10時に南木曽駅に行きました。バスを出す南木曽観光の運転手とJR東海の職員2人が、夜遅くまでバスのために働いておられました。乗客はわずか4名ですが、公共交通が災害をのりこえて維持されていくために、多くの方々の労苦がはらわれているのです。
そうしたことを教員は、生徒にしっかり伝えていくべきだと思うのです。
本校の生徒たちの通学を支えていただいていることに、御礼を申し上げながら、南木曽駅を出発するバスを見送りました。
今朝は、3週間ぶりに北からの列車が南木曽駅にやってきました。その列車を迎えたくて、朝早く南木曽駅近くの跨線橋にのぼりました。
私も日常を守るために汗を流していこうと、あらためて思いました。

昨晩、最後の代行バスが出発することを見送ろうと、夜の10時に南木曽駅に行きました。バスを出す南木曽観光の運転手とJR東海の職員2人が、夜遅くまでバスのために働いておられました。乗客はわずか4名ですが、公共交通が災害をのりこえて維持されていくために、多くの方々の労苦がはらわれているのです。
そうしたことを教員は、生徒にしっかり伝えていくべきだと思うのです。
本校の生徒たちの通学を支えていただいていることに、御礼を申し上げながら、南木曽駅を出発するバスを見送りました。
今朝は、3週間ぶりに北からの列車が南木曽駅にやってきました。その列車を迎えたくて、朝早く南木曽駅近くの跨線橋にのぼりました。
私も日常を守るために汗を流していこうと、あらためて思いました。
「ピンチをチャンスにかえる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月02日18:19
今日は、短縮特別日課で対面授業を行いました。
昨日、2週間にわたる完全オンライン学習について、生徒の皆さんに振り返ってもらいました。
オンラインの日々に入る前に、仕方なくオンラインに耐えるというだけでなく、オンライン学習が自分の力を伸ばすチャンスだと思ってほしいと、私は全校生徒に語りかけていました。そこで掲げた「三つの力」に対して自分がどう向き合ったのかを、生徒たちに記述してもらったのです。
まず、「学びの自己調整力」についてどんなことを試したか。
圧倒的に多かったのは、「対面授業だと板書をただ書き写すだけだったけど、メモをたくさんとるように心がけた」という声。タイムマネジメントをはかるために、「タイマーをかけて生活した」という声も多かったです。「わからないところを友人と教え合った」とか「わからないことを今まで以上に自分で調べるようになった」という声も多かった。
ちなみに「とても調整した」「まあまあ調整した」を合わせると、9割近い人数でした。
次に「試行錯誤する力(回復力)」のための努力について。
「電波状況が悪くなっても何とかつながり、授業を受け続けようとした」がとても多かったです。振り返りを見ることで、こうした生徒の努力に私たちは初めて気づけました。
「演習の時間でカメラをオフにしたときにさぼらないように、机のまわりを片付けて不要物をいっさい近くにおかないようにした」「眠気とたたかって勝った」「見られていないからサボろうとする自分とたたかった」という記述を読みながら、私は心の中で大きな拍手を贈りました。
ちなみに「とても挑戦した」「まあまあ挑戦した」を合わせると、9割の人数でした。
最後に、今回の学びがどんな未来の幸せにつながると考えたかという「自己効力感」の問い。
多かったのは、「社会に出た時にもリモートワークが多くなるだろうから、そのトレーニングをかねていると思って取り組めた」という声。…そうか、君たちは、そこまで考えていたのか!
「これから一人で考えて行動することが多くなるし、自分で時間を管理して行動することの大切さがよくわかった」という記述もありました。
厳しい現実をチャンスにかえようとする生徒たちの姿が、見えてきました。
大したものです。

昨日、2週間にわたる完全オンライン学習について、生徒の皆さんに振り返ってもらいました。
オンラインの日々に入る前に、仕方なくオンラインに耐えるというだけでなく、オンライン学習が自分の力を伸ばすチャンスだと思ってほしいと、私は全校生徒に語りかけていました。そこで掲げた「三つの力」に対して自分がどう向き合ったのかを、生徒たちに記述してもらったのです。
まず、「学びの自己調整力」についてどんなことを試したか。
圧倒的に多かったのは、「対面授業だと板書をただ書き写すだけだったけど、メモをたくさんとるように心がけた」という声。タイムマネジメントをはかるために、「タイマーをかけて生活した」という声も多かったです。「わからないところを友人と教え合った」とか「わからないことを今まで以上に自分で調べるようになった」という声も多かった。
ちなみに「とても調整した」「まあまあ調整した」を合わせると、9割近い人数でした。
次に「試行錯誤する力(回復力)」のための努力について。
「電波状況が悪くなっても何とかつながり、授業を受け続けようとした」がとても多かったです。振り返りを見ることで、こうした生徒の努力に私たちは初めて気づけました。
「演習の時間でカメラをオフにしたときにさぼらないように、机のまわりを片付けて不要物をいっさい近くにおかないようにした」「眠気とたたかって勝った」「見られていないからサボろうとする自分とたたかった」という記述を読みながら、私は心の中で大きな拍手を贈りました。
ちなみに「とても挑戦した」「まあまあ挑戦した」を合わせると、9割の人数でした。
最後に、今回の学びがどんな未来の幸せにつながると考えたかという「自己効力感」の問い。
多かったのは、「社会に出た時にもリモートワークが多くなるだろうから、そのトレーニングをかねていると思って取り組めた」という声。…そうか、君たちは、そこまで考えていたのか!
「これから一人で考えて行動することが多くなるし、自分で時間を管理して行動することの大切さがよくわかった」という記述もありました。
厳しい現実をチャンスにかえようとする生徒たちの姿が、見えてきました。
大したものです。
「モンキーたちとの駆け引き」
Posted by 蘇南高等学校長.
2021年09月01日17:43
完全オンライン授業を続けていると、この静寂に包まれたキャンパスに「侵入者」が現れます。サル軍団です。
以前に通学路の歩道に群れで寝そべっていたサルが、登校する生徒を威嚇したことがありました。立ちすくむ生徒をたまたま通りかかったPTA会長が自動車で学校に送ってくださったのです。
以来、頭にきた校長は「モンキー・ハンター」と自称し、キャンパスにサルが侵入したという情報を得ると、すぐさま出動してサルを追い払っています。
最近では、戸外の物音の中でもサルの叫び声を聞き分けられるようになり、気配を感じただけですぐ出動しています。
モンキーたちからは、それなりに恐れられているようです。以前は私に追い払われると、少し離れた樹の上に登り、こちらの出方を伺っていましたが、最近では少しでも校長の姿を見ると、森の中に一目散に逃げていきます。「ヤバイ、あいつだ!」という表情で、振り返ることを一切せずに逃げていきます。
形勢がこちらに有利になったのは、モンキーたちが森に逃げ込んだときに、校長も森の中に深く分け入って追いかけて以来だと思っています。「ここまでくるのか、クレイジーだぜ」と思ったことでしょう。
これも駆け引きのひとつで、スキを見せると動物に攻め込まれるので、徹底して嫌われるしかありません。
今朝は、5時半頃から教員住宅の駐輪場の屋根で、モンキーたちが「走り幅跳び」を遊び始めました。私は玄関から出て、彼らを追う払うことはせずに、そのまま別方向に歩きました。
でもモンキーたちは、血相をかえて森の奥に走り去っていきました。

以前に通学路の歩道に群れで寝そべっていたサルが、登校する生徒を威嚇したことがありました。立ちすくむ生徒をたまたま通りかかったPTA会長が自動車で学校に送ってくださったのです。
以来、頭にきた校長は「モンキー・ハンター」と自称し、キャンパスにサルが侵入したという情報を得ると、すぐさま出動してサルを追い払っています。
最近では、戸外の物音の中でもサルの叫び声を聞き分けられるようになり、気配を感じただけですぐ出動しています。
モンキーたちからは、それなりに恐れられているようです。以前は私に追い払われると、少し離れた樹の上に登り、こちらの出方を伺っていましたが、最近では少しでも校長の姿を見ると、森の中に一目散に逃げていきます。「ヤバイ、あいつだ!」という表情で、振り返ることを一切せずに逃げていきます。
形勢がこちらに有利になったのは、モンキーたちが森に逃げ込んだときに、校長も森の中に深く分け入って追いかけて以来だと思っています。「ここまでくるのか、クレイジーだぜ」と思ったことでしょう。
これも駆け引きのひとつで、スキを見せると動物に攻め込まれるので、徹底して嫌われるしかありません。
今朝は、5時半頃から教員住宅の駐輪場の屋根で、モンキーたちが「走り幅跳び」を遊び始めました。私は玄関から出て、彼らを追う払うことはせずに、そのまま別方向に歩きました。
でもモンキーたちは、血相をかえて森の奥に走り去っていきました。
カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長