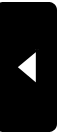「部活動を終えるにあたって未来への展望を語れる大切さ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月17日17:09
中信地区大会を終えた男子バレーボール部の3年生、上田さん・堀さん・大脇さん・原さんが校長室に来て報告をしてくれました。
試合は、南安曇農業高校に対して負けてしまい、ミスが目立った悔しい部分はありましたが、格上の相手に対して自分たちの試合運びができたところもいくつかあり、3年間部活動を続けてきた充実感をしっかり感じることが出来たとのこと。
これまでの部活動で培った力で、このあとの人生に役立つだろうと実感しているものは何ですかと生徒たちに聞いてみました。
「人との関係性を大切にして生きるということ。そのためのコミュニケーション力です。」
「チームスポーツだから、協力し合うことを大切にしてきました。この協力する力です。」
「人と何かをするとき、その人に合った方法は何かをずっと考えてきたように思います。そう考えることは、これからも続けたいです。」
「協調性です。これからも社会に出て何かに頑張るとき、大切にしていきたいです。」
こう語ってくれた生徒たちの表情を見ながら、随分と大人になったと、私は感心したのでした。
残念ながら負けたとしても、雨の日も酷暑の日も、毎日の練習をひたむきに続けてきて、たくさんのことに悩み、たくさんのことに感動して、最後の試合を迎えたはず。
そして自分の何が成長したのかを明確に語って、明日につなげていこうとしている生徒たちに、私は心からの拍手を贈りたいと思ったのでした。

試合は、南安曇農業高校に対して負けてしまい、ミスが目立った悔しい部分はありましたが、格上の相手に対して自分たちの試合運びができたところもいくつかあり、3年間部活動を続けてきた充実感をしっかり感じることが出来たとのこと。
これまでの部活動で培った力で、このあとの人生に役立つだろうと実感しているものは何ですかと生徒たちに聞いてみました。
「人との関係性を大切にして生きるということ。そのためのコミュニケーション力です。」
「チームスポーツだから、協力し合うことを大切にしてきました。この協力する力です。」
「人と何かをするとき、その人に合った方法は何かをずっと考えてきたように思います。そう考えることは、これからも続けたいです。」
「協調性です。これからも社会に出て何かに頑張るとき、大切にしていきたいです。」
こう語ってくれた生徒たちの表情を見ながら、随分と大人になったと、私は感心したのでした。
残念ながら負けたとしても、雨の日も酷暑の日も、毎日の練習をひたむきに続けてきて、たくさんのことに悩み、たくさんのことに感動して、最後の試合を迎えたはず。
そして自分の何が成長したのかを明確に語って、明日につなげていこうとしている生徒たちに、私は心からの拍手を贈りたいと思ったのでした。
「みんなで考える部活動を続けて勝利をつかむ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月16日16:55
この土日にインターハイ予選中信地区大会が行われました。これから何回かに分けて、大会に臨んだ各クラブの生徒たちの様子を紹介していきます。
今日の昼休みに、女子バレーボール部の3年生たち7名が校長室に来て、大会の報告をしてくれました。弱小チームの状態から「公式試合で勝てるチームになりたい」という目標を立ててこれまで努力を積み重ねてきた彼女たちは、13日(土)の地区大会で、ついに穂高商業高校に2セットをとって勝利をおさめることができました。
本当に「勝てるチーム」になったのです。
3年生に今の思いを聞きました。
「「みんなで考える部活動をする」というのが私たちの方針でした。どうすれば勝てるようになるのかを常に考えて、努力してきました。そして最後の試合で「勝つ」ことが出来ました。自分たちが成長できたという実感をもっています。」
「「勝てるチーム」という目標を最後に達成することが出来ました。本当にうれしいです。」
2年と1カ月、彼女たちを指導してきた鷹野先生にも思いを聞きました。
「互いに尊敬しあえるチームになろう。自分たちも、そして関わってくださった人たちも、部活動を通じて、幸せになれるチームになろう。そんなことを呼びかけ続けた2年間でした。3年生最後の大会で、とても楽しい試合ができ、充実感でいっぱいです。」
たくさんの苦しい壁を乗り越えながら、大きなものをつかんだ生徒と先生の姿がそこにはありました。

今日の昼休みに、女子バレーボール部の3年生たち7名が校長室に来て、大会の報告をしてくれました。弱小チームの状態から「公式試合で勝てるチームになりたい」という目標を立ててこれまで努力を積み重ねてきた彼女たちは、13日(土)の地区大会で、ついに穂高商業高校に2セットをとって勝利をおさめることができました。
本当に「勝てるチーム」になったのです。
3年生に今の思いを聞きました。
「「みんなで考える部活動をする」というのが私たちの方針でした。どうすれば勝てるようになるのかを常に考えて、努力してきました。そして最後の試合で「勝つ」ことが出来ました。自分たちが成長できたという実感をもっています。」
「「勝てるチーム」という目標を最後に達成することが出来ました。本当にうれしいです。」
2年と1カ月、彼女たちを指導してきた鷹野先生にも思いを聞きました。
「互いに尊敬しあえるチームになろう。自分たちも、そして関わってくださった人たちも、部活動を通じて、幸せになれるチームになろう。そんなことを呼びかけ続けた2年間でした。3年生最後の大会で、とても楽しい試合ができ、充実感でいっぱいです。」
たくさんの苦しい壁を乗り越えながら、大きなものをつかんだ生徒と先生の姿がそこにはありました。
「蘇南高校生が日本のチカラと出会う」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月15日08:14
15日(日)5:45~6:15の早朝、信越放送のTV番組「日本のチカラ~汐凪に吹く風」が放映されました。
東日本大震災で父・妻・次女を失った、木村紀夫さんと長女の「その後」の日々を丁寧にたどったドキュメンタリーです。長野県の白馬村に避難して長女を高校に通学させ、長女の卒業を機に福島県に戻った木村さん。太陽光発電から得られる電気だけを利用する簡素な生活をいとなみながら、福島第一原子力発電所からわずか3キロの自宅(帰宅困難区域)の手入れと次女の汐凪(ゆうな)さんの捜索を続けてきました。自宅からわずか200メートルの場所で汐凪さんの遺骨の一部が発見されたのが、ようやく2016年のこと。
今も汐凪さんの遺骨を探し続けながら、木村さんは、大熊町の現状をリアル配信して「いのち」を守ることはどういうことかを若い世代に問いかける伝承活動を展開されています。
今日のTV番組の後半は、昨年暮れに木村さんが蘇南高校の全校生徒たちに行ってくださったオンライン講演会の様子が映し出されました。木村さんの思いを本校の生徒たちがしっかり受け止めて、「自分ごと」として大震災と原発事故を考えようとしている風景でした。
番組のラストシーンでは、木村さんが汐凪さんのために建てたお地蔵さんの映像に、今もなお汐凪さんの遺骨を探して土を掘り返す、木村さんの鎌の音が重ねられていました。あきらめない、絶対にあきらめない、という響きに聞こえました。
まさにこれこそ「日本のチカラ」だろうと、私は胸が熱くなったのでした。

東日本大震災で父・妻・次女を失った、木村紀夫さんと長女の「その後」の日々を丁寧にたどったドキュメンタリーです。長野県の白馬村に避難して長女を高校に通学させ、長女の卒業を機に福島県に戻った木村さん。太陽光発電から得られる電気だけを利用する簡素な生活をいとなみながら、福島第一原子力発電所からわずか3キロの自宅(帰宅困難区域)の手入れと次女の汐凪(ゆうな)さんの捜索を続けてきました。自宅からわずか200メートルの場所で汐凪さんの遺骨の一部が発見されたのが、ようやく2016年のこと。
今も汐凪さんの遺骨を探し続けながら、木村さんは、大熊町の現状をリアル配信して「いのち」を守ることはどういうことかを若い世代に問いかける伝承活動を展開されています。
今日のTV番組の後半は、昨年暮れに木村さんが蘇南高校の全校生徒たちに行ってくださったオンライン講演会の様子が映し出されました。木村さんの思いを本校の生徒たちがしっかり受け止めて、「自分ごと」として大震災と原発事故を考えようとしている風景でした。
番組のラストシーンでは、木村さんが汐凪さんのために建てたお地蔵さんの映像に、今もなお汐凪さんの遺骨を探して土を掘り返す、木村さんの鎌の音が重ねられていました。あきらめない、絶対にあきらめない、という響きに聞こえました。
まさにこれこそ「日本のチカラ」だろうと、私は胸が熱くなったのでした。

「茶摘みをすることで開拓者精神を受け継ぐ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月12日18:27
今日は、本校の伝統行事「茶摘み」を行いました。
70年前に本校が創立された当初、生徒会や部活動の費用を自分たちで準備しようと、学校の校舎の裏側に広大な茶畑がつくられました。1年生が中心となって三日がかりで「茶摘み」をして、その販売収益を生徒会などの活動資金にあてたという記録が残っています。
やがて生徒数が増加して、工業棟・プール・テニスコートなどが作られ、茶畑は姿を消しました。しかし十数年前、当時を懐かしむ保護者たちの努力で合宿所脇に茶畑がつくられ、1年生の「茶摘み」が復活して、こんにちに至っています。
南木曽町は長野県のお茶の栽培のほぼ北限で、町内の田立地区がお茶の名産地でもあります。そんなふるさとの特産品を学ぶとともに、改めて本校の校是「開拓者精神」を意識する機会が、この「茶摘み」なのです。
生徒たちは「1芯3葉」の原則にしたがって、ひとつひとつ丁寧にお茶を摘み取っていきます。手に握りしめてお茶を発酵させてはいけないので、すぐに袋に入れながら、「やってみると面白いですね」「お茶の葉ってきれいですね」「キャー(蜘蛛がいたから)」などと語り合い(叫び合い)ながら、一生懸命作業を進めていきました。
親指の爪を使ってお茶の茎を摘むときの感触が、やわらかくて気持ちいいのです。
今春に入ってからの気温の低下で茶葉が小さく、例年よりも収穫量は落ちてしまいそうです。
それでも本日、製茶工場に持ち込んで、手摘みのお茶の完成品を楽しみに待つことにしました。できあがった「蘇南茶」は、①来客をおもてなしするお茶にする、②生徒に家で飲んでもらうように小袋に入れて渡す、③地域貢献としての活用を考える、といった3種類の活用を考えています。
「茶摘み」をするたびに、1年生が新しい「開拓者」の列に加わってくれたという実感がわき、私は感無量になります。

70年前に本校が創立された当初、生徒会や部活動の費用を自分たちで準備しようと、学校の校舎の裏側に広大な茶畑がつくられました。1年生が中心となって三日がかりで「茶摘み」をして、その販売収益を生徒会などの活動資金にあてたという記録が残っています。
やがて生徒数が増加して、工業棟・プール・テニスコートなどが作られ、茶畑は姿を消しました。しかし十数年前、当時を懐かしむ保護者たちの努力で合宿所脇に茶畑がつくられ、1年生の「茶摘み」が復活して、こんにちに至っています。
南木曽町は長野県のお茶の栽培のほぼ北限で、町内の田立地区がお茶の名産地でもあります。そんなふるさとの特産品を学ぶとともに、改めて本校の校是「開拓者精神」を意識する機会が、この「茶摘み」なのです。
生徒たちは「1芯3葉」の原則にしたがって、ひとつひとつ丁寧にお茶を摘み取っていきます。手に握りしめてお茶を発酵させてはいけないので、すぐに袋に入れながら、「やってみると面白いですね」「お茶の葉ってきれいですね」「キャー(蜘蛛がいたから)」などと語り合い(叫び合い)ながら、一生懸命作業を進めていきました。
親指の爪を使ってお茶の茎を摘むときの感触が、やわらかくて気持ちいいのです。
今春に入ってからの気温の低下で茶葉が小さく、例年よりも収穫量は落ちてしまいそうです。
それでも本日、製茶工場に持ち込んで、手摘みのお茶の完成品を楽しみに待つことにしました。できあがった「蘇南茶」は、①来客をおもてなしするお茶にする、②生徒に家で飲んでもらうように小袋に入れて渡す、③地域貢献としての活用を考える、といった3種類の活用を考えています。
「茶摘み」をするたびに、1年生が新しい「開拓者」の列に加わってくれたという実感がわき、私は感無量になります。
「ステンレス製の鍋と透明なクラゲに魅せられて」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月11日17:27
玄関ロビーに展示している美術部の生徒たちの作品を紹介する続編です。同じく県展に出品した二人の生徒の作品についてとりあげたいと思います。
3年の平尾さんの「キッチン用具の集まり」は、キャンバスにアクリル絵の具で描かれた作品です。作品には作者の次のような言葉が添えられています。
――ステンレス製の鍋とやかんは金属らしい光沢が出るよう、様々な色を何回も重ねました。金属らしい光沢は遠くからの方が感じられるので是非見てみてください。
とても面白い作品です。作者がこだわった金属の光沢は、まるで透き通った湖の水面のようです。身近な日用品が深い美しさをたたえることができるのは、まさにアートの力です。

もうひとり、3年の南山さんの「夜に沈む月明かり」は、やはりキャンバスにアクリル絵の具で描かれた作品です。作者の言葉を聞きましょう。
――クラゲの触手が、海に浮いているようにするため、薄い色で何度も重ね塗りをしました。
これもとても個性豊かな作品です。本来は、海のなかの小さな生命体クラゲが、ここではまるで宇宙をただよう壮大な生命の源であるかのように見えてきます。作者がこだわった透明感それ自体が、万物を包み込む大きさに見えてきます。

アートって、本当に面白いですね。
3年の平尾さんの「キッチン用具の集まり」は、キャンバスにアクリル絵の具で描かれた作品です。作品には作者の次のような言葉が添えられています。
――ステンレス製の鍋とやかんは金属らしい光沢が出るよう、様々な色を何回も重ねました。金属らしい光沢は遠くからの方が感じられるので是非見てみてください。
とても面白い作品です。作者がこだわった金属の光沢は、まるで透き通った湖の水面のようです。身近な日用品が深い美しさをたたえることができるのは、まさにアートの力です。
もうひとり、3年の南山さんの「夜に沈む月明かり」は、やはりキャンバスにアクリル絵の具で描かれた作品です。作者の言葉を聞きましょう。
――クラゲの触手が、海に浮いているようにするため、薄い色で何度も重ね塗りをしました。
これもとても個性豊かな作品です。本来は、海のなかの小さな生命体クラゲが、ここではまるで宇宙をただよう壮大な生命の源であるかのように見えてきます。作者がこだわった透明感それ自体が、万物を包み込む大きさに見えてきます。
アートって、本当に面白いですね。
生徒たちの作品を見つめながら、私はいくらでもエッセイが書けそうです。
「昇降口ロビーに飾られた色鉛筆の点描アートを楽しむ」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月10日13:23
現在、本校の昇降口ロビーでは、美術部の生徒たちの作品が展示されています。
そのうち3点は、高文連美術専門部の県大会(県展)に出品された作品です。今日からそれらを紹介していきます。
第一回目は、3年の森畑さんの作品「かなた」。ワトソン紙に色鉛筆で点描された絵画です。作者のこんな言葉が添えられています。
――今回の作品は、普段見ることのないような景色を、色鉛筆を用いて制作しました。空に浮かぶ雲の動きや川の流れに力を入れたので、ぜひ細かい所まで目を向けてみてください。
淡い繊細な色彩で描かれた風車のある農村の風景は、なぜか懐かしさを感じさせる温かみをもっています。近くに寄って見ると、微細な点の集積で、この絵が描き出されていることがよくわかります。
点描と言えば、私はフランスのスーラやピサロといった代表的な画家の作品を好んで展覧会で鑑賞してきました。異なる点の色が見る者の脳の中で混合していくスーラの作品と異なり、森畑さんの作品を構成する点は、色彩を限りなく透明の方向に分解していくようです。
蘇南高校のロビーで、素敵な点描アートにめぐりあえるとは! なんという幸せでしょう。


そのうち3点は、高文連美術専門部の県大会(県展)に出品された作品です。今日からそれらを紹介していきます。
第一回目は、3年の森畑さんの作品「かなた」。ワトソン紙に色鉛筆で点描された絵画です。作者のこんな言葉が添えられています。
――今回の作品は、普段見ることのないような景色を、色鉛筆を用いて制作しました。空に浮かぶ雲の動きや川の流れに力を入れたので、ぜひ細かい所まで目を向けてみてください。
淡い繊細な色彩で描かれた風車のある農村の風景は、なぜか懐かしさを感じさせる温かみをもっています。近くに寄って見ると、微細な点の集積で、この絵が描き出されていることがよくわかります。
点描と言えば、私はフランスのスーラやピサロといった代表的な画家の作品を好んで展覧会で鑑賞してきました。異なる点の色が見る者の脳の中で混合していくスーラの作品と異なり、森畑さんの作品を構成する点は、色彩を限りなく透明の方向に分解していくようです。
蘇南高校のロビーで、素敵な点描アートにめぐりあえるとは! なんという幸せでしょう。
「3年生の進学向け補習体制の計画をたてる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月09日17:48
GWが明けて、今週末からインターハイ予選の中信地区大会が本格化します。県大会に進むことができない場合には、部活動から引退することになります。もちろん文化系クラブの生徒は文化祭まで続けますし、インターハイを目指して頑張り続ける生徒も出てくるでしょう。
しかし本校では、地区大会を一つの区切りとして、進学補習体制を開始します。今日は、その打ち合わせを進路指導係の先生方と行いました。
具体的には、希望者に対して、朝・放課後・土日の補習を計画的に進めていきます。さらには長期休業の補習、受験直前の特編授業を行います。高校生向けの受験産業が少ない中山間地の学校なので、「学校の中で受験勉強がひととおりできること」が本校のモットーです。
昨年から「〇月までには□□の単元の復習を終了させる」という計画を教科担任全員にたててもらい、受験本番までに余裕をもって全範囲の受験勉強を進められるようにしています。
生徒たちの多様な進路希望について、それぞれの第一志望がかなえられる学校でありたいと思っています。この補習体制に参加する生徒は、3学年全体の3分の1くらい。他の生徒には、就職試験合格に向けてのメニュー、専門学校・短大の試験合格に向けてのメニューが組まれることになります。
都市部で言えば四つくらいの高校にわかれる生徒が、本校では同じ屋根の下でいきいきと学んでいます。私たち教職員は、その多様な生徒のひとりひとりのキャリア実現を精一杯応援していきたいと考えています。

しかし本校では、地区大会を一つの区切りとして、進学補習体制を開始します。今日は、その打ち合わせを進路指導係の先生方と行いました。
具体的には、希望者に対して、朝・放課後・土日の補習を計画的に進めていきます。さらには長期休業の補習、受験直前の特編授業を行います。高校生向けの受験産業が少ない中山間地の学校なので、「学校の中で受験勉強がひととおりできること」が本校のモットーです。
昨年から「〇月までには□□の単元の復習を終了させる」という計画を教科担任全員にたててもらい、受験本番までに余裕をもって全範囲の受験勉強を進められるようにしています。
生徒たちの多様な進路希望について、それぞれの第一志望がかなえられる学校でありたいと思っています。この補習体制に参加する生徒は、3学年全体の3分の1くらい。他の生徒には、就職試験合格に向けてのメニュー、専門学校・短大の試験合格に向けてのメニューが組まれることになります。
都市部で言えば四つくらいの高校にわかれる生徒が、本校では同じ屋根の下でいきいきと学んでいます。私たち教職員は、その多様な生徒のひとりひとりのキャリア実現を精一杯応援していきたいと考えています。
「ウクライナ避難民のために奔走している日本人のことばを聴く」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月08日20:29
昨日の夜、「千曲市ウクライナ避難民を支える会」のオンライン講演会に参加し、深く心を動かされました。
講師は、千曲市出身でポーランドのワルシャワ日本語学校の教頭をしている坂本龍太郎さん。現在、ポーランドに避難してきたウクライナ難民の支援活動や、ウクライナに支援物資を送る活動などに奔走しています。自宅の部屋を避難民に提供し、様々な物資を多くの避難民に届け、避難民のポーランド生活を軌道に乗せるための支援や、避難民が第三国に移住するための支援など、坂本さんの活動は本当に多岐にわたっています。
何度もことばを詰まらせながら、坂本さんは緊迫するウクライナの人々の今を伝えてくれました。
「小さな子どもたちは戦争が起こったことを知りません。頭上を飛んでいくミサイルについて、お母さんは、わが子を怖がらせないように『あれはゲームだからね』と必死に教えているのです。何が起こっているのかわからないまま、子どもたちは、平和な日常生活を奪われてしまっているのです。」
(私は、昔カンヌ映画祭の審査員グランプリをとったイタリア映画『ライフ・イズ・ビューティフル』を思い出しました。ナチスドイツの強制収容所に送られたユダヤ人の両親が、わが子を怖がらせないよう、これはゲームなのだと必死に嘘をつくドラマでした。)
「なぜ支援をしているのかとよく聞かれますが、理由などありません。すぐ隣の国の人々が平穏な日常生活を奪われてしまっているときに、私は無関心ではいられません。あえて言えば、自分の心の平穏のために、隣の国の人々を支援しているのかもしれません。」
「私は、3・11のときに東北やフクシマの人々のために何もできなかった。今はそのリベンジだという思いもあります。」
こうした坂本さんの生き方を、私は蘇南高校の生徒たちに伝えていきたいと思いました。
坂本さんの講演会は、YouTubeで公開されています。URLは以下のとおりです。
https://www.youtube.com/watch?v=T8FSnxM0HT4
冒頭の千曲市長さん、坂城町長さんのスピーチのあと、実行委員会の皆さんのコカリナ演奏があり、坂本さんの講演が始まります。ポーランドからの電波状況が当初あまりよくないために、音声が頻繁に弱まりますが、大きめの音量にすれば理解できます。電波状況は講演の途中から改善されます。私は、坂本さんのメッセージを聞くのに夢中で、電波状況のことはあまり気になりませんでした。
最後に、この講演会を企画してくださった竹下先生(現在は稲荷山養護学校勤務、坂本さんが教え子なのだそうです)をはじめとする皆様に、心からの感謝を申し上げます。
私自身の大きな学びの機会となりました。本当にありがとうございました。

講師は、千曲市出身でポーランドのワルシャワ日本語学校の教頭をしている坂本龍太郎さん。現在、ポーランドに避難してきたウクライナ難民の支援活動や、ウクライナに支援物資を送る活動などに奔走しています。自宅の部屋を避難民に提供し、様々な物資を多くの避難民に届け、避難民のポーランド生活を軌道に乗せるための支援や、避難民が第三国に移住するための支援など、坂本さんの活動は本当に多岐にわたっています。
何度もことばを詰まらせながら、坂本さんは緊迫するウクライナの人々の今を伝えてくれました。
「小さな子どもたちは戦争が起こったことを知りません。頭上を飛んでいくミサイルについて、お母さんは、わが子を怖がらせないように『あれはゲームだからね』と必死に教えているのです。何が起こっているのかわからないまま、子どもたちは、平和な日常生活を奪われてしまっているのです。」
(私は、昔カンヌ映画祭の審査員グランプリをとったイタリア映画『ライフ・イズ・ビューティフル』を思い出しました。ナチスドイツの強制収容所に送られたユダヤ人の両親が、わが子を怖がらせないよう、これはゲームなのだと必死に嘘をつくドラマでした。)
「なぜ支援をしているのかとよく聞かれますが、理由などありません。すぐ隣の国の人々が平穏な日常生活を奪われてしまっているときに、私は無関心ではいられません。あえて言えば、自分の心の平穏のために、隣の国の人々を支援しているのかもしれません。」
「私は、3・11のときに東北やフクシマの人々のために何もできなかった。今はそのリベンジだという思いもあります。」
こうした坂本さんの生き方を、私は蘇南高校の生徒たちに伝えていきたいと思いました。
坂本さんの講演会は、YouTubeで公開されています。URLは以下のとおりです。
https://www.youtube.com/watch?v=T8FSnxM0HT4
冒頭の千曲市長さん、坂城町長さんのスピーチのあと、実行委員会の皆さんのコカリナ演奏があり、坂本さんの講演が始まります。ポーランドからの電波状況が当初あまりよくないために、音声が頻繁に弱まりますが、大きめの音量にすれば理解できます。電波状況は講演の途中から改善されます。私は、坂本さんのメッセージを聞くのに夢中で、電波状況のことはあまり気になりませんでした。
最後に、この講演会を企画してくださった竹下先生(現在は稲荷山養護学校勤務、坂本さんが教え子なのだそうです)をはじめとする皆様に、心からの感謝を申し上げます。
私自身の大きな学びの機会となりました。本当にありがとうございました。
「毒があるけれどもとても美しい」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月06日17:39
世の中にはゴールデンウィークの真っ最中という方もいらっしゃると思いますが、本校はカレンダーどおりに歩んでいますので、今日は登校日でした。
5月になると身の回りの花々が一気に美しくなります。
飯田市の我が家の庭も一気に華やいでいますが、台所の窓の下には、昨年くらいからオダマキの群落が形成されています。山野草でもあるオダマキが数多く咲き誇っている光景は、とても美しいものです。
オダマキは感じで書くと苧環となり、機織りのときに使う糸玉(苧環)に形が似ていることに由来します。
きれいな花には毒があると言われるように、オダマキも有毒植物です。切り口から出る液が皮膚に付着すると水疱ができるそうですし、口に入れるなどもってのほか。でもヨーロッパ中世で黒死病が大流行した時は、薬草として用いられたと言われます。まさに「劇薬」です。
生徒たちは、自然界の美しいものにあまり関心を示さないので、自然教育を何とかして進めていきたいよねと、教頭先生と語り合ったのでした。

5月になると身の回りの花々が一気に美しくなります。
飯田市の我が家の庭も一気に華やいでいますが、台所の窓の下には、昨年くらいからオダマキの群落が形成されています。山野草でもあるオダマキが数多く咲き誇っている光景は、とても美しいものです。
オダマキは感じで書くと苧環となり、機織りのときに使う糸玉(苧環)に形が似ていることに由来します。
きれいな花には毒があると言われるように、オダマキも有毒植物です。切り口から出る液が皮膚に付着すると水疱ができるそうですし、口に入れるなどもってのほか。でもヨーロッパ中世で黒死病が大流行した時は、薬草として用いられたと言われます。まさに「劇薬」です。
生徒たちは、自然界の美しいものにあまり関心を示さないので、自然教育を何とかして進めていきたいよねと、教頭先生と語り合ったのでした。
「GWの読書の中からこの一冊」
Posted by 蘇南高等学校長.
2022年05月03日19:04
長野道を北に走って明科トンネルから出た時に、正面に見えてくる秀麗な尖峰が「会田虚空蔵山(会田富士)」です。標高こそ1139メートルに過ぎませんが、山体や周囲に洞窟や巨岩に係る幾つもの宗教施設をもち、山城としての役割も担った、信仰の山です。私もこの山に登ったとき、中腹の岩屋神社や山頂直下の巨岩の迫力に感嘆し、さらには頂からの眺望に深く心を動かされました。
登山をしていると、上田の虚空蔵山や独鈷山麓の虚空蔵堂、飯田の虚空蔵山(風越山の前衛峰)など、印象的な山岳景観のなかで「虚空蔵(こくぞう)」の文字に出会います。
本書は、長野県立歴史館の笹本館長が「会田虚空蔵山」の信仰を分析し、県内そして全国の虚空蔵山・虚空蔵信仰のなかにそれを位置付け、さらには全国の霊山信仰・洞窟巨岩信仰との比較を試みた600ページを超える大著です。
膨大な史料・先行文献を読み解き、緻密な現地調査を重ねながら、著者は山岳信仰がどのように形成され、発展し、やがては衰退していったかを鮮やかに描き出しました。
山岳という「景観そのもの、及びその景観に対する感性そのもの」を歴史分析の対象とするときに浮かび上がってくるのは、人が雄大な自然に何を願って生きてきたかという「いのち」のありようです。自らが万能であるかのように錯覚している現代文明のなかで私たちが忘れつつある、森羅万象とつながっている「いのち」のありように、私たちは本書によって再度気づかされます。そして私たちを包み込んでくれている山岳の景観が、ただの風景から「いのち」について語りかけてくれるような存在に変貌していきます。
虚空蔵とは、仏教の教理で言えば、「虚空のように無限の慈悲を現わす菩薩」(中村元)に対する信仰です。しかしその根源には、①自然災害から安全性を確保したいという願い、②水や風が安定することで食糧を確保したいという願い、③愛する死者と再度会いたいという願いなどが存在すると著者は考察します。
「会田虚空蔵山」は、秀麗で目立つ山容をもち、磐座と思われる巨岩があり、水や風の信仰とのつながりがある点において、富士山のような全国的知名度はないものの身近な「地域」における山岳信仰の典型であったと位置付けられます。
私には、諏訪の守屋山との比較がことに印象的でした。台地形の山容をもち、水や風と結びついた山岳信仰の対象であったという点で二つの山は共通しているものの、守屋山は、これを神体山とする諏訪大社が記紀神話と結合することで、信仰の形を大きく変えながらも後世に継承されてきました。著者は、守屋山こそ諏訪の人々の原初の信仰対象であったことを、上社本宮の神楽殿と拝殿が一直線に配置されていない景観などから考察・復元しています。
他にも、戸隠山と善光寺、霧訪山と小野神社など、本書によって眼前の信仰の原初形態が復元され、宗教にこめた人々の「願い」が、より身近なものとして蘇ってきます。
本書を読んだ人は、世界の姿がいっそう豊かな意味あるものとして見えてくるようになるでしょう。
私は本書と出会えた幸せを、静かにいつまでも抱き続けたいと思っています。
(岩田書院、20224月刊、608頁、16800円+税)
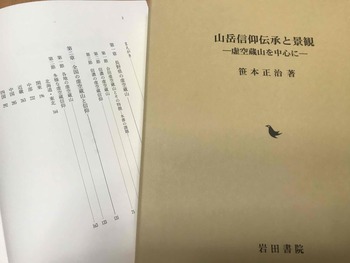
登山をしていると、上田の虚空蔵山や独鈷山麓の虚空蔵堂、飯田の虚空蔵山(風越山の前衛峰)など、印象的な山岳景観のなかで「虚空蔵(こくぞう)」の文字に出会います。
本書は、長野県立歴史館の笹本館長が「会田虚空蔵山」の信仰を分析し、県内そして全国の虚空蔵山・虚空蔵信仰のなかにそれを位置付け、さらには全国の霊山信仰・洞窟巨岩信仰との比較を試みた600ページを超える大著です。
膨大な史料・先行文献を読み解き、緻密な現地調査を重ねながら、著者は山岳信仰がどのように形成され、発展し、やがては衰退していったかを鮮やかに描き出しました。
山岳という「景観そのもの、及びその景観に対する感性そのもの」を歴史分析の対象とするときに浮かび上がってくるのは、人が雄大な自然に何を願って生きてきたかという「いのち」のありようです。自らが万能であるかのように錯覚している現代文明のなかで私たちが忘れつつある、森羅万象とつながっている「いのち」のありように、私たちは本書によって再度気づかされます。そして私たちを包み込んでくれている山岳の景観が、ただの風景から「いのち」について語りかけてくれるような存在に変貌していきます。
虚空蔵とは、仏教の教理で言えば、「虚空のように無限の慈悲を現わす菩薩」(中村元)に対する信仰です。しかしその根源には、①自然災害から安全性を確保したいという願い、②水や風が安定することで食糧を確保したいという願い、③愛する死者と再度会いたいという願いなどが存在すると著者は考察します。
「会田虚空蔵山」は、秀麗で目立つ山容をもち、磐座と思われる巨岩があり、水や風の信仰とのつながりがある点において、富士山のような全国的知名度はないものの身近な「地域」における山岳信仰の典型であったと位置付けられます。
私には、諏訪の守屋山との比較がことに印象的でした。台地形の山容をもち、水や風と結びついた山岳信仰の対象であったという点で二つの山は共通しているものの、守屋山は、これを神体山とする諏訪大社が記紀神話と結合することで、信仰の形を大きく変えながらも後世に継承されてきました。著者は、守屋山こそ諏訪の人々の原初の信仰対象であったことを、上社本宮の神楽殿と拝殿が一直線に配置されていない景観などから考察・復元しています。
他にも、戸隠山と善光寺、霧訪山と小野神社など、本書によって眼前の信仰の原初形態が復元され、宗教にこめた人々の「願い」が、より身近なものとして蘇ってきます。
本書を読んだ人は、世界の姿がいっそう豊かな意味あるものとして見えてくるようになるでしょう。
私は本書と出会えた幸せを、静かにいつまでも抱き続けたいと思っています。
(岩田書院、20224月刊、608頁、16800円+税)
カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長