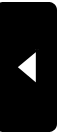「本校の通学路がさらに整備されていきます」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月14日19:43
南木曽町のご厚意により、本校の通学路沿いの茂みがさらに伐採され、見通しが断然よくなっています。
森の木の実の凶作によりクマが里におりてくる事案が連続してきたことの対策として、先週の前半に、木曽川河畔の雑木を伐採していただきました。そしてさらに先週末より伊勢小屋沢を渡って本校に登っていく坂道(自動車道と歩道の両方)に沿った茂みを刈り込んでいただいています。夕暮れ以降に茂みからクマが飛び出して生徒と鉢合わせしてしまう危険が、断然防止されることになります。
これは本当にありがたいことです。町長さんをはじめとする南木曽町役場の皆様と、工事にあたっていただいた業者さんに心より御礼を申し上げます。
本校では、夕暮れ以降に通学路で音響を流すことにタイマーを導入するとともに、音響を大きくする機材を導入します。
こうした環境整備と、生徒の皆さんひとりひとりの注意の徹底によって、大自然との共生をはかっていきたいと思っています。
それにしても茂みを伐採していただいてわかったことは、大岩が重なる峻厳な地形を懸命に開拓して蘇南高校が建設されたのだという事実の重みです。「開拓者」である先人たちの多大な努力によって、美しい渓谷の中、大空に翼を広げるような形の蘇南高校が建設されたのでした。
通学路をたどりながら、その先人のたくましい軌跡を想像できるようになりました。蘇南高校で生徒と一緒に学べる自分の幸せをあらためてかみしめています。

森の木の実の凶作によりクマが里におりてくる事案が連続してきたことの対策として、先週の前半に、木曽川河畔の雑木を伐採していただきました。そしてさらに先週末より伊勢小屋沢を渡って本校に登っていく坂道(自動車道と歩道の両方)に沿った茂みを刈り込んでいただいています。夕暮れ以降に茂みからクマが飛び出して生徒と鉢合わせしてしまう危険が、断然防止されることになります。
これは本当にありがたいことです。町長さんをはじめとする南木曽町役場の皆様と、工事にあたっていただいた業者さんに心より御礼を申し上げます。
本校では、夕暮れ以降に通学路で音響を流すことにタイマーを導入するとともに、音響を大きくする機材を導入します。
こうした環境整備と、生徒の皆さんひとりひとりの注意の徹底によって、大自然との共生をはかっていきたいと思っています。
それにしても茂みを伐採していただいてわかったことは、大岩が重なる峻厳な地形を懸命に開拓して蘇南高校が建設されたのだという事実の重みです。「開拓者」である先人たちの多大な努力によって、美しい渓谷の中、大空に翼を広げるような形の蘇南高校が建設されたのでした。
通学路をたどりながら、その先人のたくましい軌跡を想像できるようになりました。蘇南高校で生徒と一緒に学べる自分の幸せをあらためてかみしめています。

「中学生体験入学を午前の部・午後の部にわかれて実施する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月12日15:02
7月末に実施予定であった中学生体験入学について、ようやく本日、開催できました。実に何か月ぶりかで、本校生以外の生徒が、蘇南高校の学び舎に入ってきました。
新型コロナウイルス感染症予防の徹底をはかり、午前の部・午後の部と同じ内容を二度繰り返すこととし、クラブ見学は昼の時間帯に実施しました。全体会については体育館で密になることを避けるために、各教室にわかれて、全校放送やビデオ上映などを組み合わせて行いました。ここ数日、不安定な空模様だったのですが、今日は青空のもと南木曽の山々の緑も輝き、美しい風景の中での体験入学となりました。
用意した体験授業は、10種類。国語・地歴公民(社会)・数学・理科・英語・家庭・美術・体育・商業・工業です。
たとえば、商業の授業では、このコロナ禍で企業の収益がどのように落ち込んだかを分析し、かわりにどのような業種の企業が売り上げを伸ばしたかをみていきます。そして「自己資本比率」という概念を学ぶなど、経営学の基礎を丁寧に学びました。頷きながら学んでいる中学生たちの姿を見て、大いに頼もしく思いました。
全体会では3名の生徒たち(3年生の伊藤さん、秋山さん、松永さん)が、自分が選択している系列の授業をいかして、どのような進路を目指しているかという自分のキャリアデザインについて、中学生に語りかけてくれました。本校生がどのようにいきいきと学んでいるかという「生の声」は、中学生の皆さんの大きな参考になったことでしょう。
校長による学校説明では、本校の教育目標が「開拓者精神」の育成であることと、まさにその精神を発揮して活躍している生徒の様子について、何人かの具体例とともに紹介しました。そして次のように呼びかけて、しめくくりとしました。
「では、皆さん。この校舎のように思い切り翼を広げて、未来にはばたく=未来を開拓する学びを一緒にしませんか。蘇南高校だからこそ体験できる、たくさんの感動、ひとりひとりの進路実現があります。蘇南高校は、『小さくてもキラリと光る高校』です。必ず、『蘇南高校の生徒になってよかった』と思うはずです。皆さんと受験会場で、そして入学式で再会できることを、心から待っています!」

新型コロナウイルス感染症予防の徹底をはかり、午前の部・午後の部と同じ内容を二度繰り返すこととし、クラブ見学は昼の時間帯に実施しました。全体会については体育館で密になることを避けるために、各教室にわかれて、全校放送やビデオ上映などを組み合わせて行いました。ここ数日、不安定な空模様だったのですが、今日は青空のもと南木曽の山々の緑も輝き、美しい風景の中での体験入学となりました。
用意した体験授業は、10種類。国語・地歴公民(社会)・数学・理科・英語・家庭・美術・体育・商業・工業です。
たとえば、商業の授業では、このコロナ禍で企業の収益がどのように落ち込んだかを分析し、かわりにどのような業種の企業が売り上げを伸ばしたかをみていきます。そして「自己資本比率」という概念を学ぶなど、経営学の基礎を丁寧に学びました。頷きながら学んでいる中学生たちの姿を見て、大いに頼もしく思いました。
全体会では3名の生徒たち(3年生の伊藤さん、秋山さん、松永さん)が、自分が選択している系列の授業をいかして、どのような進路を目指しているかという自分のキャリアデザインについて、中学生に語りかけてくれました。本校生がどのようにいきいきと学んでいるかという「生の声」は、中学生の皆さんの大きな参考になったことでしょう。
校長による学校説明では、本校の教育目標が「開拓者精神」の育成であることと、まさにその精神を発揮して活躍している生徒の様子について、何人かの具体例とともに紹介しました。そして次のように呼びかけて、しめくくりとしました。
「では、皆さん。この校舎のように思い切り翼を広げて、未来にはばたく=未来を開拓する学びを一緒にしませんか。蘇南高校だからこそ体験できる、たくさんの感動、ひとりひとりの進路実現があります。蘇南高校は、『小さくてもキラリと光る高校』です。必ず、『蘇南高校の生徒になってよかった』と思うはずです。皆さんと受験会場で、そして入学式で再会できることを、心から待っています!」

「学び舎の環境を美しく維持管理すること」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月11日18:17
本校は、南木曽町の天白地区の丘の上に、大空にはばたく鳥の翼のような学び舎を持っています。南木曽駅の西側を走る国道19号から三留野大橋を渡り、南木曽町の記念館群の脇から伊勢小屋沢沿いに坂道を一気に登ると、やがて広い庭が斜面に展開し、その上に赤い屋根と白い壁の校舎が見えてきます。
この広い前庭には、石碑、初代校長の肖像、彫刻作品などとともに、季節をいろどる様々な植栽が植えられています。1年生が茶摘みをする茶畑もあるし、教職員が春先に山菜採りを楽しめるワラビやタラの芽の群生もあります。その分、絶えず草刈りをし、落ち葉を片付ける校用技師さんの苦労は並大抵のものではありません。本校は2人の校用技師さんが、学び舎の維持・管理のために日々汗を流しています。
現在、クマ対策として、南木曽町が伊勢小屋沢沿いの雑木伐採をどんどん進めています。本校の周辺の環境がさらに美しくなっていきます。
実は、先週の話なのですが、本校の校用技師さんが、伊勢小屋沢にかかる岩つつじ橋から本校に登る坂のガードレールをすべてぴかぴかに磨き上げてくれました。300メートルはある長さだと思います。おそらく何年も汚れるがままになっていたガードレールです。学び舎につながる一本道の景観が、何となくわびしく見えていました。
校用技師さんは、じょうろで水をかけ、洗車用のブラシと亀の子たわしを使って、丁寧にごしごし磨いてくれました。何日もかかって、端から端まで磨き上げていったのです。おかげで今は、ガードレールがこんなにきれいだったのかと驚くような白さで学び舎に導いてくれます。
ふと、校用技師さんが、「生徒たちが、このような環境整備をしていく学びが必要かもしれませんね」と話しかけてくれました。確かにそうだと思いました。町の皆様、職員に支えてもらっていることに、生徒は感謝の思いをもっているのですが、それだけではなく、自分もまた支援を「する側に立つ」ことを学ぶようなプログラムが、もっとあっていいのだと思います。
ぴかぴかのガードレールを見ながら、思考と実践の両輪を大切にするような学びをさらにつくっていきたいと考えています。

この広い前庭には、石碑、初代校長の肖像、彫刻作品などとともに、季節をいろどる様々な植栽が植えられています。1年生が茶摘みをする茶畑もあるし、教職員が春先に山菜採りを楽しめるワラビやタラの芽の群生もあります。その分、絶えず草刈りをし、落ち葉を片付ける校用技師さんの苦労は並大抵のものではありません。本校は2人の校用技師さんが、学び舎の維持・管理のために日々汗を流しています。
現在、クマ対策として、南木曽町が伊勢小屋沢沿いの雑木伐採をどんどん進めています。本校の周辺の環境がさらに美しくなっていきます。
実は、先週の話なのですが、本校の校用技師さんが、伊勢小屋沢にかかる岩つつじ橋から本校に登る坂のガードレールをすべてぴかぴかに磨き上げてくれました。300メートルはある長さだと思います。おそらく何年も汚れるがままになっていたガードレールです。学び舎につながる一本道の景観が、何となくわびしく見えていました。
校用技師さんは、じょうろで水をかけ、洗車用のブラシと亀の子たわしを使って、丁寧にごしごし磨いてくれました。何日もかかって、端から端まで磨き上げていったのです。おかげで今は、ガードレールがこんなにきれいだったのかと驚くような白さで学び舎に導いてくれます。
ふと、校用技師さんが、「生徒たちが、このような環境整備をしていく学びが必要かもしれませんね」と話しかけてくれました。確かにそうだと思いました。町の皆様、職員に支えてもらっていることに、生徒は感謝の思いをもっているのですが、それだけではなく、自分もまた支援を「する側に立つ」ことを学ぶようなプログラムが、もっとあっていいのだと思います。
ぴかぴかのガードレールを見ながら、思考と実践の両輪を大切にするような学びをさらにつくっていきたいと考えています。

「主権者教育としての生徒会選挙」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月10日07:30
今日は、午後に生徒会役員選挙の立会演説会と投票が行われます。
昨日までに生徒会長・副会長などに立候補した生徒たち全員による演説と推薦人による応援演説がクラスごとに行われました。それぞれの生徒が、自分が当選したらどのような生徒会を創りたいのかをスピーチします。候補者は1年A組で演説をすると、次に1年B組に移動します。3日間かけて3学年すべてのクラスでの演説を終えました。まさに国政選挙の候補者たちが行う、ミニ演説集会の趣です。
私も教室のうしろのほうで聞きましたが、自分の思いや願いを友人たちに訴えかける熱い語りに感心させられました。
今日は全校が集まっての立会演説会を総括演説という凝縮した形で行い(コロナ対策で全校集会は30分以下にするのが本校の方針)、いつもはその場でおこなっている投票をクラスごとに変更して実施します。
投票は、南木曽町の選挙管理委員会さんから国政選挙で使用されている投票箱をお借りして、国政選挙を連想させる手続きで行います。生徒会というのは、自分たちの社会を自分たちで創造するという大切な「主権者教育」の機会なのです。
新たに誕生した新生徒会長さんたちと新たな対話ができることを、私は楽しみにしています。

昨日までに生徒会長・副会長などに立候補した生徒たち全員による演説と推薦人による応援演説がクラスごとに行われました。それぞれの生徒が、自分が当選したらどのような生徒会を創りたいのかをスピーチします。候補者は1年A組で演説をすると、次に1年B組に移動します。3日間かけて3学年すべてのクラスでの演説を終えました。まさに国政選挙の候補者たちが行う、ミニ演説集会の趣です。
私も教室のうしろのほうで聞きましたが、自分の思いや願いを友人たちに訴えかける熱い語りに感心させられました。
今日は全校が集まっての立会演説会を総括演説という凝縮した形で行い(コロナ対策で全校集会は30分以下にするのが本校の方針)、いつもはその場でおこなっている投票をクラスごとに変更して実施します。
投票は、南木曽町の選挙管理委員会さんから国政選挙で使用されている投票箱をお借りして、国政選挙を連想させる手続きで行います。生徒会というのは、自分たちの社会を自分たちで創造するという大切な「主権者教育」の機会なのです。
新たに誕生した新生徒会長さんたちと新たな対話ができることを、私は楽しみにしています。

「3年生が大学入学共通テストの説明を熱心に聞く」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月09日06:57
いよいよこの時期になったという緊張感が教室にはりつめます。
8日(火)は、大学入学共通テストの説明会を大講義室で開催しました。進路がとても多様な本校のなかで、全体の4分の1の生徒が集まっています。
冒頭で校長から激励のメッセージを贈りました。ここから先の大学入試は、ひとつの手続きミスも許されない厳しい世界になるので、「自分は守ってもらえる」という感覚から脱却すること。そして、入試というのは徹底した「他者と比較される」経験であるけれども、比較されることで不安に苛まれ苦しむのは、誰もが同じであるから、私たちは目の前のことを一つ一つ着実に学んでいくことが大切であること。この二つを3年生に語りかけました。
英語4技能資格・検定試験の活用、記述式の導入など、この生徒たちは、教育行政の混迷に翻弄されてきました。それだけに、いよいよ試験本番に立ち向かっていく生徒たちの真剣なまなざしに、私は胸がいっぱいになります。
そして鈴木先生から受験手続のことが詳しく説明され、3年生は要点をメモしながら熱心に聞き入っていました。
3年生は朝や放課後の補習のほか、学習室を20時まで開設して受験勉強を支援しています。現役生の秋は、一気に受験学力が伸びる時期です。コロナ禍をくぐりぬけて、たくさんの逞しい学びの経験を重ねてきた3年生たちですから、きっと「秋の伸び」を実現するでしょう。
3年生の皆さん、「きっとうまくいく(All is well)」!

8日(火)は、大学入学共通テストの説明会を大講義室で開催しました。進路がとても多様な本校のなかで、全体の4分の1の生徒が集まっています。
冒頭で校長から激励のメッセージを贈りました。ここから先の大学入試は、ひとつの手続きミスも許されない厳しい世界になるので、「自分は守ってもらえる」という感覚から脱却すること。そして、入試というのは徹底した「他者と比較される」経験であるけれども、比較されることで不安に苛まれ苦しむのは、誰もが同じであるから、私たちは目の前のことを一つ一つ着実に学んでいくことが大切であること。この二つを3年生に語りかけました。
英語4技能資格・検定試験の活用、記述式の導入など、この生徒たちは、教育行政の混迷に翻弄されてきました。それだけに、いよいよ試験本番に立ち向かっていく生徒たちの真剣なまなざしに、私は胸がいっぱいになります。
そして鈴木先生から受験手続のことが詳しく説明され、3年生は要点をメモしながら熱心に聞き入っていました。
3年生は朝や放課後の補習のほか、学習室を20時まで開設して受験勉強を支援しています。現役生の秋は、一気に受験学力が伸びる時期です。コロナ禍をくぐりぬけて、たくさんの逞しい学びの経験を重ねてきた3年生たちですから、きっと「秋の伸び」を実現するでしょう。
3年生の皆さん、「きっとうまくいく(All is well)」!

「夢は職業ではなくて生き方だと思う」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月08日19:35
1学年の授業「産業社会と人間」は、これまで自分史の作成に取り組んできました。その際、自分のこれまでの人生にどのような困難があり、それをどのように乗り越えてきたのかを言語化することを試みたのです。
今日は、そのしめくくりの授業として、シンガーソングライター、音楽プロデューサーの小田ルイさんの講義&生徒との質疑応答&ミニコンサートを開催しました。
小田さんは、日本全国やイタリアで音楽活動を行ったり、県内でもいくつかの学校で音楽教育を行ったりするなど、まさに多彩な活躍をしているアーティスト。今年のコロナ臨時休業のとき、蘇南高校応援メッセージソングを寄せてほしいという私の願いを叶えてくださり、感動的な動画を届けてくださいました。
今回は、1年生だけがその続きを学べるという企画です。小田さんの講義のタイトルは、「壁や挫折を乗り越えて、夢をどのように追い求めてきたのか」。事前に生徒たちが提出していた質問事項にも丁寧に対応しながら、そして本番での生徒からの直接の質問にも丁寧に答えていただきながら、あっという間の1時間が過ぎていきました。ちなみに、Zoomでむすんだオンライン講演会を普通に行えたのは、コロナ経験の成果のひとつです。
「夢は職業ではない。生き方だと思う。」というのが、今日の小田さんの生徒たちへのメッセージでした。夢は、職業のように成功する・しないで割り切れるようなものではない。それは自分らしく生きること、そのものなのだ、と。たくさんの挫折を重ねて、多くの回り道をして、音楽という夢を追い求めてきた小田さんだからこその言葉です。
キャリアデザインとは、「どんな学校に進みたいか」「どんな職業につきたいのか」という選択の問題ではなくて、「どんなふうに生きたいのか」というエッセンシャル・クエスチョンを考えることです。
最後に小田さんが歌ってくださった「ヒビキアイ」のメッセージが、生徒たちの心と響き合って、今日の授業が終わりました。
言葉の向こう側へ 行きたいと思ってた。
うまく生きれないことに 一人もがきながら。
自分の中の暗闇を 目を凝らして見つめた。
誰かを照らす光が ここにあると信じてたんだ。
小田さん、素敵な講義をいただき、本当にありがとうございました。

今日は、そのしめくくりの授業として、シンガーソングライター、音楽プロデューサーの小田ルイさんの講義&生徒との質疑応答&ミニコンサートを開催しました。
小田さんは、日本全国やイタリアで音楽活動を行ったり、県内でもいくつかの学校で音楽教育を行ったりするなど、まさに多彩な活躍をしているアーティスト。今年のコロナ臨時休業のとき、蘇南高校応援メッセージソングを寄せてほしいという私の願いを叶えてくださり、感動的な動画を届けてくださいました。
今回は、1年生だけがその続きを学べるという企画です。小田さんの講義のタイトルは、「壁や挫折を乗り越えて、夢をどのように追い求めてきたのか」。事前に生徒たちが提出していた質問事項にも丁寧に対応しながら、そして本番での生徒からの直接の質問にも丁寧に答えていただきながら、あっという間の1時間が過ぎていきました。ちなみに、Zoomでむすんだオンライン講演会を普通に行えたのは、コロナ経験の成果のひとつです。
「夢は職業ではない。生き方だと思う。」というのが、今日の小田さんの生徒たちへのメッセージでした。夢は、職業のように成功する・しないで割り切れるようなものではない。それは自分らしく生きること、そのものなのだ、と。たくさんの挫折を重ねて、多くの回り道をして、音楽という夢を追い求めてきた小田さんだからこその言葉です。
キャリアデザインとは、「どんな学校に進みたいか」「どんな職業につきたいのか」という選択の問題ではなくて、「どんなふうに生きたいのか」というエッセンシャル・クエスチョンを考えることです。
最後に小田さんが歌ってくださった「ヒビキアイ」のメッセージが、生徒たちの心と響き合って、今日の授業が終わりました。
言葉の向こう側へ 行きたいと思ってた。
うまく生きれないことに 一人もがきながら。
自分の中の暗闇を 目を凝らして見つめた。
誰かを照らす光が ここにあると信じてたんだ。
小田さん、素敵な講義をいただき、本当にありがとうございました。

「コロナ、集中豪雨の次に眼前にあらわれたものは…」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月07日21:49
今年の異常気象により山の木の実が凶作で、各地でクマが人里に出没する事件がおこっています。
自然豊かな南木曽町にある本校も例外ではなく、先週は通学路の周辺で3度もクマが目撃されました。週末の金曜日は夜8時過ぎに三留野大橋のたもとで複数のクマが目撃され、幸いにもケガ人はいなかったものの一時緊迫した状態となりました。(下校途中の生徒は教員が自家用車で南木曽駅まで送り届けました。)
土日には南木曽町長さん、教育長さんをはじめ、町の関係者が現場を検証し、早速、今日には木曽川の河畔に自生している、クマのえさになりそうなクルミなどの樹木を、南木曽町の尽力で伐採していただきました。また、登下校の時間帯に合わせてのパトロールを始めていただいています。学校では、18時以降の下校を集団で行うことを指導するとともに、三留野大橋までの伊勢小屋沢沿いの坂道の二か所にラジオを大音響で鳴らし始めました。21時までスイッチを入れ続けます。
先週木曜日には全校放送にて、私が直接生徒たちに、(繰り返しになりますが)クマに襲われるとどのような重傷を負うかとか、万が一遭遇したときの対処法などを語りかけました。単独登山でクマに至近距離で遭遇した経験のある私としては、理論通りにはいかないものだということも実感しています。
この土日、通学路で何回か町長さんや教育長さんの姿をお見かけしました。私も何度となく巡回しました。ラジオの設置については町の電気屋さんの協力もいただいています。
木曽川にかける桃介橋のまわりに、南木曽岳・伊勢山・中央アルプスが屏風のように並ぶ、信州有数の美しい景観のなかに蘇南高校はあります。
クマも生きるために必死なのですが、私たちは人里の境界線を死守しなければなりません。それが里山を守ることにつながります。異常気象の影響を肌身で感じながら、生徒の安全を全力で守っていく覚悟です。

自然豊かな南木曽町にある本校も例外ではなく、先週は通学路の周辺で3度もクマが目撃されました。週末の金曜日は夜8時過ぎに三留野大橋のたもとで複数のクマが目撃され、幸いにもケガ人はいなかったものの一時緊迫した状態となりました。(下校途中の生徒は教員が自家用車で南木曽駅まで送り届けました。)
土日には南木曽町長さん、教育長さんをはじめ、町の関係者が現場を検証し、早速、今日には木曽川の河畔に自生している、クマのえさになりそうなクルミなどの樹木を、南木曽町の尽力で伐採していただきました。また、登下校の時間帯に合わせてのパトロールを始めていただいています。学校では、18時以降の下校を集団で行うことを指導するとともに、三留野大橋までの伊勢小屋沢沿いの坂道の二か所にラジオを大音響で鳴らし始めました。21時までスイッチを入れ続けます。
先週木曜日には全校放送にて、私が直接生徒たちに、(繰り返しになりますが)クマに襲われるとどのような重傷を負うかとか、万が一遭遇したときの対処法などを語りかけました。単独登山でクマに至近距離で遭遇した経験のある私としては、理論通りにはいかないものだということも実感しています。
この土日、通学路で何回か町長さんや教育長さんの姿をお見かけしました。私も何度となく巡回しました。ラジオの設置については町の電気屋さんの協力もいただいています。
木曽川にかける桃介橋のまわりに、南木曽岳・伊勢山・中央アルプスが屏風のように並ぶ、信州有数の美しい景観のなかに蘇南高校はあります。
クマも生きるために必死なのですが、私たちは人里の境界線を死守しなければなりません。それが里山を守ることにつながります。異常気象の影響を肌身で感じながら、生徒の安全を全力で守っていく覚悟です。

「満洲移民の体験者と授業の計画をつくる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月04日17:56
南木曽町(当時は読書村・吾妻村)には、アジア・太平洋戦争の時代に、多くの満洲移民を中国大陸に送り出した歴史があります。863名の開拓移民のなんと6割以上が日本に戻れずに中国大陸で死亡しました。
大陸から引き揚げてきた当事者で、現在も生存されている方は、本当に少なくなってきています。
そのような当事者のひとり、南木曽町の可児さんは、今年88歳。ひのき箸などを製造する可児工芸の会長をつとめるかたわら、下伊那郡阿智村にある満蒙開拓平和記念館の語り部の活動を続けておられます。
「いつか一緒に授業をやりたいですね」と可児さんと対話をしてきたのですが、今月の17日(木)の人権講演会で全校生徒に対して、可児さん&私のタッグを組み、歴史を振り返りながら、コロナ時代の今をどう生きるべきかについて考える授業をしたいと思っています。
今日は、可児さんに校長室に来ていただき、1時間以上かけて打ち合わせをしました。(写真の時だけマスクを外しました。)
敗戦時の満洲で、この世の地獄を見た可児さんは、同時に多くの人のやさしさに出会いました。可児さんの人生が見てきた「この世界」に対する思いについて、私がしっかりバトンを受け取り、一緒に授業をしようと思っています。おそらく、新しい平和人権教育のスタイルの創造になるのではないかと思っています。
可児さん、一緒に頑張りましょうね。

大陸から引き揚げてきた当事者で、現在も生存されている方は、本当に少なくなってきています。
そのような当事者のひとり、南木曽町の可児さんは、今年88歳。ひのき箸などを製造する可児工芸の会長をつとめるかたわら、下伊那郡阿智村にある満蒙開拓平和記念館の語り部の活動を続けておられます。
「いつか一緒に授業をやりたいですね」と可児さんと対話をしてきたのですが、今月の17日(木)の人権講演会で全校生徒に対して、可児さん&私のタッグを組み、歴史を振り返りながら、コロナ時代の今をどう生きるべきかについて考える授業をしたいと思っています。
今日は、可児さんに校長室に来ていただき、1時間以上かけて打ち合わせをしました。(写真の時だけマスクを外しました。)
敗戦時の満洲で、この世の地獄を見た可児さんは、同時に多くの人のやさしさに出会いました。可児さんの人生が見てきた「この世界」に対する思いについて、私がしっかりバトンを受け取り、一緒に授業をしようと思っています。おそらく、新しい平和人権教育のスタイルの創造になるのではないかと思っています。
可児さん、一緒に頑張りましょうね。

「『VIEW21』8月号に本校を紹介していただく」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月03日16:52
ベネッセ教育総合研究所が発行している雑誌『VIEW21高校版8月号』に本校のインタビュー記事が掲載されました。
この号は、「教育の『これから』を考える」という特集で、コロナ禍の時代に未来を展望するような学びをどのように進めていくかという観点で、高校生(自修館中等教育学校の生徒等)、教育長(広島県の平川氏)、高校教員(広島叡智学園中学校・高校、広島国泰寺高校)などの取材記事とともに、本校のことを取り上げていただきました。
(インターネットからも閲覧できます。
https://berd.benesse.jp/magazine/kou/booklet/?id=5530 )
タイトルは「臨時休業中の生徒の成長を、グランドデザインの見直しにつなげる」というもの。実は、取材の依頼を受けるかどうかで私は随分迷いました。赴任してまだ半年も経っていないし、コロナ禍の中の学校づくりもまだ始まったばかり。長野県内を見ても、もっとふさわしいフロントランナーはいくらでもいる。しかし、全国の読者にとっては、本校のような試行錯誤中の取組も身近で参考になるところがあるかもしれないし、そもそも本校の取組は、職員集団と生徒の「集合知」の産物であり、その基礎には私が週1回のペースで参加してきた全国の先生たちとのWEB対話「生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」(小村俊平さんの主宰)の「集合知」の恩恵があります。「集合知」はたえず社会に開き、新たな対話を重ねながらリニューアルしていくべきものなので、せっかくいただいた機会は、やはり大事にしていくべきなのだろうと考えた次第です。
『VIEW21』の記事は、4月からここまでの5カ月間の軌跡をコンパクトにまとめていただきました。記事の核心は、臨時休業中に生徒が頑張ったことを各教科の担当がきちんと評価してあげるためには、テストの点数だけでは不十分であり、生徒の努力を丁寧に振り返り、教員がコメントをするアセスメントの取組が必要だと気付いたという点にあります。点数評価ではなくて、記述による評価(定性評価)に意味があるのだと考えています。そしてアセスメントをしていくと、本校がグランドデザインでかかげていた生徒育成方針(卒業までにこのような資質・能力を身に付けさせるという目標)は、生徒にとって本当に必要だと思えるものなのか、あるいはこの時代に本当に大切なものなのか、さらに吟味していく必要があるということに、気づいたのでした。
昨日の職員会でも、今月中旬の定期考査を前にして、引き続きアセスメントに取り組んでみようという呼びかけが教務係からなされました。
机上の資質・能力論ではなく、地に足のついた、生徒の学びをみるまなざしが必要だと考えています。自分がこうだと思っていたことが、実は思い込みだったりする。生徒のためと思っていたことが、実は生徒をよく見ていなかった決めつけだったりする。だからこそ、対話を重ねて、試行錯誤しながら、よりよい教育実践を目指すしかありません。
今まさに様々な「次の手」に挑戦し始めているところです。きらびやかな真新しさではなく、生徒と教師がしっかりつながっていると思えるような学校づくりに、これからも取り組みたいと思っています。

この号は、「教育の『これから』を考える」という特集で、コロナ禍の時代に未来を展望するような学びをどのように進めていくかという観点で、高校生(自修館中等教育学校の生徒等)、教育長(広島県の平川氏)、高校教員(広島叡智学園中学校・高校、広島国泰寺高校)などの取材記事とともに、本校のことを取り上げていただきました。
(インターネットからも閲覧できます。
https://berd.benesse.jp/magazine/kou/booklet/?id=5530 )
タイトルは「臨時休業中の生徒の成長を、グランドデザインの見直しにつなげる」というもの。実は、取材の依頼を受けるかどうかで私は随分迷いました。赴任してまだ半年も経っていないし、コロナ禍の中の学校づくりもまだ始まったばかり。長野県内を見ても、もっとふさわしいフロントランナーはいくらでもいる。しかし、全国の読者にとっては、本校のような試行錯誤中の取組も身近で参考になるところがあるかもしれないし、そもそも本校の取組は、職員集団と生徒の「集合知」の産物であり、その基礎には私が週1回のペースで参加してきた全国の先生たちとのWEB対話「生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」(小村俊平さんの主宰)の「集合知」の恩恵があります。「集合知」はたえず社会に開き、新たな対話を重ねながらリニューアルしていくべきものなので、せっかくいただいた機会は、やはり大事にしていくべきなのだろうと考えた次第です。
『VIEW21』の記事は、4月からここまでの5カ月間の軌跡をコンパクトにまとめていただきました。記事の核心は、臨時休業中に生徒が頑張ったことを各教科の担当がきちんと評価してあげるためには、テストの点数だけでは不十分であり、生徒の努力を丁寧に振り返り、教員がコメントをするアセスメントの取組が必要だと気付いたという点にあります。点数評価ではなくて、記述による評価(定性評価)に意味があるのだと考えています。そしてアセスメントをしていくと、本校がグランドデザインでかかげていた生徒育成方針(卒業までにこのような資質・能力を身に付けさせるという目標)は、生徒にとって本当に必要だと思えるものなのか、あるいはこの時代に本当に大切なものなのか、さらに吟味していく必要があるということに、気づいたのでした。
昨日の職員会でも、今月中旬の定期考査を前にして、引き続きアセスメントに取り組んでみようという呼びかけが教務係からなされました。
机上の資質・能力論ではなく、地に足のついた、生徒の学びをみるまなざしが必要だと考えています。自分がこうだと思っていたことが、実は思い込みだったりする。生徒のためと思っていたことが、実は生徒をよく見ていなかった決めつけだったりする。だからこそ、対話を重ねて、試行錯誤しながら、よりよい教育実践を目指すしかありません。
今まさに様々な「次の手」に挑戦し始めているところです。きらびやかな真新しさではなく、生徒と教師がしっかりつながっていると思えるような学校づくりに、これからも取り組みたいと思っています。

「チームLと一緒に授業評価のあり方を考える」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年09月01日18:39
長野県の県立高校では「匿名性を担保した授業評価」を実施しています。生徒が、自分が受けている授業の教員による進め方について、無記名で評価するというもので、先生方は毎回緊張してこの結果を参照して、自分の授業改善にいかしています。
ところが振り返ってみると、この授業評価の観点は教員が作ったものであって、生徒が「授業はこうあってほしい」と思っていることが反映されているかがわからない。
ならば、生徒と対話してみよう。
今日は、蘇南高校「チームL」を校長室で結成しました。3年生の正副生徒会長と1~3年のルーム長の8名から構成されます。
「これから学校にかかわる色んなことを皆さんに聞いていきます。チームLのLは、リーダーのLです。時には、ホームルームでクラスのみんなの意見を聞いてきてもらうこともあるでしょう。是非、蘇南高校のあり方を一緒に考えてくださいね。」
続いて昨年度までの授業評価のアンケート用紙を見ながら、生徒に自由に意見を言ってもらいました。これが予想以上(!)に意見が次々に出てきます。
「授業中で『深く考える場面』があるかどうかが大事だと思います。」
「先生が一方的に話すだけの授業って、先生自身が理解しようとしているにすぎないんですよね。それっておかしい。」
「生徒自身の取組の問題点を自覚させるような質問項目も必要です。先生の問題点をあげるだけでは、授業はよくならないと思います。」
・・・おー、君たちは、何と素晴らしい生徒たちなのだ。私は、心の中でつぶやいていました。
早速、生徒の考えを取り入れて授業評価改訂案を作りました。明日の職員会で先生方と共有していきたいと思います。
生徒が学校づくりに主体的に関わるための工夫が、色々な高校で取り組まれています。長野県では、辰野高校の三者協議会とか、松本深志高校の「鼎談深志」など、感心させられる素晴らしい取組がいくつもあります。
本日、気楽な形でスタートした対話組織「チームL」が、どんなふうに展開していくか。結構ワクワクしています。

ところが振り返ってみると、この授業評価の観点は教員が作ったものであって、生徒が「授業はこうあってほしい」と思っていることが反映されているかがわからない。
ならば、生徒と対話してみよう。
今日は、蘇南高校「チームL」を校長室で結成しました。3年生の正副生徒会長と1~3年のルーム長の8名から構成されます。
「これから学校にかかわる色んなことを皆さんに聞いていきます。チームLのLは、リーダーのLです。時には、ホームルームでクラスのみんなの意見を聞いてきてもらうこともあるでしょう。是非、蘇南高校のあり方を一緒に考えてくださいね。」
続いて昨年度までの授業評価のアンケート用紙を見ながら、生徒に自由に意見を言ってもらいました。これが予想以上(!)に意見が次々に出てきます。
「授業中で『深く考える場面』があるかどうかが大事だと思います。」
「先生が一方的に話すだけの授業って、先生自身が理解しようとしているにすぎないんですよね。それっておかしい。」
「生徒自身の取組の問題点を自覚させるような質問項目も必要です。先生の問題点をあげるだけでは、授業はよくならないと思います。」
・・・おー、君たちは、何と素晴らしい生徒たちなのだ。私は、心の中でつぶやいていました。
早速、生徒の考えを取り入れて授業評価改訂案を作りました。明日の職員会で先生方と共有していきたいと思います。
生徒が学校づくりに主体的に関わるための工夫が、色々な高校で取り組まれています。長野県では、辰野高校の三者協議会とか、松本深志高校の「鼎談深志」など、感心させられる素晴らしい取組がいくつもあります。
本日、気楽な形でスタートした対話組織「チームL」が、どんなふうに展開していくか。結構ワクワクしています。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長