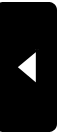「生徒はネットで調べる前に、誰かと会う~第10回総合研究発表会が終わる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月11日19:58
今日は、3年「総合研究」(総合的な学習の時間)の発表会を開催しました。33班すべての作品をエントランスに展示し、4班のプレゼンを大講義室で行いました。大講義室には3年生全員と5名の審査員の皆さんが集まり、その様子をオンラインでそれぞれの教室にいる1・2年生に配信しました。審査員は、向井南木曽町長さん、伊藤南木曽町教育長さん、コンソーシアム委員の高橋さん、吉田さん、川本さん、そして県教育委員会の卯之原さんです。
今回は、さらに木曽郡・中津川市・伊那市など本校生の出身中学校の校長先生方がつながってくださいました。そのうち開田中学校と南木曽中学校では3年生の生徒の皆さんが全員で参加してくださいました。そして同じ総合学科の塩尻志学館高校と丸子修学館高校の皆さん、福島県立ふたば未来高校の林先生、神奈川の聖和学院中学・高校の栢本先生と生徒の皆さんがつながってくださいました。
あらためて深く御礼を申し上げます。
今日、発表した4本は、次のような探究です。
①運動不足に陥りがちな中山間地の人々(山坂が多いから運動すると思われがちだが、逆に車に頼ってしまう)のために、手軽に取り組める運動プログラムを作って47家庭に取り組んでもらったほか、町内のさまざまな坂道を走って記録を投稿するインスタグラムを開設した。(池上さん、尾上さん)
➁Arduinoを使った作曲のプログラミングを容易にできる方法を考案し、中学生向けの教育ツールとして、実際にプログラミング教室を実践した。(松永さん、垂見さん)
③南木曽を代表する「ろくろ工芸」の魅力を調べていく中で、保温性を科学的に検証しようとしたら、「木のお椀は、すぐに温度がさがり、適温となって持続する」という性質を見出し、これを新たなセールストークにすることを提案した。(大畑さん、上村さん)
④南木曽の失われゆく里山の希少植物から自然酵母をつくり、30回以上の試行錯誤(さまざまな条件を変更しては試した)を繰り返して、ついにふくらむおいしいパンの製造に成功した。(長岡さん)
あらためて私は思いました。蘇南高校の生徒たちの「探究」は、とにかく外に出て、いろいろな大人たちと出会い、対話をし、そこから考えたことを探究しようとしています。そして実験とか実践をとにかく試行錯誤して、うまくいかないことや予想外の展開にとまどい、それを逆にバネにしたりして、探究を磨いています。
私はこれまでいろいろな高校生の探究を見てきましたが、ネットで調べた知識をくみあわせて並べて、結論としては「この社会問題に対してのひとりひとりの意識を高めていくことが大切だと思います」という型にはまった言葉が出てくるものが多かったのです。私は「頭でっかち型」と呼んできました。
うちの生徒は、ネットで調べる前に、まず誰かと会って、自分の目と耳と心で経験しようとする。そして自分の実践をくみたてようとする。これはとても大切なことではないでしょうか。
(つづく)

今回は、さらに木曽郡・中津川市・伊那市など本校生の出身中学校の校長先生方がつながってくださいました。そのうち開田中学校と南木曽中学校では3年生の生徒の皆さんが全員で参加してくださいました。そして同じ総合学科の塩尻志学館高校と丸子修学館高校の皆さん、福島県立ふたば未来高校の林先生、神奈川の聖和学院中学・高校の栢本先生と生徒の皆さんがつながってくださいました。
あらためて深く御礼を申し上げます。
今日、発表した4本は、次のような探究です。
①運動不足に陥りがちな中山間地の人々(山坂が多いから運動すると思われがちだが、逆に車に頼ってしまう)のために、手軽に取り組める運動プログラムを作って47家庭に取り組んでもらったほか、町内のさまざまな坂道を走って記録を投稿するインスタグラムを開設した。(池上さん、尾上さん)
➁Arduinoを使った作曲のプログラミングを容易にできる方法を考案し、中学生向けの教育ツールとして、実際にプログラミング教室を実践した。(松永さん、垂見さん)
③南木曽を代表する「ろくろ工芸」の魅力を調べていく中で、保温性を科学的に検証しようとしたら、「木のお椀は、すぐに温度がさがり、適温となって持続する」という性質を見出し、これを新たなセールストークにすることを提案した。(大畑さん、上村さん)
④南木曽の失われゆく里山の希少植物から自然酵母をつくり、30回以上の試行錯誤(さまざまな条件を変更しては試した)を繰り返して、ついにふくらむおいしいパンの製造に成功した。(長岡さん)
あらためて私は思いました。蘇南高校の生徒たちの「探究」は、とにかく外に出て、いろいろな大人たちと出会い、対話をし、そこから考えたことを探究しようとしています。そして実験とか実践をとにかく試行錯誤して、うまくいかないことや予想外の展開にとまどい、それを逆にバネにしたりして、探究を磨いています。
私はこれまでいろいろな高校生の探究を見てきましたが、ネットで調べた知識をくみあわせて並べて、結論としては「この社会問題に対してのひとりひとりの意識を高めていくことが大切だと思います」という型にはまった言葉が出てくるものが多かったのです。私は「頭でっかち型」と呼んできました。
うちの生徒は、ネットで調べる前に、まず誰かと会って、自分の目と耳と心で経験しようとする。そして自分の実践をくみたてようとする。これはとても大切なことではないでしょうか。
(つづく)

「エントランスの窓ガラスを高所作業車に乗ってきれいにする」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月10日21:40
本年度のPTA環境整備作業は、10月の予定日に荒天のために延期となり、翌週の代替日も荒天になるという受難つづきでした。熊対策として校舎と裏山のあいだの草地を刈り込む作業は校用技師さんが何日もかけてやりとげましたが、どうしても私たちだけではできないことがありました。それを本日、3名の保護者の皆さんが半日かけて実行してくださったのです。
永友さんはご家族とともに高所作業車を運転して、昇降口ロビーの窓をきれいにする作業をしてくれました。蘇南高校のエントランスの壁は、2階までの吹き抜けのガラス窓なのですが、上部はクモの巣が張り、残念な光景だったのです。それを3時間半もかけて、完璧にきれいにふき取っていただきました。あとは私たちが内側から清掃をすれば、さらに光り輝くことでしょう。輝くエントランスの実現です。
小椋さんと矢沢さんは、通学路に張り出した桜の幹や枝を伐採する作業を、これまた完璧におこなってくださいました。春になると桜の花びらが燃え上がるようなのですが、いかんせんカーブの車道に枝が生い茂っていて、それを避ける自動車が対向車とぶつかりそうになる状況でした。4時間近くをかけて、とてもすっきりした通学路になりました。
お三方には、ただただ感謝の思いでいっぱいです。本当にありがとうございました。
皆さんの善意に支えられて、蘇南高校の美しい学びの環境が守られています。

永友さんはご家族とともに高所作業車を運転して、昇降口ロビーの窓をきれいにする作業をしてくれました。蘇南高校のエントランスの壁は、2階までの吹き抜けのガラス窓なのですが、上部はクモの巣が張り、残念な光景だったのです。それを3時間半もかけて、完璧にきれいにふき取っていただきました。あとは私たちが内側から清掃をすれば、さらに光り輝くことでしょう。輝くエントランスの実現です。
小椋さんと矢沢さんは、通学路に張り出した桜の幹や枝を伐採する作業を、これまた完璧におこなってくださいました。春になると桜の花びらが燃え上がるようなのですが、いかんせんカーブの車道に枝が生い茂っていて、それを避ける自動車が対向車とぶつかりそうになる状況でした。4時間近くをかけて、とてもすっきりした通学路になりました。
お三方には、ただただ感謝の思いでいっぱいです。本当にありがとうございました。
皆さんの善意に支えられて、蘇南高校の美しい学びの環境が守られています。

「木のお椀の保温性を実験で証明しようとしたら…」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月09日19:09
今週の金曜日は、「第10回総合研究発表会」。3年生の「総合研究」(総合的な学習の時間)の成果発表会です。コロナ対策としてオンライン配信方式という新しいやり方で実施します。
その予告として一つの班の研究内容を紹介します。
南木曽の代表的な特産品に、木を回転させて削り、美しいお椀やお皿を創作する「ろくろ工芸」があります。妻籠宿から下伊那の昼神温泉に向かう清内路峠の中腹にある広瀬地区は、代表的な木地師(きじし)の里です。
本校の大畑さん、上村さんは、その「ろくろ工芸」の魅力をインタビュー取材しながら調べていくうちに、「すぐれた保温性がある」と言い伝えられてきた製品の性能を「科学実験で証明して魅力的なセールストークを開発しよう」という課題を設定しました。かくして、セラミック、ステンレス、プラスチックなどの容器と材質別のろくろ工芸品が並べられ、熱湯が時間を経過していくうちにどのように冷めていくか(保温されていくか)という科学実験が始まりました。
実験を重ねるうちに彼女たちは、大いに困惑しました。10分後、20分後の温度の下がり方は、「ろくろ工芸品」と他の容器にあまり違いがなさそうだということがわかってきたのです。むしろ2分後の下がり方は、「ろくろ工芸品」のほうが急降下(!)といってもよい。
あらためて考えると、①木のお椀は急に温度が低下して、その後、緩やかに下がる。これはやけどをせずに快適な温度で汁物を楽しめる性能と言える。➁木のお椀は液体の温度に対して手の感触に熱さを感じないので、相対的に保温性を感じるのではないか。…という結論を導き出しました。南木曽「ろくろ工芸品」の新たなセールストークの誕生ではないでしょうか。
私は、探究することで思いもかけないようなことに出会った彼女たちの研究に、探究することの面白さを心から感じています。

その予告として一つの班の研究内容を紹介します。
南木曽の代表的な特産品に、木を回転させて削り、美しいお椀やお皿を創作する「ろくろ工芸」があります。妻籠宿から下伊那の昼神温泉に向かう清内路峠の中腹にある広瀬地区は、代表的な木地師(きじし)の里です。
本校の大畑さん、上村さんは、その「ろくろ工芸」の魅力をインタビュー取材しながら調べていくうちに、「すぐれた保温性がある」と言い伝えられてきた製品の性能を「科学実験で証明して魅力的なセールストークを開発しよう」という課題を設定しました。かくして、セラミック、ステンレス、プラスチックなどの容器と材質別のろくろ工芸品が並べられ、熱湯が時間を経過していくうちにどのように冷めていくか(保温されていくか)という科学実験が始まりました。
実験を重ねるうちに彼女たちは、大いに困惑しました。10分後、20分後の温度の下がり方は、「ろくろ工芸品」と他の容器にあまり違いがなさそうだということがわかってきたのです。むしろ2分後の下がり方は、「ろくろ工芸品」のほうが急降下(!)といってもよい。
あらためて考えると、①木のお椀は急に温度が低下して、その後、緩やかに下がる。これはやけどをせずに快適な温度で汁物を楽しめる性能と言える。➁木のお椀は液体の温度に対して手の感触に熱さを感じないので、相対的に保温性を感じるのではないか。…という結論を導き出しました。南木曽「ろくろ工芸品」の新たなセールストークの誕生ではないでしょうか。
私は、探究することで思いもかけないようなことに出会った彼女たちの研究に、探究することの面白さを心から感じています。

「向井南木曽町長さんをバドミントン部が表敬訪問する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月08日17:57
本日の夕方、バドミントン部が、先日の新人戦県大会の学校対抗、ダブルス、シングルスそれぞれにおいて北信越大会に出場することになったことを報告するために、南木曽町役場の向井町長さんを訪問しました。
バドミントン部からは森さんと後藤さんが、大会結果を報告しつつ、ふだん南木曽町から多大なご支援をいただいていることに御礼を述べました。向井町長さんからは、強豪が揃う北信越大会に思い切り挑戦してきてほしいという激励のお言葉をいただきました。
コロナの感染予防のために、本校はすべての練習試合を自粛しているので、これまで岐阜県や愛知県の高校生・大学生との交流の中で鍛えてきたバドミントン部の生徒は、例年のような練習が出来ません。そのような状況下であっても出来ることを工夫して努力し続けているバドミントン部です。
今年度はインターハイ予選がコロナのために中止になってしまい、バドミントン部としては初めての表敬訪問でした。町長さん、そして町民の皆様に次の報告が出来るよう、頑張ってまいります。

バドミントン部からは森さんと後藤さんが、大会結果を報告しつつ、ふだん南木曽町から多大なご支援をいただいていることに御礼を述べました。向井町長さんからは、強豪が揃う北信越大会に思い切り挑戦してきてほしいという激励のお言葉をいただきました。
コロナの感染予防のために、本校はすべての練習試合を自粛しているので、これまで岐阜県や愛知県の高校生・大学生との交流の中で鍛えてきたバドミントン部の生徒は、例年のような練習が出来ません。そのような状況下であっても出来ることを工夫して努力し続けているバドミントン部です。
今年度はインターハイ予選がコロナのために中止になってしまい、バドミントン部としては初めての表敬訪問でした。町長さん、そして町民の皆様に次の報告が出来るよう、頑張ってまいります。

「校長ラウンドテーブル・番外編」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月07日20:03
少しさかのぼっての報告になりますが、先週の12月2日(水)のWEB対話「生徒の気づきと学びを最大化するプロジェクト」(小村俊平さん主宰)は、「校長ラウンドテーブル」という企画で、3名の校長に「目指す学校像」についての短いスピーチをさせ、参加者がさまざまな質問をぶつけて対話を試みるという2時間でした。
北海道札幌北高等学校長の林正憲先生と宮城県仙台第三高等学校長の佐々木克敬先生という、心から尊敬するお二人にまじって、長野県蘇南高等学校の小川がラウンドテーブルの画面に並んだ次第です。あとで気づいたことなのですが、3名に共通することは、道県立高校の校長なのですが、いずれも「立」が校名に入っていないことです。ちなみに長野県の場合は、大正9年の長野県令38号によって旧制中学校の名称が「長野県立~中学校」から「長野県~中学校」に一斉に改称されて、現在に受け継がれています。あえて「立」がないということの意味を様々な大先輩たちが熱く語るのを、初任の頃から私は聞いてきました。
実は、3人で自己紹介をしましょうとメールの交換を始めたら、すでに本番前にかなりな量の資料とメッセージがとびかう盛り上がりになり、私は本番前にすでに大満足していたのでした。林先生、佐々木先生の熱量の迫力に圧倒されていたと言った方がよいのかもしれません。
WEB対話でも少しふれられていましたが、お二人の現任校での教育理念の根底には、それぞれの教師生命をかけた原体験があることを私はひしひしと感じました。林先生の地域高校のたてなおしや佐々木先生の被災地の高校における新たな試みには、その高校をこえた普遍性が宿っています。
私の分科会では、私が2校目で体験した「松本サリン事件」をめぐって様々な関係者と対話をかさね、そのなかから教育実践を自分なりに探究したことが、今の自分につながっているのかもしれないということを報告しました。「第一通報者」でありながら冤罪をきせられて、それでも毅然として歩んでおられた河野さん一家、サリン事件の意味を必死に考えようとした生徒たち、記憶を未来につなごうとする坂本弁護士事件のご遺族…そうした人々とともにあの頃の私の日々はありました。
自分の目指す学校像の核には、生徒と教師がともに「探究者」であるという目標があります。「松本サリン事件」をくぐりぬけて自分の人生を「探究した」人々の思い出が、いつも私の根底にあるのだとあらためて思いました。
いつか、本校の生徒にもあの頃のことをじっくり話してみたいと考えています。

北海道札幌北高等学校長の林正憲先生と宮城県仙台第三高等学校長の佐々木克敬先生という、心から尊敬するお二人にまじって、長野県蘇南高等学校の小川がラウンドテーブルの画面に並んだ次第です。あとで気づいたことなのですが、3名に共通することは、道県立高校の校長なのですが、いずれも「立」が校名に入っていないことです。ちなみに長野県の場合は、大正9年の長野県令38号によって旧制中学校の名称が「長野県立~中学校」から「長野県~中学校」に一斉に改称されて、現在に受け継がれています。あえて「立」がないということの意味を様々な大先輩たちが熱く語るのを、初任の頃から私は聞いてきました。
実は、3人で自己紹介をしましょうとメールの交換を始めたら、すでに本番前にかなりな量の資料とメッセージがとびかう盛り上がりになり、私は本番前にすでに大満足していたのでした。林先生、佐々木先生の熱量の迫力に圧倒されていたと言った方がよいのかもしれません。
WEB対話でも少しふれられていましたが、お二人の現任校での教育理念の根底には、それぞれの教師生命をかけた原体験があることを私はひしひしと感じました。林先生の地域高校のたてなおしや佐々木先生の被災地の高校における新たな試みには、その高校をこえた普遍性が宿っています。
私の分科会では、私が2校目で体験した「松本サリン事件」をめぐって様々な関係者と対話をかさね、そのなかから教育実践を自分なりに探究したことが、今の自分につながっているのかもしれないということを報告しました。「第一通報者」でありながら冤罪をきせられて、それでも毅然として歩んでおられた河野さん一家、サリン事件の意味を必死に考えようとした生徒たち、記憶を未来につなごうとする坂本弁護士事件のご遺族…そうした人々とともにあの頃の私の日々はありました。
自分の目指す学校像の核には、生徒と教師がともに「探究者」であるという目標があります。「松本サリン事件」をくぐりぬけて自分の人生を「探究した」人々の思い出が、いつも私の根底にあるのだとあらためて思いました。
いつか、本校の生徒にもあの頃のことをじっくり話してみたいと考えています。

「地元市町村の代表の皆さんと本校のこれからを対話する」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月04日19:06
今日は、蘇南高等学校地元市町村協議会が、本校会議室にて開催されました。
南木曽町・大桑村からは首長さん、議会議長さん、教育長さん、教育次長さん、そして中津川市からは教育長さん、指導主事さん、本校の同窓会長さん、PTA会長さんにお越しいただきました。まさに本校の「地元」の関係者の皆さんが勢揃いし、カナダ語学研修や蘇南アカデミー(多くの補習講座)への支援策を話し合っていただいたのです。
あわせて4月から現在に至るまでのオンライン教育の導入、「100を0にしない」努力、評価の改革などの学びの充実策、課題研究発表会にいたる生徒の探究的な学び、新たに立ち上げた地域とのコンソーシアムや「ふるさと探究学」について私から報告し、出席いただいた皆さんからとても貴重なご意見、アドバイスをたくさんいただきました。
〇課題研究発表会のレベルが年々上がってきている。参観することがとても楽しみだ。地域としてしっかり蘇南高校を支える。
〇県境に位置する蘇南高校だからこそ、人と人との多様で素敵なつながりが作れる。
〇ふるさとを愛し、ここで暮らしてみたいと人生設計をするような生徒を是非育ててほしい。
〇家族が通学しているが、学校生活の何何が嫌だと聞いたことがない。是非頑張ってほしい。
〇多様な生徒をひとりひとり丁寧に育ててくれる蘇南高校をこれからも応援したい。
〇昨日の地域協議会のキーワードだった「地域と高校の連携」を一層進めてほしい。
〇木曽谷南部の子どもたちの学ぶ権利を蘇南高校が是非守ってほしい。
ひとつひとつのご意見が、心に刻まれ、これからの本校の方向性であると思った次第です。
今日、地元市町村の代表の皆様に報告をしながら、4月から本当に色々なことを生徒の皆さん、先生方と頑張ってきたと、あらためて振り返りました。そして地域とのコンソーシアムを来年度は大桑村や中津川市の北部地区の皆さんに広げていきたいという私の夢にも、温かなエールをいただきました。本当にありがとうございました。
そして来週、再来週にかけて、それらの総決算のような大きな学びの企画が怒涛の如く続きます。「できるかな」と若干の不安があるのですが、今日の協議会で「できるよ、やってみてごらん」と地域の方々から背中を押してもらえたような気がします。
あらためて本校を支援していただいている地域の皆様に、心からの御礼を申し上げます。
いつも本当にありがとうございます。

南木曽町・大桑村からは首長さん、議会議長さん、教育長さん、教育次長さん、そして中津川市からは教育長さん、指導主事さん、本校の同窓会長さん、PTA会長さんにお越しいただきました。まさに本校の「地元」の関係者の皆さんが勢揃いし、カナダ語学研修や蘇南アカデミー(多くの補習講座)への支援策を話し合っていただいたのです。
あわせて4月から現在に至るまでのオンライン教育の導入、「100を0にしない」努力、評価の改革などの学びの充実策、課題研究発表会にいたる生徒の探究的な学び、新たに立ち上げた地域とのコンソーシアムや「ふるさと探究学」について私から報告し、出席いただいた皆さんからとても貴重なご意見、アドバイスをたくさんいただきました。
〇課題研究発表会のレベルが年々上がってきている。参観することがとても楽しみだ。地域としてしっかり蘇南高校を支える。
〇県境に位置する蘇南高校だからこそ、人と人との多様で素敵なつながりが作れる。
〇ふるさとを愛し、ここで暮らしてみたいと人生設計をするような生徒を是非育ててほしい。
〇家族が通学しているが、学校生活の何何が嫌だと聞いたことがない。是非頑張ってほしい。
〇多様な生徒をひとりひとり丁寧に育ててくれる蘇南高校をこれからも応援したい。
〇昨日の地域協議会のキーワードだった「地域と高校の連携」を一層進めてほしい。
〇木曽谷南部の子どもたちの学ぶ権利を蘇南高校が是非守ってほしい。
ひとつひとつのご意見が、心に刻まれ、これからの本校の方向性であると思った次第です。
今日、地元市町村の代表の皆様に報告をしながら、4月から本当に色々なことを生徒の皆さん、先生方と頑張ってきたと、あらためて振り返りました。そして地域とのコンソーシアムを来年度は大桑村や中津川市の北部地区の皆さんに広げていきたいという私の夢にも、温かなエールをいただきました。本当にありがとうございました。
そして来週、再来週にかけて、それらの総決算のような大きな学びの企画が怒涛の如く続きます。「できるかな」と若干の不安があるのですが、今日の協議会で「できるよ、やってみてごらん」と地域の方々から背中を押してもらえたような気がします。
あらためて本校を支援していただいている地域の皆様に、心からの御礼を申し上げます。
いつも本当にありがとうございます。

「木曽地域の高校の将来像についての意見・提案書がまとまる」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月03日21:34
長野県の高校再編・高校改革にかかわって、旧第10通学区(木曽地域)の「将来像」を考える協議会の第5回会議が木曽町文化交流センターで行われ、「意見・提案書」がまとまりました。
南北に約90キロ、東西に約50キロという広大な地域に、木曽青峰高校とわが蘇南高校の2校が存在しており、両校のあいだを自動車で移動するのに50分かかります。地域の人口減少が進むなか、これからの高校はどうあるべきかを、行政・経済・高等教育機関・町村教委・小中学校・PTAなどさまざまな団体の代表が一堂に会し、議論を重ねてきました。
「意見・提案書」の根幹は、木曽地域の2校がともに「存続されていくべき」であること、そしてそのための2校の学びの一層の発展を地域と連携しながらはかっていくというところにあります。
今回の会議の冒頭で、会長の原久仁男・木曽町長さんより、「今日が終わりではなく、出発点だと考えている。県立高校ではあるけれども、地域が高校を支え、育てていくことをより一層努力していくべき」という挨拶をいただき、私は深い感銘を受けました。
今回の協議会は、私にとってこれからの蘇南高校のありかたを考えるための素敵な出会いの場でした。人との出会い、提言されたアイデアとの出会い、教育といういとなみについての考え方との出会いです。
「意見・提案書」がまとまる前に、すぐにでも始められることが実際に動き出しています。
木曽郡PTA連合会の千村さんは、郡内の保護者を集めて2校への見学会を組織してくださいました。ただの参観ではありません。校長から学校経営の思いを聞き、じっくり授業を参観し、そこで考えたことを相互に対話し合うという、たっぷり半日をかけた研修です。来ていただいた保護者の方々からは、2校の魅力に温かいエールをいただいただけでなく、私たちと保護者の皆さんが子育てをともに行う「同志」であるというようなきずなが生まれたような気がしています。小中高の垣根をこえた教員と保護者の皆さんとのきずなの構築が、この地域では始まっています。
地域とのより一層の連携も始まりました。木曽青峰高校は「未来の学校」の先進的な取り組みを重ねています。わが蘇南高校は、3年生の課題研究発表会を中学校とオンラインで結び、高校生の探究の姿を中学生が間近に見るという試みを始めます。その翌週には、「ふるさと探究学・序章」と銘打ち、南木曽町の魅力的な大人たちが高校生たちと「ふるさとをつくる」ことの意味を対話するという学びを立ち上げます。
こうした連携を進めていくと、私たち教員が、今、つとめているこの木曽の地域をもうひとつの「ふるさと」と愛おしむようになり、「ふるさと」の人々、自然、文化遺産と手をたずさえて教育を進めるのだという姿勢が生まれてくるように感じています。
「意見・提案書」の「おわりに」は、このような文でしめくくられています。
――「木曽地域の高校2校は『小さくてもキラリと光る高校』になり、木曽地域においてすぐれた高校教育を創造していくことが十分に可能であると考えています。」
地域の皆さんからいただいた、この言葉の重みを心の支えにして、蘇南高校をさらに磨いていこうとあらためて決意しました。
「意見・提案書」のためにかかわっていただいたすべての皆様に心からの感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

南北に約90キロ、東西に約50キロという広大な地域に、木曽青峰高校とわが蘇南高校の2校が存在しており、両校のあいだを自動車で移動するのに50分かかります。地域の人口減少が進むなか、これからの高校はどうあるべきかを、行政・経済・高等教育機関・町村教委・小中学校・PTAなどさまざまな団体の代表が一堂に会し、議論を重ねてきました。
「意見・提案書」の根幹は、木曽地域の2校がともに「存続されていくべき」であること、そしてそのための2校の学びの一層の発展を地域と連携しながらはかっていくというところにあります。
今回の会議の冒頭で、会長の原久仁男・木曽町長さんより、「今日が終わりではなく、出発点だと考えている。県立高校ではあるけれども、地域が高校を支え、育てていくことをより一層努力していくべき」という挨拶をいただき、私は深い感銘を受けました。
今回の協議会は、私にとってこれからの蘇南高校のありかたを考えるための素敵な出会いの場でした。人との出会い、提言されたアイデアとの出会い、教育といういとなみについての考え方との出会いです。
「意見・提案書」がまとまる前に、すぐにでも始められることが実際に動き出しています。
木曽郡PTA連合会の千村さんは、郡内の保護者を集めて2校への見学会を組織してくださいました。ただの参観ではありません。校長から学校経営の思いを聞き、じっくり授業を参観し、そこで考えたことを相互に対話し合うという、たっぷり半日をかけた研修です。来ていただいた保護者の方々からは、2校の魅力に温かいエールをいただいただけでなく、私たちと保護者の皆さんが子育てをともに行う「同志」であるというようなきずなが生まれたような気がしています。小中高の垣根をこえた教員と保護者の皆さんとのきずなの構築が、この地域では始まっています。
地域とのより一層の連携も始まりました。木曽青峰高校は「未来の学校」の先進的な取り組みを重ねています。わが蘇南高校は、3年生の課題研究発表会を中学校とオンラインで結び、高校生の探究の姿を中学生が間近に見るという試みを始めます。その翌週には、「ふるさと探究学・序章」と銘打ち、南木曽町の魅力的な大人たちが高校生たちと「ふるさとをつくる」ことの意味を対話するという学びを立ち上げます。
こうした連携を進めていくと、私たち教員が、今、つとめているこの木曽の地域をもうひとつの「ふるさと」と愛おしむようになり、「ふるさと」の人々、自然、文化遺産と手をたずさえて教育を進めるのだという姿勢が生まれてくるように感じています。
「意見・提案書」の「おわりに」は、このような文でしめくくられています。
――「木曽地域の高校2校は『小さくてもキラリと光る高校』になり、木曽地域においてすぐれた高校教育を創造していくことが十分に可能であると考えています。」
地域の皆さんからいただいた、この言葉の重みを心の支えにして、蘇南高校をさらに磨いていこうとあらためて決意しました。
「意見・提案書」のためにかかわっていただいたすべての皆様に心からの感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

「バトミントン部が高体連新人戦で北信越大会進出を決める」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月02日12:25
11月28日(土)~30日(月)に上田市で行われた高体連バドミントン専門部の新人戦県大会で、本校の生徒がめざましい活躍をしました。
《おもな結果》
男子 団体戦3位(森・有賀伊・三石・有賀詩・藤森)
ダブルス2位(有賀伊・有賀詩)☛北信越大会出場
ダブルス3位(森・三石)☛北信越大会出場
シングルス3位(三石)☛北信越大会出場
シングルスベスト8(森)
女子 団体戦2位(小澤・後藤・小林・嶋﨑・安江・松瀬)☛北信越大会出場
ダブルス3位(小澤・後藤)☛北信越大会出場
シングルス1位(小澤)☛北信越大会出場
コロナ禍のなかで例年練習試合を重ねている愛知県・岐阜県の高校との交流を自粛せざるを得なくなり、思うように練習ができないなか、努力を重ねての成果です。
社会体育において指導をいただいている松井コーチをはじめとする皆様にも改めて感謝を申し上げます。
実は、先月、県下各地から本校に集まっている生徒を受け入れてくださっている3軒の下宿先を校長として訪問して御礼を申し上げました。3軒の下宿屋さんともに、生徒が健全に学校生活を送り、バドミントンに打ち込めるよう、本当に温かな支援をいただいているのだということが、よくわかりました。私は胸が熱くなり、帰路についたのでした。
そのうちの一軒のお宅では、生徒たちが臨時休校中に体力を落とさないように働いたという「薪割り」の成果が屋根まで届くような、ものすごい分量で積み上げられていました。こうした下宿生と地元の生徒が支え合って、インターハイ出場を目指して、日々、懸命に努力を重ねています。
心からの「おめでとう」という言葉を贈ります。

《おもな結果》
男子 団体戦3位(森・有賀伊・三石・有賀詩・藤森)
ダブルス2位(有賀伊・有賀詩)☛北信越大会出場
ダブルス3位(森・三石)☛北信越大会出場
シングルス3位(三石)☛北信越大会出場
シングルスベスト8(森)
女子 団体戦2位(小澤・後藤・小林・嶋﨑・安江・松瀬)☛北信越大会出場
ダブルス3位(小澤・後藤)☛北信越大会出場
シングルス1位(小澤)☛北信越大会出場
コロナ禍のなかで例年練習試合を重ねている愛知県・岐阜県の高校との交流を自粛せざるを得なくなり、思うように練習ができないなか、努力を重ねての成果です。
社会体育において指導をいただいている松井コーチをはじめとする皆様にも改めて感謝を申し上げます。
実は、先月、県下各地から本校に集まっている生徒を受け入れてくださっている3軒の下宿先を校長として訪問して御礼を申し上げました。3軒の下宿屋さんともに、生徒が健全に学校生活を送り、バドミントンに打ち込めるよう、本当に温かな支援をいただいているのだということが、よくわかりました。私は胸が熱くなり、帰路についたのでした。
そのうちの一軒のお宅では、生徒たちが臨時休校中に体力を落とさないように働いたという「薪割り」の成果が屋根まで届くような、ものすごい分量で積み上げられていました。こうした下宿生と地元の生徒が支え合って、インターハイ出場を目指して、日々、懸命に努力を重ねています。
心からの「おめでとう」という言葉を贈ります。

「ここまでできるんだという心意気を共有できるような一日にしたい」
Posted by 蘇南高等学校長.
2020年12月01日20:36
今日は、12月11日に開催する3年生の課題研究発表会(オンライン配信)に出場する4班を選考する会議を先生方と行いました。これまで課題研究を指導してきた担当の先生方ですから、本校の3分の1強の人数になります。2次選考会で発表した9班をひとつひとつ吟味しました。
先生方はやはり、ひとりひとりの生徒の成長の軌跡にとても注目していることがよくわかりました。本校の大切にしていることがひとりひとりの生徒へのまなざしですから、入学してからこの課題研究をまとめるまでの道のりを丁寧に見ています。
私は、ここはあえてアウトプットされた発表内容のほうに焦点を絞り、以下の3点に注目しました。
①課題設定と結論がきちんと対応しており、その間の試行錯誤(探究のサイクル)が濃いこと。
➁教員や地域の大人が知らないようなオリジナルな気づきや社会的な意義があること。
③研究の過程で多くの他者と出会い、他者の検証の目線をもって研究を総括できていること。
こうした議論を重ねることは、私たちの「学ぶ」といういとなみを見つめることにほかなりません。一つ一つの研究の何が素晴らしく、何が改善点なのかを議論し、改善点をクリアすればさらに素晴らしくなりそうな4つの研究を選びました。
本番まで1週間半ほどしかないのですが、当日は、全校生徒のみならず地域の中学校や近隣の高校にも配信されますし、南木曽町長さん、教育長さん、コンソーシアム委員さんをはじめとするゲスト審査員にもお越しいただきます。高校生の探究って、ここまでできるんだという心意気を共有できるような一日にしたいと思っています。

先生方はやはり、ひとりひとりの生徒の成長の軌跡にとても注目していることがよくわかりました。本校の大切にしていることがひとりひとりの生徒へのまなざしですから、入学してからこの課題研究をまとめるまでの道のりを丁寧に見ています。
私は、ここはあえてアウトプットされた発表内容のほうに焦点を絞り、以下の3点に注目しました。
①課題設定と結論がきちんと対応しており、その間の試行錯誤(探究のサイクル)が濃いこと。
➁教員や地域の大人が知らないようなオリジナルな気づきや社会的な意義があること。
③研究の過程で多くの他者と出会い、他者の検証の目線をもって研究を総括できていること。
こうした議論を重ねることは、私たちの「学ぶ」といういとなみを見つめることにほかなりません。一つ一つの研究の何が素晴らしく、何が改善点なのかを議論し、改善点をクリアすればさらに素晴らしくなりそうな4つの研究を選びました。
本番まで1週間半ほどしかないのですが、当日は、全校生徒のみならず地域の中学校や近隣の高校にも配信されますし、南木曽町長さん、教育長さん、コンソーシアム委員さんをはじめとするゲスト審査員にもお越しいただきます。高校生の探究って、ここまでできるんだという心意気を共有できるような一日にしたいと思っています。

カテゴリ
最近の記事
「校長最後の日に学校がみんなのためのミュージアムになる」 (3/31)
「誰でも学びに積極的になれる力をもっている」 (3/30)
「蘇南高校の生徒たちに語りかけたことばがロシア語になる」 (3/29)
「学ぶ意義を確認しながら着実に学び続ける」 (3/28)
「この桜の花びらの数くらい」 (3/27)
「雑誌『思想』4月号はなんと歴史教育の特集です」 (3/25)
「3年間で“最初で最後の”盃を先生方とくみかわしました」 (3/24)
「学生時代に授業中に寝ていそうな先生は校長先生」 (3/22)
過去記事
最近のコメント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード

インフォメーション
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
蘇南高等学校長